F6スパーリングは最後の4枚目、こちらは茶+黒を空以外の部分に全面がけした。1枚目から3枚目とは違う方法を採らないと複数枚描いている意味がない。とはいえこの描き方はあまりやりたくなかった。かつてこの描き方で半分成功、半分失敗という成果を手に入れ、結果論だがそれで油彩技法の迷宮に私自身が入り込んでしまったからだ。しかし今回は必要な厚みは出来ているわけで、前提条件が全く違うので敢えて再挑戦することにした。次回から本格的な描画着彩に入る。
さて問題はF20号。どうしたらいいか。今日は休みでまだ午前中。時間はたっぷりある。しばらく画面を見ながらあれこれ考える。寒いのでマグカップにインスタントコーヒーを淹れ、それを飲みながら悩む。
当初は白で厚塗りを再度必要な個所に施して終わりにするつもりだったが、一応必要なところに最低限の厚みはできている。仮に今日厚みをつけて終わりにしたとしても、次回どうするかという問題は残る。だからいずれにせよ考えておく必要がある。
そこである決断をした。今日のF6スパーリング4枚目と同じく空以外に茶+黒を全面がけし、さらに同じ茶+黒で陰影づけすることにした。4枚目よりさらに踏み込んだ形で、かつてこれと同じようなことをやって何回もそれと気づかずに失敗している。4枚目同様、今回は事前に厚みができているので条件は違う。
どちらも何が問題かというと、完成予想時の色彩が描画の早い段階で出来上がりやすいという点。つまり本格的に描き込む、細部描写をする、その前に色彩が完成してしまう。するとそれ以上手を出しづらくなる。未完成のデッサンみたいな状態で色彩だけが完成してしまう状態。そこで構わず描き込んで後で色彩を戻そうとしてもそうはいかない。同じ色彩には戻らないし、無理矢理戻そうとしても、画面に不自然な厚みができてそこだけが目立ってしまう。かといってせっかくできた色彩を崩す(つまり画面全体に何か別の色をかけたりする)のは、気分的に良くないし、そこからまた細部描写しつつ色彩を戻していくのは(果たして本当に戻せるかどうかは別にして)、効率が悪い。
油絵制作では全てが徐々に出来上がっていくのが望ましい。それは、デッサンと色彩が別であろうが、筆で(つまり色彩で)デッサンしようが同じである。
では私は何故この方法を採るのかというと、これでうまく行けば一番いいと思っているからだ。でも先に述べた通りなかなかうまく行かない。だからこれ以外の油彩技法として、この絵画制作記のカテゴリー記事の「風景画改革」で試したF12号が、私の最善の描き方になっている。
別段、このF20号の描き方が画期的だったりはしない(もちろん私なりの多少の工夫はしているけれど)。むしろより古典的である。「風景画改革」のF12号の方がよっぽど風変わりだと思う。
この古典的な描き方がすたれたのは、やはりやり通すのが難しいからだと思う。理由は既に述べた通り、色彩が出来上がりやすいから。油絵具がチューブ入りで市販されるようになり、その性質が根本的に変わったせいではないと私は考える。市販の白いカンバスに下地色としてローシェンナを塗ったり、土性顔料絵具をテレピンで溶いて下描きデッサンしたりすることは入門書にも書いてあるし、一般的にもよく行われているが、これらはその名残り、つまり古典技法の残骸なんじゃないか。わずかに残された手がかりと言っていい。
何だか話が脱線してしまった。要するにこれからうまく行くかどうかが見もの。で私自身に勝算があるのかというと、一応あります。こっちもだいぶ進歩しているので、今度こそかつてのような失敗はせずに済むんじゃないかと。次回やってみれば成功か失敗がすぐにわかるんですが、おそらくこつは色の明度よりも彩度を落とすこと。そしてその色を薄すぎず厚すぎず塗ること。この2つでしょう。
あのですね、別に古典技法の再現なんてことは全く考えておりません。昔ながらの描き方を少し取り入れることで、それが自分の目指す表現に近づく最短ルートだと考えているだけですので。
まあ「風景画改革」の描き方という保険がありますから、結構気楽にテストできます。今度こそは成功したいなあ。
さて問題はF20号。どうしたらいいか。今日は休みでまだ午前中。時間はたっぷりある。しばらく画面を見ながらあれこれ考える。寒いのでマグカップにインスタントコーヒーを淹れ、それを飲みながら悩む。
当初は白で厚塗りを再度必要な個所に施して終わりにするつもりだったが、一応必要なところに最低限の厚みはできている。仮に今日厚みをつけて終わりにしたとしても、次回どうするかという問題は残る。だからいずれにせよ考えておく必要がある。
そこである決断をした。今日のF6スパーリング4枚目と同じく空以外に茶+黒を全面がけし、さらに同じ茶+黒で陰影づけすることにした。4枚目よりさらに踏み込んだ形で、かつてこれと同じようなことをやって何回もそれと気づかずに失敗している。4枚目同様、今回は事前に厚みができているので条件は違う。
どちらも何が問題かというと、完成予想時の色彩が描画の早い段階で出来上がりやすいという点。つまり本格的に描き込む、細部描写をする、その前に色彩が完成してしまう。するとそれ以上手を出しづらくなる。未完成のデッサンみたいな状態で色彩だけが完成してしまう状態。そこで構わず描き込んで後で色彩を戻そうとしてもそうはいかない。同じ色彩には戻らないし、無理矢理戻そうとしても、画面に不自然な厚みができてそこだけが目立ってしまう。かといってせっかくできた色彩を崩す(つまり画面全体に何か別の色をかけたりする)のは、気分的に良くないし、そこからまた細部描写しつつ色彩を戻していくのは(果たして本当に戻せるかどうかは別にして)、効率が悪い。
油絵制作では全てが徐々に出来上がっていくのが望ましい。それは、デッサンと色彩が別であろうが、筆で(つまり色彩で)デッサンしようが同じである。
では私は何故この方法を採るのかというと、これでうまく行けば一番いいと思っているからだ。でも先に述べた通りなかなかうまく行かない。だからこれ以外の油彩技法として、この絵画制作記のカテゴリー記事の「風景画改革」で試したF12号が、私の最善の描き方になっている。
別段、このF20号の描き方が画期的だったりはしない(もちろん私なりの多少の工夫はしているけれど)。むしろより古典的である。「風景画改革」のF12号の方がよっぽど風変わりだと思う。
この古典的な描き方がすたれたのは、やはりやり通すのが難しいからだと思う。理由は既に述べた通り、色彩が出来上がりやすいから。油絵具がチューブ入りで市販されるようになり、その性質が根本的に変わったせいではないと私は考える。市販の白いカンバスに下地色としてローシェンナを塗ったり、土性顔料絵具をテレピンで溶いて下描きデッサンしたりすることは入門書にも書いてあるし、一般的にもよく行われているが、これらはその名残り、つまり古典技法の残骸なんじゃないか。わずかに残された手がかりと言っていい。
何だか話が脱線してしまった。要するにこれからうまく行くかどうかが見もの。で私自身に勝算があるのかというと、一応あります。こっちもだいぶ進歩しているので、今度こそかつてのような失敗はせずに済むんじゃないかと。次回やってみれば成功か失敗がすぐにわかるんですが、おそらくこつは色の明度よりも彩度を落とすこと。そしてその色を薄すぎず厚すぎず塗ること。この2つでしょう。
あのですね、別に古典技法の再現なんてことは全く考えておりません。昔ながらの描き方を少し取り入れることで、それが自分の目指す表現に近づく最短ルートだと考えているだけですので。
まあ「風景画改革」の描き方という保険がありますから、結構気楽にテストできます。今度こそは成功したいなあ。











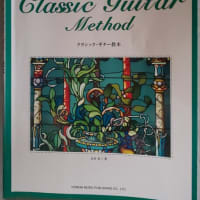





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます