結局アンリ・ルソーの精神を受け継いだのは、エコール・ド・パリだったのではなかろうか。キスリング、モディリアーニ、パスキン、フジタ、スーチン。皆個性的な絵画で、その独自性は高く評価されている。そして大事なのは皆好きなように描いていることだ。輪郭線の有無などに悩んだりしないし、既に登場して久しい写真についても特に考慮したりしているように見えない。もはや絵画制作を束縛するものは何もなくなった。そんな時代に出現したのがエコール・ド・パリだ。
もちろん彼らにも特徴がある。それは人物画が多いことだ。それは彼らがいたパリは当時世界一の大都市、大都会であり、そこへ集まった人々、つまり人間に、彼らの興味が向いたのは当然と言える。
エコール・ド・パリの絵画を見ていると非常に勢いがある。堂々としているというより、鋭い切れ味がある。都会で生活する人を描くことを通して、近代都市そのものを描き出そうとしたかのようだ。
西洋美術評論家たちはエコール・ド・パリの評価に困るようだ。画家の評価は西洋美術史にどう組み込まれるかで決まるのが常だが、幻想画家(例えばモロー)同様、エコール・ド・パリをどう組み入れるべきかわからないからだ。
もういい加減、そうした進歩史観は止めたらいい。どう西洋美術史を発展させたか、なんて視点でしか評価できない時代は終わってしまった。エコール・ド・パリの出現によって、それ以降の画家は、そして彼らの描く絵は、西洋美術史そのものから解放され、束縛から自由になった。
つまりは評価基準の消失である。画家がパトロンから解放された先にあったのは、美術史からの離脱であった。そしてそれは西洋美術史の終焉でもあった。それをもたらしたのが、アンリ・ルソーであり、エコール・ド・パリである。それ故にエコール・ド・パリは偉大だったと思うのですが、どうでしょうか。
もちろん彼らにも特徴がある。それは人物画が多いことだ。それは彼らがいたパリは当時世界一の大都市、大都会であり、そこへ集まった人々、つまり人間に、彼らの興味が向いたのは当然と言える。
エコール・ド・パリの絵画を見ていると非常に勢いがある。堂々としているというより、鋭い切れ味がある。都会で生活する人を描くことを通して、近代都市そのものを描き出そうとしたかのようだ。
西洋美術評論家たちはエコール・ド・パリの評価に困るようだ。画家の評価は西洋美術史にどう組み込まれるかで決まるのが常だが、幻想画家(例えばモロー)同様、エコール・ド・パリをどう組み入れるべきかわからないからだ。
もういい加減、そうした進歩史観は止めたらいい。どう西洋美術史を発展させたか、なんて視点でしか評価できない時代は終わってしまった。エコール・ド・パリの出現によって、それ以降の画家は、そして彼らの描く絵は、西洋美術史そのものから解放され、束縛から自由になった。
つまりは評価基準の消失である。画家がパトロンから解放された先にあったのは、美術史からの離脱であった。そしてそれは西洋美術史の終焉でもあった。それをもたらしたのが、アンリ・ルソーであり、エコール・ド・パリである。それ故にエコール・ド・パリは偉大だったと思うのですが、どうでしょうか。











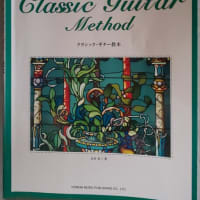





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます