
*よかったら「トラ・トラ・トラ!(映画)」(2015-08-22)、「第二次世界大戦映画DVDコレクションその1(Vol.1~Vol.9)」(2015-11-17) も読んでみて下さい。
第二次世界大戦映画DVDコレクション KADOKAWA
各巻1750円+税
*隔週刊火曜発売(全19巻で完結)
まず日本公開順に並べてみるとこうなります。
①頭上の敵機 (Vol.18)日本公開1950(昭和25)年
②サハラ戦車隊 (Vol.15)日本公開1951(昭和26)年
③空軍大戦略 (Vol.14)日本公開1969(昭和44)年
④レマゲン鉄橋 (Vol.12)日本公開1970(昭和45)年
⑤戦略大作戦 (Vol.17) 〃
⑥ミッドウェイ (Vol.13)日本公開1976(昭和51)年
⑦戦争のはらわた (Vol.11)日本公開1977(昭和52)年
⑧遠すぎた橋 (Vol.10) 〃
⑨最前線物語 (Vol.19)日本公開1981(昭和56)年
⑩父親たちの星条旗(Vol.16)日本公開2006(平成18)年
さてこの中で戦争映画好きでない人でも、映画ファンなら見逃せないのが⑧「遠すぎた橋」だ。「史上最大の作戦」(Vol.4)に負けず劣らずの戦争映像が展開される。正直驚いた。カメラも引いて撮っているので(これは遠くまで全体が映るわけでセットに自信がないとできない)、その圧倒的映像を堪能できる。見て得したと思う映画である。お薦めというよりもはや必見である。この映画はもちろん単独で楽しめるが、できれば「パットン大戦車軍団」(Vol.9)を先に見ておくとさらに楽しめると思う。
この⑧に比べると他は皆色褪せて見えてしまうが、簡単に感想を述べると、⑦は第二次世界大戦の雰囲気が出てないし、ドイツとソ連の兵士の見分けがつきにくいが、これはわざとそうしており、要するにこの映画は独ソ戦を借りてベトナム戦争の戦場を描いた反戦映画である。映画の最後にベトナム戦争のスライド写真が出てくることからもわかる。物語は途中で終わっているが、それもわざとやっている。ベトナム戦争の戦場を描き出せればいいわけで、それさえできれば物語など途中で終わっていてもいいというわけだ。
④はお金をかけてもいい映画は撮れない典型。脚本があまり良くない。余計な脇の話が多く、レマゲン鉄橋の攻防のみに絞るべきだった。逆に⑥は脚本が良く、物語の展開も速く、てきぱきとした映像でテンポよく見ることができる。「トラ・トラ・トラ!」(Vol.1)同様、歴史の記録フィルムとして制作されたと思われる。日米双方が客観的に描かれており、歴史的にアメリカの勝因(日本の敗因)がわからないため、映画でもそこははっきりさせていない。だから1本の映画として、つまり1つの物語として見るとすっきりしない。
③は実機を飛ばしているだけあって、空中戦の映像は臨場感があるものの、全体的には今ひとつ、中途半端な印象。この映画も歴史的にバトル・オブ・ブリテンのイギリスの勝因(ドイツの敗因)がわからないため、そこははっきりさせていないので、1つの物語として見るとすっきりしない。②は1943(昭和14)年に制作された反ナチプロパガンダ、つまり戦意高揚映画で、日本公開は戦後の1951(昭和26)年。1本の映画として楽しめる。よくまとまった映画だが、ご都合主義。そこをどう見るか、所詮は戦意高揚映画と見るか、ご愛嬌と見るか。
⑩「父親たちの星条旗」は「硫黄島からの手紙」(Vol.7)と合わせて硫黄島2部作となっている。2部作にしなくとも、第2部の「硫黄島からの手紙」を第1部の「父親たちの星条旗」に組み込むことはできたと思う。やはり「硫黄島からの手紙」は、1本の映画にするために、いろいろなエピソードをつけ加えて引き延ばしたと思う。ではなぜ2つに分けたのか。この2本の映画を見て、第1部は「消耗」、第2部は「悲惨」という2つのキーワードが浮かんできた。
第1部のキーワード「消耗」。圧倒的な物量で優勢な米軍だが、最前線にいる兵士たちは命がけで戦うため、肉体的にも精神的にも消耗していく。戦費調達のため、戦時国債購入キャンペーンに駆り出された兵士たちも、自分たちはこんなことをしていていいのかと悩み、消耗する。
第2部のキーワード「悲惨」。圧倒的に不利な日本軍は、食糧も物資も不足する中、生きては帰れないと知りつつ、祖国のために全力で戦う。最前線の兵士たちは、悲惨な状況で悲惨な戦いを強いられる。
この硫黄島2部作は戦争は悲惨な消耗戦であることを描いたのだと思う。
⑤はユーモアたっぷりの戦争風刺映画。ちょっとばかばかしい設定で戦争風刺をやってのけてくれる。①は一指揮官の苦悩を描いた映画で、「パットン大戦車軍団」(Vol.9)同様、狭義には戦争映画に含まれない。映画の最後12分間が、この映画を価値あるものにしていると思う。⑨は監督自身の従軍経験が基になっているため(脚本も監督が書いた)、興味深いところが多々ある。戦争映画好きは見ないと駄目でしょう。
今回で第二次世界大戦映画DVDコレクションも終わってしまうのだが、今回のお薦めは何といっても⑧「遠すぎた橋」(Vol.10)。これに尽きるが、もう1つ加えるとすれば「最前線物語」(Vol.19)になる。
付)最後に「第二次世界大戦映画コレクションその3(まとめ)」を書いて終わりにしたいと思います(次の記事がそれです)。
第二次世界大戦映画DVDコレクション KADOKAWA
各巻1750円+税
*隔週刊火曜発売(全19巻で完結)
まず日本公開順に並べてみるとこうなります。
①頭上の敵機 (Vol.18)日本公開1950(昭和25)年
②サハラ戦車隊 (Vol.15)日本公開1951(昭和26)年
③空軍大戦略 (Vol.14)日本公開1969(昭和44)年
④レマゲン鉄橋 (Vol.12)日本公開1970(昭和45)年
⑤戦略大作戦 (Vol.17) 〃
⑥ミッドウェイ (Vol.13)日本公開1976(昭和51)年
⑦戦争のはらわた (Vol.11)日本公開1977(昭和52)年
⑧遠すぎた橋 (Vol.10) 〃
⑨最前線物語 (Vol.19)日本公開1981(昭和56)年
⑩父親たちの星条旗(Vol.16)日本公開2006(平成18)年
さてこの中で戦争映画好きでない人でも、映画ファンなら見逃せないのが⑧「遠すぎた橋」だ。「史上最大の作戦」(Vol.4)に負けず劣らずの戦争映像が展開される。正直驚いた。カメラも引いて撮っているので(これは遠くまで全体が映るわけでセットに自信がないとできない)、その圧倒的映像を堪能できる。見て得したと思う映画である。お薦めというよりもはや必見である。この映画はもちろん単独で楽しめるが、できれば「パットン大戦車軍団」(Vol.9)を先に見ておくとさらに楽しめると思う。
この⑧に比べると他は皆色褪せて見えてしまうが、簡単に感想を述べると、⑦は第二次世界大戦の雰囲気が出てないし、ドイツとソ連の兵士の見分けがつきにくいが、これはわざとそうしており、要するにこの映画は独ソ戦を借りてベトナム戦争の戦場を描いた反戦映画である。映画の最後にベトナム戦争のスライド写真が出てくることからもわかる。物語は途中で終わっているが、それもわざとやっている。ベトナム戦争の戦場を描き出せればいいわけで、それさえできれば物語など途中で終わっていてもいいというわけだ。
④はお金をかけてもいい映画は撮れない典型。脚本があまり良くない。余計な脇の話が多く、レマゲン鉄橋の攻防のみに絞るべきだった。逆に⑥は脚本が良く、物語の展開も速く、てきぱきとした映像でテンポよく見ることができる。「トラ・トラ・トラ!」(Vol.1)同様、歴史の記録フィルムとして制作されたと思われる。日米双方が客観的に描かれており、歴史的にアメリカの勝因(日本の敗因)がわからないため、映画でもそこははっきりさせていない。だから1本の映画として、つまり1つの物語として見るとすっきりしない。
③は実機を飛ばしているだけあって、空中戦の映像は臨場感があるものの、全体的には今ひとつ、中途半端な印象。この映画も歴史的にバトル・オブ・ブリテンのイギリスの勝因(ドイツの敗因)がわからないため、そこははっきりさせていないので、1つの物語として見るとすっきりしない。②は1943(昭和14)年に制作された反ナチプロパガンダ、つまり戦意高揚映画で、日本公開は戦後の1951(昭和26)年。1本の映画として楽しめる。よくまとまった映画だが、ご都合主義。そこをどう見るか、所詮は戦意高揚映画と見るか、ご愛嬌と見るか。
⑩「父親たちの星条旗」は「硫黄島からの手紙」(Vol.7)と合わせて硫黄島2部作となっている。2部作にしなくとも、第2部の「硫黄島からの手紙」を第1部の「父親たちの星条旗」に組み込むことはできたと思う。やはり「硫黄島からの手紙」は、1本の映画にするために、いろいろなエピソードをつけ加えて引き延ばしたと思う。ではなぜ2つに分けたのか。この2本の映画を見て、第1部は「消耗」、第2部は「悲惨」という2つのキーワードが浮かんできた。
第1部のキーワード「消耗」。圧倒的な物量で優勢な米軍だが、最前線にいる兵士たちは命がけで戦うため、肉体的にも精神的にも消耗していく。戦費調達のため、戦時国債購入キャンペーンに駆り出された兵士たちも、自分たちはこんなことをしていていいのかと悩み、消耗する。
第2部のキーワード「悲惨」。圧倒的に不利な日本軍は、食糧も物資も不足する中、生きては帰れないと知りつつ、祖国のために全力で戦う。最前線の兵士たちは、悲惨な状況で悲惨な戦いを強いられる。
この硫黄島2部作は戦争は悲惨な消耗戦であることを描いたのだと思う。
⑤はユーモアたっぷりの戦争風刺映画。ちょっとばかばかしい設定で戦争風刺をやってのけてくれる。①は一指揮官の苦悩を描いた映画で、「パットン大戦車軍団」(Vol.9)同様、狭義には戦争映画に含まれない。映画の最後12分間が、この映画を価値あるものにしていると思う。⑨は監督自身の従軍経験が基になっているため(脚本も監督が書いた)、興味深いところが多々ある。戦争映画好きは見ないと駄目でしょう。
今回で第二次世界大戦映画DVDコレクションも終わってしまうのだが、今回のお薦めは何といっても⑧「遠すぎた橋」(Vol.10)。これに尽きるが、もう1つ加えるとすれば「最前線物語」(Vol.19)になる。
付)最後に「第二次世界大戦映画コレクションその3(まとめ)」を書いて終わりにしたいと思います(次の記事がそれです)。











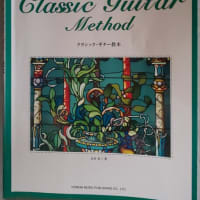





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます