昨日の夜でようやく木版画制作全般も把握した。私がやりたいのは一版刷りなので、多色刷り主版法(浮世絵)のような大変さはない。
調べていてちょっと困ったことがあって、彫刻刀は主に4種類(版木刀、平刀、丸刀、三角刀)あるのだが、これの使い分けをきちんと説明してくれるところがない。ほぼ唯一といっていいのが、武蔵野美術大学造形ファイルの彫刻刀という項目での説明文である(ネット検索)。これで私もようやく納得できた。
意外だったのは、銅版画でいうインクは、木版画では市販のチューブ入り水彩絵具を使うということだった。へえーって感じ。私は透明水彩絵具を使いたい。普段透明水彩画を使っているということもあり、非常に親しみを感じてしまう。
銅版画同様、木版画も奥が深い。個人的には木版画の方がはるかに奥が深いと思う。木版なので彫るときに細工がしやすいし、人間の手でバレンを使って行われる刷りにも工夫が凝らせそうだ。
さて問題は道具の置き場だ。どこに置くのか。やっぱり背の高いカラーボックスを買って、物を置ける棚を増やすしかなさそう。
カラーボックスか。いよいよ本格的に探すことになりそうだ。
調べていてちょっと困ったことがあって、彫刻刀は主に4種類(版木刀、平刀、丸刀、三角刀)あるのだが、これの使い分けをきちんと説明してくれるところがない。ほぼ唯一といっていいのが、武蔵野美術大学造形ファイルの彫刻刀という項目での説明文である(ネット検索)。これで私もようやく納得できた。
意外だったのは、銅版画でいうインクは、木版画では市販のチューブ入り水彩絵具を使うということだった。へえーって感じ。私は透明水彩絵具を使いたい。普段透明水彩画を使っているということもあり、非常に親しみを感じてしまう。
銅版画同様、木版画も奥が深い。個人的には木版画の方がはるかに奥が深いと思う。木版なので彫るときに細工がしやすいし、人間の手でバレンを使って行われる刷りにも工夫が凝らせそうだ。
さて問題は道具の置き場だ。どこに置くのか。やっぱり背の高いカラーボックスを買って、物を置ける棚を増やすしかなさそう。
カラーボックスか。いよいよ本格的に探すことになりそうだ。











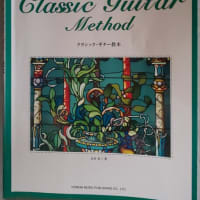





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます