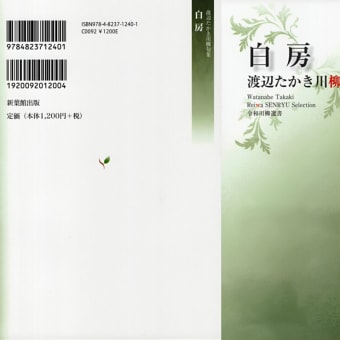□本日落語一席。
◆春雨や雷蔵「ざこ八」(NHK-Eテレ『日本の話芸』)。
東京渋谷NHK放送センター内スタジオ、令和3(2021)年9月24日収録。
たちどころに梗概を思い出せないほど、ずいぶん久しぶりに聞く噺だなあと。ちょっと記録を調べてみると、2011年以後は一度も聞いていないと知る。最後に聞いたのは、2009年の入船亭扇橋だったと確認。ちなみに、これも『日本の話芸』だった。十二年間も聞いていなかったわけだ。してみると、「NHK東京落語会」でも、十二年間誰も演っていなかったということになるのだろうか。
また、その前は、レコード・CD等の昭和の音源を除けば、2006年に笑福亭松喬で聞いている。このあたりの年代だと、まだしばしば「ざこ八」は高座にかけられていたのだろうか。
確かに、この噺はちょっと陰惨な内容を含んでいるので、笑いをとりたい落語家にとっては、あまり演りたくないネタなのかもしれない。
久しぶりに聞いたので、あらためて川戸貞吉『落語大百科』を繙いて、ちょっと確認してみた。そこに書かれていた梗概を読むと、嗚呼、そうだったなと思い出した。今日聞いた雷蔵の「ざこ八」は、本来の型を短くしたものだった。最後の四分の一ほどがカットされていた。確かにその部分は、噺の展開的にちょっとむりがあるかもしれない。もしかして、この四分の一を嫌って、多くの落語家はこれを敬遠したのだろうか。
もっとも、川戸に言わせると、ここより前の四分の三の部分でも、「いかにも作り過ぎといった感じで……ついていけない」内容というようだ。同意。かたがた演りにくい落語なのだな。しかし、それをこの雷蔵は、すこし演りやすくなる道を作ったのではないだろうか。もっと他の落語家もチャレンジして、より聞きやすい噺にならないだろうか。
◆春雨や雷蔵「ざこ八」(NHK-Eテレ『日本の話芸』)。
東京渋谷NHK放送センター内スタジオ、令和3(2021)年9月24日収録。
たちどころに梗概を思い出せないほど、ずいぶん久しぶりに聞く噺だなあと。ちょっと記録を調べてみると、2011年以後は一度も聞いていないと知る。最後に聞いたのは、2009年の入船亭扇橋だったと確認。ちなみに、これも『日本の話芸』だった。十二年間も聞いていなかったわけだ。してみると、「NHK東京落語会」でも、十二年間誰も演っていなかったということになるのだろうか。
また、その前は、レコード・CD等の昭和の音源を除けば、2006年に笑福亭松喬で聞いている。このあたりの年代だと、まだしばしば「ざこ八」は高座にかけられていたのだろうか。
確かに、この噺はちょっと陰惨な内容を含んでいるので、笑いをとりたい落語家にとっては、あまり演りたくないネタなのかもしれない。
久しぶりに聞いたので、あらためて川戸貞吉『落語大百科』を繙いて、ちょっと確認してみた。そこに書かれていた梗概を読むと、嗚呼、そうだったなと思い出した。今日聞いた雷蔵の「ざこ八」は、本来の型を短くしたものだった。最後の四分の一ほどがカットされていた。確かにその部分は、噺の展開的にちょっとむりがあるかもしれない。もしかして、この四分の一を嫌って、多くの落語家はこれを敬遠したのだろうか。
もっとも、川戸に言わせると、ここより前の四分の三の部分でも、「いかにも作り過ぎといった感じで……ついていけない」内容というようだ。同意。かたがた演りにくい落語なのだな。しかし、それをこの雷蔵は、すこし演りやすくなる道を作ったのではないだろうか。もっと他の落語家もチャレンジして、より聞きやすい噺にならないだろうか。