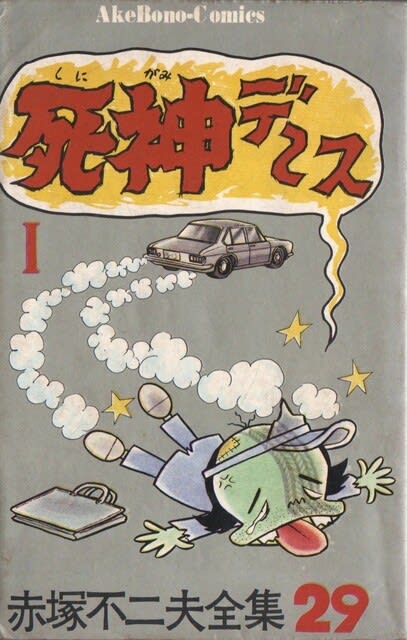東大安田講堂の陥落、70年安保闘争における一般学生の離反等、引き潮の如く沈静化の一途を辿った新左翼運動は、1970年代初頭、各セクトによるイデオロギー上の紛糾を抱える中、その後分裂や党派再編を恒常化させ、熾烈な武装闘争へと活路を見出してゆく。
そんな激動の時代の最中、滝沢から、赤塚漫画、それも少年向けギャグ漫画で、ポリティカル・ナンセンスなるジャンルを開拓出来ないかという打診があり、実現化に至ったのが、短期連載という形でシリーズ化された『狂犬トロッキー』(「別冊少年マガジン」71年1月号~9月号)である。
ロシア革命の史実をモチーフに、ソ連共産党最高指導者・ヨシフ・スターリンの最大の宿敵であったレフ・トロツキーの革命的英雄神話を、現代日本の、それも犬の世界に挿げ替え、観念の象徴としてカリカチュアしたピカレスクロマンだ。
主人公のレオン・トロッキーは、ロシア産ボルゾイ種という誇り高き血統を持つ犬であると、自らを称するが、真っ赤な嘘だった。
ジステンバーを患い、そのため、鼻が全く効かない野良犬として生まれ落ち、飢え死に寸前のところを、大学の哲学教授・蹴毛豪留氏に拾われ、飼い犬として生活していた。
だが、トロッキーは惰眠を貪る用なし犬。論理学的立場からの追求を名目に、ドイツ観念論を専攻する蹴毛から、いつも虐待を受けていた。
悔しさを募らせたトロッキーは、「人間の本質なるものがその書物にある」と嘯く蹴毛を凌駕する存在になるべく、蹴毛所蔵の万感の書物を全て読破する。
そして、単なる書物の受け売りでしか全てを語れない蹴毛を圧倒する思想と哲学をもって論破し、遂には、蹴毛家を解放区として、犬仲間のスターリン、マルクス、レーニンと共に、制圧下に置く。
トロッキーは、犬の主体性回復を訴え、仲間達と革ワン連を結成。陸上自衛隊の総監室を占拠し、前年(1970年)の「三島由紀夫事件」と同様に、総監を人質に取るやいなや、自衛隊員を集結させ、バルコニーに立ち、国家の番犬からの脱却を促す。
だが、この革命は敢えなく挫折に終わってしまい、トロッキーらは捕獲員に捕らわれ、野犬収容所に移送されてしまう。
しかし、こんなことでめげるトロッキーではなかった。
トロッキーは、野犬収容所で同志を募り、叛乱を起こし脱走。再び革命の狼煙を上げるが、ある同志の壮絶な裏切りにより、その革命は、今まさに阻止されようとしていた……。
*
本作『狂犬トロッキー』の連載中、折しも、藤子不二雄Ⓐの『劇画 毛沢東伝』が話題を集めていた頃で、宮谷一彦が『性蝕記』をはじめとする、性と政治に彩られた珠玉の作品群を発表し、カリスマ劇画作家としてカルト的な人気を確立したほか、山上たつひこや真崎守といった新進気鋭の作家達も、『光る風』、『共犯幻想』等、政治的メッセージを含有した力作を相次いで執筆するなど、あらゆる芸術分野において、政治的テーマを閑却出来ない時代の空気感が、漫画界全般にも大きな影響を及ぼしている、まさにそんな時代であった。
従って、赤塚が滝沢を原作者に迎え、『狂犬トロッキー』のような政治色濃厚な連載を立ち上げたのも、そうしたポリティカルの季節固有の時代的必然性が、背景として根強く存在していたからなのだろう。
だが、『狂犬トロッキー』の作画は、当初は赤塚が受け持っていたものの、その後三ヶ月間、自身のオーバーホールを目的に渡米したため、途中から、フジオ・プロ、チーフスタッフの斎藤あきらにバトンタッチされる。
そのためなのか、ラストシーンが、中途半端なまま投げ出されたような格好となり、ドラマとして、もやもやとした燻りを残しての結末を迎えてしまったことが、非常に悔やまれるところでもあった。
とはいえ、『狂犬トロッキー』は、全編に渡り、アグレッシブなアクションを目一杯に詰め込んだ緊迫感と、血飛沫が吹き出すスプラッター描写の毒々しさによって隈取りされており、そのダークさを底光りさせた震慴のミクスチャーは、初めて本作を読む読者を、今尚驚倒させてやまない。
また、革命はお預けという、足踏み状態のまま迎えた、唐突のラストシーンは、幾分カタルシスに欠けるものの、それでも、矢継ぎ早の展開で、一気に最後まで読ませてしまうその疾走感は、非の打ち所が一切なく、ドラマの躍動感を弥増しに高めてゆく。
そう、本作の生命線とは、このスピード感であり、テンポの良いコマ運びこそが、ドラマに跳躍を与える原動力となるのだ。
そして、赤塚漫画独特のアトラクティブな文体は、この流麗なコマ運び、即ち構成力にこそあり、滝沢が持つ特殊な作家性を血肉化し、至妙の間合いでもって、オリジナル同様に昇華している点は、まさにグレイトとしか言い様がない。