




































(一) 浮橋 Ukihashi
机上の正面には書斎の歴史が刻まれている。
他に何も飾りのない白壁には一枚のモノクローム写真が一つだけ掲げられ、漆の和額に入れ、入れ子の赤と白と黒の3本ラインで写真を囲んでいた。見ようでは赤い慶事の水引、黒い弔事の水引にも思える。
額縁のデザインはそれだけで何事かの吉凶を暗示させるのだが、あとは額の下にある銀の小さなプレートに黒字で「 ほのほのほ 」という標題らしき文字が、妙に意図知れず特徴といえば特徴なのだが、それにしてもじつに楚々とした趣きの額装なのだ。
しかし、その一枚のモノクローム写真こそは、雨田博士が書斎で何を考えてきたかのすべてを物語っていた。
「 6人は向かって右端から順に、阿部清太郎、雨田虎次郎、知花圭一、五流誠子、名嘉真いと 華代・・・・・ 」
と、裏書にそう記されていた。撮影日は明治24年8月とされている。
右端の「明笛」を手に持った老紳士が阿部清太郎で、どうやらまだ、頭にはチョンマゲを結っている。つぎの「月琴」を弾いてるヒゲの人物が雨田虎次郎。次の年若い青年の持っているのは、おそらく「提琴(テイキン)」だと思われるが、そであれば現在の中国楽器で言うと「板胡(バンフー)」の類となる。五流誠子という女性の楽器は「唐琵琶(トウビワ)」。これは雅楽の琵琶や、薩摩・筑前よりは現在中国の「琵琶(ピーパー)」に近いものでフレットは14本、撥(バチ)ではなく,指に月琴のと同じような長い義甲をつまんでいるのが、写真からも見てとれる。次の古風な老婦人が琉球姓らしき名嘉真いと、持っている楽器は「阮咸(ゲンカン)」である。最後の華代という若い女性の前にある楽器は、一見日本の琴のようだが、猫足が四本(琴は2本)、琴柱の位置も和琴とは少し違うし、さらに糸弦が琴と違って左右のブリッジにピン止めされているが、これは「洋琴(ヨウキン)」だと思われる。
「 するとこれは、明清楽(みんしんがく)の演奏風景ということになるが・・・・・ 」
明清楽(みんしんがく)とは、明楽つまり江戸時代中期に明朝末期に中国南方(福建を中心とした地方)から日本へもたらされた唐宋の詩詞を歌詞とした音楽と、清楽つまり江戸時代後期に中国南方からもたらされた俗曲を中心とする音楽の、両者を総じて呼ぶ際の用語である。両者は明確に区別されるべきであるが、明治初年に清楽が明楽を吸収しつつ拡大したこともあって、一般的にあわせて明清楽と呼ばれる。
この写真と額装をみたとき丸彦は、人間には分からないであろうが、すでに猫のわれわれは、誰かと接していたり猫前や人前にいたりするとき、何かのきっかけで顔を赤らめたり、上気したり、冷や汗をかいたりすることをよく知っている。この写真の反応はあきらかにフィジカルな反応なのだが、そこには微妙なメンタルなものが関与していることが感じとれた。どうやら猫の、われわれの体にはメンタリティの具合を厳密にフィジカルな反応に切り替える装置が機能して備えられているようなのだ。
「 ほ・の・ほ・の・ほ 」
この表題の何とも不可思議をみつめたとき、それだけでも充分に不気味だが、博士が突くステッキの音にその不可思議の響きが重なると、丸彦はどうしてか眼がふと血走った。人間はねじれている、生体のどこかしこもねじれている、生命の本質はねじれであろう、直感的にそんな写真であることを悟ったのだ。





虎哉が泉涌寺の参道をみて、そうした遠い眼をするのには、香織に係わることで少々気にかゝる仔細があった。
花雪という芸子が、九州長崎の造船界の有力者陣内剛蔵に身請(みうけ)されて、泉涌寺付近の別宅に囲われ暮らし始めたのは六十年も前のことだ。
「 虎哉の養母であったお琴は、京にくるたびに、同郷の剛蔵に呼ばれちょいちょい別宅に遊びに行っていたという・・・・・ 」
そんな話を小生は聞いた。
その花雪はやがて、妊娠(みごも)って戦争直前に京北の花背(はなせ)辺りに移り住み暮らすようになる。同じころお琴も疎開騒ぎに紛れて自然と別宅から足が遠のいた。そして戦争が終わってお琴が奈良吉野の疎開先から京都へ行ってみたときは、花雪はすでに労咳(ろうがい)で死んでいた。女児を産んで二年目に死んだという。さらにその三年後に花雪の産んだ児が、当時、泉涌寺近くの別宅に出入りしていた、清原増二郎という、これもお琴とは遠縁の男に養われていたと聞いた。お琴はこの増二郎を探したが所在は不明だったという。
虎哉も確かにそう聞かされていたのだが、これは戦後四年してお琴が知りえた話なのだ。
「 養母お琴がそう言い遺したことが事実であるのならば、その児の生まれ年から存命であるとして逆算すると、花雪という女性は60歳前後のはずである。増二郎の子と名乗る香織は17歳であるから、増二郎が養っていたという赤児とは、さらに香織との関係とは・・・・・ 」
この丸彦の知る香織の母親に関わる消息は、いずれも亡きお琴からの聞伝でしかなく、いまさら確かめ難きことであるのだが、虎哉は泉涌寺の山ふところとなる月輪山(つきのわやま)や泉涌山の空をあおぎみながら遠い眼をしてその消息の彼方を泛かばせていた。

「 あもなるや おとたなばたの うながせる たまのみすまるの あなだまはや みた 」
鴨川を越えて眼に写す西の冬空に想い重ねれば、どうしてもそこに映えてくる一つの古い歌があった。虎哉は胸の内ポケットに忍ばせている「 ひなぶり 」という古びた筆文字の書付をコートの上から手に押えては枯れて薄暗く広がる西の彼方をじっと見た。
「 尼にするいうて驚かさはるさかい、うち、何や気色わるいわ 」
と、白い顔を仄かに青く臼づいて香織はそっと俯いていた。
「 尼さんは・・・・・、そんなに薄気味悪いものなのかい・・・・・? 」
「 そうやおへん。せやけど、うち、罪ほろぼしせなあかんこと何ィ一つしてへん思うんや 」
香織は暈(かさ)をかぶった太陽がようやく雲の切れ間から顔をのぞかせるように、しかし少しはまだ戸惑いを口に籠らせた声でそういうと、かすかに睫毛(まつげ)がうるむ顔をさせて虎哉をぼんやりとみた。
「 この娘の眼には、尼の修行が、罪ほろぼしの生活として映っているのか!。出家とは、そう映るのであろうか。しかし、それはそれでいゝ。香織がどう思おうが、そんなことは人それぞれの自由だ。さて・・・私はどう応え返せばいゝ。あゝ、たしかに本当だね、かさねは罪ほろぼしなどする必要はないからね・・・・・ 」
と、素直に肯定してやろうとするそんな優しい言葉が、虎哉の喉もとまで出かゝった。
だが虎哉は、それをじっと堪こらえた。
以前の虎哉の気性なら、忍し殺して黙っていられる筈はなかった。そこは肯定してその場を適当に済ませ終えるか、あるいは少しの反論などしただろう。だがそれは気勢にも柔軟であった昔のことで、今は老いの疲れがそうさせるのか、はからずとも虎哉は、すでに円満に済ませることすら面倒で、投げやりたいような妥協癖にちかいものを心の中に抱くのであった。
しかし、泉涌寺の坂に至る道は人生のそれと等しく、山あり谷ありであるらしい。
この坂に、世のくびきから離れ、煩悩と対峙しては、いくばくかの悟りを求めようとする、そんな覚悟の女僧らが歩いた影がある。その尼を罪ほろぼしと存外にあしらわれると、それはやはり穏やかではない。
「 比丘尼(びくに)とは仏門の闇夜にゆっくりと炸裂してのぼり行く、この世からはそう見せる、あの世の花火なのだ・・・・・ 」
と、胸の内でそう想う虎哉は、香織の言葉を聞いた耳朶(みみたぶ)に、かすかな冷や汗を感じた。



「 東福寺駅前から泉涌寺の仏殿までは、往復でおそらく3キロほどあるだろう。この膝は、もう自力でそれだけの距離をあるくことに耐えきれやしない 」
そう往(ゆ)きあぐねると、虎哉はやはり口を堪え、何か妙にもの哀しく、細い一本の老木のように立ちつくしていた。
「 冷やっこいなぁ~。そないじィ~ッとツッ立つてはって、奈良ァ、いつ着きますねんかいなァ。あゝ、しゃ~ないなぁ~・・・。とんま・ひょうろく玉・おたんちん・のろま・すかたん・うすのろ・ぼんつく・とんちき・おたんこなす、これ皆、盆暗(ぼんくら)いうんやわ。そないしてはる老先生ィ、えろう盆暗やわ・・・・・ 」
と、声には出せそうにない言葉が連なって湧いて出る。北風の中でそうして寂しく棒切れのようにぼ~っと立っていられたら居たゝまれない。奈良までは未だ南へ随分と距離がある。香織にはそんな虎哉の姿が、朝起きようとしてまだ寒いからと、蒲団(ふとん)から首だけ出している老亀のように思われた。
「 一体、どないしはるンや・・・・・! 」
と、そう急かされた虎哉はこの場でさらに一歩踏み込めば、香織は苦しむことになるのかも知れないとも思える。しかしその少しの苦痛がやがてはこの娘の歓びとなることもある。そのいずれかをどうするか迷っていた。仔とは、やはり母子一つの流れを断ち切れぬものだ。
「 もし・・・・・、その苦しみが、香織の幸福へと繋がっているのなら、苦しんでみるのもよいが、真実にうちのめされることもある。さて、どうする・・・・・ 」
漠然としてはいられない。駒丸扇太郎と落ち合う約束はしたものゝ、やはり厄介なところでバスを降りてしまったと思った。
「 かさね、東福寺駅へ向かうが、少し西へ出て下ることにしようか・・・・・ 」
約束の時間までにはもう少しある。虎哉は少し思案する時間が欲しかった。
こゝにきて気の抜けた遺言では、遺されて手にする側はとんだ生涯の迷惑となる。
「 何や寒空を、まだ歩かはる気ィかいな・・・・・ 」
泉涌寺道の少し北に鳥辺野という陵地がある。そこは一条天皇皇后定子(ていし)以下六つの火葬塚で藤原氏時代の貴族らの埋葬地だった。この鳥辺野と泉涌寺は細い山路で結ばれて密接である。泉涌寺は古くから皇族の香華院(こうげいん)、つまり菩提所とされ御寺(みでら)とも呼ばれた。
「 詮子(せんし)と・・・、定子とが・・・、同じ軒下で眠れる。あの世とは、そうしたところなのか! 」
一度、じっと北へ目配せした虎哉は、すっとステッキを西に返した。
一条天皇の母上で円融天皇の皇后が詮子である。定子には叔母にあたる。その詮子は、定子の兄の藤原伊周(これちか)を関白にさせなかった「大鏡」ではそういう意地悪の人で、定子には姑(しゅうとめ)でもあるが、詮子はその定子まで憎み終えた。亡くなってみると、その二人が今一つ墓所に葬られて眠る。いや眠らされているのだ。死人に口無しというが、その死人の小言とはじつに怖く密かである。
「 近くて遠きもの・・・、思わぬ親族はらからの仲・・・か 」
と、思う虎哉は泉涌寺、鳥辺野、さらにその北にある清水寺までの長々とした音羽山へといたる細い山路を想い泛かべてみると、いかにも草子(そうし)のいう眼差しが「をかし」かった。
泉涌寺や鳥辺野は、敗者によって埋められた場所である。
清少納言(せいしょうなごん)は定子の御陵近くに住んでいたらしいから、この道を通って清水寺に詣ったのだと思う。虎哉がそうした清少納言の影を追いかけてみると、当時の視線で描かれたはずの枕草子(まくらのそうし)には定子の没落の背景が触れられていない。これは、むしろ触れようとはしなかったから、第段のはしばしに筆を曲げたとみとめられる辻褄の悪い痕跡がある。曲げねばならぬ痕跡は行間の暗がりにある。この時代、藤原氏は同族相はむ暗闘を演じ、陰険でしかも徹底した抗争が、王朝のきらびやかな表面とはうらはらに、裏面では強かに渦巻いていた。
追いやられる定子に宮仕えする清少納言は、藤原道長が存命であったがゆえに、世相には無関心を装うかに意を忍殺し、眼を伏せ、口をつぐみ、筆を曲げている。それでは真の「ものの哀れ」ではない。だが曲げさせられた怨念の哀れは行間に宿る。
虎哉はそんな敗者の場所を背に感じながら、また寒々とした参道口を西へと歩いた。この地域は敗者という死体の吹溜りなのだ。


「 老先生、歩かはるんやしたら、お薬のみはらんと・・・・・ 」
右足の関節が伸びたまゝ、歩き辛そうに虎哉は踵(かかと)を地に引ひて歩く。それもよく見れば下半身はかすかな震えをともなわしていた。後ろから支えようとした香織は、居たゝまれなく、サッと滑るようにして虎哉の脇に肩口を差し入れて下支えすると、それでもステッキを突こうとする虎哉に労わる眼差しでいった。佳都子の顔が過ぎるが、このまゝ放置するとその震えはしだいに痙攣(けいれん)することを香織は知っている。口元は柔らかくしキッと眼だけは固くした。
「 ぶゞな、ちょっと熱いさかい、そろそろと飲んでおくれやし。ほしてこれ赤いの一錠、白いの三錠、黄色いの一錠、そして粉ァのカプセル一錠やわ。ほんに寒いし、先にぶゞ一口含んでうがいしとくれやす。口ィ温こうなる。そして一気ィに呑まんと、一粒ずつやわ 」
香織はそういゝながら虎哉のステッキをさっと引き取ると、小脇に挟み、ポシェットのクスリ袋から六粒の錠剤をつまみ出し、それを手渡しつゝ左手にカップを持たせ、常備した保温ボトルから白湯さゆを手際よく注いだ。

前に虎哉が引き出した歌は、長い療養生活からようやく日常生活へ回復したころに祇園の置屋女将佳都子の祖母清原茂女がつゞり遺した一筆である。彼女は随筆『ひなぶり』にこの歌に題する内容を記した。その中に清原文代という実娘の話がある。それによると文代は1920年(大正9年)12月3日付けで療養先、佐賀県小城郡古湯温泉の旅館にて密かに産み落とされた。
そして文代は旅館の主人に引き取られ扶養されるとある。
「 古湯温泉の清原茂女と文代・・・、そして長崎の陣内剛蔵との関係・・・・・ 」
虎哉はこの三人の人影を眼に結ばせていた。
「 自分という小川に清らかな泉がゆっくりと湧き出ていれば、そこへ向こうから濁水が入ってくることはない・・・・・ 」
風邪で大熱をだしたとき枕元でそうさゝやかれて虎哉は川にされた。
香織から薬を飲むよう促された虎哉は、ふとそんな母菊乃の言葉を想い起こした。
清泉には緩まぬ湧出があるのだ。人の血流もまた似たようなものである。年が明けても去年からの続きのようなもの、何かの「残念」や「無念」というものが、あいかわらず蟠(わだかま)っていた。虎哉はしだいにそんな思いを強めると、もはや崩れかけた塀の背後にでも自身が居るようであり、弛緩して血流の悪い体に、始末の悪い焦げ臭い匂いを感じた。
悩ましい期間が長引くと、自分の才能や境遇を疑い始め、さらには身近な者を疑うようになる。そのうち自分を失う。自分を失えば、人を失う。人を失えば、物を失う。しかし悩んでくよくよ、ぐずぐずしているときは、このことがまるで分からない。どうやら体調も同じなのだ。幼い耳奥について残る、こうした戒めの言葉も、能(よく)した母の抄言であった。
厳格であったその母に言わせれば、やはり精進の足りぬ心身の血流が悪いのであろう。最近、ふわふわとした遊仙感覚のような幽かな影に危うさを覚えて不安なのである。虎哉は香織から渡された錠剤を、一錠ごとていねいに口にふくむと、しずかに白湯を流し込んだ。そうして処方に委ねたそのまゝの姿勢で、ステッキに両手をかけていると、辛うじて自分の心が保たれているようにある。
すると一瞬、どうしたことか自分をみて頷く母の影が泛かんでみえた。
虎哉はしずかに黙祷(もくとう)でもするかのごとく眼を閉じていた。鳥辺野があり、その南の蛇ヵ谷(じゃがたに)から深草にかけての光景は、虎哉にとって一つの原郷のようなものだ。
蛇ヵ谷は大正期後、五条坂界隈が手狭になり、多くの陶工が工房の地を拓くために移り住んだ谷である。
何かと気随であった母菊乃はよくこの蛇ヵ谷を訪ねていた。泉涌寺の帰りにはいつも細く淋しい山路を北に道草でもするようにして、工房をめぐり、鳥辺野の墓地を詣でて奈良へと帰るのである。幼い虎哉の眼に、その名からして妖気なそれらは薄暗く怖い道草であった。だがそうした怖い墓場続きの道にも艶やかな母の面影が一つある。

母は泉涌寺から蛇ヵ谷、鳥辺野墓地を廻るときは決まって同じ絵柄の着物を着た。源氏香紋である。さも占いか縁起でも担ぐかのようにその華やかな紫地に黒符の香紋を連ねた服を着ていた。






「 かさね・・・、少しは源氏物語を読んでいるのかい?・・・・・ 」
と、脇にいる香織に、虎哉はふとそんなことを訊いてみたくなった。その香織は、どうやらクスリの量が気がかりのようで、錠剤の残り数をかぞえている。
一昨年の夏、香織が別荘に住み込むようになって半年を過ぎたころのことだが、誕生日のプレゼントに神田神保町の古書店から源氏物語を取り寄せて、香織にそれを贈ったということを君子から聞いていた。
母菊乃が幼い虎哉に語り聞かせた深草とは、記憶の中にしかない「けものみち」のように滲み出してきて、百夜通いの深草(ふかくさ)の少将(しょうしょう)や無名抄のうずら鳴く里などは、それでもう、存分の気分になった古典なのである。また小野小町(おののこまち)ほど、有名でありながら、謎に包まれている女性はいないのだが、道草のついでに母菊乃が語り聞かせた紫式部も幼き耳にはまことに謎多き女なのだ。そんな女が書き遺した「源氏物語」とは、到底、男の興味の外にしか置かれないような物語にしか思えないのだが、しかし、女性の嗜好とは存外侮れない人間の本質に眼を輝かせるものらしく、母菊乃が若くしてそうであったことを思うと、はたして若い香織がどう感じるのかは随分と興味があった。
「 へぇ~・・・、読ませてもろてます。君子はん、京都に生まれたんなら、一度は読みィな、そないいゝはった。そんなんで貰うた本やさかい、大事ィに読ませてもろてます 」
突飛な問い掛けにもそう答えると香織は、自分の部屋に小さくとも人生初の本棚を密かにあつらえ、そこに堂々と整列させて並べた大長編の書を泛かべた。揃えた束を眼に撫でると御利益がでる。それはもう香織にとって本棚は、天照(あまてらす)の座る神棚のごとくあった。
「 そうか・・・・・、で・・・・・、どれほど読みこんでみた? 」
この物語は男の巷(ちまた)という色眼にはさまざまな憶測を呼んできた。
「 どれほどや、そういゝはッてもなぁ~・・・。貰うたの一昨年の七月やから、もう三、四十回は読んでますやろか・・・・・ 」
とは答えても読めばますます誰かと話したくなる本ということだけは感じるが、他のことは混沌としてよくは分からない。
「 ほう・・・・・、そんなに読み返したのか! 」
「 へぇ~・・・。せやかて、うちには、ほんに難しい本やわ。読み始めたら、最初えろう面白い物語やと思いましたんやけど、何度か読み返すうち、そないしてたら、うち、えらいうっかりやした。読むほどに、えろう難しなって、そのうち、うちにはよう分からへんなった。時々、君子はんに分からんとこ習うてみるんやけど、そやけど、よう分からしまへん。せやけど・・・・・あの本、嫌いやあらへん。分からへんでも、折角、君子はんが呉れはッた本や思うと、何やうちそれだけで嬉しいんや。せやから、うち、大切に読も思てます。少し分からへんけど、あれ、何回も読みたくなる本やわ・・・・・ 」
そう香織は答えたが、虎哉が思うには、香織の年齢がそう言わせる意図が手にとるようにある。それそこが紫式部の比類ない気性というものなのだ。またそれは彼(か)の平安時代の、持ち前の「気っぷ」というものであるのかもしれない。宮仕えに抑制されてきた創造力の香気が一挙に吹き出した衝撃がある。
それは虎哉が読んでも、どこか女世帯の鏡台の匂いをこっそり嗅ぐようなものだった。強いてそれを言えば、式部の目を通して、時代とともにしだいに女の性(さが)がめざめ磨ぎ澄まされていく物語である。しかしそれを読んだからといって、女性の心身が育まれる物語というわけでもない。この物語は一筋の川であるが、清らかでもあり、澱(よど)みでもある。華やぐとみせて、そう感じさせながら落魄(おちこぼ)れる。そして最期は、濁流となり、式部はその川に夢の浮橋を架けた。これは夢とはいうが仏(さとり)の夢で、どうやら虎哉の尋ね方は、香織が強いて答えねばならない何の意義のない愚問だったようだ。だが、源氏物語はしつこく読み砕けば、かならずどこかに気楽な風が通ってくる。そこらが紫式部の企(たくらみ)というものだ。
虎哉はそう思いながら泉涌寺道の西方をじっとみた。そしてまた泉涌寺の方向へと眼をおもむろに回しながら記憶に残る一つの小川を想い泛かべた。その川の流れは、泉涌寺の後ろの山から出て、今熊野の南をめぐり、さらに一ノ橋の下を流れて、やがては鴨川へと入り混じる。そしてその流れはいつか淀川となる。かって虎哉が幼いころにみた泉涌寺参道には、この川があり、一ノ橋、二ノ橋、三ノ橋とあった。虎哉の眼の奥にはぼんやりとその一ノ橋が描かれていた。この橋が蘇ると母が現れ、そんな気にさせられる。
おそらくは誰もがあの母と語れることではあるまい。虎哉が母と佐保山の真夜中に交わした時間からは、まるで好きな古典歌謡を唄っていさえすれば、人生をソツなく刻む、そんなことは気分よくできるのだよというような、そんな美妙な安堵が伝わってきたのだ。


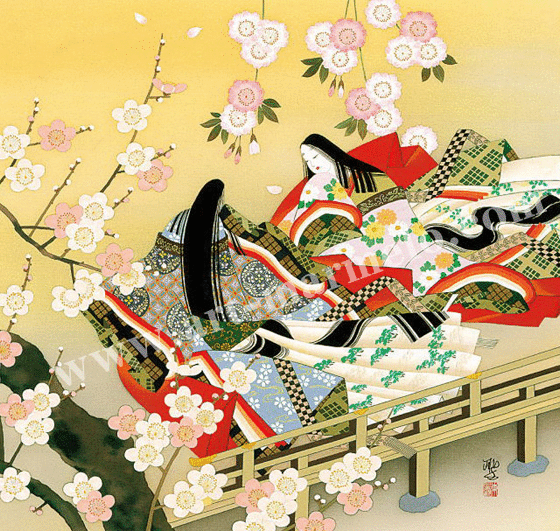


「 かさね、少し歩こう。向こうの方だ・・・・・ 」
と、ステッキで西を指すと、古い記憶に連なる参道と細い道路とが交わる場所まで香織を連れて歩いた。虎哉は病んだ右足を曳きながらパタリと止まると、借りた香織の肩からそっと手を放し、す~っとステッキを水平に上げ、また静かに下ろすとその尖(とがり)で路面の上をかるく叩いた。コッンと一つ納音なっちんが鳴いた。この納音とは五行の音律(宮・商・角・緻・羽)である。
「 かさね・・・こゝだよ。ここが夢の浮き橋だよ・・・・・ 」
唐突に、そう虎哉に促されても香織には、虎哉が意図する状況がよく呑み込めなかった。
二人は十字路にいる。角は居酒屋・牛若丸である。路面のどこを見回してみても、たゞの十字路上ににしか過ぎない。何一つ落ちてもいない。こゝが夢の浮き橋というが、虎哉がコツンと叩いたその路面は、どうどこから見つめても単なる路面で、ことさらそれらしきモノは何も見えなかった。香織はわけもわからずたゞポカンと小さな口を開けている。
しかし虎哉はそこに「源氏物語宇治十帖」に描かれた「夢の浮橋」に由来する跡であることを母菊乃から聴かされた記憶がある。何よりも養母お琴から浄瑠璃ごとのように繰り返し聴かされていたし、現に何度か、そのお琴の手に連れられて訪れていた。ともかくもこゝは、紫式部が源氏物語の幕を閉じる最終章で描き現わした橋を偲ぶのであれば、京の市井に唯一面影を止める跡なのである。
「 かさね・・・・・、もう眼で確かめることは不可能だよ。千年も前の浮橋だからね。今となっては私の眼でも、かさねの眼でも、他の誰の眼をしてでも、この結界に架けられた橋は、見えるはずもない橋なのだ。・・・・・しかしやはりこゝは納音だから顕れている・・・・・! 」
と、言葉尻を消してそう言ってはみたが、同じ言葉は、幼い虎哉の耳にも同じように聞かされた。
母菊乃も養母のお琴も同じ言葉で語ってくれた。
その言葉通りに繰り返している虎哉自身がいることが、香織に語りかけている虎哉には不思議であった。
あえて納音を語ろうとしたわけではない。語らせられているような妙にふわりとした感覚を覚えた。あのとき母菊乃は、赤い蛇の目傘の尖さきで橋の上をポトンと軽く叩いたのだ。その音の響きとともに、幼い小さな五体は逆さにした盥(たらい)の底でもた叩いたような、あるいは洞窟の入り口で叫んだときに風が震えるような体感を覚えた。当時は、確かにそのはずである。
しかし、その夢の浮橋という、小野の里の川に架けられていたという平安の橋は、香織の眼で見つめる現在、川はコンクリートで覆われて暗渠(あんきょ)となっている。どう、そこに夢の浮橋が架けられていたのかを求めようとしても、すでに名残を止める一つの欠片かけらさえない。川は地下深くへと埋設された。
紫式部の描いた橋の形跡はすべて千年の闇の彼方へと消え去っている。昭和30年ごろにこの橋は消えた。
「 いゝかい、かさね。これから話すことを後でレシティーションできるよう、しっかりと頭に刻み、その光景を心の眼の中に、いつでも再現できるよう繰り返し覚えるように・・・・・ 」
虎哉はそういうと、向かい合った香織と、五歳で他界した光太郎と、その母である香代が香織と同じ歳の十七で嫁いだ日の姿とを見比べられる眼の高さのところに身を置こうとした。
いや、そうとは違う。光太郎と妻香代と、母菊乃の御霊がみな呼び逢えて還り、香織の眼の高さで落ち合える位置に、曲がろうとはしない膝を虎哉はそっとかばいながら、片足を伸ばしたまゝ冷え切った地べたにストンと腰を落とした。虎哉が一旦こうなると、もう誰もそのテンポを乱そうとするものはない。世の中で一番重要なことは、夢の浮橋以外にはなくなってしまっていた。
「 あゝ、またかいな。れしてィ~しョん・・・・・、暗誦(あんしょう)いうことやったなぁ。老先生これいゝ出しはったら、もうアカンわ。きかん人やし。せやけど、これほっといたら、うちがァあかんなる。そないいうても、ほんに、かなわんしなぁ~・・・・・ 」
香織は虎哉のそんな視線をえらい恐ろしく感じるが、途中まで小声でそういって、しかしもう逃れようもなく、ふと間を置いた眼を空に向けると、雪を含んだ灰色の雲が、低く頭をおさえつけるように垂れこめていた。
そして香織はまた胸のサザンカを押えた。
新世紀になって80歳を過ぎたここ数年、虎哉はしだいに過ぎ去っていく恐怖に苛立ちがあった。そうした苛立ちが、残されて流れ去ろうとする時間に対するしびれるような重宝な味わいに拍車をかけていた。
そうしてふと気づいたときに、空や海や野が薄暗くみえて、これから拡がろうとする青い光線がその中心にみえた。それがまた未明から朝の陽が昇る間の、かけがえのない隠国(こもりく)から誘い導くかのサインなのであったのだ。
京から奈良坂を越えるとは、そのこもりくへの道であった。やがて丹(に)の色の仄かな光がそこに加わると、逢初(あいそ)める青と丹の光がしだいに落ち合いながら、鮮やかにプリズムで結ばれては、一面を染めるバイオレットの空間が広がってくる。虎哉はいつしかこれを本物の夜明けなのだと想うようになっていた。かさねに、その隠国の夜明けをみせたかった。そう思う虎哉は、おもむろに鞄から古い一通の、昭和十八年当時の電文を引き出すと、少し振るえる手のまゝに香織の手を引き寄せ、そっとその紙をてのひらの上に置いた。
「 イマサラ二 オウベクモナシ ムラサキノ ノノハテ二キエタマエキミノカヨト 」
この片仮名の羅列する響きは電信の歌である。
当時、養母お琴が打ってよこした妻香代の、享年23の辞世のそれは「 今更に追うべくもなしむらさきの野の果てに消えたまえ君の香代と 」という一首であった。虎哉はこの電信の経緯(いきさつ)を香織にいゝ終えてから、またそっと鞄の中に納めようと手を伸ばしたが、瞬時、風に吹き煽られた古い紙切れは、はらはらひらひらと路傍を舞い回りながら、地べたに落ちてカサカサと転がった。この電報を受け取った昭和18年当時、虎哉はシャンハイにいた。外套(がいとう)の襟をたて、凍えるようにひっそりとこの歌を涙して読んだ。雨田虎哉は上海の路傍で、酷く落胆し、日本の国というものが、もう自分の心を揺さぶらなくなっていることに気づいたのである。
虎哉は転んでいくその電報をみつめながら、そっと香織に微笑した。香織にはそれが、電信を追いかけてしまいたい虎哉がそこに居て、それでも必死に何かを堪え我慢しているかのような虎哉が居て、うずくまる影が二人の虎哉に見えた。
「 うち、もうよう分からへん。こゝ、宇治やあらへんし。せやけど老先生、こゝが夢の浮橋いゝはる・・・。納音て何んなんや? 」
どうにも訳が分からず香織はたゞしょんぼりとした。
四条天皇が崩御されたのは、鎌倉時代の1242年のこと。享年12歳での崩御については、幼い天皇が近習の人や女房たちを転ばせて楽しもうと試みて御所の廊下に滑石を撒いたところ、誤って自ら転倒したことが直接の原因になったと伝える。突然の崩御を不可思議に思う者が少なくなかったようで、巷では後鳥羽上皇の怨霊とか慈円の祟りによるものとの噂が立った。あるいは死因を脳挫傷とする憶説もある。
なぜ泉涌寺参道の一ノ橋をいつしか夢の浮橋と呼ぶようになったかについては、壇ノ浦で安徳天皇が入水し、平家もろともに滅んだことから語ることになろう。
平家が滅ぶと、後鳥羽天皇が即位した、にわかに天皇が権力盛り返してみると、後鳥羽系の天皇を擁した後鳥羽上皇方と、出来てまだ間もない、不安定な各勢力寄り合い所帯の鎌倉幕府との間で承久の乱が起きることになる。鎌倉時代は第80代高倉天皇から第88代後嵯峨天皇まで受難続きの時代であった。承久の乱で敗北した側の首謀者・後鳥羽系列の天皇一族が一斉に処分された。当時まだ10歳の後掘川天皇が即位すると、出家していた父の守貞親王が上皇となり院政を敷くことから幕府との混乱はしだいに回復する。そしてその孫が病弱な御堀川天皇に変わり四条天皇となる。しかし父の譲位に伴って即位した年齢はわずか2歳であった。さらにわずか10年の即位期間、12歳での崩御。かくして四条天皇は泉涌寺に葬られるために現生に架けられた夢の浮橋を渡った。
こうして夢の浮橋は今の世に出現したことになる。

源氏物語が紫式部によって「いつ頃」、「どのくらいの期間かけて」執筆されたのかについて、いつ起筆されたのか、あるいはいつ完成したのかといった、その全体を直接明らかにするような史料は存在しない。そうした源氏物語を、妻香代は、必ずしも長編の物語であるから長い執筆期間が必要であるとはいえず、数百人にも及ぶ登場人物が織りなす長編物語が矛盾無く描かれているのは、短期間に一気に書き上げられたからであると考えるべきで、若くして確かにそうであるとすら語っていた。香代が人より特段感性を高くして生まれたわけではない。京都とは、そんな女性をいともたやすく育てる風土なのである。そこには人にやわらかで柔軟な日本独自の豊かな風土があった。
比べて今、日本国の人民がタイ米を食べることを余儀なくされ、松本サリン事件や霞が関地下鉄サリン事件など、国家未曾有のオウム真理教が関与するテロ犯罪で国内は混沌とされる年次に明け暮れている。虎哉には暴走を始めた日本国が見えるようである。
しんしんとくる北風に晒されながらそう思う虎哉は、間もなく東福寺駅へと来るであろう駒丸扇太郎のことを気に止めると、昨年その扇太郎が語っていたフランスで見たという薄暗い海峡の漂いが腕時計の盤上で今をめぐり、その秒針の動きを絡らめ止めるかのようだ。眼に遺されたそれは、亡国の暗い泡立ちである。



消え去らないその暗い泡が、清原香織の出生の秘密に、とぐろでも巻く黒い蛇ように泛かんでいた。
またその蛇は佐賀県小城郡古湯温泉の一宿にからみついている。
「 新型インフルエンザが猛威をふるい、パンデミー(世界的流行)となる危険性が叫ばれていた。もしも大流行したならば、人々はパニックに陥らずに、冷静な行動を取ることができるだろうか。医療体制も十分な対応が備えられているのだろうか。人が動き、モノが動けば、目に見えない病気も動き、疫病が流行する。まさに、負の異文化交流となるのである。ようやく近代となり交通網が発達し、国際交流が活発になればなるほど、病気はエンデミー(風土病)からエピデミー(地方病)、そしてパンデミーへと激変するのである・・・・・ 」
この最中に、長崎へと向かった清原茂女は酷い「はやりかぜ」に冒された。その「はやりかぜ」とは1918年(大正7)年から20年にかけて、「スペイン風邪」と呼ばれ世界中に猖獗(くるけつ)したインフルエンザのことである。推定では約6億人が感染し、少なくとも二千万人から、一説には四千万人が死亡した。
発生源は諸説あるが、ヨーロッパでは第一次世界大戦の最中であり、西部戦線で睨み合っていた両陣営で爆発的に流行し、フランス全土に席捲し、やがてスペインへと蔓延していった。1918年秋になると、この恐懼の「スペイン風邪」が、日本へと上陸し、越年して全国に猛威をふるった。日本でも約二千三百万人が感染し、3年間に38万8千人が死亡した。人口千人当たりの死亡者数は6・76人、患者百人当たりの死亡者数は1・63人であった。大正時代にはこのようなインフルエンザの流行があった。
清原茂女が発症したのは大正9年6月である。スペイン風邪に罹かかり、急激に発熱し、寝込んでしまったのだという。肺炎を併発し、四、五日間は生死を彷徨し、一時は生命を危ぶむ状況であった。
「 8月から温泉嶽(雲仙)に療養、9月には佐賀県唐津海岸へ、10月から12月までは佐賀県小城郡古湯温泉の扇屋へ逗留し療養した。この期間中の雲仙、唐津、古湯温泉この三か所のいずれかに陣内剛蔵と清原茂女との接点がある。そしてどうやら古湯温泉が花雪という源氏名をもつ文代の生まれ在所になるようだ。しかしこの脚ではもう・・・・・ 」
そう西へ眼差してみると虎哉には眼の潤む痛みがあった。そうした感染症といえば、1935年から1950年までの15年間、日本の死亡原因の首位は結核である。これは当時「亡国病」とも称された。
未だ我が国には結核に有効な薬はなく、病気になればひたすら安静の日々を何年も過ごさねばならず絶望的な日々を送っていた。この結核で妻香代は胸を破(や)り痰壺(たんつぼ)を赤くさせながら他界した。
それは長女君子を出産した半年後のことであった。
「 消えたまえ君の香代と・・・・・。むらさきの野の果てに・・・・・ 」
この歌で「いはれなき切実」の消息は途絶えた。
しかし、いはれなき切実の浮橋は胸に遺される。未だ生き残る虎哉は亡き香代の影が夢の浮橋に座るのを覚えた。
そして新たな彼方には香織へと架け遺すべき母恋の浮橋がある。この浮橋は、奇遇ではない宿命という実在を体感したようで身震いがし、すると今にも一羽の雉(きじ)が藪奥から飛び出してきて、ほろうちの甲高い声を空に向かって突きあげるのだ。
五体は指先の根まで振るえ、まったくそんな身震いをさせた。そして眼に泛かぶのは、太古の古い錆びれた日本の神々の弔いであった。人間よる古事記が記される以前のその昔、雉の鳴女(きじのなきめ)という神がいた。この鳴女こそが虎哉の全身を振るえさせる。そして虎哉は、老いた眼を若かりしころのように悠々とさせた。
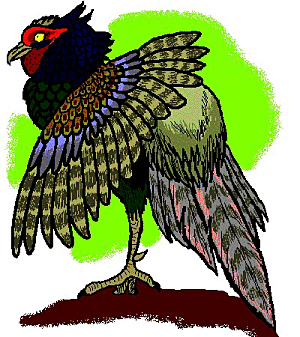
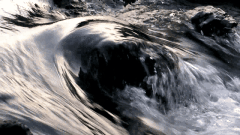


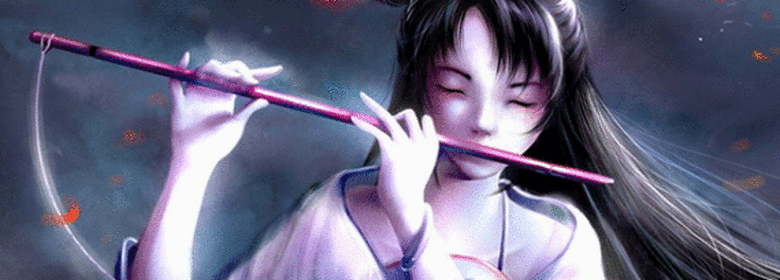











京都・泉涌寺









