




































(三) 亡国の泡 ① Boukokunoawa
デリケート・アーチをくゞり映る紫陽なラ・サール山脈の雪渓を眼に入れてたゝずむと、阿部秋子は記憶の奥底から目醒めるように、泛き上がる回想を早めぐりさせては、何度も何度もうなずき返した。そして比叡の深山を想いながら篠笛を吹いたのだ。
そのデリケート・アーチを連想し、笛の音を感じる雨田博士の背中には、阿部一族のかげろう夢の浮橋がある。
赤く枯れた塩岩のアーチ、それはまた逝く我が妻の渡る浮橋、香織の母影を求めた夢橋であった。
夢の浮橋跡に来て駒丸扇太郎のいう「 亡国に生まれた黒い泡の酒 」を胸に含ませたせいか、雨田虎哉は妙に今、背でも叩かれるごとくまた今朝けさ方の夢のこと、あらゆる夢の記憶のことに黒く泡立つごとく急かされていた。
依然として日中が不発弾をかかえ、竹島をめぐっては日韓に亀裂が走っている。北方四島問題もロシア有利のままに再燃している。




「 そうか・・・・・、今夜は、氷輪(ひょうりん)はない・・・・・! 」
常世(とこよ)でも月光は常に移ろう。もう七年前とは違う月の像かたちであること、雨田虎哉は今宵の下弦がふと細く過ぎった。
「 明慧(みょうえ)の夢記・・・・・。そして一乗寺六号・・・・・! 」
虎哉の夢の記憶といえば、外国から伝えられた仏教が日本人の魂との触れ合いのなかで変貌してゆく時代に遺された一冊の夢記があった。この書は、紀ノ国和歌浦(わかのうら)の風土に因む人のつゞり遺したものである。幽けきこの一冊も虎哉を揺らし起こしてくる。虎哉がそれを思い起こしたのは、今世紀の初頭に、フロイド、アドラー、ユングという三人の巨人が互いに同様の接触を重ねつゝエレンベルガーの「 無意識の発見 」の仕事に力を尽くしてゆく過程があった記憶を強く引き出したからだ。

その過程を見事に描写したエレンベルガーの書に想いが重なる虎哉の眼には、自然と明慧(みょうえ・明恵)の『夢記』が泛かび、さらにその夢に夜の海峡を越える一乗寺六号という銀の羽ばたきがあることを覚えた。
「 銀翼と言えば、日本には、あの零(ゼロ)式艦上戦闘機があった・・・・・ 」
一乗寺六号の飛んだ遥かな夜空を想うと、またそこにはあの暗闘の大戦にあった悲劇の夜空が泛かんできた。
零戦の出現当時、零戦はいかなる戦闘機に比べても空戦性能がすぐれていただけではなく、航続距離においてまさっていた。当時、零戦は2200キロの航続距離を持っていたが、当時連合軍の戦闘機がロンドンとベルリン間(片道約900キロ)を飛行し帰ってくることは夢物語であったのだ。この二つの銀翼は雨田博士に「国境とは何か」を問いかけてきた。

ゼロ戦は、日米双方でこの格闘性能の高さが評価された。横須賀航空隊戦闘機隊長であった花本清登少佐(横須賀航空隊戦闘機隊長)は実戦でゼロ戦が敵機を制圧していたのは速度だけではなく格闘性能が優れているためで、次期艦戦機の烈風でも速度をある程度犠牲にしても格闘性能の高さに直結する翼面過重を低くすべきと主張し、空技廠飛行実験部の小林淑人中佐もこれを支持している。 鹵獲(ろかく)した零戦を研究した米軍も決して零戦と格闘戦をしてはならないと厳命したほどだ。そして米軍は低い急降下性能などを突く対処法を考案した。
さらにゼロ戦の航続力も強みとなった。長大な航続力は作戦の幅を広げ戦術面での優位をもたらす。実際、開戦時のフィリピン攻略戦などは、当時の常識からすると空母なしでは実施不可能な距離があったが、ゼロ戦は遠距離に配備された基地航空隊だけで作戦を完遂した。
「しかし、ゼロ戦が空の王者を誇ったのも大戦半ばまでで、ミッドウェー海戦、さらにマリアナ沖海戦の手痛い敗北により、日本は主力空母と、パールハーバー以来の優秀な操縦士を多数失い 次第に劣勢に追いこまれた。零戦は徹底した軽量化による機動性の向上を重視して開発されたため同世代の米軍機に比べ、被弾に弱かった・・・・・ 」
大戦末期に老兵となったゼロ戦は、その背にあまたの若き日本兵を乗せ、ある者は敵艦へと、またある者は撃墜され、命そのものを弾丸とした哀れな特攻撃に身を供し、彼らの魂を黄泉へと運んでいる。それら栄衰をはらんだ運命は、まさしく帝国の興亡と不断一体であった。



「 アメリカ軍に占領されたマリアナ諸島などから日本本土に襲来する新型爆撃機・B-29スーパーフォートレスの迎撃戦においては、零戦の高高度性能に不足があったため撃墜は困難であった。大型爆弾用懸吊・投下装置を追加した末期型は代用艦爆(戦爆)として、また特別攻撃隊(神風特別攻撃)にも用いられ、レイテ沖海戦や硫黄島の戦いでは空母を撃沈破するといった戦果を挙げている。しかしやはり沖縄戦では、特別攻撃隊に対応して更に強化されたアメリカ軍の警戒網を突破するために日本側も戦術を工夫して突入を成功させ、空母を含む艦船を撃破したものの、艦隊到達前に撃墜される機も多く、アメリカ艦隊を撃退するまでには至らなかった・・・・・ 」
海底に今も遺棄された銀翼から滲み出る黒い泡音を感じ、そして香織を後に伴わせた虎哉は東福寺駅へと、宝樹寺と龍尾神社の角を南へと曲がった。
その東福寺(とうふくじ)は、京都市東山区本町にある臨済宗東福寺派大本山の寺院である。山号を慧日山(えにちさん)という。本尊は釈迦如来、開基は九条道家(くじょうみちいえ)、開山は円爾(えんに)で、京都五山の第四位の禅寺として中世、近世を通じて栄えた。明治の廃仏毀釈で規模が縮小されたとはいえ、今なお25か寺の塔頭(たっちゅう)を有する大寺院である。

「 それにしても一万キロの帰還とは、何と比翼(ひよく)なことか・・・・・ 」
東福寺駅へと歩きながら驚異的な一乗寺六号の生還を想い描く虎哉は、扇太郎から昨年のフランス話を聞かされつゝ手土産に貰って味わった、黒いカルヴァドスの一瓶を想い泛かべていた。
「 たしかに、一杯のカルヴァドスには、人を騙(だま)して奇跡を起こす力でもあるようだ。比翼はその酒のせいなのか・・・・・! 」
扇太郎はフランス留学を体験した男だけあって「 南フランスでは呑まない北西部フランスの酒である 」と言っていたが、醸造されながら完成に至らぬ(存在しないワイン)というものが、葡萄の育たないノルマンディー史には無数に存在した。またそうした日陰の存在を扇太郎は「挫折の裏面史」だとも物憂い顔で語っていた。そう聞かされてみて口に含んだワングラスの味わいには、たしかに挫折の裏面史にあるカルヴァドスならではの哀しい土に醸された慟哭でも嗅ぐような香気があった。
「 しばしば現実に存在するボルドーやブルゴーニュの上質ワインよりも、やはり刺激的なようだ。それはノルマンディー地方の風土を抜きにしてはやはり語れそうもない、その快い刺激はあらかじめ挫折することで、やはり生まれたのだ。奈良や京都の都こそが、あのカルヴァドスの一瓶と同じではないか。夢の浮橋、広島や長崎の被爆、これらもやはりその闇の泡なのであろう。そして今、日本人はその暗い泡立ちに泳いでいる 」
と、そう思える虎哉には、戦乱絶え間なく継いできた日本の都なのであることが、一瓶のカルヴァドスが醸し出す香気を聞くと、現実に存在して図太くも繊細な林檎の隔世(かくせい)な味わいなのであった。
そんなカルヴァドスが珠玉の一瓶であるというには、虎哉にとって、この酒がひたすら凝縮されたものだということがなければならない。それは天体を語る長大なものではなく、わずか2000年ほどの土地に織りこまれた一片の布切れのようでありながらも、そこからは尽きぬ物語の真髄が、山水絵巻のごとくにいくらでも流出してくるということである。
日本の国が古来からそうであったと考えれば、源氏物語の作品が、日本の近代文学史上の最高成果に値する位置に輝いていることを、虎哉は改めて重く思わねばならなかった。

「 この一作だけをもってしても紫式部の名は永遠であってよい。したがって物語には、光源氏が数多の恋愛遍歴を繰り広げつゝ王朝人として最高の栄誉を極める前半生で始まり、源氏没後の子孫たちの恋と人生で結び終えるこゝには、主題から文体におよぶ文芸作品が孕(はら)む本格的な議論のすべてを通過しうる装置が周到に準備されているということではないか。源氏物語にはそう準備した紫式部のロジックがある。しかもそこに六(ろく)の密言があるとは!・・・・・ 」
時間を経過させ人が読み砕くほどに、仏教思想を織り交ぜて描く源氏没落後の恋物語は未完なのだ。その未完ゆえにこの装置は常に希望を蓄えている。そしてその六(りく)の密言には、星一つ分ほどの空白がある。この空白こそが人間への許しなのだ。
「すると光源氏が抱えこんだ陰陽の世界というものが、現代の我々の存在がついに落着すべき行方であって、そのことを紫式部がとっくの昔から見据えていたということ、しかもその存在の行方を描くには、いっさいの論争や議論から遠のく視点をもって叙述しなければならないことを彼女は知っていた。あの式部は、その上で知らぬ振りか・・・・・! 」
と、いうことを、奈良に向かう虎哉は今そのことにこそ触れなければならぬように思えた。
眼で追えば届きそうな平凡な東福寺以南の宇治までの距離にある風景が、地の底をなぞると橋姫、椎本、総角、早蕨、宿木、東屋、浮舟、蜻蛉、手習、夢浮橋の十帖なのである。しかし式部の一人筆は、現代のつまらない立体を一呑みにして往時に凌駕(りょうが)する。
「 紫式部の文体が言霊(ことだま)であり密言(みつごん)であるのなら、人はたゞ唱えるだけでいゝ。人は式部の吐いた平安の言葉をたゞひたすらに聞くだけでいゝ。それが言語装置本来の効能なのであろう 」
東福寺駅へと香織と向かいながら扇太郎の顔を泛かべる雨田虎哉は、さきほど夢の浮橋の暗渠をみた感触を抱きつゝ宇治十帖でも覗き見るごとくに眼を細く鋭くさせていた。
「 源氏物語が単なる女子供の手慰みという、そんなことはないでしょう 」
と、陰陽を継ぐ駒丸扇太郎もそんなことを言っていた。その扇太郎という男は、幼い時からそばにいて父を見ていて、扇太郎にはその父が、学問や芸術に対して、山の頂を極める人のようなきれいな熱情を持っていた人のように、見えたという。またそう語る扇太郎とは、そのような父の「きれいな熱情」をひたむきに追う影とでもなるように生きているようだ。
「 やはり根の髄に、かって京都を歩いた馬借(ばしゃく)の風土が沁みついている。そうした駒丸家の馬借の披歴は、阿部家の披歴と同体を成して個性豊かな伝統を継いできた。その陰陽は摂理に真摯なのだ・・・・・ 」
虎哉の眼には、それが彼らの上に一生つゞく道のように思われる。何事も迷信という言葉に投げ捨てられてしまう現代の車社会に馬借気質(ばしゃくかたぎ)とは不思議だが、一乗寺の扇太郎は、どこか懐かしい日本の何かを背負おうとする男なのである。そんな扇太郎が間もなくして東福寺駅に姿をみせる。虎哉は扇太郎が語ったフランスで過ごしたという彼の休日をもう一度思い起こした。


「 フランスには、葡萄(ぶどう)のワインやコニャックでは語れない潮騒があるようだ・・・・・ 」
と、そういって彼は語り始めたのだ。
その潮の音が幾重にも重なる駒丸扇太郎には、いつしか綻(ほころ)びの醜聞に耳を塞ぎたくなる惨めな色音の泡立ちとなっていた。とはいえ、人間への潮流のストレートな攻撃衝動はすでになくなっている。
「 このまゝでは過去の話には戻らないのである・・・・・ 」
戦禍の正体は、勝利者のシンボルでみごとに華麗に風化していた。
何一つ汚れのない瞳のような海がじっと扇太郎をみつめている。しばしそう見入ってみると、その大罪を訴えてやまない。扇太郎は不可思議な地上の星でも見る心地がした。人間とは、かくもゆゝしいことをする。丸い目にカミソリの刃を細く引き貌(かお)を厳(いかつ)くした。
「 いつでもそうだ。どこでもそうだ。痕(あと)はいつも机上の空論とさせる。日本の海も同じだが、やはりフランスの海も同様だ 」
と、扇太郎は開口一番に怒りに近い気勢をあげたのだ。
香織の肩を借りて片足を曳きながら駅へと歩く雨田虎哉は、そう扇太郎がまず気勢をあげて語り始めたフランス滞在時での旅の話と、いかにも空しく語り続けた姿とを、眼に強く鋭く泛かばせていた。核の拡散と分有は、現在もアメリカを頂点に巨大なコンパスを拡げている。
眼の前の波に、たゞ美しさだけが遺されている。すでに「1944年6月6日」という時間が当たり前ではなくなっていた。造作であれ微笑む顔を突き出されては、握る手の拳(こぶし)は熾(おこ)せないのだ。
「 これでは、落胆を忘れ、人間は苦しまなくても済んだのではないかと、誤解してしまうではないか・・・・・ 」
扇太郎はたゞ手を拳(こぶし)にしたまゝ震わせた。やはりそうでしかないのかという予測した震えなのである。しかし理不尽な埋没を許さない矜恃(きょうじ)さえあれば、腐ったリンゴはひと噛みでわかるのだ。
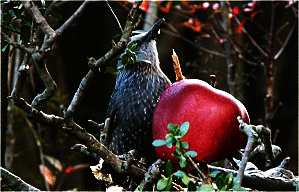
「 アメリカ軍は中部南太平洋の島々を次々と陥落、6月にはサイパン、テニアン、グアムなどマリアナ諸島への攻撃を開始した。その海は、この海とつながっている・・・・・ 」
すでに半世紀を過ぎた時間、本来なら煮詰まって一連の海は腐りきっているのだが、そうは感じさせない。扇太郎は父誠一の眼に成り変って前方をじっとみた。常に、勝利者は悲しみの手応えを亡くそうとする。因果まるのみして全ては抹殺されて終えようとする。
扇太郎は、どのように向き合うべきかについては、その「 近現代の彫琢(ちょうたく) 」をどう理解するかゞ、自身は今後どこにどう立ち向かおうとしているのかを、読み解くヒントとなることを密かに期待していたのだ。しかし不毛な反目を見せるべき海の姿はすでに消えていた。
「 闘争の心理を、美しく誤魔化そうとする・・・・・ 」
この世には、誰にも感謝されない非情の泡沫(あぶく)というものがたくさんある。扇太郎にとっては、弾ける泡のその一つが、明治末期に編集された前衛の一冊であるのだ。この浜辺では何よりもその手垢に染められた一冊が示唆的であった。
日本人に西欧の風物文物へのあこがれを『海潮音』が抱かせてくれた。
上田敏の象徴派訳詩集の「 選ばれし者の不幸 」をそう思う者は、永井荷風がそうである。北原白秋がそうであった。あるいは三木露風がいた。「calvados・カルヴァドス」の黒いボトルを片手に揺らしながらその「秋の歌(枯葉)」をつぶやくと、棄てられた戦場の淵を濯(あら)う異国の海峡は、神への冒涜さえもダンディーで、たゞ深く静かな淪(さざなみ)を聴かしてくれた。
それは一粒の人間でしかないと、あざ笑うかのように揺れるさゞなみだ。しかし「 Erich Maria Remarque(エーリッヒ・マリア・レマルク) 」による第二次世界大戦後の逸作「凱旋門」にはたびたびカルヴァドスが登場し、この酒を有名にしたが、ドーバー海峡には、どうやら、この「りんごの酒」が確かに似合うようである。
レマルクは、第二次世界大戦中のパリを舞台に、ナチスの影におびえ復讐相手を追い続ける日々を生きる医師ラヴィックと女優ジョアンの鮮烈な恋を中心に、時代に翻弄されながらもひたむきに生き抜く人々を描いた。
この物語は2000年に宝塚歌劇団によってミュージカル化されている。そして初演のS席に虎哉と香織はいた。
「 おれは復讐をし、恋をした。これで充分だ。すべてというわけではないけれど、人間としてこれ以上は望めないほどだ・・・・・ 」
という。これは最悪の時代と境遇の中で精いっぱいに生きて、望みを果たし、ついに心の動揺が鎮まったときの主人公ラヴィックの心の底からの感慨であった。著者レマルクは、敗者の国を抜け出し、勝者の国で生き延びる人間を描いた。
扇太郎がパリにあこがれたのは、まだ高校生のころに読んだこの「凱旋門」からである。
ゲシュタポに追われるユダヤ人亡命医師、ラビックと天涯孤独な端役女優、ジョアンが、ナチの暗雲迫り来るパリで繰り広げられる絶望的な恋の物語を読んで、まだ見たこともない異国の町に思いを馳せたものである。
この小説には凱旋門近くと思われる通りの名前がしばしば登場した。そしてエトランゼにパリの夢を灯した。シャンゼリーゼ通りはもちろんだが、マルソー通りとか、エトワール広場、ピエール・プロシェール・ド・セルビエ通りなどといった、いかにもパリらしい通りの名前が次々に出てきて、小説を読んでいるうちに自分が行ったこともないパリの街中をうろついている思いにさせられたのである。だから、いつか海外に行けるようになったら、まず真っ先にパリに行って、ラビックとジョアンが歩いた街を歩きたいとずっと思っていたのであった。
その望みが扇太郎にかなったのは1973年(昭和48年)である。
凱旋門を自分の目で見、シャンゼリーゼの裏通りを歩いて、それがレマルクの小説と同じイメージであったことを確認した。しかし小説の中でどうしても理解出来ないことが一つだけあった。それはラビックとジョアンがパリの裏町をさまよった後に、必ずお酒を飲んでいたことだ。それも水代わりにである。ジョアンが「 喉が渇いたわ 」というと、「 コニャックを飲むかい。それともカルヴァドスにする 」と、ラビックが聞いている。
これを読んでフランス人とは、喉が渇くとコニャックのような強いお酒を日常的に飲むのかと、そう思い驚いたのだが、後でレマルクが無類の酒好きから書いた文章だと分かった。じつはカルヴァドスという林檎の酒がフランス産であることもこの小説で初めて知った。
「 しかし小説でそれを知って、敗戦国の人間が、勝者の国に素直に憧れていゝのか 」
という、しだいに固い殻のそんな思いが真剣につのる。いつも傷痍(しょうい)の父が脇にいたからだ。
そして自虐して見えてくる人間の愚かな逆さかしまがあることに気づいてきた。
「 人間が繰り返す闘争の心理とは、意外に単純なものだ。そこにあるものはたゞ唯物である。父誠一は出征先の中国南方からレイテ島に征く途上で、兵站(へいたん)の補給がまゝならず、常に飢餓の恐怖と隣り合わせであったのだという。戦争は物の不均衡(ふきんこう)から起こる)とも語っていた。そういうあの眼の薄暗さは尋常(じんじょう)ではなかった・・・・・ 」
日本では飼い犬の強制供出「 毛皮は飛行服に、肉は食用に、大3円、小1円 」とは、それはもう正気ではないほどに馬鹿げている。
「 西部戦線異状なし・・・・・ 」
と、レマルクの名を耳にしたとき、突然と触れて至極親しみのある名の響きに、雨田虎哉はこの表題を浮かべ、そして晩年はスイスで暮らし療養中であったレマルクの蒼白な顔を思い出した。
療養中だと思えたのは、1970年に動脈硬化に起因する大動脈瘤で死去したからだ。虎哉がスイスのロカルノでエーリッヒ・マリア・レマルクと出逢えたのは1969年のことであった。
「 最初の砲撃で目が醒めた。戦死はたゞ汚く、無惨だ。国の為になど死んではならない。無駄死だ。・・・・・ 」
とは、西部戦線異状なし、その一節である。
虎哉はリクエストに応えたレマルクの地声を聞いた。戦火を踏んだその口の実態とは地雷なのだ。
1933年にナチスが政権を握ってから彼の本は焼却されたり、「 彼は実はフランス系ユダヤ人の末裔だ 」「 実の本名はクレーマーというのだ 」と、名前までも逆さに綴られて呼ばれるといったデマが広まり、書籍の焚書(ふんしょ)処分を受けた。そして1938年にドイツ国籍を剥奪され、1939年にアメリカ合衆国に亡命し、帰化して47年に合衆国の市民権をえた。なぜ彼が帰化した後に晩年がスイスなのかは、1929年に彼は『 西部戦線異状なし 』を発表し、大ベストセラーとなる。早くも翌年にはハリウッドで映画化された。やや通俗的だが反戦的内容でもあったため、右傾化するドイツを避け1932年にスイスに移住した体験による。
雨田虎哉が初めてマジョーレ湖を見たのは1969年、日曜の晴れた朝であった。
異国の旅は予定に任せないところがある。マジョーレ湖畔のイタリアの町カンノッビオのメルカートに着いたのは昨晩の遅くになってしまった。マジョーレ湖を見たかったわけではない。予定通りならスイスのロカルノに夕刻到着していたはずだ。
「 しかたなくメルカートに小さな宿を見つけた・・・・・ 」
そうなると翌日は日曜日、急いでロカルノに向かったとして日曜では用が足せるはずもなかった。
マジョーレ湖畔には別荘が狭い崖のような土地にぎっしり建てられている。道路わきに小さい箱のような小屋があるのだが、何かと思えば、エレベーターの入り口である。道路口から家の中にエレベーターが引き込んであるって細い空間は何か不思議ですらあった。メルカートの小さな町の日曜では、どこもかしこも軒並み閉店みたいなものだ。そこで午前中に国境を越えることにした。
「 酒は積んでないよ! 」
と、冗談を言った。すると国境警備員は微笑んで通過するよう頷いた。酒を積んだ車で通過しようとするとよく税金逃れと怪しまれ時間をロスすることになる。国境を越え、ブリサーゴ島が見えるとロカルノ、保養地ではあるが坂の多い街であった。ともかくも空腹である。眼についた手頃なホテル内のレストランへ駆け込んだ。選んだのは「Ossobuko(オッソブッコ)」、仔牛の骨付きすね肉を輪切りにして煮込んだものだそうだが、そう説明を聞かされてオーダーをし、待ちながらふと何気なく右横のテーブルを見るとアラビアータをのんびりと食べる洒落(しゃれ)た紳士がいた。意識不在のまさしくそれが一期一会、レマルクなのであった。

「 おいしそうですね。そのアラビアータは・・・・・ 」
と、つい何気なく声をかけていた。正直な感想ではあった。当時レマルクが日本に対してどのような感想を抱いているかなど、まして目の前の紳士がレマルク自身であるなど知るよしもなく一旅行者の振る舞う軽い挨拶でしかなかった。
すると紳士は意外な言葉を応え返してきた。
「 一人のリトルボーイは英雄ではある。その子に毒を盛られたのでは食感などないでしょう 」
と、少しニヒルに笑った。虎哉はその言い回しが妙で、自分に返されたであろう言葉を呑み込めぬまゝに数回反芻(はんすう)した。どうやらそれはレマルクのトリップであった。
「 やはり貴方は、日本人ですね! 」
と、直ぐに射返された。東洋人であることは判っても、彼は二段立ての反応で相手の国籍を確かめようとした。それはたしかに年齢相応の投げかけであった。お互いが大戦を体験したはずの年齢なのだ。その年齢に達した東洋人が、リトルボーイと聞かされて何かの反応を示すのであれば、十中八九、日本人であり、しかも敏感に反応するのであれば当時の階級も知れるであろうと考えたようだ。
そのレマルクは1898年にドイツ北西部のオスナブリュックに生まれ、ミュンスター大学で学んでいる。
第一次世界大戦中にドイツ軍兵士として従軍し、そのときの体験を元に『 西部戦線異状なし 』を書いた。29歳の青年による兵士の苦しみ、友情、惨めな死など戦争の前線をリアルに描いたこの作品は軍国主義への批判をこめた戦争文学の傑作となった。発表されるやたちまち世界的な反響をよび、あらゆる時代をとおして広く読みつがれる小説のひとつになっている。この作品をもとに三種類の映画がつくられた。そしてつゞいて彼は31歳の作「還りゆく道」で、大戦後のドイツの現状を鮮やかに描き上げた。
坂道の多いロカルノは、マッジャ河が谷を少しづつ削って作った三角州の上に出来た町である。
「 私のお気に入りの場所がある。そこに案内しよう・・・・・ 」
と言って、彼は虎哉が食事を終えるのを待っていてくれた。
「 リトルボーイも食べられたものではないが、豚男はもっと不味(まず)い。食べぬよう忠告されたのにも関わらず食べてしまった。おかげで下痢続き、だから口直しにロカルノに来ようと思いました・・・・・ 」
と、虎哉が紳士に応え返していたからだ。高台からロカルノ方向を見下ろすと、マドンナ・デル・サッソの聖所がやわらかな霞の中で榛(はしばみ)色いろの黄味がかった薄茶壁が仄かに溶かされていた。それはさも天空に座る城郭のごとく泛いていた。この場所に来て虎哉は、初めて案内者がレマルクであることを知った。
第一次世界大戦が始まった当時はギムナジウムの生徒で、1916年に級友たちと共に徴兵されて西部戦線に配属された。戦場に出て翌月には榴弾砲弾の破片を首や腕に受け、終戦までデュイスブルクの野戦病院で過ごした。ドイツの敗戦後、負傷兵として帰還し復学、卒業後は教員など経て、ベルリンに出てジャーナリストになったという。
レマルクは、マドンナ・デル・サッソの聖所を臨みながらそう語った。虎哉は上海で「西部前線異常なし」を読んだことを、感動を覚えたことを告げると、少しはにかんで笑った。そしてリクエストされた作品の一部をそっと呟いてくれたのだ。
こうして虎哉は自身の体験を交えると・・・、扇太郎は、中国と日本の話に切り替えた。
「 もう喧嘩はすみましたか。喧嘩をしてこそ初めて仲良くなるものですよ・・・・・ 」
と、毛沢東主席が田中角栄首相と握手した。それは扇太郎が初めてパリを訪れる前年の出来事であった。日中は戦後30年近く続いた対立関係を終え、国交正常化を果たした。その友好の会談の場であった釣魚台の迎賓館の一室には銀座「木村屋のアンパン」が用意されていた。九月の30℃を超える猛暑日であった。パンは腐らずに、日本が腐ることになる。中国のいう口喧嘩とは友好の互換性がない。その田中首相の好物と引き換えに、翌年の日本には、パンダのぬいぐるみに大はしやぎする日本人の姿があった。そうした風潮に扇太郎の父誠一は「 日本人はすぐあゝなんだから 」と渋い顔をした。未だ日本はアメリカ頼み、ぶら下がりの高度経済成長を信じていた。

誠一は中国大陸を転戦して帰還した傷痍軍人であった。中尉として所属する第16師団は支那事変(日中戦争)が勃発すると南京攻略戦に参戦した。さらに大東亜戦争(太平洋戦争)ではフィリピン攻略に参戦しマニラ陥落後フィリピンに駐屯した。
だがレイテ島に移駐すときに機銃掃射にて負傷し傷痍(しょうい)者となった。その父が他界した7年後、ドーバー海峡を見つめながら扇太郎は父誠一の遺品である『海潮音』の序を見開きにして暫く佇んでいた。
序文の冒頭を引くと「 詩に象徴を用ゐること、必らずしも近代の創意にあらず、これ或は山岳と共に旧きものならむ。然れどもこれを作詩の中心とし本義として故らに標榜する処あるは、蓋し二十年来の仏蘭西新詩を以て嚆矢とす。近代の仏詩は高踏派の名篇に於て発展の極に達し、彫心鏤骨の技巧実に燦爛の美を恣にす、今ここに一転機を生ぜずむばあらざるなり。マラルメ、ヴェルレエヌの名家これに観る処ありて、清新の機運を促成し、終に象徴を唱へ、自由詩形を説けり・・・・・ 」とある。
扇太郎自身、何度こゝを読んだことであろうか。実際、永井荷風の「ふらんす物語」もこれによって誕生したようなものだ。
父誠一は生前、秋深くなると切断された右足の付け根が冷えて痛むのか、義足を支える腰骨の肌を涙眼で擦り撫でながらよくこの詩を口号(くちずさ)んでいた。そうしてまで呟(つぶや)くのは「 好き嫌いではなく。日本はまさに世界に正面から向き合わねばならないのだ 」と、慟哭を更地に変えて切り拓くほどの切実な飢えを体験したからなのだ。
「 あれは、蛮行と過酷な戦争体験からくる平和への思いであった。父誠一のような死闘の辛酸をなめた戦闘経験者世代は台湾に愛着があり、国交正常化と言われても素直には喜べない。しかし最終的には世間が日中友好ムードに流されていく。父が見せたあのときの渋い言葉の表情は、当時の日本人の心理をよく表していた・・・・・ 」
そういう口ぶりの、深いしわを刻んだその父の皮をむいたら、芯にはみずみずしい明治生まれの青年がいるのでは、と思わせたのだ。中国は国交回復後、友好の証しとして「カンカン」「ランラン」の二頭のパンダを贈り、日本はしばしそのパンダブームに酔いしれていたのだが、父誠一はそうした真下に他界した。
相互の歴史認識、台湾問題など難題だらけの国交正常化交渉がまとまったのは、その交渉の背景に前年の米中接近、中ソの対立があったからだ。1972年9月29日の日中共同声明で、相互が大きな譲歩に踏み出せたのは、つまるところソ連国を会談のテーブルに乗せた軍事問題の取引である。この声明によって日本側は、過去において日本国が戦争を通じて中国国民に重大な損害を与えたことについての責任を痛感し、深く反省することが声明に盛り込まれた。
両国間のこれまでの不正常な状態は、この共同声明が発出された日に終了した、とする認識に父誠一はいかにも疑心暗鬼で否定的であった。5年後の1978年8月には日中友好条約が締結され、中国側は賠償金請求を放棄する代わりに、日本側からODA等の巨額な経済援助を引き出した。これがパンダ二頭分の代価であった。こうした決着の行為が不正常なのだ。父誠一は数多くの不況を体験した。
その誠一が「 不況ということは世界諸国との兼ね合いもあり致し方ない国家の側面として国民は耐え忍ばならない理解しうることであろうが、しかし何よりに増して不況であることは、戦後における政治家たる人の不況ではないか。その不況を胸に深く刻まずして、一体何が果たせるというのだ・・・・・ 」
と、よく唸るようにして新聞を見開きにしていた。
「 パンダさんが転んだ・・・・・か・・・・・ 」
日中友好条約後の9月に長女夕実(ゆみ)が生まれた。祖父となった誠一はその3年後に他界するのであるが、生前の面影として、2歳半ほどの孫娘を子守する誠一は、達磨さん遊びを「パンダさん遊び」と揶揄しながらも初孫とする遊戯が、唯一憂さ晴らしらしく、じつに嬉しそうであった。そしてこの義足では二つの小娘にもまゝならないと笑っていた。


誠一は駒丸家の嫡男として明治38年に生まれた。遺品である「海潮音」は同年に初版されている。嫡男の誕生を祝賀する記念の一冊として祖父誠太郎が所望し買い求めたものだ。
扇太郎が誕生したときも誠太郎は上田敏の『うづまき』、これは自伝的小説であるが、その復刻版を命名の下の床の間に飾り立てゝくれた。それらは祖父の嗜好品ではあるが、駒丸家では代々上田敏が身近な存在として無意識のうちにあった。
「 秋の日の ヴィオロンの ためいきの・・・・・ 」
眼の前に「D―DAY」と同じ波濤(はとう)がある。
訳詩は意味を伝えれば用が足りるものではない。英独仏三カ国語の詩の味わいを感得し翻訳するとは、想像を絶する語学力だ。
「 近代詩壇の母はまさしくこの人である 」
とは、北原白秋が上田敏について語ったことばであった。一体どんな男かと、感嘆してそう想う扇太郎は、どうしても、青白い兵士らの生気をくみとらねばならなかった。生前、父誠一には自身が軍人であったことが、結果として村の若者を戦場に向かわせたことに、自責に似た思いがあったからだ。人を駆り出す役目がそう呵責させた。
その誠一は戦後、公職に就かず、ひっそりと暮らした。そして海潮音は祖父誠太郎から父誠一に継がれながら遺された品である。そうした戦時の経緯を自らへと引き取るために扇太郎は覚悟すべき認識を持たねばならない。上陸作戦の暗号とされたこの詩を読み聞く度に、誠一は胸がかきむしられる様な、全体を強く縛られる呵責に打たれたという。扇太郎はその慟哭をみせられた。今は淡い輪郭しかもたないが、かつては大西洋の壁、その要塞の浜辺であったことを意識しながら、扇太郎は「ポール・ヴェルレーヌ(Paul Verlaine)」の歌をつぶやいて七月にしては暑いとも思えない冷やりとした風のビーチを歩いた。
落 葉
げにわれは 秋の日の 鐘のおとに
うらぶれて ヴィオロンの 胸ふたぎ
こゝかしこ ためいきの 色かへて
さだめなく 身にしみて 涙ぐむ
とび散らふ ひたぶるに 過ぎし日の
落葉かな。 うら悲し。 おもひでや。
「 この暗号を、海峡は今どのように聴いてくれているのであろうか 」
上田敏は、ヴェルレーヌの詩を日本古来の和歌の手法を使い七五調の変形五五調にして、和音のシャンソンとしてリズム感を出した。だから、日本人の誰にでも、安心して耳に入ってくるのではないか。日本語として詩情を湛えた作品に生まれ変わらせた。「とび散らふ」の「ふ」は反復、継続の助動詞ではないか。したがって「しきりにとび散る」「散りつゞける」ということになる。そうだから日本人の心に飛び散り続けてきた。その落魄の心は永遠のものとして現在も散り続けている。
詩作とは、識字する人が人らしく生きる拠よりどころではないか。心打つ詩は尊厳と言っても過言ではない。それを冒した理不尽の世界がこゝにある。血のオハマF地区というビーチに立あおぐと、頭上の高みから血とも肉ともつかぬ赤色の粒が、ぱらぱらと零こぼれてくるがしかし眼の前では眩(まぶし)いばかりに白く光っている。遠い現実にたゝずむ扇太郎は気温25℃という少し肌寒い夏の盛りの海峡の浜に、たゞ心だけが爛(ただれ)るような傷みを感じ、しばらくとり残されていた。

「 上陸は六月だった。その暗号が秋の歌とは・・・・・ヴェルレーヌ・・・・・ 」
第二次世界大戦の末期、BBC放送がヴェルレーヌの「 Chanson d'automne(秋の歌)」を放送した。
これは「 連合軍の上陸近し。準備して待機せよ 」という、ヨーロッパ大陸の対ドイツレジスタンス全グループにあてた暗号放送であった。ドイツ軍の国防軍情報部は事前にキャッチしていたというが、この秋の歌で、ノルマンディー上陸作戦は開始されたのである。
インパール作戦は、当初から補給や制空権の確保を無視した無謀な作戦だった。3月作戦開始、緒戦は目覚ましく、日本軍はインパール後方のコヒマを占領したが、インパールを目前にした食糧と弾薬は底をつき、ついに退却を余儀なくされた。撤退途中、飢えと病気で多くの兵士が倒れ、戦死者3万人、戦傷病死者4万人とする。そうしてノルマンディー上陸作戦のころ、サイパンが陥落した。
「 あの人形も、アホウドリではないか。あのボードレールの・・・・・ 」
サン・メール・エグリーズのサン・コーム・デュモン教会の壁に82空挺師団ジョン・スティール二等兵の人形がある。勝者の眼が教会をカンバスにして描く宗教壁画の美学とみた。ドイツ軍がいる町の真ん中に降下してしまったスティール二等兵のパラシュートは教会の塔に引っかゝり、彼は捕虜になるまで死んだふりをしていたのだ。
「 1980年・・・・・・ 」
この年、二度目のフランス体験となった。7年振りにまた訪れることができた。丁度、父誠一の七回忌と重なって、巡り合わされた訪仏として思われ前回よりも奇縁さが増して鎮痛であった。
「 朝目覚めると、父誠一は眠るように死んでいた・・・・・ 」
それは自然死のようでじつは病死である。糖尿病患者は、人工透析の影響による水分量の変化により、断端形状の収縮・肥大といった変化が問題となるからだ。そうした体脂肪は断端を不安定にする原因となる。また、過剰な肥満に伴う体重変化は断端周径を大きく変化させ、不適合の原因となりやすい。死後硬直の死体はしばらく贅肉(ぜいにく)に歪(ゆが)みがあった。


「 戦後の誠一は、義足と闘って戦死したのだ。それはアホウドリ・・・・・。僕もまた、世間という甲板に捕まえられた、まるで悪の華のアホウドリと同じだ・・・・・ 」
扇太郎はこのL'Albatrosを泛かべると、自身も人類が生れるずっと以前に、深海に漂っていた無数の原始の生き物、単細胞の生命体、あるいはプランクトンのような、クラゲのような水中生物であったことを想像した。そのたよりない生命は、生れたときから孤独の中に投げ出され、だれと話しあうこともなく、相談することなく、たゞひたすら生きるためだけに浮遊しているのである。
「 その生命体のいくつかは餌を取るために周期的に発光する。それは自己完結的な、絶対的な孤立だ。僕は、あの原初のライフスタイルからどのくらい変化し、あれからどれくらいへだたっているのであろうか・・・・・ 」
とも思う。就寝前に、グラスを掌で包んで暖め、立ち昇る芳醇な香りを愛でるのが、いつしか扇太郎には欠かせない日課のようになっていた。最初に微量のカルヴァドスをグラスに注ぎ、火を点けて燃やすのである。美しい青白い炎こそが、真の美味しさを引き出してくれる。まずグラス中に香りを充満させて、その酒は捨て、立ち初めし香りのそこに新しいカルヴァドスを注ぐのである。そうすることで、20年以上眠っていた酒を生き返らせる。火を点けることで、元の香りの10倍以上、香りが引き立ってくる。まずはひと口、口に含むと、カルヴァドス特有の風味が、スーッとあたかも音を立てるように、口から鼻へと突き抜けてゆくのだ。
この香ばしさこそ、カルヴァドスの醍醐味なのである。20年以上のカルヴァドスは、リンゴパイのように少し甘く、深い香りを持っているが、こうすることで、最高の状態の味と香りを引き出すことができる。
そうすることで、扇太郎には、レマルクの小説『凱旋門』に描かれた古きよきパリ街が脳裏に甦るのであった。
しかし今は、小説にあるパリ街に憧れる気持ちなどはない。レマルクの見た敗戦国という亡国に耽るのである。その亡国の一連から、やはり亡国である不自由な日本の現在について考えさせられ、亡国の泡が湧き上がるのであった。
そして小生である丸彦の眼にも、黒い泡の中で蠢く1億2千という日本人が、どうやら反形而上的無国籍者の精神を日本語であしらい安手のユートピア思想に勤しむ奇特なロマンチストにみえてきた。











D-Day Invasion of Normandy ノルマンディー上陸作戦









