




































(三) 狸谷 ② Tanukidani
沖縄では御嶽(うたき)の精子が鈴の音を揺らしていた。
夢の中で比江島修治はそんな鈴の音を聞いていた。
きっと就寝前に、七色の日傘を開いてクルクルと回しながら京都の早春を思い抱いていたからだ。
踊る精子の、その音色に包まれて夢の中では昨夜眼差した久高島の夜陰の灯火が重なるように揺れている。
「 ニコライ・A・ネフスキーは、宮古島の方言に強い興味を抱いた。そうして宮古島における調査を行った。彼は6年間、宮古島以外にも琉球諸島や台湾に住む少数民族の言語と民族史を研究したのだ。この期間に数多くの雑誌や新聞にその研究内容を発表する。妻イソとの間に娘エレーナが生まれたのはこの時期であった・・・・・ 」
修治は早朝にはホテルを発ち、那覇空港から宮古島島へと渡る予定でいる。
日本トランスオーシャン航空便07:30発のチケットを手配した。約45分のフライトだ。宮古島市の漲水御嶽の近くに「 ネフスキー通り 」と呼ばれる長さ約90mの石畳の坂道があるのだが、二三日島内を巡る予定でいた。


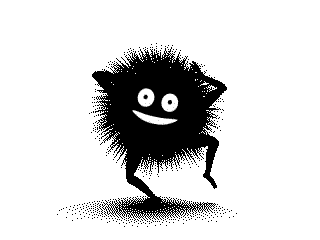




「 あゝ・・・・・今日は28日。そうや、星まつりの日ィや・・・・・! 」
書斎の前に佇んでいた秋一郎がくるりと振り向くと、やゝ小首を傾かしげ何ごとかを促そうとする貌(かお)は、そのことを言いたげな目をしていたし、和歌子は一瞬、自身の目が洗われるような気がした。
「 せやけど、忘れてたこと、死にはった人に話ィすることもできィへん。ほやけど、ご先祖はんは、それでもジッと睨みはるンや! 」
夜明け前の暗がりに和歌子が窓辺から頬杖(ほほづえ)を立てゝみる、その足音の無い冷たい雨は、裏庭のもみじ葉の青をふるえさせ山陰(やまげ)にある大きな菩提樹(ぼだいじゅ)の葉を寒々と濡らし続けていた。




瓜生山をこぬかに濡らしながら狸谷を地の底のように凍らす早春の雨なのである。
この季節の雨を木芽起(こもめおこし)ともいうが、立春を過ぎて京都に降る雨は未だ氷雨のように冷たいものであった。これを春と聞かねば知らでありしを、という。
「 世間さまに対しシニカルにふるまうのは簡単なことや。そうして、背負わされるもの、心の中にたまるものを発散さして、リバタリアンで生きてゆけたら、そらぁ~素晴らしいことやァ~。せやけどそれが昨今の日本人の先行きが暗うなった理由(わけ)なのやおまへんか。せやろ、秋一郎はん!。あんた、生きてはったら、そらァ~怒らはるやろな~・・・・・ 」
と、誰と語るでもなく菩提樹をながめる和歌子はそうしんみりとつぶやいた。
じっと見いるそれは、阿部家に永く長く居座る菩提樹なのだ。
「 たしか、あの詩ィの吉丸一昌というお人は、豊後の国のお武家さんの子どしたなぁ~・・・・・ 」
比叡山の山端に秋子と暮らす和歌子は、この早春の賦(ふ)に思惑という怖さを感じるのだ。
幕末生まれの祖父二十三代目の清衛門が他界して早50年になる。父秋一郎が他界して40年目の春を迎えた。その思惑とは和歌子にとって或る種の石のような存在であり、清らかな川の流れを保つ葦でもあった。早春賦(そうしゅんふ)がこの世に生まれた大正二年、清衛門は同年に初めて秋一郎と廻り逢えたのである。それは天の思惑に違いない。かねて定められた天の配剤に違いないのだ。

「 和歌子・・・・・!。加賀にな、白山いう神様の山があるんや。その山の冬の終わりにな、淡い赤の花が美しゅう咲くんや。そりゃ~綺麗な花でな、その花がある雪の降る日、ポトリと涙ァ流しはるのや。寒いんや。それを雪が見てゝな、寒いんやなぁ~と思うんや。そしたらな・・・・・、雪は悲しくなってな、羽ェ落しはるんや。それ、お父ちゃん見てゝ、冬いうもんはこないして終わるんやと思たんや。そない思いながらみてたら雪の羽・・・・・、ふわりと、どこかへ消えてしもた・・・・・ 」
これは父から習った呪文のような子守唄である。と、そう言うと、夢の白山に立つ秋太郎は静かに眼を閉じてそれをじっと聞いた。そして聞き届けたかのようにス~ッと姿を消したのだ。

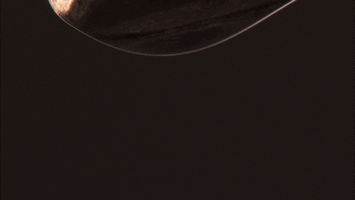

「 せんないなぁ~・・・・・ 」
こゝ数年、立春が過ぎると喜びより不安が先に立ちあがる和歌子である。
胸の底から黒雲のように不安が湧き上がるのであった。昭和天皇がお隠れになると、塗炭(とたん)に世の中が乱れ心安らかならぬものを感じるようになった。今の世間には人々の悪意に満ちた視線(まなざし)が多すぎるのである。
「 これらは末法の世の証あかしなのか・・・・・ 」
母ひとり子ひとりの少年によって毎朝宅配される新聞には、心にひそむ地獄を目の当たりにするし、目を伏せたくなるような惨事が多く載るようになってきた。すると、毎日ながめつゞける新聞上欄に刻まれる小さな平成という文字は、すでに血色が絶えて言霊(ことだま)は失われている。平成という意味なき姿だけが何やら哀し過ぎるのだ。
「ほんに、戦後の日本人は陰湿に奇妙なんやさけ・・・・・ 」
そう思う耳には、チリリン・・チリリン・・チリリンと、狸谷を静かに渡る鈴がある。
おそらくお山の御坊にも届いているであろう。
風が東へとなびけば、琵琶湖の左岸、鈴の音は峰を下り、坂本の日枝社辺りまで届く。いや気流に乗れば彦根にも届く。雪化粧の瓜生山へと分け入り、秋子は村人が天にでも昇るような趣の神さびた鈴音をゆるやかに鳴らしていた。
じっと居間に正座してその鈴の音を耳もとに曳きつけていた和歌子は、一度コクリと頷うなずいて、さらにゆっくりと安堵したかに二度頷くと、おもむろに裏山の方をじっとみつめた。
そして今朝も昨朝と変わらずに比叡の空に凍える一樹であることを看取ると、阿部家のその菩提樹が、春の賦(くばり)を語りかけてくる幽かな声に耳をそっと澄ました。
「 聞けば急かるゝ胸の思を、いかにせよとのこの頃か・・・・・ 」
と、今年もまた菩提樹は和歌子の胸にそう訴えている。和歌子はその声にまた頷いた。
阿部家には三度頷くという覚書があるからだ。
菩提樹の声は、阿部家が生まれつき授かる天賦(てんぷ)なのである。代々の家長が、春のくばりを聞かされてきた。そしてこの稟性(ひんせい)を授かるからこそ、阿部家は民衆を束ね集落の生を守り抜いてきたのだ。

立春は二十四節気の一つで、冬至と春分の中間にあたり、この日から立夏の前日までが暦の上での「春」となる。吉丸一昌(よしまるかずまさ)は、大正の初期に長野県安曇野を訪れ、穂高町あたりの雪解け風景に感銘を受けて「 早春賦 」の詩を書き上げたが、狸谷の「 春は名のみの 」とは、菩提樹によって交感させられる春のくばりであった。
鈴の音が続けば続くほどに、菩提樹の枝先は揺れた。狂うほど揺れ騒げば大吉である。
「 秋子、それで、えゝんや・・・・・。ようやくこゝまでに・・・・・ 」
この鈴音は狸谷の冬を溶かすために、秋子が今振り注ぐ代々に阿部家が守り継がねばならぬ呪文である。瓜生山の頂から秋子は菩提樹に向かって一心に祈祷の咤怒鬼(たぬき・鈴)を振り続けていた。

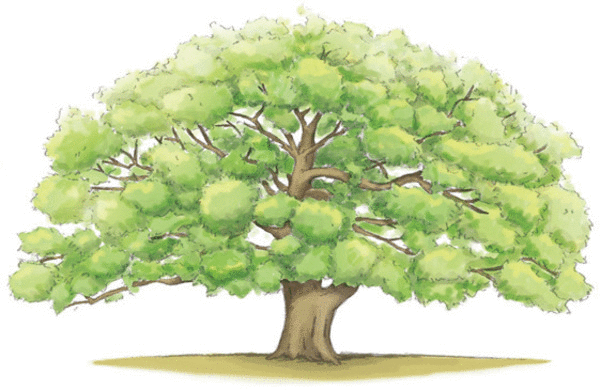
「 やはりこの一樹は、永い絶望と失望を照らさはるための、神か仏の手による一筋の光なんやと思う。私(うち)らはその木守なんや。そないして、今、この樹ィは十代目なんや・・・・・! 」
日本へは、臨済宗の開祖栄西が中国から持ち帰ったと伝えられるが、阿部家初代の菩提樹は紀貫之(きのつらゆき)のころと伝えられている。そして十代目は明治期に、祖父の阿部清衛門の手で長崎を経て移植された。そう伝えられるこの十代目も、和歌子が思うには、何やら伝説めいている。が、ともかくも清国五山寺院の一つ径山寺(杭州余杭)のモノを、清衛門が遠く船で運んだと伝え聞く菩提樹の老樹は、冬の終わりの雨に、たゞしっとりと濡れるに身を任せながら、一時も怠ることなく和歌子が気にかけている暗示を永年物語り続けてきたのだ。そして、くばりには警鐘の凶事を兆す声のときもある。そこには聞き逃すことが許されぬ兆候があった。
「 そや、半夏生はんげしょうや・・・・・!今年もきはるんやなぁ~・・・・・ 」
また菩提樹は、さらに夏を告げて、修験者は深山幽谷へと分け入り修行に籠る。
決まって毎年六月も末になると、一樹は或(あ)る花言葉と、ふくよかに誘う香りとでそのことを証明してくれるのであるから、やがて梅雨を越えるであろうそんな菩提樹をみつめていると、兄富造の声が和歌子の耳に懐かしく聞こえた。
「 半夏生の日は、天地に毒がみちるから裏の竹林には入るな! 」
という。村衆や幼子らを戒めていた言葉が、今朝もまた自然に蘇るのであった。
遠い空の上から聞こえてくる、そんな富造の厳格で野太い声がす~っと耳奥で籠こもると、今年もまた和歌子には確かな期待と不安が交錯して溢れ出してきた。夏が廻ることの序に従いて、小雪を散らす仕種で此(こ)の一樹の花が裏山に落ちると、決まって半夏生となる。菩提樹の淡い黄蘗(きはだ)の花は、父秋一郎や一族の面々らと和歌子に夏至を、そして今尚、同族と村衆を固く結ばせていてくれる花なのである。 夏安吾(げあんご)の山入りの前になると、数多くの修験道が阿部家の門を法螺貝(ほらがい)の音で叩いた。

毎年、阿部家では、黄蘗の花を草木染めにして黄海松茶(きみるちゃ)の細縄をなう。 最多角念珠(いらたかねんじゅ)にその荒縄を結いつけるのである。それは修験者が使う念珠で一つ一つの珠はそろばんのような形をして、これを摺ることによって煩悩を打ち砕くという意味をもち、珠は衆生の本来的な悟りを表している。
阿部家の黄海松茶の縄を結えば、星月菩提樹の念珠より霊験あらたかとの評判を呼び、多くの修験道が入山の際に訪れた。修験者は常に世寿(せじゅ)を求め、つゝがなく夏安居を終えると夏臘(げろう)を得て、また一つ法臘(ほうろう)を足すことになる。安居の回数が僧侶の仏教界での経験を指し、その後の昇進の基準になるなど、非常に重要視される。阿部家の黄蘗縄はいつしか飛鳥寺や延暦寺の安居院法印にも用いられるようになった。

人知れず花を咲かせ続けるそんな一樹には、やはり語り尽くせぬ深い感慨がある。
そうであるからこそ和歌子もまた、まだ花の無い二月の季節に無言(しじま)に立ちつくす、古老の黒い菩提樹を愛おしく大切に見届けたかった。いつも和歌子はそんな一心から、一樹が春立ちて変わり行く様子を眼を凝らしてじっと見続けてきた。

六時前にはすでに旅支度を整え終えた和歌子には、まだ一時間ほどの余裕が残されていた。
今日、和歌子はニューヨークへと旅立つのだ。
旅支度を整え終えて間もなく山を下りてくる秋子を静かに待っていた。今一度言い含めておくこともある。三千院は2月になると和歌子に星を咲かせてくれ宿曜経を伝える寺であった。幼くして母を亡くした和歌子は毎年立春を過ぎると祖父や父の手にひかれて、50年前に祖父清衛門が他界し、父も他界してからは欠かさず一人で星まつりに訪れていた。
「 雲母漬ゆうんは、おそらく京都でもこのお店でしか売ってないのんと違いますやろか。穂野出(ほので)ゆう店で売ったはるのが それになります。そやかて、今の時期、予約しとかんと、もうありまへんわ 」
という、何かと手配をこまごまとする、先日そんな話をくどくどと秋子にした。
三千院の星まつりの日では、祖父の代から毎年欠かさずに雲母漬(きららづけ)を大原に持参する手筈となっている。
ことしは秋子を参代させることにした。手筈とは、阿部家では仕来たり。その仕来たりとは欠かすことのできぬ神事となる。この手筈に落度とか欠落は許されなかった。
今の内によくよく言い含めておかねばならぬことは、その一つ一つがいずれも欠落を許されるはずもなき神事なのである。
しかし、それは宮司や禰宜(ねぎ)のように神の心を和ませてその加護を願い祭祀に専従する者の立場とは違う。また御仏に仕え経・律・論を修める三蔵でもなければ具足戒を授ける僧伽(さんが)や比丘(びく)などとも異なる。阿部の家長は、神に祈請をし、祈請を憑依させ、神意を示現せしめる六神通(ろくじんつう)の手立者でなければならなかった。そうであれば、あるいは神・仏の立場からみる波羅夷(はらい)罪者であるのかも知れない。その波羅夷罪とは波羅夷法四ヶ条を犯すこと、その犯人は僧伽を追放される。この世に必要悪というモノがある。しかし反面、不必要善というものもある。この両者は矛盾して闘争を繰り返し続ける宿命にある。阿部家はそこに介在することで存在する。だがそこには啓示をえるしかるべき手続きが必要であった。
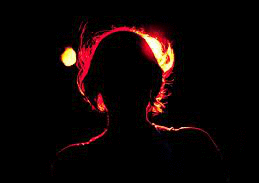
「 第二十六代いうても、未だおぼつかない・・・・・。二十五代の半分目しかあらへん・・・・・! 」
秋子をそう憂い思えばもうさほどの余裕もない。
整理箱の引き出しの奥から一枚のCDを取り出すと、そっとパソコンのイジェクトボタンを押した和歌子は、秋子から習った通りに、開いたトレイへとそのCDを乗せてドライブへとスルーした。秋子もこのようにスルーできたらと考えたくもなる。
和歌子は少し笑った。それはミュラーが遺した「冬の旅」の詩と、シューベルトの旋律を思い出させるCDであった。この冬の雨には、もう決して手に入らないものへの憧れが満ちていた。
和歌子はこれがどう自身に聞こえるのかを試みたかった。音楽は阿部家の子女に欠かせぬ素養なのだ。唯一の慰めである「死」を求めながらも、旅を続ける若者の姿は間もなく現代を閉じようとするから、今少し何かに生きようとする老人にとっては強く訴えかけるものを感じさせた。和歌子の眼には、ヴィルヘルム・ミュラーの水車小屋がある。そこに行けば、決して得られないもの、もう失われてしまったものへの憧れに満たされるに違いない。たしかにそう感じされるものがあった。和歌子はスーツケースの荷物をもう一度確認し直した。そこには河井寛次郎作の紅彩鉢が厳重に梱包されている。愛おしく改めると丁寧にそっとケースを閉じた。

「 あゝ~・・・・・、あのときの、うちの夢・・・・・、空っぽのまゝやわ・・・・・ 」
あのとき和歌子は、日付変更線上の大海原に浮かぶ甲板に立ち東へと雲がなびく感じをさせて師走の冬空の鈍い広がりに一等の嬉しさで希望の夢を描いていた。しかし今にしてそれは空回りする夢である。たしかあと五日するとロスに着き、そこから鉄路で大陸を横断して聖夜のボストンに到着するのだ。乙女であった和歌子には、かってそんな一人洋行の大志があった。
「 あれや・・・・・、龍田丸や! 」
出航時、みんなが持つ紙テープも華やかに舞っていた。
日米開戦が噂される中、昭和16年12月2日、日本郵船の豪華客船龍田丸(16955トン)が静かに横浜港を出航した。行く先はロサンゼルス経由バルボア(パナマ)である。和歌子もその渡航者の一員であった。国事動乱の最中に、西洋音楽に武者修行させる親もいたのだ。音とは一大事、その父秋一郎が一人だけ多勢の見送り者から離れた位置でポツリと立っていた。このとき大本営は龍田丸の出航停止を検討していた。しかしそれでは日米開戦を知らせることになってしまう。そこで当初11月20日であった出航日を、変更させることにした。
出航が11月20日の場合、ロス着12月3日、バルボア着17日、18日ごろになる。真珠湾攻撃日が決定されている以上、バルボアでは確実にアメリカ軍に拿捕されることが明らかであった。大本営は12月2日に日程をずらした。そして大本営の計画通り12月2日に出航した龍田丸は、12月8日には、まだ180度あたり(日付変更線)なので、敵に拿捕されないギリギリの地域でUターンし、全速力で横浜に向かい、12月14日横浜に寄港した。この計画を知っていたのは、乗船した海軍軍務局の市川少佐と本村船長だけだった。

「 あの当時、花形やった。今の飛鳥より、そらァ豪華に思われたもんや・・・・・ 」
他の客船を圧倒する大豪華客船であった。龍田丸は航海運航終了後、海軍に徴用された。昭和18年2月8日、風速20mの暴風雨の中、トラック島に向けて横浜港を出航した龍田丸は、米潜水艦ターホンの雷撃を受け、御蔵島近海で沈没した。
乗組員198名、乗船員1283名、全員死亡、生存者は一人もいないという悲劇的な最期を遂げた。太平洋横断を100回以上にも超えた龍田丸一世は今も東京湾から南西約200㎞の御蔵島沖に静かに眠っている。その当時は、大時化ということもあって、雷撃を受けて20分後には姿が見えなくなり、翌日朝から本格捜索をするも、重油以外の浮遊物は見つからず、飛行機での捜索も行われたが、龍田丸の痕跡は何一つ見つかる事はなかった。
「 僕は彼女のところから帰る。明るい月夜だった。僕は再び頼みたい。愛する月の光よ。月はまさに僕の顔を見て、合図してくれているようだった。その時僕は月を覗き込んだ。僕には、彼女の青い両目が金色の円から見ているように思えた。ルイーゼ、きみは確かにその瞬間、上を見ていた・・・・・ 」
と、紡ぎ出す言葉に合わせ、和歌子はもう一度、ミュラーが遺した「冬の旅」の詩と、シューベルトの旋律を頭から聴き直した。つぶやいた詩的な言葉はミュラーの日記から拾った。ヴィルヘルム・ミュラーの詩は、天体を愛する人の目に喩たとえた。渡米に際し和歌子は、その天体を愛する人の瞳を持たねばならなかった。今回、ニューヨークにては、と或るドイツ人女性が渡米を待ち望んでいる。またヴィルヘルム・ミュラーもドイツに生まれた。そしてそのドイツ人女性と会った後に、M・モンテネクロ氏と会うことになるだろう。この冬の空から一時も早く離れて、和歌子はまた春の狸谷の夜空を仰げたらと考えている。

「 遣独(けんどく)潜水艦作戦の手記・・・・・これをお還しすることで阿部家もまた本来に還るんやわ・・・・・ 」
と、内容を未だ人知れずする古い手記を、スーツケースの一隅に、当時のまゝの包み袋の状態で入れてあるが、和歌子はその風体を眼に浮かべた。それは兄富造の遺品である。しかし正確には富造が密かに保管していたドイツ人女性の遺族者に拘わる私有物なのだ。
ドイツによる怒涛の攻勢が落ち着きを見せた1942年も半ばを過ぎると、大西洋上に張り巡らされた連合軍の哨戒網(しょうかいもう)により、これらの水上艦にとって安全な航路はもはやなかった。このためドイツより電波探信儀(レーダー装置)導入を希望する日本海軍は、大型潜水艦をドイツに派遣することを決した。これが遣独潜水艦作戦の始まりであった。
富造が保管して遺した手記とは、その遣独潜水艦作戦の極秘記録である。
そして富造はこの作戦に関与していた。生前に富造は「 もしこの手記が、終戦直後に露呈していれば、違いなく俺は戦犯を免れることはなかっただろう・・・・・ 」と、手記の存在を和歌子に打ち明けたとき、そう語った。
すると、阿部家に連なる龍神の船影には幾人もの人影が赤く重なる。
「 しかし・・・・・、これを万事解決とすれば、山端集落の再生に目途がたつ。その確約はあのときの秋子の生死にかゝっていたんや! 」
と、思えたとき、またふと父秋太郎の言葉の遺り影を拾った。
「 山端には、そして比叡の森にはじょうさん花があるんや。その花、上手に使わしてもろうてな。木の卒塔婆やなくて、あれどうにも冷たいやないか。そうやから替わりにな、野に咲く花卒塔婆(はなそとば)じょうさん立てたろ思うとる。いつか山端いっぱいに、そうしたるんや 」
その声の柔らかさは、加賀白山に降る秋一郎が語った雪の羽のように暖かくふわりと飛び跳ねて冬を終わらせる聲(こえ)と同じように聞こえた。和歌子はこの聲に背を押されたがために雨田博士に一切を委ねたのだ。
「 花そとば・・・・・羽そとば、・・・・・これは六(りく)の花と羽なンや・・・・・ 」
何やら、どこに、どの花をと、思いめぐらせば、手向けてみたくなる花は数限りなくある。ようやく瓜生山から下りてきた秋子は手に小さな花籠を持って微笑んでいた。
「 うち・・・・・、見送りしィへんえ。星まつりの花、探さなならへん・・・・・ 」
と、あっさりとしたもので、その秋子が手のひらに乗せた可憐な白花のハナネコノメの赤い葯(やく)に指先が触れた和歌子は、この娘はすでに花卒塔婆をあしらう巫女(ひと)に熟(なれ)たのだと思えた。そしてそんな秋子の健やかな表情を看取ると、あのときの雨田博士の思惑がようやく成功裏に終わったのだと思えた。

「 千賀子、京都駅に来るいうてたから、来るやろうし。秋子はそれでかまへん。星ィ~になッ、雨田博士ェも入れへんとあかンえ!。あんたの恩人やさかいに・・・・・ 」
そういゝ返してまた秋子の眼をじっと見てみると、その眼の湖(うみ)にある静かさはやはり甥の清四郎と瓜二つである。秋子は清文やというが、和歌子に、甥の本名はやはり阿部清四郎なのである。その清四郎はやはり秋子を遺すためにこの世に生まれ山へ消えたのだと思えた。
「 籠(こも)よ み籠持ち 堀串(ふくし)もよ み堀串(ぶくし)持ち この岡に 菜摘ます子 家告のらせ 名告らさね そらみつ 大和の国は おしなべて 我れこそ居れ しきなべて 我れこそ居れ 告らめ 家をも名をも 」
と、妹の千賀子は京都駅のロビーで姉和歌子の背にこの歌を問いかけた。
「 泊瀬(とまりせ)の朝倉の宮に天の下知らしめす天皇の代 」
問いかけに、和歌子はこう応え返した。これは阿部家に継がれる陰陽の問答である。

門出に添えるべきはこの方違(かたちがえ)の仕来たりであるが、その門出とはモノの初め、千賀子が問いかけた歌は、万葉集の巻頭を飾る矢立てなる初めの歌であり、阿部家では門出にこれを天晴(あっぱれ)の言霊(ことだま)とした。今に訳すと「 籠もよい籠を持ち、掘り串もよい掘り串を持って、この丘で菜を摘む娘よ。あなたの家を教えておくれ、あなたの名前を教えておくれ。この大和の国は私が従えているのだ。私がすっかり支配しているのだ。私は告げよう、家も名も 」となる。この歌は、もともと求婚のための民謡歌であったが、古代を代表する天皇である雄略天皇の物語と重なり、いつしか、雄略天皇の作とされるようになったようだ。

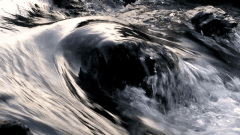
「 せっかくやして、うちもこれから、初瀬(はつせ)、いこ思いましてな・・・・・ 」
どうやら千賀子は、和歌子を見送った後、長谷寺へと行く予定でいる。その長谷寺の初瀬とは平安遷都以来忘れ去られたようにあるが、奈良朝の当時は阿部家太祖に因む土地柄であった。海石榴市(つばいち)から東へ初瀬川沿いを進むと長谷寺のある初瀬にいたる。現在、初瀬川は大和川とも呼ばれているが、当時は泊瀬川と記された。また三輪山麓では三輪川と呼ばれていた。初瀬にむかって上り坂で、初瀬川をはさんで、北に現在の国道165号線、南側に近鉄大坂線が走っている。万葉の時代、ここは埋葬の地であった。そして泊瀬の水と狸谷の井は、代々継々にして龍田神の守る一筋の流れで結ばれている。
昭和という時代が終焉し、平成という新時代になった今、この濁流に、和歌子は時代に褪(あせ)たその水の澱みを動かそうとしていた。
「 そうかえ、で・・・・・、長谷寺の真悟はん、今日来てくれはるいうてはったなぁ~。真悟はんなら秋子も安心やろし・・・・・ 」
初瀬山の山麓から中腹にかけて伽藍が広がる長谷寺は、平安時代中期以降、観音霊場として貴族らの信仰を集めた。和歌子がそういう真悟とは、雨田虎哉が芹生の里でみかけた牛を曳く少年である。和歌子の留守中、秋子の加勢を頼んであった。
「 きっとこの時間、もう狸谷に着いてますやろ。でっち洋かん。、忘れんと一乗寺中谷(なかたに)で買うよう頼みましたさけ。毎年きらら漬だけやと何や味気ない思いましてなッ。それ、星まつりに持たせたろと真悟に頼みましたんや。ほならこれ、襟の合わせに挿してくれやす 」
と、千賀子はそういって、さりげなく小さな一輪を差し出した。
それは白花のハナネコノメ、どうやら秋子と示し合わせたようである。千賀子は芹生で同じ花を早朝に摘んでいた。昨夜、秋子に頼まれたのだという。和歌子はまた留守を守る秋子を案じながら指先で赤い葯(やく)に触れた。
すると憂いた狸谷を眼に浮かばす和歌子の母心は、晴れ晴れとその花の彩りに〆(しめ)られた。
そして阿部和歌子80歳は単身、ニューヨークへと旅立った。










奈良 桜井 長谷寺









