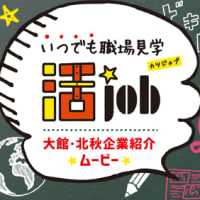太公望といえば、魚を抱えて肩に釣竿、といったイメージを浮かべがちだが、実は中国兵法の始祖とされる名軍師。そして「六韜」も「三略」も、この太公望の流れをくむ兵法書の名著とされ、時にあの「孫子」に比肩するものとされてきた。
たとえば「六韜」については、三国志の主役の一人、呉の孫権は部下の将軍に向かって、必読兵書として「六韜」を「孫子」と共に名指しであげている。すでに「六韜」は、この時代からリーダーの座右の書とされてきたのである。また、日本では大化の改新の藤原鎌足は、自らの政治処世の参考に、この書をしばしば使ったといわれる。
また、「三略」にもファンは多く、たとえば小田原北条氏の始祖早雲は、「三略」の一句を聞いて兵法の極意を悟ったと伝えられている。あるいはまた、明治になると嘉納治五郎が現れ、「柔よく剛を制す」を柔道の極意としたことは広く知られている。 「六韜・三略」のおもしろさは、単に兵法、いわゆる戦いの原則のみならず、加えて政治学の要諦、人材活用術、リーダー学などにも言及し、内容に奥行きと広がりがある点にある。 なお、「六韜・三略」は単発で、1994年に刊行され好評を博したが、今回「武経七書」の一冊として刊行するに当たり、大幅に手を入れ加筆修正している
たとえば「六韜」については、三国志の主役の一人、呉の孫権は部下の将軍に向かって、必読兵書として「六韜」を「孫子」と共に名指しであげている。すでに「六韜」は、この時代からリーダーの座右の書とされてきたのである。また、日本では大化の改新の藤原鎌足は、自らの政治処世の参考に、この書をしばしば使ったといわれる。
また、「三略」にもファンは多く、たとえば小田原北条氏の始祖早雲は、「三略」の一句を聞いて兵法の極意を悟ったと伝えられている。あるいはまた、明治になると嘉納治五郎が現れ、「柔よく剛を制す」を柔道の極意としたことは広く知られている。 「六韜・三略」のおもしろさは、単に兵法、いわゆる戦いの原則のみならず、加えて政治学の要諦、人材活用術、リーダー学などにも言及し、内容に奥行きと広がりがある点にある。 なお、「六韜・三略」は単発で、1994年に刊行され好評を博したが、今回「武経七書」の一冊として刊行するに当たり、大幅に手を入れ加筆修正している