老年に思うこと
「野上弥生子女史は、私より15歳も年上で、まだ生きておられる。10年近く前、86歳の頃の女史のことを小林勇氏は次のように書いておられる。「86歳で女史が北軽井沢で創作に打ち込む日々は充実したもので、今書き続けている長編が完結しようが、未完で終ろうが、どちらでもよいという。悠々と青空を流れる白雲を見る思いだ。すべてのものに終りがある。日々終りに近づきつつ思うことは日々に新たである。昨日よりは深くものを見、その美しさを感ずる」すぐれた人の老年の心境を美しいと思う。そして私もそうなりたいと思う。
私は毎朝『聖書』を読む。私は英語の教師だったので、英語で『聖書』を読むことが長年の日課である。「朝は起きて『聖書』を読み、昼はつかれるまで働き、夜は祈りて眠る」という羽仁もと子さんの言葉を日記の扉に書き記したこともあるが、私は『聖書』に導かれ、力づけられて生きている。
私が今日まで続いて集会に出て、教えを受けている宗教上の先生は、川合信水先生のキリスト教を受け継いでおられる原田美実先生である。この先生に導かれること40年に近いが、この先生についたことの幸せを思わないではいられない。先生もすでに85歳、いつまで生きていていただきたいと思う。
近頃私と同年輩の人、私より少し年下の人が次から次へと亡くなって行く。若い頃関西学院高商部の教師として一緒に働き、生涯親近感をもって交わった加藤秀次郎氏も亡くなった。加藤氏と私は専攻も同じ英語だったし、高商部で学生指導の労苦を共にし、私の中学部長退職のときには、私のあとを加藤氏に引き受けてもらったり、また加藤氏の理事長退任のあと、私が理事長になったりして、氏とは長く親交をもったが、加藤氏のように、学院の年上の人とも、同年輩の人とも、年下の人ともきれいに交わった人は少ない。同僚や教え子が病気になったら、必ずといってよいほど見舞に行かれた。加藤氏は関西学院の卒業生ではなかったが、関西学院にとけ入って、これほどみんなから好感を持たれていた人は少ない。
萌え出でて光たゆたう青芝に
季毎まむかい年経りにけり
これは加藤氏の歌集『青芝』の表題となった作品だが、なつかしい歌だ。
加藤氏からも、其他多くの同僚からも私の学んだことは多い。私の教え子も立派に社会的に活躍している人が沢山あり、そういう人たちから教えられたことも数限りなく思い出される。小さい頃弱く、若い頃結核にもなった私がこうして80までも生き残るために、医師その他お世話になった多くの方々も忘れがたい。
結婚当時、家に帰ると玄関でかばんを投げ出して、「ああ、疲れた」といって妻を心配させたが、今日まで生き得たのは、妻が私の健康に気を配ってくれたことにもよる。
生涯を顧みてつくづく思うことは、人間は一人で生きられるものではなく、一人で育つものではないということである。私の生涯は、「目に見えないもの」「目に見えるもの」に守られ、導かれ、支えられた生涯であった。そして私が他から与えられ、教えられたものに比べれば、私が他に与え、教えたものは、全くいうに足りないほどに乏しい。
これから後の年月をどう生きるかが、私の課題である。 」
『人間の幸福と人間の教育』矢内 正一著(昭和59年9月30日創文社) より
「野上弥生子女史は、私より15歳も年上で、まだ生きておられる。10年近く前、86歳の頃の女史のことを小林勇氏は次のように書いておられる。「86歳で女史が北軽井沢で創作に打ち込む日々は充実したもので、今書き続けている長編が完結しようが、未完で終ろうが、どちらでもよいという。悠々と青空を流れる白雲を見る思いだ。すべてのものに終りがある。日々終りに近づきつつ思うことは日々に新たである。昨日よりは深くものを見、その美しさを感ずる」すぐれた人の老年の心境を美しいと思う。そして私もそうなりたいと思う。
私は毎朝『聖書』を読む。私は英語の教師だったので、英語で『聖書』を読むことが長年の日課である。「朝は起きて『聖書』を読み、昼はつかれるまで働き、夜は祈りて眠る」という羽仁もと子さんの言葉を日記の扉に書き記したこともあるが、私は『聖書』に導かれ、力づけられて生きている。
私が今日まで続いて集会に出て、教えを受けている宗教上の先生は、川合信水先生のキリスト教を受け継いでおられる原田美実先生である。この先生に導かれること40年に近いが、この先生についたことの幸せを思わないではいられない。先生もすでに85歳、いつまで生きていていただきたいと思う。
近頃私と同年輩の人、私より少し年下の人が次から次へと亡くなって行く。若い頃関西学院高商部の教師として一緒に働き、生涯親近感をもって交わった加藤秀次郎氏も亡くなった。加藤氏と私は専攻も同じ英語だったし、高商部で学生指導の労苦を共にし、私の中学部長退職のときには、私のあとを加藤氏に引き受けてもらったり、また加藤氏の理事長退任のあと、私が理事長になったりして、氏とは長く親交をもったが、加藤氏のように、学院の年上の人とも、同年輩の人とも、年下の人ともきれいに交わった人は少ない。同僚や教え子が病気になったら、必ずといってよいほど見舞に行かれた。加藤氏は関西学院の卒業生ではなかったが、関西学院にとけ入って、これほどみんなから好感を持たれていた人は少ない。
萌え出でて光たゆたう青芝に
季毎まむかい年経りにけり
これは加藤氏の歌集『青芝』の表題となった作品だが、なつかしい歌だ。
加藤氏からも、其他多くの同僚からも私の学んだことは多い。私の教え子も立派に社会的に活躍している人が沢山あり、そういう人たちから教えられたことも数限りなく思い出される。小さい頃弱く、若い頃結核にもなった私がこうして80までも生き残るために、医師その他お世話になった多くの方々も忘れがたい。
結婚当時、家に帰ると玄関でかばんを投げ出して、「ああ、疲れた」といって妻を心配させたが、今日まで生き得たのは、妻が私の健康に気を配ってくれたことにもよる。
生涯を顧みてつくづく思うことは、人間は一人で生きられるものではなく、一人で育つものではないということである。私の生涯は、「目に見えないもの」「目に見えるもの」に守られ、導かれ、支えられた生涯であった。そして私が他から与えられ、教えられたものに比べれば、私が他に与え、教えたものは、全くいうに足りないほどに乏しい。
これから後の年月をどう生きるかが、私の課題である。 」
『人間の幸福と人間の教育』矢内 正一著(昭和59年9月30日創文社) より










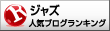










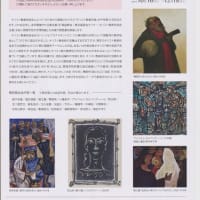






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます