中学部の教育
「関西学院中学部の教育はキリスト教を中心とし、知育・体育・徳育のバランスのとれた教育をしたいと私は心から願った。毎朝全校の礼拝があり、私もそれに必ず参加した。中学部長になってからも、私は週に12時間の授業を最後まで担当した。私の英語の授業はきびしくて、生徒にはつらかったようだ。毎朝始業前に生徒の有志と1700メートルばかり走ることも10数年続いた私の日課だった。
愛すべき生徒が多かった。1人の生徒は次のような文を書いた。
僕は小学校のころは野球がすきでしたが、中学部ではバレーボール部に入りました。3年になって一つの悩みがありました。それは一年の部員が少なく、2学期には1年は1人だけになってしまいました。その子は1BのM君でした。体が大変小さいので、なかなかボールがうまく扱えませんでしたが、毎日練習をしていました。
2学期のある日、練習を終ってから上ケ原の道を走り、1周して帰って来た者から帰宅することにしました。大きな3年生にまじり小さなM君も走りました。そして皆に大変おくれて帰って来ました。もちろん一番びりでした。
僕とキャプテンと2人残っていて、帰って来たM君と3人でお祈りをしました。祈ることはバレー部の習慣でした。練習のあとみんなで輪になってだれかが祈るのですが、その日は他の者を先に帰らせましたので、3人だけで祈ったのです。すると祈りの途中でM君が泣きだしたのです。それで"練習がつらいか"とききますと、"つらくない"と答えたのですが、きっとつらかったのだろうと思います。 僕は次の日にM君が来るだろうか、つらくなってやめはしないだろうかと心配しましたが、次の日にM君はやっぱりいつものように来ていたので、ほっとするやら、うれしいやら、ほんとうに感激しました。
今では1年の部員も増えました。僕は下級生をしっかり練習させ、団結力とファイトを養いたいと思います。安心してあとをまかすことの出来るバレー部にすることが僕の願いであります。
私は昭和32年欧米を旅して、英国ではイートン、ラグビー等たくさんのバブリック スクールを見、ますますこれらの学校の教育がすきになった。これらの学校は宗教、スポーツ、寄宿舎を重要視しているが、これらの学校のような行き届いた皆寄宿制度は日本ではなかなか困難なので、中学部ではキャンプによる鍛錬を計画し、入学と同時に全生徒を千刈のキャンプ場につれて行って宿泊訓練をし、夏は海のキャンプ場において生活訓練をした。
中学部は、昭和37年瀬戸内海の無人島(青島)を専用のキャンプ場として買った。青島は岡山県の牛窓の沖にある約11万平方メートルの島で、生徒たちは毎年汗を流してこの島を開拓し、幾棟かの宿舎が建って大変いいキャンプ場になったことは、私の心からの喜びであった。
中学部は500人の小さな学校で、休暇などにも全校の生徒に対し、私が1人1人文通出来たことは、私と生徒との心のつながりのもととなった。私は返事を出すのではなくて、私の方から先に、お正月と夏休みに1人1人の個性に合わせて激励の言葉を書いて、全校の生徒に葉書を出した。これはむしろ私の趣味だったかも知れない。中学生は実にかわいかった。「なぜ世間の人は中学の教師にならないのだろう」と、私はよく人に語った。 」
『人間の幸福と人間の教育』矢内 正一著(昭和59年9月30日創文社) より
「関西学院中学部の教育はキリスト教を中心とし、知育・体育・徳育のバランスのとれた教育をしたいと私は心から願った。毎朝全校の礼拝があり、私もそれに必ず参加した。中学部長になってからも、私は週に12時間の授業を最後まで担当した。私の英語の授業はきびしくて、生徒にはつらかったようだ。毎朝始業前に生徒の有志と1700メートルばかり走ることも10数年続いた私の日課だった。
愛すべき生徒が多かった。1人の生徒は次のような文を書いた。
僕は小学校のころは野球がすきでしたが、中学部ではバレーボール部に入りました。3年になって一つの悩みがありました。それは一年の部員が少なく、2学期には1年は1人だけになってしまいました。その子は1BのM君でした。体が大変小さいので、なかなかボールがうまく扱えませんでしたが、毎日練習をしていました。
2学期のある日、練習を終ってから上ケ原の道を走り、1周して帰って来た者から帰宅することにしました。大きな3年生にまじり小さなM君も走りました。そして皆に大変おくれて帰って来ました。もちろん一番びりでした。
僕とキャプテンと2人残っていて、帰って来たM君と3人でお祈りをしました。祈ることはバレー部の習慣でした。練習のあとみんなで輪になってだれかが祈るのですが、その日は他の者を先に帰らせましたので、3人だけで祈ったのです。すると祈りの途中でM君が泣きだしたのです。それで"練習がつらいか"とききますと、"つらくない"と答えたのですが、きっとつらかったのだろうと思います。 僕は次の日にM君が来るだろうか、つらくなってやめはしないだろうかと心配しましたが、次の日にM君はやっぱりいつものように来ていたので、ほっとするやら、うれしいやら、ほんとうに感激しました。
今では1年の部員も増えました。僕は下級生をしっかり練習させ、団結力とファイトを養いたいと思います。安心してあとをまかすことの出来るバレー部にすることが僕の願いであります。
私は昭和32年欧米を旅して、英国ではイートン、ラグビー等たくさんのバブリック スクールを見、ますますこれらの学校の教育がすきになった。これらの学校は宗教、スポーツ、寄宿舎を重要視しているが、これらの学校のような行き届いた皆寄宿制度は日本ではなかなか困難なので、中学部ではキャンプによる鍛錬を計画し、入学と同時に全生徒を千刈のキャンプ場につれて行って宿泊訓練をし、夏は海のキャンプ場において生活訓練をした。
中学部は、昭和37年瀬戸内海の無人島(青島)を専用のキャンプ場として買った。青島は岡山県の牛窓の沖にある約11万平方メートルの島で、生徒たちは毎年汗を流してこの島を開拓し、幾棟かの宿舎が建って大変いいキャンプ場になったことは、私の心からの喜びであった。
中学部は500人の小さな学校で、休暇などにも全校の生徒に対し、私が1人1人文通出来たことは、私と生徒との心のつながりのもととなった。私は返事を出すのではなくて、私の方から先に、お正月と夏休みに1人1人の個性に合わせて激励の言葉を書いて、全校の生徒に葉書を出した。これはむしろ私の趣味だったかも知れない。中学生は実にかわいかった。「なぜ世間の人は中学の教師にならないのだろう」と、私はよく人に語った。 」
『人間の幸福と人間の教育』矢内 正一著(昭和59年9月30日創文社) より





















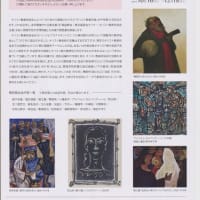






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます