定年で退職
「入学試験は、日本の教育をゆがめるものとして大きな問題になっている。入学試験は、決して公平に人間の学力をはかりうるものではない。将来の学力がどう伸びるかの可能性をはかりうるものでもない。追跡調査をしてみても、入学試験が入学後の成績と一致するものではない。まして創造力とか指導性とかをはかることは、今の入学試験ではとうてい出来ない。
私も今日まで一万人以上の学生・生徒を教え、ある者はすでに70歳を越しているが、学問だけからいっても、中学時代に一向ふるわなかった者が、何かに発奮して大学では最優秀な学生になったり、成績は悪かったが、社会人としてすばらしく伸びた者も無数にある。人間の価値はある一面だけでとらえてはならないし、また今の状態で直ちにその将来をはかるべきものではない。
殊にまだ本質的なものが出ていない小学生を、不備な入学試験で合格者と不合格者に分けることは、私としては教師の仕事のうちで一番つらい仕事だった。
関西学院中学部の入学試験を受けて落ちた生徒すべてに、私が激励の手紙を出すようになったのは、まだ小さい少年がこの不合格のゆえに、自分はだめだと絶望したり、劣等惑を持ったりすると、これほど残念なことはないと思ったからである。そして、この失敗の中から多くの教訓を得て、この失敗がかえって将来の大きな躍進の源となるなら、これほどうれしいことはないと思ったからである。
少年たちからは種々の返事が来た。ある小学生は次のように書いた。 「ぼくの努力が足りなかったのです。はじめて体験する悲しみですが、いつまでも悲しむのはやめにします。先生からいただいたお手紙をぼくは何べんも読みました。暗記するまで読みました。努力すればぼくだって人に負けないりっぱな人になれる、という自信を持つことができるようになりました…」
健康に恵まれ、天分に恵まれた者に対しては、その健康と天分とを祝福してやり、彼らを激励して、人類のためにその生涯を捧げる決心をさせるべきであろうし、健康を失い、天分の乏しい者に対しては、これを温かく包み、いたわり、励まして、一人一人がその生存の意義を全うするのを助けるのが教育者の使命であろう。
私は多くの夢と理想を持ったが、未熟なままで昭和40年満65歳の定年に達して、関西学院を退職した。これまで私を包み育ててくれたすべての人々、長い間の協力者であった関西学院の同僚の人々に対し、また幾千人の関西学院での教え子とその両親たちの好意に対して、感謝の思いの尽きぬものがあった。
教育委員になる
関西学院を定年で退職する一年半前の昭和38年10月から、西宮市の教育委員を兼ね、翌年から教育委員長になっていたので、40年関西学院を定年退職してからは、西宮市の教育委員長としての仕事に専念することになった。私が教育委員を頼まれて引き受けたのは、小幼の教育の大切さを痛感していたからであり、小幼の教育に関係してみたいと思ったからであるが、教育委員長として、色々の問題にぶつかり、色々のことを学んだ。
公立の小学校・中学校・幼稚園は、様々な境遇の子ども、様々な能力の子どもたちの集団である。サリドマイド児の小学生がいて、足に鉛筆をはさんでノートに字を書くことの出来る特別の机を、いろいろ工夫してつくったこともあった。ある日突然母が蒸発し、まもなく父も蒸発して、さびしく残された不幸な子もあった。差別に悩んでいる未解放の子どもたちの深刻な間題もあった。いくら勉強しても点数のとれない子の問題、身体障害の子どもの問題、こういう問題と直面しなければならなかったことは、私にとって、教育者として意義の深い体験だった。こういう苦しみをもつ人が世の中にたくさんあるとき、幸せな人間は何をなすべきかということを私はしみじみと考えた。
教育正常化運動
私が教育委員長をした時代は、西宮市の財政が豊かで、教育費も多く、教育行政のやり易い時期だった。学校の設備も充実して行き、社会教育のための公民館が次から次へと建てられて、日本全国の注目をあびた。
しかし「文教住宅都市」であるということは、学歴社会の日本では「受験教育過熱都市」という傾向を深めて行くことになった。受験塾がいたるところに乱立した。受験準備過熱は小学校下級にまで及んだ。ある日の幼稚園長会で、ある幼稚園では3桁の掛け算・割り算が出来るが、20m走らせると一番びりだし、洋服を自分で着ることも出来ない、というような子どもがいることが報告された。全国的に、勉強のよく出来る生徒は利己主義者になり、出来ない生徒は点数競争に脱落して非行化するという傾向が社会の問題となり、兵庫県も高校入試に学科試験を廃し、東京都は学校群制度によって、受験教育の過熱をおさえようとした時代だった。
こういう時代の姿を憂えて、西宮市も教育正常化運動を起した。運動の中心となったのは教育長の刀禰館正也氏で、委員長の私も協力した。刀禰館氏がよく口にしたのは、「一人では何も出来ない。しかし一人が始めるのでなければ何事も出来ない。その一人になろう」という言葉だった。「人間回復の教育」「全人教育」を主張する理想主義的な教育運動だった。刀禰館氏はこの精神を国政に生かそうとして後に代議士になったが、若くして病に倒れたのは本人にとっても最大の痛恨事だったにちがいない。 」
『人間の幸福と人間の教育』矢内 正一著(昭和59年9月30日創文社) より
「入学試験は、日本の教育をゆがめるものとして大きな問題になっている。入学試験は、決して公平に人間の学力をはかりうるものではない。将来の学力がどう伸びるかの可能性をはかりうるものでもない。追跡調査をしてみても、入学試験が入学後の成績と一致するものではない。まして創造力とか指導性とかをはかることは、今の入学試験ではとうてい出来ない。
私も今日まで一万人以上の学生・生徒を教え、ある者はすでに70歳を越しているが、学問だけからいっても、中学時代に一向ふるわなかった者が、何かに発奮して大学では最優秀な学生になったり、成績は悪かったが、社会人としてすばらしく伸びた者も無数にある。人間の価値はある一面だけでとらえてはならないし、また今の状態で直ちにその将来をはかるべきものではない。
殊にまだ本質的なものが出ていない小学生を、不備な入学試験で合格者と不合格者に分けることは、私としては教師の仕事のうちで一番つらい仕事だった。
関西学院中学部の入学試験を受けて落ちた生徒すべてに、私が激励の手紙を出すようになったのは、まだ小さい少年がこの不合格のゆえに、自分はだめだと絶望したり、劣等惑を持ったりすると、これほど残念なことはないと思ったからである。そして、この失敗の中から多くの教訓を得て、この失敗がかえって将来の大きな躍進の源となるなら、これほどうれしいことはないと思ったからである。
少年たちからは種々の返事が来た。ある小学生は次のように書いた。 「ぼくの努力が足りなかったのです。はじめて体験する悲しみですが、いつまでも悲しむのはやめにします。先生からいただいたお手紙をぼくは何べんも読みました。暗記するまで読みました。努力すればぼくだって人に負けないりっぱな人になれる、という自信を持つことができるようになりました…」
健康に恵まれ、天分に恵まれた者に対しては、その健康と天分とを祝福してやり、彼らを激励して、人類のためにその生涯を捧げる決心をさせるべきであろうし、健康を失い、天分の乏しい者に対しては、これを温かく包み、いたわり、励まして、一人一人がその生存の意義を全うするのを助けるのが教育者の使命であろう。
私は多くの夢と理想を持ったが、未熟なままで昭和40年満65歳の定年に達して、関西学院を退職した。これまで私を包み育ててくれたすべての人々、長い間の協力者であった関西学院の同僚の人々に対し、また幾千人の関西学院での教え子とその両親たちの好意に対して、感謝の思いの尽きぬものがあった。
教育委員になる
関西学院を定年で退職する一年半前の昭和38年10月から、西宮市の教育委員を兼ね、翌年から教育委員長になっていたので、40年関西学院を定年退職してからは、西宮市の教育委員長としての仕事に専念することになった。私が教育委員を頼まれて引き受けたのは、小幼の教育の大切さを痛感していたからであり、小幼の教育に関係してみたいと思ったからであるが、教育委員長として、色々の問題にぶつかり、色々のことを学んだ。
公立の小学校・中学校・幼稚園は、様々な境遇の子ども、様々な能力の子どもたちの集団である。サリドマイド児の小学生がいて、足に鉛筆をはさんでノートに字を書くことの出来る特別の机を、いろいろ工夫してつくったこともあった。ある日突然母が蒸発し、まもなく父も蒸発して、さびしく残された不幸な子もあった。差別に悩んでいる未解放の子どもたちの深刻な間題もあった。いくら勉強しても点数のとれない子の問題、身体障害の子どもの問題、こういう問題と直面しなければならなかったことは、私にとって、教育者として意義の深い体験だった。こういう苦しみをもつ人が世の中にたくさんあるとき、幸せな人間は何をなすべきかということを私はしみじみと考えた。
教育正常化運動
私が教育委員長をした時代は、西宮市の財政が豊かで、教育費も多く、教育行政のやり易い時期だった。学校の設備も充実して行き、社会教育のための公民館が次から次へと建てられて、日本全国の注目をあびた。
しかし「文教住宅都市」であるということは、学歴社会の日本では「受験教育過熱都市」という傾向を深めて行くことになった。受験塾がいたるところに乱立した。受験準備過熱は小学校下級にまで及んだ。ある日の幼稚園長会で、ある幼稚園では3桁の掛け算・割り算が出来るが、20m走らせると一番びりだし、洋服を自分で着ることも出来ない、というような子どもがいることが報告された。全国的に、勉強のよく出来る生徒は利己主義者になり、出来ない生徒は点数競争に脱落して非行化するという傾向が社会の問題となり、兵庫県も高校入試に学科試験を廃し、東京都は学校群制度によって、受験教育の過熱をおさえようとした時代だった。
こういう時代の姿を憂えて、西宮市も教育正常化運動を起した。運動の中心となったのは教育長の刀禰館正也氏で、委員長の私も協力した。刀禰館氏がよく口にしたのは、「一人では何も出来ない。しかし一人が始めるのでなければ何事も出来ない。その一人になろう」という言葉だった。「人間回復の教育」「全人教育」を主張する理想主義的な教育運動だった。刀禰館氏はこの精神を国政に生かそうとして後に代議士になったが、若くして病に倒れたのは本人にとっても最大の痛恨事だったにちがいない。 」
『人間の幸福と人間の教育』矢内 正一著(昭和59年9月30日創文社) より










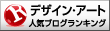










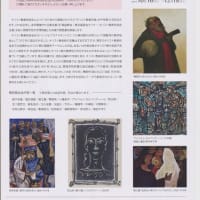






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます