
私の記憶法(勉強法の中での記憶の仕方)と比較するために、記憶法の本を読みます。記憶の基本、記憶術について詳述した本です。もともと、難しい記憶術を身につけたいとは全く思っていないので、記憶について体系をまとめる本として、読みました。
前半では、記憶の基本について、後半で記憶術について、その方法をテスト付きで行っていきます。記憶術の最後のほうのテストは、難しいのでスキップしました。
気づきは、
1)記憶の過程は、①記銘 ②保持 ③想起 のステップを踏みます。3つの段階のうち一つでも機能しなければ、情報を思い出すことができない。
2)ある情報を長期記憶するには、「その情報を一定時間後に想起することを繰り返せばよい」
→ この本のメインメッセージの一つであり、いろんな記憶の本と同じやり方です。エビングハウスの忘却曲線に応じて、数秒後、数分後、1時間後、1日後、1か月後の5回にわけて想起するというやり方です。
3)手がかりとの関連付けが大事。手がかりは多ければ多いほど良い。
4)記憶術の中では、
関係法、語呂合わせ法、頭文字法が使いやすい。
→いずれも、受験のときには使っていると思います。頭文字法など、社会人の勉強、資格試験の勉強でやってみようと思いました。
5)たいていの物事の記憶には記憶術を使う必要はない。
記憶のメカニズムとして、3段階で記憶してそのどれかが欠落しても思い出せない。そのための対策としての、想起の反復は、私の資格試験合格のための勉強法と意見が一致します。
語呂合わせや頭文字法は最近使っていませんでしたが、新しい分野の勉強の際に使って、久しぶりに自分のものにしたいと思いました。
著者の意欲も感じる、参考になる本でした。
前半では、記憶の基本について、後半で記憶術について、その方法をテスト付きで行っていきます。記憶術の最後のほうのテストは、難しいのでスキップしました。
気づきは、
1)記憶の過程は、①記銘 ②保持 ③想起 のステップを踏みます。3つの段階のうち一つでも機能しなければ、情報を思い出すことができない。
2)ある情報を長期記憶するには、「その情報を一定時間後に想起することを繰り返せばよい」
→ この本のメインメッセージの一つであり、いろんな記憶の本と同じやり方です。エビングハウスの忘却曲線に応じて、数秒後、数分後、1時間後、1日後、1か月後の5回にわけて想起するというやり方です。
3)手がかりとの関連付けが大事。手がかりは多ければ多いほど良い。
4)記憶術の中では、
関係法、語呂合わせ法、頭文字法が使いやすい。
→いずれも、受験のときには使っていると思います。頭文字法など、社会人の勉強、資格試験の勉強でやってみようと思いました。
5)たいていの物事の記憶には記憶術を使う必要はない。
記憶のメカニズムとして、3段階で記憶してそのどれかが欠落しても思い出せない。そのための対策としての、想起の反復は、私の資格試験合格のための勉強法と意見が一致します。
語呂合わせや頭文字法は最近使っていませんでしたが、新しい分野の勉強の際に使って、久しぶりに自分のものにしたいと思いました。
著者の意欲も感じる、参考になる本でした。











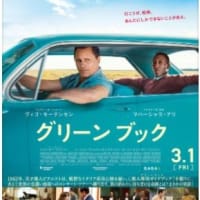
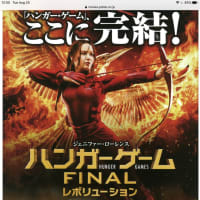




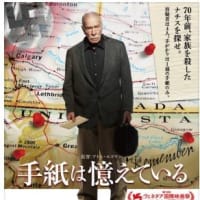
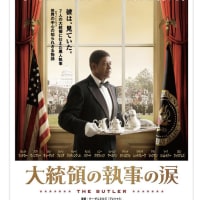
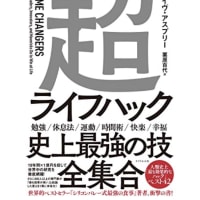
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます