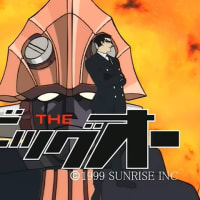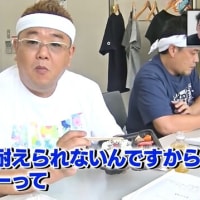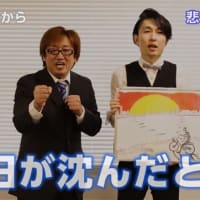「井の中の蛙、大海を知らず(いのなかのかわず、たいかいをしらず)」とは、「自分の狭い知識や経験にとらわれ、他に広い世界があるのを知らないこと」などにたとえられている日本のことわざです。
もともとは、紀元前300年ころの戦国時代の思想家の荘子(そうし)さんの著書「荘子」の「秋水篇」が由来になっています。
原文
井鼃不可以語於海者、拘於虛也。夏蟲不可以語於冰者、篤於時也。曲士不可以語於道者、束於教也。(「鼃」はアマガエル。「蛙」とするテキストもあり)
現代語訳
井の中の蛙と海のことを語ることができないのは、虚(くぼみ)のことしか知らないからである。夏の虫と氷のことを語ることができないのは、もっぱら夏の時季のものだからである。曲士(田舎者または心のよこしまな人、あるいはあることに秀でる人)と「道」のことを語ることができないのは、ある教条にとらわれているからである
つまり、自分だけの狭い範囲で落ち着いていて、もっと広い視野で物ごとを考えることができない様子をあらわしています。狭い世界に生きて広い世界のことを知らない、ということです。
確かに自分がまったく知らないことを話されても、よくわかりません。正直なところ、現代では情報社会ですから実際に見たり、体験したりしていなくても概要として知ることはできますが、自分で実際に見たわけでもなければ正確には理解できないこともある、と私は思っています。
転じて、視野を広く持つことの大切さについても述べていると考えられます。
さて、実は「井の中の蛙、大海を知らず」には続きがあるということを最近知りました。
「されど空の深さ(青さ)を知る」

この文言はあとになって日本で付け加えられたと言われています。
蛙は井戸のなかで生きており、井戸の外のことを知りません。井戸から見える空は毎日見ることができます。見ることができるというか、空を毎日見続けています。
その結果、ふだんだったら見過ごしてしまっているような、小さな空の変化に気づけたということなのでしょうね。
たとえ、狭い世界にいたとしても「自分の道を突き詰めたことにより、その世界の深いところまで知ることができる」ということなのでしょう。世の中にもその道を究めた方のなかには、自分が専門とする分野のことにはくわしいが、それ以外のことはまったく知らないなんてこともありますから。
「浅く広く」なのか、「深く狭く」なのか、どちらの道を突き詰めていくのかは人それぞれだと思います。でも、どちらにしても、「何かこれはほかの人には負けない」というものを持ちたいですよね。
ちなみに、荘子さんは「宋(そう)国」の「蒙(もう)(河南省商邱(しょうきゅう)県)」に生まれ、役人となったときもあるそうですが、おおむね自由な生涯を送ったと言われています。
本日も、拙文最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さまにとって、今日という日が昨日よりも特別ないい日でありますようにお祈りいたしております。
また、明日、ここで、お会いしましょう。それではごめんください。
もともとは、紀元前300年ころの戦国時代の思想家の荘子(そうし)さんの著書「荘子」の「秋水篇」が由来になっています。
原文
井鼃不可以語於海者、拘於虛也。夏蟲不可以語於冰者、篤於時也。曲士不可以語於道者、束於教也。(「鼃」はアマガエル。「蛙」とするテキストもあり)
現代語訳
井の中の蛙と海のことを語ることができないのは、虚(くぼみ)のことしか知らないからである。夏の虫と氷のことを語ることができないのは、もっぱら夏の時季のものだからである。曲士(田舎者または心のよこしまな人、あるいはあることに秀でる人)と「道」のことを語ることができないのは、ある教条にとらわれているからである
つまり、自分だけの狭い範囲で落ち着いていて、もっと広い視野で物ごとを考えることができない様子をあらわしています。狭い世界に生きて広い世界のことを知らない、ということです。
確かに自分がまったく知らないことを話されても、よくわかりません。正直なところ、現代では情報社会ですから実際に見たり、体験したりしていなくても概要として知ることはできますが、自分で実際に見たわけでもなければ正確には理解できないこともある、と私は思っています。
転じて、視野を広く持つことの大切さについても述べていると考えられます。
さて、実は「井の中の蛙、大海を知らず」には続きがあるということを最近知りました。
「されど空の深さ(青さ)を知る」

この文言はあとになって日本で付け加えられたと言われています。
蛙は井戸のなかで生きており、井戸の外のことを知りません。井戸から見える空は毎日見ることができます。見ることができるというか、空を毎日見続けています。
その結果、ふだんだったら見過ごしてしまっているような、小さな空の変化に気づけたということなのでしょうね。
たとえ、狭い世界にいたとしても「自分の道を突き詰めたことにより、その世界の深いところまで知ることができる」ということなのでしょう。世の中にもその道を究めた方のなかには、自分が専門とする分野のことにはくわしいが、それ以外のことはまったく知らないなんてこともありますから。
「浅く広く」なのか、「深く狭く」なのか、どちらの道を突き詰めていくのかは人それぞれだと思います。でも、どちらにしても、「何かこれはほかの人には負けない」というものを持ちたいですよね。
ちなみに、荘子さんは「宋(そう)国」の「蒙(もう)(河南省商邱(しょうきゅう)県)」に生まれ、役人となったときもあるそうですが、おおむね自由な生涯を送ったと言われています。
本日も、拙文最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さまにとって、今日という日が昨日よりも特別ないい日でありますようにお祈りいたしております。
また、明日、ここで、お会いしましょう。それではごめんください。