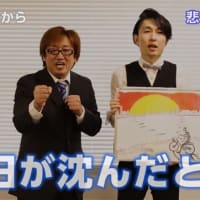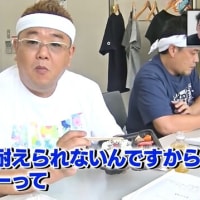現在のドラフト制度は一見、公平のように見えて実は不公平ではないかと。
1965年に始まったころの制度は、日本シリーズで負けたリーグの最下位チームから順番に選手を指名して行くというものでした。これはチームが最下位なのだから、戦力として一番良い選手を指名出来、戦力の均衡化と新人の契約金の高騰を防ごうというものです。メジャーを含め米国のプロスポーツのほとんどが同じシステムを導入し、それなりの成果を挙げていると考えます。
その後、制度は何回か変わり、1993年以降、大学・社会人選手の「逆指名」「自由枠」あるいは「希望枠」という訳のわからない制度が出来ました。早い話が自由競争であり、その結果、契約金の上限を破ったり、裏金を与えて囲い込むなどの事件が発生しました。
そして、この制度は2006年で廃止され、2008年から1巡目入札式、2巡目ウエーバー順、3巡目逆ウエーバー順、4巡目ウエーバー順・・・となって行く方式に変わりました。
これは一見公平で、下位チームが優遇されているようですが、今年の場合にはそうでもないのです。
おさらいですが、ウェーバー順はシーズンの順位で決まり、セ・パの優先順はオールスターの勝敗で決まります。2013年は1勝1敗1分けだったのでクジを引き、パ・リーグ優先となりましたので、ウエーバー順は1番目がファイターズで12番目がジャイアンツです。
しかし、ファイターズは1巡目の松井裕樹選手(桐光学園高)の入札指名は重複して抽選となり、それが外れると、2回目の柿田裕太選手(日本生命)、3回目の岩貞祐太選手(横浜商大)と3連敗。4回目でようやく渡辺諒選手(東海大甲府高)を指名出来ました。つまりファイターズにとっては4番目、1巡目全体としては12番目の選手だったということです。
下位チームに優位性を持たせるのが本来のドラフトの目的なのでしょうけど、これだと公平な指名が出来るのは2巡目以降ということになってしまうのです。
それでも、プロで成功するのはドラフトの指名順だけでは決まりませんから。
で、ファイターズが12番目、13番目と指名し、その後は36番目、37番目の指名順になったのに対して、ジャイアンツは1巡目の石川歩選手(東京ガス)を外したものの、チームとして2番目に欲しかった小林誠司選手(日本生命)を指名。以降は24番目、25番目を指名。
クジ運もあるのですが、今の制度で下位チームの優位性はあったと言えるのでしょうか?