いろいろのものが流行した
死さえも流行したことがある
しかし吝嗇(りんしょく=ケチ)だけは
かつて流行したことがない
このことがおそらく流行が、
まだ存在することをやめない証明になるかもしれぬ
ポール・モラン(1888~1976年) フランスの作家
【我がココロのみにて ~ はやりやまいの時を生きて ~ 親の因果? 子に報う? の巻】
江戸のはじめ、京都・妙心寺にて。
名僧・盤珪禅師の元を訪れた一人の武士が
「私は生まれつきの短気者で
時々カンシャク玉を破裂させては
失敗を繰り返してきました。
どうしたら直りましょうか」
と訊ねた。
すると禅師は
「お前さんは妙なものを生まれつき持たしゃったものだな。
カンシャク玉とはどんなものじゃ?
ちょっと その腹の立つ物を出してごらん。
取ってあげよう」
「いや、コブのように身体に出来ているものではなく
どうかすると出てくるのです」
「では、生まれつきではない。
生まれつきなら今でも出る。
今、出ておらずに、時々出るものなら
それはお前さんが作り出す物じゃ。
それを『生まれつき』などと言って
両親に罪をきせるのは不幸者である。
全て世間一切の迷いは、みな我見から生ずるので、
自分でカンシャク玉という迷いの塊を作り出し、
それを直そうとするのは誤りじゃ。
我見も起こさず、迷いさえせねば、
何も直す手間はかからぬ」
と諭した。
盤珪永琢(ばんけい・ようたく、1622~93年) 江戸前期の臨済宗の僧。やさしい言葉で大名から庶民にいたるまで広く法を説いた。法名を授けられ、弟子の礼をとった者は五万人余に上ったといわれる。
人の親の心は闇にあらねども
子を思ふ道に迷ひぬるかな
読人不知

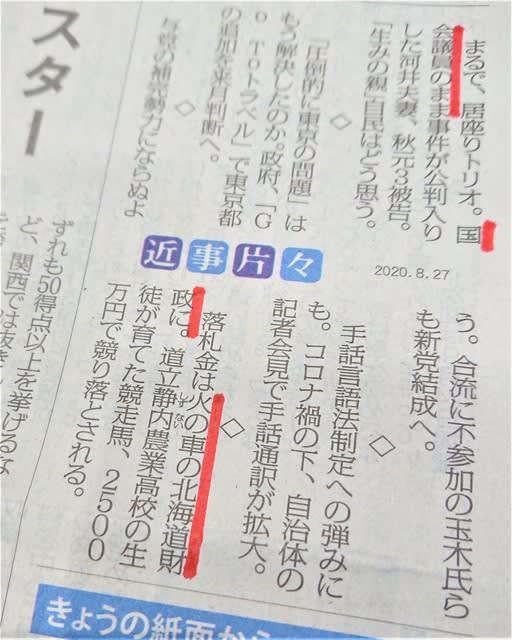
流行の新型コロナ渦中が続き
自分に向き合う時間が増えた
この世の迷いは他人事でない
旧態依然たる“生みの親”――

















