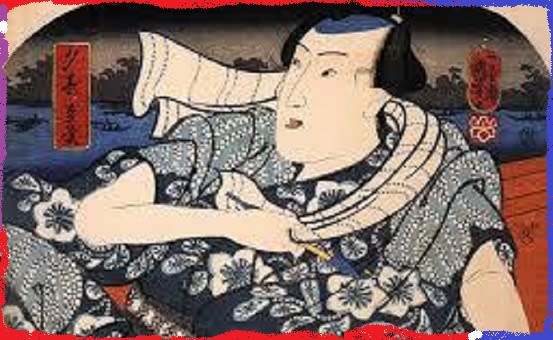
◆宵越しの金を持たない理由。。◆
江戸っ子の生態を知れば知るほど、唸ってしまう。
今の平成が最先端だと思ったら、大間違いだった。
よく江戸っ子を<粋>とか<いなせ>だのと云うが、
その根底には貧乏と住宅事情がある。
江戸の人口の半分は武士、あとは農工商。
金持ちの商人が町のまとめ役をやり、町のために私財を出す。
その下には多くの長屋を持つ大家たちがいて、
店子の職を世話したり、長屋の冠婚葬祭を取りまとめる。
水道料金は大家が負担し、掃きだめのごみ処理も大家がする。
店子は四畳半一間400文(6000円)さえ払えばノープロブレム。
そのせいか、江戸の男衆はガツガツ働かなかった。
江戸は仕事がなくても、
ちょっとした良いことをするとチップを貰える。
道行く人を笑わせたり、玄関先の履物を揃えてあげたりなどで、
一文二文のチップをくれる。
そんな僅かなお金でも物価が安いため
一日四時間程度働けば、その日を凌げるお金が入った。
杉浦日向子さんの「江戸アルキ帖」では
『江戸っ子の貧乏は
社会構造の未熟さからくるのではなく、彼ら自身の選択によるもの
ニコニコと趣味で貧乏をしている。。のが不思議だ』
その背景には江戸の大火がある。
江戸はなぜか五年に一度の割合で火の洗礼を受ける。
蔵を持つ大商人を除けば、大半の人々は一瞬で財産を失う。
江戸の町の風情は、ズラーーーと並ぶ茶色い家々と茶色い土。
茶色の寺院と茶色の橋。
朱色で塗られていても、すべての建物は木で造られている。
ひとたび火種が起きれば、阻むものはなく、、
町全体が燃え尽すまで火は収まらない構造になっていた。
火は棟伝いでドンドン大きくなるため、消火方法は家を壊す<破壊消火>
水を使うのは、火消しの人を守るためにかけるだけだった。
そして
大火に見舞われるのは、江戸っ子なら先刻承知の助!
地主や大家はお上に納税する他に
「町入用」という積立金をし、町や長屋の修繕費に充てていた。
そして長屋が燃えてしまった場合に備え、すぐに建てれる蓄えもしておく。
燃えたとしても廃材やストックしておいた木材を使い、
すぐにトテカントテカンと建て直してしまう。
多くの大商人や大家たちは人望があり、
店子たちからもリスペクトされる懐の深さを持っていた。
そんな町の気質と仕組みからか、、
江戸の住人となった時から
最小限度の家財とその日を暮らせるお金が入れば、大して困らなかった。
江戸の火事の譚を読んでて思い出したのが、
時代劇で観る
闇夜に「火の用心!」カチカチ🎵
あれは、あまりにも多い火事の警告と見回りの意味があった。
歩き煙草や夜間に火を使う営業は禁止。
風の強い日は銭湯も営業禁止になったほど。
江戸っ子がよく口にした
「一寸先は闇」や「江戸っ子は宵越のカネを持たない」は、
大火で命からがら逃げ延び、
一夜にしてすべてを失うことが一生で何度も起こる。
だからこそ
困った時はお互いさまで、助け合う。
親の帰りが遅い子供は、よその家で食べさせたり。
行儀の悪いよその子を、叱ったり。
お裾分けというのも、江戸っ子から生まれたもの。
町全体がそういう気質だったため、今のような孤独死などはなかった。
鍵もない長屋でプライバシーは守りながら、お互い助け合う。
そこには恩に着せるなどという発想はない。
江戸中期から熟成していった江戸の気風や江戸しぐさは<粋>であった。
二世紀半に及ぶ江戸時代の優れた文化は、
庶民から発信したものだった。
杉浦さん曰く
「ヨーロッパは戦争することで、大きな道が出来て多彩な文化が入ってきた。
それは貴族などの上流の人達から齎された文化。
江戸だけは長い平和と庶民の気質から生まれた稀な文化です」
**火消しはめちゃくちゃモテた!**
纏(まとい)持ちが特にモテた。
火の手の最前線に纏を持って立つ役目。
「め組」だと分かるように立つ若者は、超イケメンだった。
その組のイメージボーイなので
若い
背が高い
美男子
この条件を満たすため、組は競ってスカウトしたという。
余談だが、、
あの「八百屋お七」は恋人に会いたさのあまり、
火つけをし江戸を火の海にした。
江戸始まって以来の大事件だったとなっている。
今回は書いていて予想外に長くなった。
次回は、ちょいと面白いへぇーーー譚を書きます。
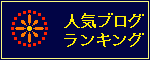 人気ブログランキングへ☜ブログランキングに参加してます。ポチッと応援クリックいただけると、とても励みになります!( `・∀・´)ノヨロシクお願いします 読んでくれてありがとう( *´艸`)
人気ブログランキングへ☜ブログランキングに参加してます。ポチッと応援クリックいただけると、とても励みになります!( `・∀・´)ノヨロシクお願いします 読んでくれてありがとう( *´艸`)











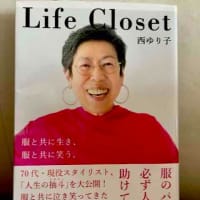


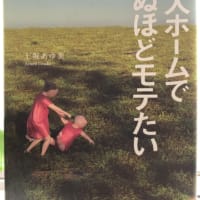



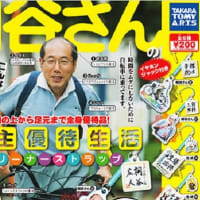

江戸っ子気質
納得致しましたぁ。
ガッテンデェ。
こんな町人気質なら、江戸に住んでみたい・・
お七の恋人は・・
超イケメンだったんでしょうね♪
「江戸っ子は宵越しのカネを持たない」
と言う言葉ですが、基本的に江戸時代は
衣・食・住すべて掛け払いが基本で、
大家が支給工賃から相殺して
一定期間で清算した残りを支給して
いたわけで、実は個人では銭を持っておく
必要がなかったわけです。
今現在飲食・レストランは現金かクレジット・
電子マネー・ポイントで支払えるように
なっていますが、現金払いが日本経済に
定着してきたのは昭和時代に入ってからの
ようです。ちなみに純野の出身の熊本では
30年くらい前まで、移動販売車、クリーニング、
などは帳面での掛け払いが普通でした。
また関東での老舗の百貨店(三越本店、東急本店)
などには今でも「お帳場」と言う言葉が残って
いまして、優良顧客は口座(お帳場)さえあれば
すべて外商さんが対応してくれて、
現金全くなしでも生活ができます。
間違いなく火消しにスカウトされていた
め組に・・・
だが高所恐怖症・・・アラララ!!
昭和の東京はまだまだその文化の名残がありました
近所の母方のおばあちゃんの家は長屋で運送や実家は瓦職人(歌舞伎座の屋根はおじいちゃんが指名されてました)
きょうぎやその隣は洗張り裏手に洗い場があり共同井戸がありました・・ケン坊ケン坊と周りから可愛がられてね
あっ・・長くなるから・・ここまで