石川倉次は,1859年,今の中区鹿谷町に生まれました。
倉次は,子どものころから近くの学問所や書道塾で,よく勉強をしました。そして,
大人になると,小学校の教師を務めた後,訓盲唖院(くんもうあいん)(後の東京盲唖学校)の教師になりました。
そのころの訓盲唖院では「目の不自由な人が使いやすい文字がほしい」という声が上がっていました。当時でも,目の不自由な人のための文字はありましたが,読むことができるようになるのにとても苦労するほど使いにくいものだったのです。
そこで倉次は,目の不自由な人でも簡単に文字を使えるようにしたいと考えました。倉次は,当時,フランス人が考え出したアルファベット点字からヒントを得て,6個の点を使う現在の日本で使われている点字を考え出しました。
その後,倉次は全国に点字を広めただけでなく,点字を打つための点字器や点字タイプライターを開発しました。
こうして,目の不自由な人も本を読んだり,手紙を書いたりすることが楽にできるようになったのです。
倉次は,子どものころから近くの学問所や書道塾で,よく勉強をしました。そして,
大人になると,小学校の教師を務めた後,訓盲唖院(くんもうあいん)(後の東京盲唖学校)の教師になりました。
そのころの訓盲唖院では「目の不自由な人が使いやすい文字がほしい」という声が上がっていました。当時でも,目の不自由な人のための文字はありましたが,読むことができるようになるのにとても苦労するほど使いにくいものだったのです。
そこで倉次は,目の不自由な人でも簡単に文字を使えるようにしたいと考えました。倉次は,当時,フランス人が考え出したアルファベット点字からヒントを得て,6個の点を使う現在の日本で使われている点字を考え出しました。
その後,倉次は全国に点字を広めただけでなく,点字を打つための点字器や点字タイプライターを開発しました。
こうして,目の不自由な人も本を読んだり,手紙を書いたりすることが楽にできるようになったのです。















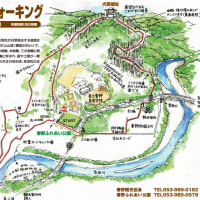



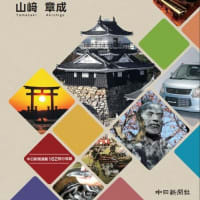





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます