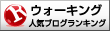道沿いにあった「身代の名号」
行ってみます。

「身代わりの名号」
常陸の国、川和田に住む平次郎は大の仏法嫌いで邪険な男でしたが、その妻おすわは親鸞聖人の教えを熱心に聞き求める信心家でした。
平次郎はおすわが法話に参詣するたび暴力をふるいます。
それを知った聖人はおすわに十字の名号を書き与え、法話に参詣しなくてもそれに礼拝するよう伝えました。
そしてそれからおすわは、平次郎に見られないようにしてこっそり名号に礼拝していました。
ある日おすわがいつものように平次郎の留守時に、名号を取り出し礼拝していると、外から平次郎が帰ってきました。
平次郎は、妻以外誰もいないはずなのに誰かに話し掛けるような妻の声に不信を抱きました。
そして妻が浮気をしているのではないかと激情下へ維持労は嫉妬の刃を振りかざして部屋に怒鳴り込みました。
しかしおすわはやはり一人です。
おすわは慌てて名号をふところに隠しました。それを見た平次郎は「今隠したものを見せろ!」と怒ります。
見せれば名号を破り捨ててしまうに違いないと思ったおすわは「こればかりは...」と許しを乞いました。
そのさまに男からの艶文と思った平次郎は逆上しておすわを切り殺してしまいました。
そして血に染まったおすわの体を古菰につつみ裏の竹やぶに埋めて家に取って返すと、
殺したはずのおすわが何食わぬ顔をして部屋の中にいます。
青くなった平次郎は事の次第をおすわに話すと二人で竹やぶに急ぎ、掘り返してみました。
すると不思議にも死体はなく、血潮に染まった名号が「帰命」の二字より真っ二つになって出てきました。
おすわがふところを確かめると名号はありません。二人はあまりのことに涙を浮かべて地にひれ伏し念仏を唱えました。
そしてその足で稲田に向かい親鸞聖人に事の顛末を話すと、聖人は阿弥陀仏の本願をねんごろに説かれ、平次郎も念仏の行者となりました。
承元元年(1207)「承元の法難」により、法然上人は、土佐に流罪となりました。
弟子の親鸞(35歳)も越後に流罪となり、その後、親鸞は恵信尼と結婚し、民衆の中にあって念仏の教えをひろめました。
42歳のとき、越後から関東に移り、その後、約20年間、茨城県笠間市稲田を中心に本願を信じ念仏に専念する生活を民衆の中で送る。
「身代わりの名号」の話は、その稲田時代の話です。

「帰命盡十万無碍光如来」の身代わり名号
そして「身代わりの名号」に手を合わせるおすわ。

殺したはずのおすわが名号となったことに驚く平次郎。


平次郎とおすわ
不思議なお話ですね。

(○'ω'○)ん?
花が咲いている。。
アセビかと思いましたが、ちょっと違う。
調べてみると、ネジキというツツジ科の植物なんだそうです。
樹皮が捻じれているので、この名前が付いたとか。
今度樹皮を見てみようと思います。

道へ戻りました。
次のお話場面へ行ってみます。
続きはまたです。