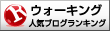令和3年10月15日(金)
近畿日本鉄道主催 きんてつハイキング てくてくまっぷコース
「❿名将「本多忠勝」、名刀「村正」ゆかりの地を征く」の続きです。

鳥居の前まで来ました。
ここは東海道五十三次の桑名宿

七里の渡しです。
桑名宿と宮宿(現名古屋市熱田区)の間は江戸時代の東海道唯一の海路で、その距離が七里(約二十八キロ)あることから、
七里の渡しと呼ばれました。
七里の渡しは、ちょうど伊勢国の東の入り口にあたるため、伊勢国の「一の鳥居」が天明年間(1781~1789)に
建てられました。
七里の渡しの西側には舟番所、高札場、脇本陣、駿河屋、大塚本陣が、南側には船会所、人馬問屋や丹羽本陣があり、
東海道を行き交う人々で賑わい、桑名宿の中心として栄えました。
昭和三三年(1958)、七里の渡し跡は三重県指定史跡となりました。
昭和三四年(1959)には伊勢湾台風によって、この付近は甚大な被害を受けました。
現在では、七里の渡し跡の前に堤防が築かれたため、七里の渡し跡の風景は、江戸時代とは異なる表情を見せています。

だいぶ整備されて、綺麗になっておりますが。。。

今でも船の出入りが出来るようになっているようです。

小舟がいっぱい停泊している。
ハマグリ漁の船かな?

七里の渡しから遊歩道を進んで来ると、櫓のような建物がありました。

なんだろうねぇ?

建物の向かいに、宝暦治水の案内板がありました。
薩摩藩のお話ですね。

あ!
空いている@@
ここは入ったことが無いので見学しようとしたら、
そばで草引きをしていたおじさんが、どうぞどうぞと案内してくださいました。

階段を上がって、2階へやってきました。
蟠龍櫓(ばんりゅうやぐら)です。
蟠龍とは、天に上る前のうずくまった状態の龍の事を言います。
渡し舟が無事に航海できるよう、ここに櫓が築かれたのだと思います。

窓からの眺めです。
龍の形をした瓦が川を見張っている。
1806年(文化3年)刊の「絵本名物時雨蛤」という書物に
「臥龍の瓦は当御城門乾櫓上にあり、この瓦名作にして龍影水にうつる。
ゆへに海魚住まずといへり」とあって、桑名の名物の一つにこの瓦を挙げているそうです。
おじさんが、ここから写真撮ってと教えてくれました^ー^

初めて中を見ました。
小さな櫓でしたが、重要な拠点だったのですね。
ありがとうございました。

蟠龍櫓を後にして、コースを進めていきます。

三之丸水門
揖斐川から水門を通って、水路へ続きます。

コースは水路の方へ続いているので、こっちへ行ってみます。

池かな?
周りでは、除草作業をしていました。

柿安コミュニティーパーク
心地よい風が吹いています。
ここでちょっと休憩しました。

桑名城三之丸御殿(新城)及び桑名紡績工場跡
いろいろと歴史があるのですね。

元々は桑名城のお堀だったようです。

これから九華公園の方へ入って行きます。

橋の手前に、いきなり大きな像が現れました。
本多忠勝の銅像です。

あの兜は鹿の角ですね。
燃え盛る炎のように見えてきて、凄い勢いを感じます。

コースは、九華公園へ行かずに、こっちへ続いています。
九華公園へはまた今度訪れたいと思います。
長くなりましたので、続きはまたにします。