労働価値論の可能性ーー贈与としての労働ーーその3
三、中上健次の労働論Ⅰ 土方労働
中上の労働論は、『黄金比の朝』(一九七四年)での《売り》と《買い》との非対称性の強調に伴う素朴な労働価値論の描写を見過ごすことは出来ないが、やはり何といっても、『岬』(七五年)や『枯木灘』(七七年)における「土方労働」に託した、自然的労働価値論の表現に輝いている。
「秋幸は土方を好きだった。日と共に働き、日と共に働き止める。一日、土を掘り、すくい、石垣を積み、コンクリを打った。土を掘りすくっても、物が育ち稔るわけではなかった。石垣を積み、側溝をつくり、コンクリを打って、自分が使うのではなかった。人には役立っても秋幸には徒労だった。だがその徒労がここちよかった。組の現場監督の秋幸は銭勘定ではなく、日を相手に働くその事だけでよかった。 」(『枯木灘』)
「肉体労働が好きである。土方が好きである。それが労働の原型にもっとも近いと思うのである。」(「作家と肉体」七六年)
中上は、肉体労働としての土方に、労働の価値を感じていたのだった。もちろん、土方労働が労働の原型にもっとも近いと中上が言うのは、あまりにも一面的であり、中上の労働論が挫折せざるをえない問題をはらんでいることを端的に示してはいる。だが、肉体労働としての土方労働にしか、それも禁欲的にそれにのめり込むことでしか、もはや労働の価値に浴することが出来ないほどに、労働が歪められているという告発の方が、ここでは大切だろう。
中上は、自然相手の肉体労働に快楽を覚え、それが労働の原型のイメージに近いものであるとさえ言っている。精神労働ではなく肉体
労働が労働の原型に近いと言っているのでは自分の身体を動かして、それが自分には徒労だが人には役立つ。そのような労働が、労働の原型だと言っているのだ。
土方労働のイメージは、単に肉体労働というものではない。 自分にではなく人に役立つ労働というイメージなのだ。それを中上は、労働の原型に重ね合わせた。










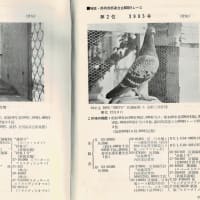

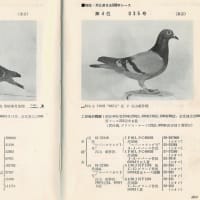







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます