労働価値論の可能性ーー贈与としての労働ーーその4
四、中上健次の労働論Ⅱ 物としての労働
肉体労働は中上にとって、歪められていない労働のイメージ、〈至福の労働〉のイメージに最も近いものだった。
「汗水たらす労働の報酬としてのキレイな金とは、〈キレイな〉この社会での一人の男の在りようであるなら、ひょっとすると、その汗水たらす労働とは、今の、われわれの時代の労働という言葉とは別のものかもしれない。労働者がいつの日か解き放たれて名づけることもいらなくなった状態、ただ、人間としか言いようのない十全な存在の至福の労働である。つまり汗水たらす労働とは、至福の労働のイメージが一等濃いのではないか、と思うのである。狩人のように狩をし、漁師のように漁をする。」(「作家と肉体」)
中上は忘れているが、太古において狩人や漁師の労働は孤立した個人の労働としてではなく、他の人々との連帯をもって行なわれていた。労働が対人間活動であることを忘却させてはいるが、労働が対自然活動であるという一方の側面を、中上は突き詰めたのだった。
そして、この方向から中上は、労働の隠された根底に到達した。
「労働の原型にあるのは物との交感であり、物質的恍惚とでも言うやつである。そして自分が物を前にして、自分もまた、物として、物質としてまず在ることに気づく。」(同)
労働で物を相手にするとき、自分が物として相手の物と格闘および共闘する場面に置かれる。労働とは、人間が物として別の物たちととりかわす運動なのだ。
ところが現実には、人間は物ではなく労働力を買われる商品であり、相手にする物たちもまた物ではなく商品や商品の原型として存在する。物と物との共闘や格闘で流す爽やかな汗は、商品(貨幣)に関わる労働では濁らざるをえない。
中上は小説家としての想像力で、貨幣の存在を超えた労働の地平に、自分を横超させた。中上の身体の中に、太古の労働の記憶が刻まれていたのだろう。










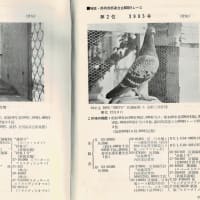

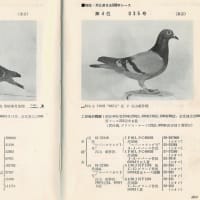







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます