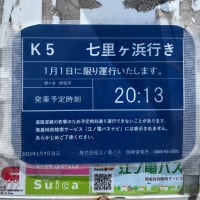稲村ケ崎公園から国道134号に合流しようと信号待ちをしていると、目の前を巨大な前輪にしがみつくようにまたがり、ペダルをギコギコ漕いで通り過ぎる山高帽のチャップリンが通って行った。
一瞬目を疑うとはこのことで、チャップリンのわけはないが、フロックコートのようなものを着て、見るからに場違いである。
そして、さらに目を丸くさせられたのはお化けのような巨大な前輪と極端に小さな後輪の乗り物が自転車であるらしいことだった。
一体どこの博物館から持ち出して来たんだ…?!
で、その正体は…「ペニーファージング」
ウィキによれば1870年ころに登場し、1890年ごろに最盛期を迎えたが、1900年ころにかけて衰退していったそうだ。
前輪を極端に巨大化した乗り物だが、お陰でスピードは現在のロードバイクにも引けを取らないが、如何せん乗る人間の足の長さに限度があり、しかもサドルが高い部分についているので安定性が悪く、乗りこなすのに苦労したらしい。
なにより、ふらついた時や障害物があった時などに、ちょっと片足をついて体勢を立て直すようなことも不可能。
もしうまく着地できなければ、かなり高い所からの転落と言うことになるわけで、肉体的なダメージも大きいと言わざるを得ない。
何と150年前の亡霊が現れたわけで、信号が変わるのを待って後を追った。
件のチャップリン氏は道路左端を悠然と漕いでゆく。
肩からたすきに掛けたカバンも往時を振り返ってのことだろうか…それにしても山高帽と言いフロックコートのようなものと言い、すっかりタイムスリップを楽しんでいるかのようである。
漕ぎ進んでいく先に波に削られた歩道の復旧工事が続いている箇所があり、路側帯付近は凸凹していてそこを走り抜ける際はボクも少し緊張させられるのだが、そこも何事も無いかのように通り抜けていく。
むしろ並走する車のほうが恐々と速度を落とし、後ろからついていくようなありさまで、ついでに珍しい乗り物だと口をアングリさせながらハンドルを握っていたんだと思う。
チャップリン氏は途中で歩道に上がり、そこで止まってしまった。
ボクもちょっと止まって様子を見ると、フロックコートが暑いらしく、脱いで肩掛けカバンの中にしまってまた漕ぎだした。
そばを通り過ぎる時によく見ると、何だかとてもスイスイ漕いでいて、涼しい顔である。
足が届かない!…なんて緊張感は微塵も感じられない。
撮影した写真を見ると、ハンドルの握り部分からワイヤーが伸びているのが分かり、ブレーキ用だろうと思う。
往時はそんなものは無かったはずだから、きっと手作りなんだろうと想像する。
それにしても、往時の姿に成り切って鎌倉から湘南にかけての海沿いの国道を悠然と行くなんてのは、なかなかのパフォーマンスじゃん。アッパレアッパレ。
まだ出くわしたことないけど、多分、鎌倉市内もこいつで走り回っているのかもしれない。
頼朝も義時も修学旅行生もビックリだろうな。

山高帽にフロックコート姿で異様な形の自転車を漕ぎ、脇をすり抜けていく車なんか眼中にないような悠然たる走り
(国道134号稲村ケ崎付近)

サドルの位置が高い分、如何にも不安定そうだが、スイスイと前進して行く
現在のチェーン駆動の自転車と違って、子どもの三輪車のように車輪に直接取り付けられたべダルを漕ぐので、「ちょっと休憩」と足を休めることができず、ペダルを漕ぎ続けなければいけないのが大変そう
それにしても乗りこなすのは容易じゃなさそうだ

このチャップリン氏、左のペダルが下に行った時、やっと足が届く感じだったのは設計ミス?
ちなみに左手と左の太ももの間に見える線がブレーキ用のワイヤーだと思う