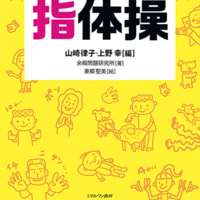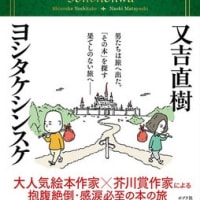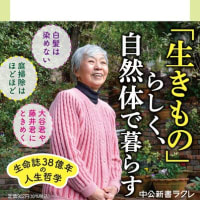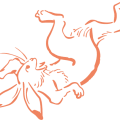二人目は、18渥美佳子さん 「歌集『迷宮の魚』発刊によせて」
以前、このBLOGでも紹介しました。保育士をしながら、句を作り続け、いろいろな方との出会い、ご縁で、このような形になりました。きっかけは、俵万智さんの歌集。
保育でのひとこまが、短い文字の中で、甦ってくるようです。保育という仕事は、楽しさだけではありません。身体がきつい時も、精神的に辛い時もあります。でも、句を作ることで乗り越えられたり、違った目線で見えてくるものがあったりしました、とのこと。保育以外での句でも、渥美さんの感性が、披露されています。句を通して、考えさせられる事もたくさん。
最後に二句披露してくださいましたが、トイレットペーパーの芯で作った双眼鏡で子どもが覗くのは「未来」という句には「おぉ~!!」という会場の感嘆のどよめきが。
受け付けで、販売されていましたが、ものすごい売れ行きのようでした。
三人目は、9武内美記子さん「工房さなえを中心とした地域活動」
言わずと知れた、前早苗会会長で、工房さなえ立ち上げ人。きつい民間保育園勤務時代から、手作りのモノを子ども達に与えたいと手芸の資格も取得し、それが退職後に生きる形に。第1・3水曜日は、早苗会生の現役退職者が中心に手弁当で1日掛かりで、和気合い合いと行っています。その作品が、今日も後にズラリと並んでおります。児童文化の授業での教え子達、49回生中心の活動では、保育の仕事をしながら、結婚、出産、育児の真っ只中でありながら、止めないで続けています。それには、感心することに若いパパの育児参加の協力があるんですよ。
さて、もうひとつは「おばあちゃんの日」の活動。子育て支援は、家庭からーということで、自分の子どもに出来なかったことを、孫の代で楽しんでいます。3番目の孫が1年生の時からお友達8人と、月2回無料で一緒に畑から野菜を取ってきて料理したり、りんごの皮むき、つい最近は、夏休み明け学校に提出する雑巾縫いもしました。今、3年生。5年生が終るまで続ける約束です。
子どもは、ゆっくり、じっくり、定期的に、継続的に取り組むことが大好き。
それを見守るのは、親の代より、祖父母の代に向いているのかもしれません。
家事も分担して、一緒にやりながら、仕事の仕方も無理なく教え、伝えていく。
雑巾も色とりどりのモノで作ってみると、“楽しい””やる気”もすごい。お友達の中の一人が「おかあさん、ボク作ったから雑巾買わなくていいからね。お金もったいないから。」と、仕事場に電話した子どもの姿に感心したそうです。