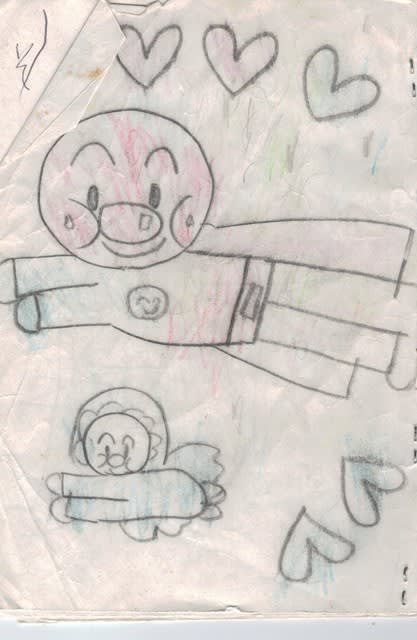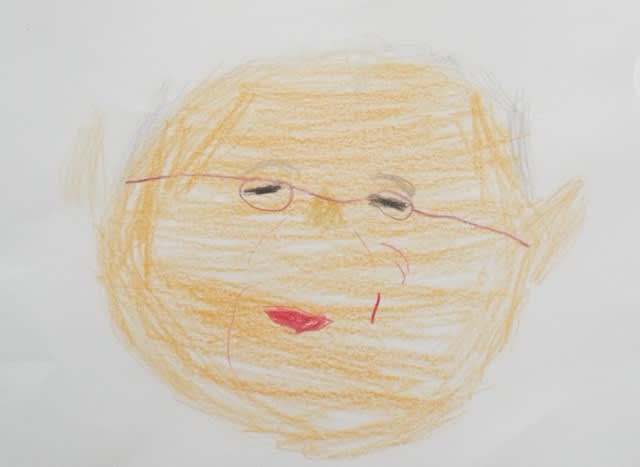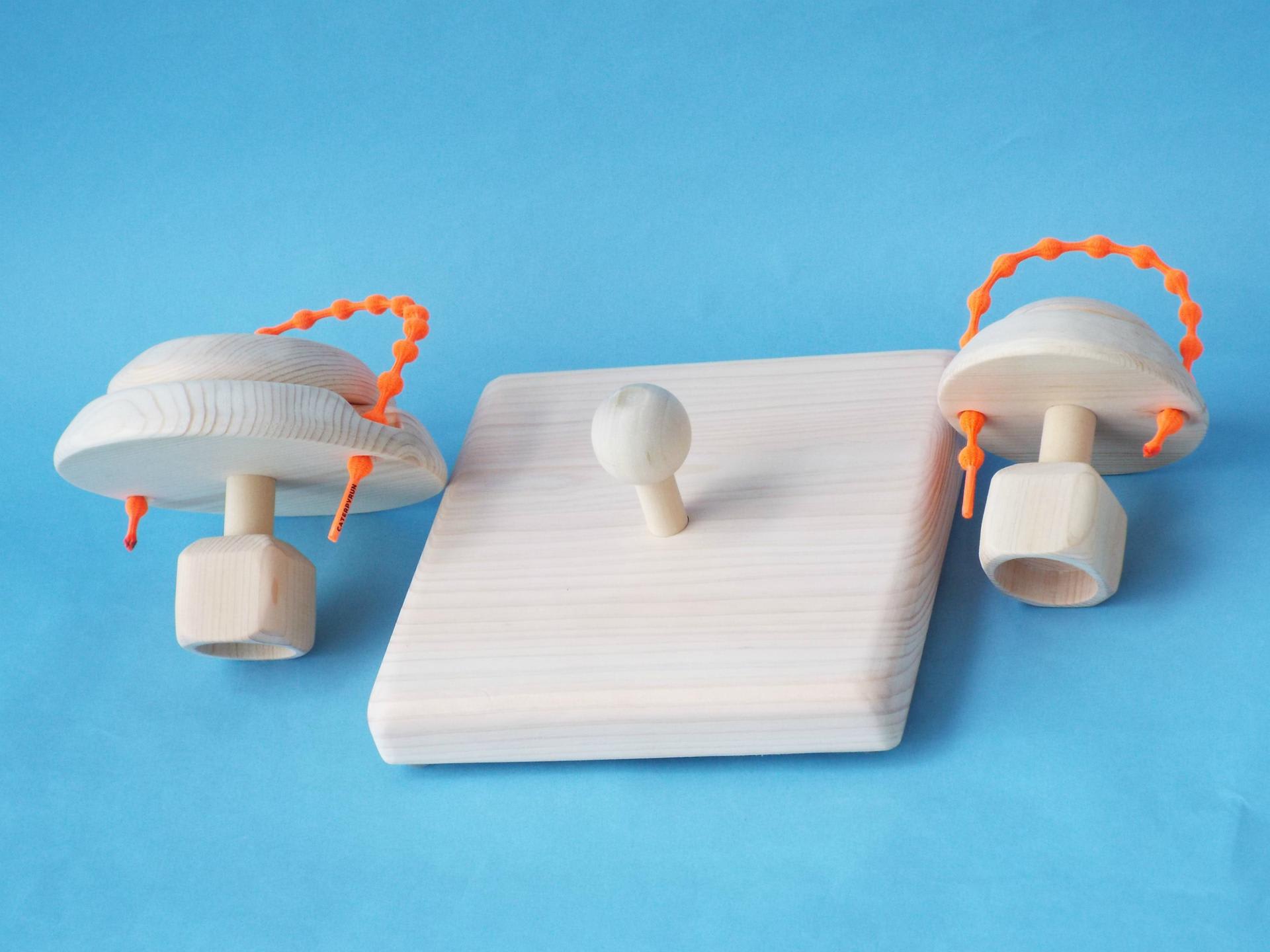[いつでも回復期、前回の足のリハビリの続き(補足)]
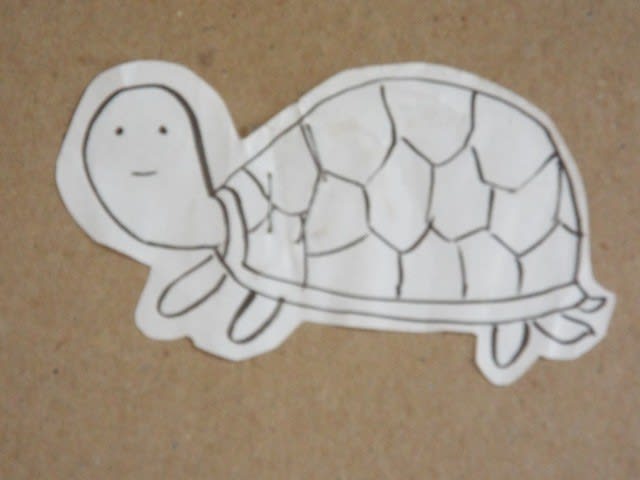
前回掲載内容に以下の1]~5]を追加します
1]退院時の足の回復状態
1)リハビリテーション病棟退院時は当初「車いす生活」との病院側の目標設定でした。
しかし、私の住い環境が、独居で、外出するにはエレベーターを使い、さらに長いスロープを
降りねばならず、外出は他人に依存することになるので、
他人依存ではない、杖歩行で退院したいと強くお願いしました。
2)したがって、歩行訓練もレベルアップ
無理やりの実績作りで、街路歩行や、踏切横断、芝生上の歩行までしました。担当の理学療法
士さんには大変迷惑をかけてしまいました。
3)歩く姿勢は、
おしりが後ろに引けて、前かがみ、左足半歩進んで、右足そろえる。の繰り返し、左に体重を
乗せたときは、上半身を左に傾けてバランスを取り、マヒ側の足を外に振り回していました。

4)マヒの左側、注意力散漫
歩いていて自然に左に寄ってしまい、常に左側との距離に意識をもっていないと、接触する危
険があった。
脳トレーニングのペーパーテストでも左側のミスが多いと言われた。
5)足の状態は
爪先、膝が上がらないので、つまずきやすく、足を外に回して歩行。膝関節周りの筋肉が弱
く、膝がガクガクで、膝の逆反り(バックニーと言われた。)
6)緊張緩和剤、精神安定剤、睡眠剤服用
リハビリ歩行後は、足が棒のようになり、就寝時でも足が折曲がらないこ ともありました。
緊張緩和剤を服用すると緊張が取れて、足の折り曲げができるようになり ました。
情緒不安定な時期もあり、理由なく呼吸がくるしいときもありました。この時は精神安定剤睡
眠剤を服用。退院時まで継続。
ですから、私は歩くに必要な筋肉ができてない状況で、いくら歩行訓練して
効果果がないと思いました。
また2年前からギックリ腰になっていて、歩行時のリハビリによる腰回り、背中の筋肉痛と筋
肉の緊張がギックリ腰に慢性的な痛みを発生させていた。一時は痛み止め薬の服用もしまし
た。
それらのため、退院後の訪問リハビリは筋肉トレーニングを優先しよう。そのメニューの中で
自分でもこなせるものは積極的に自主トレーニングをやっていこうと考えました。
2]退院後の足のリハビリ取り組み方
大筋、前回の掲載内容(歩行のリハビリがメインの掲載)ですが、以下3点追加します。
第1点) バックニー(膝が逆に反ってしまう。)と膝がぐらつくことの改善。ゴムベルトで膝の裏から強く引いた状態で、マヒ側の片足スクワットをする。
理学療法士さんには手で引っ張てもらい、負荷を与えてもらって、マヒ側の片足スクワットを
やりました。

第2点) 踏み台での乗り降りで、足を上げる力と体を支える力をつける。
両足やって、健側も強くして、マヒ側の負担を減らします。

第3点) 足指の縮みを防ぎ、足裏の感覚を大事にするため素足で歩くようにする。足指が縮ん
で仕舞うときは、靴底の薄い室内専用履きを履ました。
退院後、初めのうちは、室内履きにした外履きの靴を、室内で履いていたが、足先の上下左右
の振り・捩じり、膝の開閉等足の自由度を上げる自主トレを始めるのにあわせ、素足または薄
い室内専用履きで、日常生活、室内リハビリ歩行をしました。
3]退院時までの自主トレメニュー
1)回復期リハビリテーション病棟の理学療法士さんのリハビリ受け継いだ自主トレ
イ 腹筋の強化
☆ ベッドに仰向けになり、両膝をそろえ、左右にユックリ振る。
ベッドに仰向けになり両膝をおなかに近づける。
☆ ベッドに姿勢よく座り、お尻の右側(健側)に重心を置き、右手を水平にできるだけ遠く
に伸ばし、できるだけ右側に重心を傾けます。反対側は(マヒ側)腕が動きませんが、体をで
きるだけ重心を左になるよう傾けます。
2)足のツッパリ、マヒの改善
入院時は足がつっぱったままで、棒のようになっていました。理学療法士さんのストレッチや
マッサージや抱きかかえてもらっての歩行リハビリなどにより、足の曲げ伸ばしがやっとでき
るようになりました。
4]訪問リハビリの理学療法士さんによるストレッチと筋トレ内容
退院時と現在では多少違いますが
☆現在は、歩行リハビリ後の緊張している筋肉のほぐし、股関節の可動域を広げるためのほぐ
し、
負荷をかけて強化、膝の開閉の筋肉、膝を引き付ける筋肉です。
☆マットの上で、片膝すわりから立ち上がる運動、正座すわりで前進後退、正座のまま左右移
動のトレーニング、結構ハードです。
☆高さ20cmの踏み台に上がって
両足揃えて、マヒ側の足で踏み台の前に降りるトレーニングがあります。これらの内容は一人
ではできないし危険性があるので自主トレではやりません。
5]現在の自主トレメニュー
1)ベッドの上で
ベッドで寝た状態だと、体の緊張が少なくなるので、動きにくい筋肉を動かすのが比較的楽だ
と思います。
寝るとき、朝起きた時、夜寝られないときに気分転換に布団の中でやります。日中でもやりま
す。
☆ベッドに仰向けになって
ベッドにマヒ側膝を立てたら足を滑らせながら、足をゆっくり曲げ伸ばし縮めます。
☆ベッドに仰向けになって
マヒ側の足をベッドから浮かせたまま、足をゆっくり曲げ伸ばします。伸ばすとき、ガクガク
と2段モーションになりますが、繰り返しトレーニングしていく段階で滑らかになっていきま
す。
滑らかになったのは退院1年後の最近です。
☆ベッドに仰向けになって膝の開閉
マヒ側の膝を立て、マヒ側の足首を、健側踵の足で押えマヒ側の膝が、寝かせた健側の膝に付
けるよう動かします。
☆ベッドに仰向けになって、足のねじり、足首の上下動、左右の振り
マヒ側の足を延ばし、マヒ側のかかとを健側の足で押えてマヒ側の足首を健側の足に近づける
ようにまげる、足の捩じりの運動(足首の捩じりではありません)、合わせて足首の上下動を
します。
2)ベッドに付属した開閉する手すりを90度開いてつかまり立ち左右の足のステップ練習
☆片側の足を軸足にして、
反対側の足を大きく前後に移動、移動中は体の体重の中芯を軸足に乗せます。体を傾けての重
心移動でなく、腰を軸足の外側に振り出しへその位置が軸足の上にあるようにします。反対側
の足を前後に置いた時には、その側に体重を移動します。
軸足を変えて、両足行います。
手は、手すりにバランスを崩さない程度に、軽く添える
ます。
3)高さ20cmの踏み台で足腰の強化
上ってそろえ、そろえた足で降ります。左右やります。
4)ゴム使用

ゴムバンドを、ひざ後ろにかけゴムバンドをまえに強く張った状態で片足スクワットをやりま
す。両足やります。
5)室内歩行
☆当初は歩く力が不足していたので、まずは狭く短い室内廊下で繰り返し歩行、装具を付け杖
を突いて歩くだけ、
☆歩く力がついてきたら、歩き方に注意、廊下壁際とマヒ側の体の距離感です。
初めのうちは、接触してバランスを崩しましたが、狭い廊下なので転倒はしません。
繰り返すうち自然と壁際と空間をとれるようになりました。
☆今の室内歩行の目的は、街路歩行のまずい点を修正することや、鏡の前で姿勢を点検するこ
と、杖なし歩行でバランスの点検です。
使っていた装具、豹柄です。ちょっとじまんです。

☆今は杖なし歩行に重点を置いていません。
☆当面の目標は早く歩くこと、外部の状況を、余裕をもって、事前に察知できることです。
杖の持ち替えも容易にできるようにしたいです。
6)ボールを利用

ビニールのクッションボール持っていたソフトボール大のもの利用
☆ 足と足首の運動
床に置いた、ボールの上に、つま先、または踵を乗せ、踵または爪先がつくまで強く踏む。相
当強く踏まないと床につきません。
☆ ボールの転がりやすさと、重心を外れて押されると、その方向に回転し、移動する性
質を利用
〇 ボールを爪先で押しながら左右に足首を振る運動、足裏全体を使って、足を前後に移動す
る運動
〇 ボールに足裏を乗せて足で、円を描く運動く運動。
足の繊細な動きのコントロールを目指します。
7)壁際
☆壁際に立ち、壁に手で触りながらバランスをとって、左右にカニさん歩きします。
☆足指先を強化
素足、または、薄い靴底の室内シューズで壁際に立ち、壁に手で触りながらバランスをとって
両足のつま先立ち立ちを繰り返します。
8)リハビリの先生は理学療法士さんだけではありません。
健側の足も大事な先生です。
常にマヒ側と、健側の違いに気を付けましょう。そこから改善の方法が見つかるかもしれませ
んし、理学療法士さんに必要な、アドバイスを求めることができます。
9)足ひざの組み方で、張っている筋肉のストレッチができます。
椅子に座っている時、ベッドで寝ている時、いろいろやってみましょう。
[追記] 手のリハビリについては次回掲載させていただきます。
☆リハビリの訓練受けるときの説明って、なかなか理解できないですね、また理解できたとし
ても体が動かないですね。
たとえて言うと、なんか装置をよく知っている人が、その説明しているような感じです。
☆「パソコンに例えると。パソコンが使えるようになってから、やっと解説書がわかる。」
というような感じでしょうか。
言語療法は比較的わかりやすく、マニュアル化されているみたいです。(私見です。)
☆最近インターネットで、
リハビリの情報を調べると、小規模の整体院とか診療所で動画を使って要領よくリハビリにつ
いて情報発信しているところがあります。
リハビリで最新技術を求めるのも大切ですが、理解されやすい説明の仕方を広げていくことも
大事なことと思います。

☆足の裏って体が安定して立っているか不安定になっているか、どうすれば安定するか重要な
情報与えるところだと思います。素足で立つってすごく大事なことだと思います。装具を外し
て気が付きました。
IGA

50年前の正月の冬山登山で撮影した。北アルプス鹿島槍ヶ岳南峰北峰です。若い頃が懐かしいです。
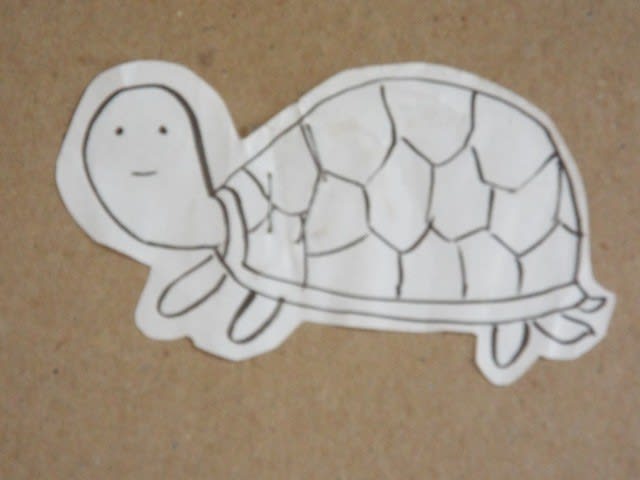
前回掲載内容に以下の1]~5]を追加します
1]退院時の足の回復状態
1)リハビリテーション病棟退院時は当初「車いす生活」との病院側の目標設定でした。
しかし、私の住い環境が、独居で、外出するにはエレベーターを使い、さらに長いスロープを
降りねばならず、外出は他人に依存することになるので、
他人依存ではない、杖歩行で退院したいと強くお願いしました。
2)したがって、歩行訓練もレベルアップ
無理やりの実績作りで、街路歩行や、踏切横断、芝生上の歩行までしました。担当の理学療法
士さんには大変迷惑をかけてしまいました。
3)歩く姿勢は、
おしりが後ろに引けて、前かがみ、左足半歩進んで、右足そろえる。の繰り返し、左に体重を
乗せたときは、上半身を左に傾けてバランスを取り、マヒ側の足を外に振り回していました。

4)マヒの左側、注意力散漫
歩いていて自然に左に寄ってしまい、常に左側との距離に意識をもっていないと、接触する危
険があった。
脳トレーニングのペーパーテストでも左側のミスが多いと言われた。
5)足の状態は
爪先、膝が上がらないので、つまずきやすく、足を外に回して歩行。膝関節周りの筋肉が弱
く、膝がガクガクで、膝の逆反り(バックニーと言われた。)
6)緊張緩和剤、精神安定剤、睡眠剤服用
リハビリ歩行後は、足が棒のようになり、就寝時でも足が折曲がらないこ ともありました。
緊張緩和剤を服用すると緊張が取れて、足の折り曲げができるようになり ました。
情緒不安定な時期もあり、理由なく呼吸がくるしいときもありました。この時は精神安定剤睡
眠剤を服用。退院時まで継続。
ですから、私は歩くに必要な筋肉ができてない状況で、いくら歩行訓練して
効果果がないと思いました。
また2年前からギックリ腰になっていて、歩行時のリハビリによる腰回り、背中の筋肉痛と筋
肉の緊張がギックリ腰に慢性的な痛みを発生させていた。一時は痛み止め薬の服用もしまし
た。
それらのため、退院後の訪問リハビリは筋肉トレーニングを優先しよう。そのメニューの中で
自分でもこなせるものは積極的に自主トレーニングをやっていこうと考えました。
2]退院後の足のリハビリ取り組み方
大筋、前回の掲載内容(歩行のリハビリがメインの掲載)ですが、以下3点追加します。
第1点) バックニー(膝が逆に反ってしまう。)と膝がぐらつくことの改善。ゴムベルトで膝の裏から強く引いた状態で、マヒ側の片足スクワットをする。
理学療法士さんには手で引っ張てもらい、負荷を与えてもらって、マヒ側の片足スクワットを
やりました。

第2点) 踏み台での乗り降りで、足を上げる力と体を支える力をつける。
両足やって、健側も強くして、マヒ側の負担を減らします。

第3点) 足指の縮みを防ぎ、足裏の感覚を大事にするため素足で歩くようにする。足指が縮ん
で仕舞うときは、靴底の薄い室内専用履きを履ました。
退院後、初めのうちは、室内履きにした外履きの靴を、室内で履いていたが、足先の上下左右
の振り・捩じり、膝の開閉等足の自由度を上げる自主トレを始めるのにあわせ、素足または薄
い室内専用履きで、日常生活、室内リハビリ歩行をしました。
3]退院時までの自主トレメニュー
1)回復期リハビリテーション病棟の理学療法士さんのリハビリ受け継いだ自主トレ
イ 腹筋の強化
☆ ベッドに仰向けになり、両膝をそろえ、左右にユックリ振る。
ベッドに仰向けになり両膝をおなかに近づける。
☆ ベッドに姿勢よく座り、お尻の右側(健側)に重心を置き、右手を水平にできるだけ遠く
に伸ばし、できるだけ右側に重心を傾けます。反対側は(マヒ側)腕が動きませんが、体をで
きるだけ重心を左になるよう傾けます。
2)足のツッパリ、マヒの改善
入院時は足がつっぱったままで、棒のようになっていました。理学療法士さんのストレッチや
マッサージや抱きかかえてもらっての歩行リハビリなどにより、足の曲げ伸ばしがやっとでき
るようになりました。
4]訪問リハビリの理学療法士さんによるストレッチと筋トレ内容
退院時と現在では多少違いますが
☆現在は、歩行リハビリ後の緊張している筋肉のほぐし、股関節の可動域を広げるためのほぐ
し、
負荷をかけて強化、膝の開閉の筋肉、膝を引き付ける筋肉です。
☆マットの上で、片膝すわりから立ち上がる運動、正座すわりで前進後退、正座のまま左右移
動のトレーニング、結構ハードです。
☆高さ20cmの踏み台に上がって
両足揃えて、マヒ側の足で踏み台の前に降りるトレーニングがあります。これらの内容は一人
ではできないし危険性があるので自主トレではやりません。
5]現在の自主トレメニュー
1)ベッドの上で
ベッドで寝た状態だと、体の緊張が少なくなるので、動きにくい筋肉を動かすのが比較的楽だ
と思います。
寝るとき、朝起きた時、夜寝られないときに気分転換に布団の中でやります。日中でもやりま
す。
☆ベッドに仰向けになって
ベッドにマヒ側膝を立てたら足を滑らせながら、足をゆっくり曲げ伸ばし縮めます。
☆ベッドに仰向けになって
マヒ側の足をベッドから浮かせたまま、足をゆっくり曲げ伸ばします。伸ばすとき、ガクガク
と2段モーションになりますが、繰り返しトレーニングしていく段階で滑らかになっていきま
す。
滑らかになったのは退院1年後の最近です。
☆ベッドに仰向けになって膝の開閉
マヒ側の膝を立て、マヒ側の足首を、健側踵の足で押えマヒ側の膝が、寝かせた健側の膝に付
けるよう動かします。
☆ベッドに仰向けになって、足のねじり、足首の上下動、左右の振り
マヒ側の足を延ばし、マヒ側のかかとを健側の足で押えてマヒ側の足首を健側の足に近づける
ようにまげる、足の捩じりの運動(足首の捩じりではありません)、合わせて足首の上下動を
します。
2)ベッドに付属した開閉する手すりを90度開いてつかまり立ち左右の足のステップ練習
☆片側の足を軸足にして、
反対側の足を大きく前後に移動、移動中は体の体重の中芯を軸足に乗せます。体を傾けての重
心移動でなく、腰を軸足の外側に振り出しへその位置が軸足の上にあるようにします。反対側
の足を前後に置いた時には、その側に体重を移動します。
軸足を変えて、両足行います。
手は、手すりにバランスを崩さない程度に、軽く添える
ます。
3)高さ20cmの踏み台で足腰の強化
上ってそろえ、そろえた足で降ります。左右やります。
4)ゴム使用

ゴムバンドを、ひざ後ろにかけゴムバンドをまえに強く張った状態で片足スクワットをやりま
す。両足やります。
5)室内歩行
☆当初は歩く力が不足していたので、まずは狭く短い室内廊下で繰り返し歩行、装具を付け杖
を突いて歩くだけ、
☆歩く力がついてきたら、歩き方に注意、廊下壁際とマヒ側の体の距離感です。
初めのうちは、接触してバランスを崩しましたが、狭い廊下なので転倒はしません。
繰り返すうち自然と壁際と空間をとれるようになりました。
☆今の室内歩行の目的は、街路歩行のまずい点を修正することや、鏡の前で姿勢を点検するこ
と、杖なし歩行でバランスの点検です。
使っていた装具、豹柄です。ちょっとじまんです。

☆今は杖なし歩行に重点を置いていません。
☆当面の目標は早く歩くこと、外部の状況を、余裕をもって、事前に察知できることです。
杖の持ち替えも容易にできるようにしたいです。
6)ボールを利用

ビニールのクッションボール持っていたソフトボール大のもの利用
☆ 足と足首の運動
床に置いた、ボールの上に、つま先、または踵を乗せ、踵または爪先がつくまで強く踏む。相
当強く踏まないと床につきません。
☆ ボールの転がりやすさと、重心を外れて押されると、その方向に回転し、移動する性
質を利用
〇 ボールを爪先で押しながら左右に足首を振る運動、足裏全体を使って、足を前後に移動す
る運動
〇 ボールに足裏を乗せて足で、円を描く運動く運動。
足の繊細な動きのコントロールを目指します。
7)壁際
☆壁際に立ち、壁に手で触りながらバランスをとって、左右にカニさん歩きします。
☆足指先を強化
素足、または、薄い靴底の室内シューズで壁際に立ち、壁に手で触りながらバランスをとって
両足のつま先立ち立ちを繰り返します。
8)リハビリの先生は理学療法士さんだけではありません。
健側の足も大事な先生です。
常にマヒ側と、健側の違いに気を付けましょう。そこから改善の方法が見つかるかもしれませ
んし、理学療法士さんに必要な、アドバイスを求めることができます。
9)足ひざの組み方で、張っている筋肉のストレッチができます。
椅子に座っている時、ベッドで寝ている時、いろいろやってみましょう。
[追記] 手のリハビリについては次回掲載させていただきます。
☆リハビリの訓練受けるときの説明って、なかなか理解できないですね、また理解できたとし
ても体が動かないですね。
たとえて言うと、なんか装置をよく知っている人が、その説明しているような感じです。
☆「パソコンに例えると。パソコンが使えるようになってから、やっと解説書がわかる。」
というような感じでしょうか。
言語療法は比較的わかりやすく、マニュアル化されているみたいです。(私見です。)
☆最近インターネットで、
リハビリの情報を調べると、小規模の整体院とか診療所で動画を使って要領よくリハビリにつ
いて情報発信しているところがあります。
リハビリで最新技術を求めるのも大切ですが、理解されやすい説明の仕方を広げていくことも
大事なことと思います。

☆足の裏って体が安定して立っているか不安定になっているか、どうすれば安定するか重要な
情報与えるところだと思います。素足で立つってすごく大事なことだと思います。装具を外し
て気が付きました。
IGA

50年前の正月の冬山登山で撮影した。北アルプス鹿島槍ヶ岳南峰北峰です。若い頃が懐かしいです。