県議会のホームページに掲載されている議事録
http://www.kensakusystem.jp/ehime/
より、2年近く前からのプルサーマル問題に関する愛媛県議会本会議での質疑内容を紹介しておきます。
●平成16年 第287回定例会 (第2号 6月10日)No.5 玉井実雄議員(自民党)
次に、伊方原子力発電所におけるプルサーマル計画についてお伺いいたします。
先般5月10日、四国電力は、県及び伊方町へ伊方3号機で2010年度までにプルサーマルを実施したいとの事前了解の願いを提出しました。
プルサーマル計画については、既に関西電力が、福井県の事前了解と国の原子炉設置変更許可を受け、本年3月にはフランスの燃料加工会社と基本契約を締結しております。また、九州電力でも、先般、2010年度までの玄海3号機での実施方針を固め、地元への申し入れを行ったところです。
このプルサーマル計画は、使用済み燃料の中に残っているウランとプルトニウムを再処理により取り出し、混合燃料いわゆるMOX燃料に再加工して使用するというものであり、国が将来にわたる我が国のエネルギーの安定供給に不可欠な政策として推進しているものです。
外国では、フランスやロシア等は、我が国と同じように原子力発電及び再処理を推進しておりますが、アメリカやカナダ等は、原子力発電は行うが使用済み燃料は直接処分する方針をとっております。一方、ドイツ・スウェーデン等のように脱原発を政策に掲げている国もあります。また、内外の一部の学者や福島県知事等から、経済的に直接処分をする方が有利との意見や核燃料サイクルの推進については立ちどまって再検討すべき等の意見が提示されていることも、御承知のとおりであります。
このようにさまざまな意見が自由に表明され議論されることは、民主国家として健全なあかしでありますが、一般国民や県民にとっては、プルサーマル計画の是非を判断することが難しい状況であると思うのであります。
そこで、改めて、我が国の原子力政策、特に、核燃料サイクル政策とその一環であるプルサーマル計画について知事の基本的な認識はどうか、その根拠とともにお示しいただきたいのであります。
次に、プルサーマル計画の安全性についてお伺いします。
もとより原子力政策は、安全確保を最優先とすべきことは言うまでもなく、知事からも管理委員会等を開催し安全性を十分確認していくとの表明がなされているところです。
先日、県が計画の容認を前提としているかのような新聞報道がなされましたが、県政与党に対して県が示したスケジュール案は、あくまで一つのケースとして手続の流れの例示があったものと認識しており、白紙の状態から検討がなされていくものと確信しております。
そこで、今後、四国電力からの事前了解願に対し、伊方原発での安全性をどのように確認し、対応していくのかお伺いしたいのであります。
No.9 加戸守行知事
次に、原子力問題で、我が国の原子力政策、特に、核燃料サイクル政策とその一環であるプルサーマル計画についての知事の基本的な認識はどうか。また、その根拠はどうかとのお尋ねでございました。
国では、エネルギー基本計画等において、我が国が将来にわたりエネルギーの安定供給を確保するため、燃料の備蓄性や地球温暖化対策等にすぐれた原子力発電を基幹電源に位置づけているところでございます。
また、使用済み燃料中の有用資源を回収・再利用する核燃料サイクル政策は、原子力発電のすぐれた供給安定性を一層改善するものとして、その推進を原子力政策の基本とし、プルサーマル計画は、核燃料サイクルの中軸として着実に推進していくとしております。
今日、我が国を取り巻くエネルギー事情を概観いたしますと、まず、自給率は、原子力を除くとわずかに4%という低い率にとどまっておりますこと、それから、石油は、輸入の86%を政情不安定な中東に依存しておりますこと、近隣国との電力融通は、地理的に考えましても不可能であること、地球温暖化防止のため、化石燃料は使用抑制が必要であること、さらに、世界のウランの可採年数は約60年と見込まれておりますこと、そして、途上国のエネルギー需要は、今後、飛躍的に増大することなど、諸般の状況の中にあります。
また、再処理よりも直接処分の方が経済的に有利との意見もございますが、その差は総発電コストの1割程度であるとされておりまして、そもそもエネルギー政策は、経済性のみならず、資源の有効利用やエネルギー安全保障など、総合的な観点から評価がなされるべきものと考えております。このようなことから、国の原子力政策は、安全確保と国民の理解が当然の前提ではございますけれども、基本的には、現実的かつ妥当なものと認識をしているところでございます。
No.12 吉野内直光副知事
玉井議員にお答えします。
私の方からは、伊方原子力発電所におけるプルサーマル計画についてのお尋ねのうちの、今後、四国電力からの事前了解願に対し、伊方原発での安全性をどう確認し、どう対応していくのかとの点についてお答えさしていただきます。
四国電力から事前了解願につきましては、お話のとおり、安全確保を最優先に、専門家や県議会、そして、県民各界各層の代表者から成ります方々の意見を十分に踏まえまして、白紙の状態から検討を進めることといたしております。
そこで、まず6月1日には、原子燃料工学等の専門家で構成しております伊方原子力発電所環境安全管理委員会の技術専門部会これを開催しまして、科学技術的観点から審議をいただきました。その結果、MOX燃料は、炉の3分の1程度までの範囲ではウラン燃料と同様な安全設計が可能であることが原子力安全委員会により確認されており、海外においても十分な安全使用実績が認められるとしまして、その基本的な安全性は確認されましたが、伊方3号機での安全性につきましては、個別に原子炉の特性を踏まえた国の安全審査結果を待って、改めて審議することが必要とされたところでございます。
このため、当面、国の安全審査の前提となります四国電力の原子炉設置変更許可申請これの取り扱いにつきましては、本議会での議論や地元の意見等を踏まえまして、伊方原発環境安全管理委員会におきまして、慎重に審議していただき、判断してまいりたいと考えております。
なお、報道のございましたスケジュールの資料につきましては、1つのケースとして例示したものでございまして、計画容認を前提としたものではございませんので御理解を願いたいと思います。
以上でございます。
●平成16年 第287回定例会 (第2号 6月10日)No.20 高橋克麿議員(社民党)
最初は、先ほど玉井議員からもありました伊方原発のプルサーマルの問題についてであります。
去る5月10日、四国電力は、2010年度までに伊方原発の3号機、加圧水型軽水炉、出力89万kwでプルサーマル計画を実施すると発表し、県と伊方町に事前協議を申し入れました。原発における安全の確保は、住民にとって最大の問題であります。
プルサーマル計画は、プルトニウムとウランの混合酸化物・MOX燃料を通常の原子力発電所で燃やすものであり、もともと従来の原発は、MOX燃料を燃やすようには設計されていないのであります。ウラン燃料を燃やせばプルトニウムを発生しますので、今でもプルトニウムを燃やしているんだと説明する向きもありますが、それは燃焼途中から発生したプルトニウムが核分裂反応に加わる設計だからということでしかありません。
しかし、プルサーマルは、燃焼の初めからプルトニウムが核分裂反応に加わるわけですから、今までの原子炉の設計では無理な可能性もあるため、国が安全審査を行い、大丈夫だと結論を出してはいます。しかし、結論を導くまでの過程で、実際には、MOX燃料が実験中に破裂したり曲がったりということが起こりましたが、安全審査の結論は、これらを問題視していない結果になっています。
そこで、まずお伺いします。
実験中に問題が生じたにもかかわらず、通常の原子炉での燃焼を大丈夫と結論づけたことは、安全上、心もとないと思うのでありますが、安全審査の結論に至るまでの経緯を含め、国の判断や対応を県はどのように認識しているのかお聞かせください。
次に、経済的には、ウラン燃料の1.6倍とも2倍以上とも言われるMOX燃料の高コストが問題になっています。電力自由化でコスト競争をしなければならないときに、どうして電力会社がわざわざ高コストの燃料を使うのでしょうか。それは、たまりにたまってしまったプルトニウムの問題に関係があると思います。
日本は、原発の使用済み核燃料を再処理してプルトニウムを取り出し、それをまた燃料として使う、核燃料サイクル政策をとっています。本来は、高速増殖炉で取り出したプルトニウムを使うこととなっていましたが、御承知のように、高速増殖原型炉「もんじゅ」において、試験運転中の平成7年12月に2次系中間熱交換器出口配管からナトリウムが漏えいする事故が発生し、以後、計画はとんざしております。高速増殖炉を成功させた国は世界に一つもなく、無理からぬことではありますが、この失敗により、日本は使い先のない分離済みのプルトニウムを国の内外に38tもためており、世界からはその処理をどうするのか注視されているのです。
こうした経緯を踏まえると、プルサーマルの推進は、たまったプルトニウムを処理するという大義名分を実現するための苦肉の策ではないかと思えるのであります。実際、プルサーマルでの利用は多くを見込めず、焼け石に水で抜本的な解消には至らないのですが、一方では、青森県の六ヶ所村に再処理工場をつくってプルトニウムの抽出に取り組んでおります。日本の政策は首尾一貫しておらず、これでは大変お粗末と言わざるを得ないのであります。
そこで、2点目としてお伺いいたします。
国の核燃料サイクル政策のため、コスト高でありながら、プルサーマル計画が推進されている点について県はどう考えているのか、御所見をお聞かせください。
ところで、週刊朝日が「上質な怪文書」と報じた論文があります。霞が関の官僚の手によるものと見られていますが、核燃料サイクルについては一たん立ちどまり、国民的議論が必要ではないのかと結ばれており、官僚でさえといった感想を持つのであります。また文中には、核燃料サイクルに疑義を唱える有識者として自民党の河野太郎衆議院議員や福島県の佐藤栄佐久知事の名前も挙がり、これまで原発を推進してきた人たちの中からもちょっと待てとの声が上がり始めています。そして、こうした議論が、今、総合資源エネルギー調査会など政府の審議会内でも始まっているのです。ここはぜひ知事に十分な検討をお願いしたいと思います。
知事は、四国電力のプルサーマルをとめる権限は自分にはないと思われているかもしれませんが、福井でも福島でも新潟でも、電力会社は知事の意向を尊重しています。法的な権限はともかくとして、計画の事前了解をしないという形で、実質的に電力会社へ待てという権限を持っていると考えるのであります。
これまで原発は、交付金をもたらしました。しかし、今まで多くの自治体が安易にそれに頼って、結果的に本来その地域で育つべき産業に水をやることを忘れてしまい枯れさせてしまった側面も多いのではないでしょうか。原発が立地する地域で産業振興に成功し発展を遂げている自治体は、残念ながら一つも見当たりません。
また、伊方原発は、発電所としては日本でも最も古い部類に入ります。一昨年にはタービンのコンクリート架台のひび割れが内部告発で明らかになりました。安山岩がコンクリートに使われたためで、同じものが原子炉本体に使われていないという保証もないと思うのであります。これからは、老朽化の進む原発は早めに廃炉とし、交付金に頼らず、風力発電や太陽光発電、木材を生かしたバイオマスなど、明るくさわやかな自然に根差したクリーンエネルギーによる県おこし、まちおこしにチャレンジすべきときと考える次第であります。
そこで、3点目としてお伺いします。
政府の審議会等が核燃料サイクル政策をどうするのか議論を始めた今、ここで少し立ちどまり、プルトニウムをこのままつくり続けるのか、やめるのか等の結論を見きわめ、さらに県民間の議論を踏まえた上で、知事は、四国電力のプルサーマル計画に対する判断を出されても遅くはないと思うのでありますが、御見解をお聞かせください。
No.24 加戸守行知事
伊方原発のプルサーマルに関します質問の中で、安全性等の問題につきましては、県民環境部長の方から答弁させますが、コスト高でありながらプルサーマル計画が推進されていることをどう考えているのかとのお尋ねがございました。国の政策に対する見解でございますので、私の方から答弁さしていただきます。
先ほど玉井議員にもお答え申し上げましたとおり、将来にわたりまして安定したエネルギーを確保するためには、単に経済性だけではなくて、多角的な評価に基づく総合的な政策判断が重要であると認識いたしております。
そのような観点から見ますと、MOX燃料は、ウラン燃料に比較して燃料取得コストは高いものの、再処理することによりまして、ウラン資源の利用効率が最大1.5倍に増加すること並びに核燃料リサイクルによりまして、高レベル廃棄物が約40%に減容され処分費用が低減するなど、大きな利点があるものと評価されております。
加えまして、プルサーマルを含めました原子力発電のコストは、国のコスト等検討小委員会において、燃料の再処理や廃炉処理等のバックエンド費用を含めましても、1kwh当たり5.3円と試算されておりまして、石炭火力の5.7円、石油火力の10.7円など、他の電源と比較いたしますと、経済的優位性についても十分に確保されるものと認識いたしているところでございます。
No.27 石川勝行県民環境部長
伊方原発のプルサーマルについて、安全審査の結論に至るまでの経緯を含め、国の判断や対応を県はどのように認識しているかとのお尋ねでございました。
お話のMOX燃料が実験中に破壊した等の事案につきましては、フランスが平成5年から9年にかけて、研究用原子炉で燃料の出力を強制的に異常上昇させることにより、模擬的に事故時の厳しい条件を加えた際の燃料破損の状況を調査したものでございます。これ以外に、商業炉での使用におきましては、MOX燃料に起因する事故は発生しておらず、海外で約40年、約4,000体に上る使用実績がございます。
また、プルサーマル計画が先行している関西電力の高浜原発では、平成10年5月に、国に対して原子炉設置変更許可申請が提出され、同年12月に許可されましたが、この国の審査におきましては、フランスでの実験結果を反映して、平成10年4月に原子力安全委員会が策定いたしました「燃料の取扱いに関する審査指針」も適用されたものと承知しており、県といたしましては、異常事故を想定した十分な安全審査が行われたものと認識いたしております。
次に、政府の審議会等の結論を見きわめ、県民間の議論を踏まえた上で四国電力の計画を判断しても遅くはないと思うがどうかとの御質問でございました。
国におきましては、昭和36年の原子力長期計画策定以来、一貫して核燃料サイクル及びプルサーマルを原子力政策の基本に位置づけますとともに、昨年10月に閣議決定されましたエネルギー基本計画におきましても、原子力発電を基幹電源として、核燃料サイクル及びプルサーマルを着実に推進することといたしております。
また、最近新聞報道されました核燃料サイクル政策の見直しにつきまして国に確認いたしましたところ、新しい原子力長期計画の策定時期を迎え、さまざまな意見がありますが、原子力委員会として政策の変更を決めた事実はなく、国としては、核燃料サイクル政策を原子力政策の基本とし、プルサーマルを着実に推進していく旨の回答がございました。
そのようなことから、県といたしましては、現時点で国の政策に基本的な変更はないと理解しており、先ほど副知事から玉井議員にお答えいたしましたとおり、当面、国の安全審査の前提となる原子炉設置変更許可申請の取り扱いにつきまして、本議会での議論や地元の意見等を踏まえ、伊方原発環境安全管理委員会におきまして慎重に審議し、判断してまいりたいと考えております。
●平成16年 第287回定例会 (第3号 6月11日)No.23 笹岡博之議員(公明党)
(拍手)質問に先立ちまして、一言申し上げます。
昨今の報道をにぎわしております県警の捜査費不正支出疑惑につきまして、本来、法を遵守し社会正義を守る警察機関でありますから、より厳正に県民が納得のいく調査、解明、また、最大限の情報を公開するなど、前向きの対応を願うものであります。
また同様に、プルサーマル計画への対応にしましても、昨今御議論がございましたように、理解のためには専門的知識が求められる事柄であり、県民の生活、生命に直接関係する重要テーマでありますので、特段の対策を要請するものであります。
----
http://www.kensakusystem.jp/ehime/
より、2年近く前からのプルサーマル問題に関する愛媛県議会本会議での質疑内容を紹介しておきます。
●平成16年 第287回定例会 (第2号 6月10日)No.5 玉井実雄議員(自民党)
次に、伊方原子力発電所におけるプルサーマル計画についてお伺いいたします。
先般5月10日、四国電力は、県及び伊方町へ伊方3号機で2010年度までにプルサーマルを実施したいとの事前了解の願いを提出しました。
プルサーマル計画については、既に関西電力が、福井県の事前了解と国の原子炉設置変更許可を受け、本年3月にはフランスの燃料加工会社と基本契約を締結しております。また、九州電力でも、先般、2010年度までの玄海3号機での実施方針を固め、地元への申し入れを行ったところです。
このプルサーマル計画は、使用済み燃料の中に残っているウランとプルトニウムを再処理により取り出し、混合燃料いわゆるMOX燃料に再加工して使用するというものであり、国が将来にわたる我が国のエネルギーの安定供給に不可欠な政策として推進しているものです。
外国では、フランスやロシア等は、我が国と同じように原子力発電及び再処理を推進しておりますが、アメリカやカナダ等は、原子力発電は行うが使用済み燃料は直接処分する方針をとっております。一方、ドイツ・スウェーデン等のように脱原発を政策に掲げている国もあります。また、内外の一部の学者や福島県知事等から、経済的に直接処分をする方が有利との意見や核燃料サイクルの推進については立ちどまって再検討すべき等の意見が提示されていることも、御承知のとおりであります。
このようにさまざまな意見が自由に表明され議論されることは、民主国家として健全なあかしでありますが、一般国民や県民にとっては、プルサーマル計画の是非を判断することが難しい状況であると思うのであります。
そこで、改めて、我が国の原子力政策、特に、核燃料サイクル政策とその一環であるプルサーマル計画について知事の基本的な認識はどうか、その根拠とともにお示しいただきたいのであります。
次に、プルサーマル計画の安全性についてお伺いします。
もとより原子力政策は、安全確保を最優先とすべきことは言うまでもなく、知事からも管理委員会等を開催し安全性を十分確認していくとの表明がなされているところです。
先日、県が計画の容認を前提としているかのような新聞報道がなされましたが、県政与党に対して県が示したスケジュール案は、あくまで一つのケースとして手続の流れの例示があったものと認識しており、白紙の状態から検討がなされていくものと確信しております。
そこで、今後、四国電力からの事前了解願に対し、伊方原発での安全性をどのように確認し、対応していくのかお伺いしたいのであります。
No.9 加戸守行知事
次に、原子力問題で、我が国の原子力政策、特に、核燃料サイクル政策とその一環であるプルサーマル計画についての知事の基本的な認識はどうか。また、その根拠はどうかとのお尋ねでございました。
国では、エネルギー基本計画等において、我が国が将来にわたりエネルギーの安定供給を確保するため、燃料の備蓄性や地球温暖化対策等にすぐれた原子力発電を基幹電源に位置づけているところでございます。
また、使用済み燃料中の有用資源を回収・再利用する核燃料サイクル政策は、原子力発電のすぐれた供給安定性を一層改善するものとして、その推進を原子力政策の基本とし、プルサーマル計画は、核燃料サイクルの中軸として着実に推進していくとしております。
今日、我が国を取り巻くエネルギー事情を概観いたしますと、まず、自給率は、原子力を除くとわずかに4%という低い率にとどまっておりますこと、それから、石油は、輸入の86%を政情不安定な中東に依存しておりますこと、近隣国との電力融通は、地理的に考えましても不可能であること、地球温暖化防止のため、化石燃料は使用抑制が必要であること、さらに、世界のウランの可採年数は約60年と見込まれておりますこと、そして、途上国のエネルギー需要は、今後、飛躍的に増大することなど、諸般の状況の中にあります。
また、再処理よりも直接処分の方が経済的に有利との意見もございますが、その差は総発電コストの1割程度であるとされておりまして、そもそもエネルギー政策は、経済性のみならず、資源の有効利用やエネルギー安全保障など、総合的な観点から評価がなされるべきものと考えております。このようなことから、国の原子力政策は、安全確保と国民の理解が当然の前提ではございますけれども、基本的には、現実的かつ妥当なものと認識をしているところでございます。
No.12 吉野内直光副知事
玉井議員にお答えします。
私の方からは、伊方原子力発電所におけるプルサーマル計画についてのお尋ねのうちの、今後、四国電力からの事前了解願に対し、伊方原発での安全性をどう確認し、どう対応していくのかとの点についてお答えさしていただきます。
四国電力から事前了解願につきましては、お話のとおり、安全確保を最優先に、専門家や県議会、そして、県民各界各層の代表者から成ります方々の意見を十分に踏まえまして、白紙の状態から検討を進めることといたしております。
そこで、まず6月1日には、原子燃料工学等の専門家で構成しております伊方原子力発電所環境安全管理委員会の技術専門部会これを開催しまして、科学技術的観点から審議をいただきました。その結果、MOX燃料は、炉の3分の1程度までの範囲ではウラン燃料と同様な安全設計が可能であることが原子力安全委員会により確認されており、海外においても十分な安全使用実績が認められるとしまして、その基本的な安全性は確認されましたが、伊方3号機での安全性につきましては、個別に原子炉の特性を踏まえた国の安全審査結果を待って、改めて審議することが必要とされたところでございます。
このため、当面、国の安全審査の前提となります四国電力の原子炉設置変更許可申請これの取り扱いにつきましては、本議会での議論や地元の意見等を踏まえまして、伊方原発環境安全管理委員会におきまして、慎重に審議していただき、判断してまいりたいと考えております。
なお、報道のございましたスケジュールの資料につきましては、1つのケースとして例示したものでございまして、計画容認を前提としたものではございませんので御理解を願いたいと思います。
以上でございます。
●平成16年 第287回定例会 (第2号 6月10日)No.20 高橋克麿議員(社民党)
最初は、先ほど玉井議員からもありました伊方原発のプルサーマルの問題についてであります。
去る5月10日、四国電力は、2010年度までに伊方原発の3号機、加圧水型軽水炉、出力89万kwでプルサーマル計画を実施すると発表し、県と伊方町に事前協議を申し入れました。原発における安全の確保は、住民にとって最大の問題であります。
プルサーマル計画は、プルトニウムとウランの混合酸化物・MOX燃料を通常の原子力発電所で燃やすものであり、もともと従来の原発は、MOX燃料を燃やすようには設計されていないのであります。ウラン燃料を燃やせばプルトニウムを発生しますので、今でもプルトニウムを燃やしているんだと説明する向きもありますが、それは燃焼途中から発生したプルトニウムが核分裂反応に加わる設計だからということでしかありません。
しかし、プルサーマルは、燃焼の初めからプルトニウムが核分裂反応に加わるわけですから、今までの原子炉の設計では無理な可能性もあるため、国が安全審査を行い、大丈夫だと結論を出してはいます。しかし、結論を導くまでの過程で、実際には、MOX燃料が実験中に破裂したり曲がったりということが起こりましたが、安全審査の結論は、これらを問題視していない結果になっています。
そこで、まずお伺いします。
実験中に問題が生じたにもかかわらず、通常の原子炉での燃焼を大丈夫と結論づけたことは、安全上、心もとないと思うのでありますが、安全審査の結論に至るまでの経緯を含め、国の判断や対応を県はどのように認識しているのかお聞かせください。
次に、経済的には、ウラン燃料の1.6倍とも2倍以上とも言われるMOX燃料の高コストが問題になっています。電力自由化でコスト競争をしなければならないときに、どうして電力会社がわざわざ高コストの燃料を使うのでしょうか。それは、たまりにたまってしまったプルトニウムの問題に関係があると思います。
日本は、原発の使用済み核燃料を再処理してプルトニウムを取り出し、それをまた燃料として使う、核燃料サイクル政策をとっています。本来は、高速増殖炉で取り出したプルトニウムを使うこととなっていましたが、御承知のように、高速増殖原型炉「もんじゅ」において、試験運転中の平成7年12月に2次系中間熱交換器出口配管からナトリウムが漏えいする事故が発生し、以後、計画はとんざしております。高速増殖炉を成功させた国は世界に一つもなく、無理からぬことではありますが、この失敗により、日本は使い先のない分離済みのプルトニウムを国の内外に38tもためており、世界からはその処理をどうするのか注視されているのです。
こうした経緯を踏まえると、プルサーマルの推進は、たまったプルトニウムを処理するという大義名分を実現するための苦肉の策ではないかと思えるのであります。実際、プルサーマルでの利用は多くを見込めず、焼け石に水で抜本的な解消には至らないのですが、一方では、青森県の六ヶ所村に再処理工場をつくってプルトニウムの抽出に取り組んでおります。日本の政策は首尾一貫しておらず、これでは大変お粗末と言わざるを得ないのであります。
そこで、2点目としてお伺いいたします。
国の核燃料サイクル政策のため、コスト高でありながら、プルサーマル計画が推進されている点について県はどう考えているのか、御所見をお聞かせください。
ところで、週刊朝日が「上質な怪文書」と報じた論文があります。霞が関の官僚の手によるものと見られていますが、核燃料サイクルについては一たん立ちどまり、国民的議論が必要ではないのかと結ばれており、官僚でさえといった感想を持つのであります。また文中には、核燃料サイクルに疑義を唱える有識者として自民党の河野太郎衆議院議員や福島県の佐藤栄佐久知事の名前も挙がり、これまで原発を推進してきた人たちの中からもちょっと待てとの声が上がり始めています。そして、こうした議論が、今、総合資源エネルギー調査会など政府の審議会内でも始まっているのです。ここはぜひ知事に十分な検討をお願いしたいと思います。
知事は、四国電力のプルサーマルをとめる権限は自分にはないと思われているかもしれませんが、福井でも福島でも新潟でも、電力会社は知事の意向を尊重しています。法的な権限はともかくとして、計画の事前了解をしないという形で、実質的に電力会社へ待てという権限を持っていると考えるのであります。
これまで原発は、交付金をもたらしました。しかし、今まで多くの自治体が安易にそれに頼って、結果的に本来その地域で育つべき産業に水をやることを忘れてしまい枯れさせてしまった側面も多いのではないでしょうか。原発が立地する地域で産業振興に成功し発展を遂げている自治体は、残念ながら一つも見当たりません。
また、伊方原発は、発電所としては日本でも最も古い部類に入ります。一昨年にはタービンのコンクリート架台のひび割れが内部告発で明らかになりました。安山岩がコンクリートに使われたためで、同じものが原子炉本体に使われていないという保証もないと思うのであります。これからは、老朽化の進む原発は早めに廃炉とし、交付金に頼らず、風力発電や太陽光発電、木材を生かしたバイオマスなど、明るくさわやかな自然に根差したクリーンエネルギーによる県おこし、まちおこしにチャレンジすべきときと考える次第であります。
そこで、3点目としてお伺いします。
政府の審議会等が核燃料サイクル政策をどうするのか議論を始めた今、ここで少し立ちどまり、プルトニウムをこのままつくり続けるのか、やめるのか等の結論を見きわめ、さらに県民間の議論を踏まえた上で、知事は、四国電力のプルサーマル計画に対する判断を出されても遅くはないと思うのでありますが、御見解をお聞かせください。
No.24 加戸守行知事
伊方原発のプルサーマルに関します質問の中で、安全性等の問題につきましては、県民環境部長の方から答弁させますが、コスト高でありながらプルサーマル計画が推進されていることをどう考えているのかとのお尋ねがございました。国の政策に対する見解でございますので、私の方から答弁さしていただきます。
先ほど玉井議員にもお答え申し上げましたとおり、将来にわたりまして安定したエネルギーを確保するためには、単に経済性だけではなくて、多角的な評価に基づく総合的な政策判断が重要であると認識いたしております。
そのような観点から見ますと、MOX燃料は、ウラン燃料に比較して燃料取得コストは高いものの、再処理することによりまして、ウラン資源の利用効率が最大1.5倍に増加すること並びに核燃料リサイクルによりまして、高レベル廃棄物が約40%に減容され処分費用が低減するなど、大きな利点があるものと評価されております。
加えまして、プルサーマルを含めました原子力発電のコストは、国のコスト等検討小委員会において、燃料の再処理や廃炉処理等のバックエンド費用を含めましても、1kwh当たり5.3円と試算されておりまして、石炭火力の5.7円、石油火力の10.7円など、他の電源と比較いたしますと、経済的優位性についても十分に確保されるものと認識いたしているところでございます。
No.27 石川勝行県民環境部長
伊方原発のプルサーマルについて、安全審査の結論に至るまでの経緯を含め、国の判断や対応を県はどのように認識しているかとのお尋ねでございました。
お話のMOX燃料が実験中に破壊した等の事案につきましては、フランスが平成5年から9年にかけて、研究用原子炉で燃料の出力を強制的に異常上昇させることにより、模擬的に事故時の厳しい条件を加えた際の燃料破損の状況を調査したものでございます。これ以外に、商業炉での使用におきましては、MOX燃料に起因する事故は発生しておらず、海外で約40年、約4,000体に上る使用実績がございます。
また、プルサーマル計画が先行している関西電力の高浜原発では、平成10年5月に、国に対して原子炉設置変更許可申請が提出され、同年12月に許可されましたが、この国の審査におきましては、フランスでの実験結果を反映して、平成10年4月に原子力安全委員会が策定いたしました「燃料の取扱いに関する審査指針」も適用されたものと承知しており、県といたしましては、異常事故を想定した十分な安全審査が行われたものと認識いたしております。
次に、政府の審議会等の結論を見きわめ、県民間の議論を踏まえた上で四国電力の計画を判断しても遅くはないと思うがどうかとの御質問でございました。
国におきましては、昭和36年の原子力長期計画策定以来、一貫して核燃料サイクル及びプルサーマルを原子力政策の基本に位置づけますとともに、昨年10月に閣議決定されましたエネルギー基本計画におきましても、原子力発電を基幹電源として、核燃料サイクル及びプルサーマルを着実に推進することといたしております。
また、最近新聞報道されました核燃料サイクル政策の見直しにつきまして国に確認いたしましたところ、新しい原子力長期計画の策定時期を迎え、さまざまな意見がありますが、原子力委員会として政策の変更を決めた事実はなく、国としては、核燃料サイクル政策を原子力政策の基本とし、プルサーマルを着実に推進していく旨の回答がございました。
そのようなことから、県といたしましては、現時点で国の政策に基本的な変更はないと理解しており、先ほど副知事から玉井議員にお答えいたしましたとおり、当面、国の安全審査の前提となる原子炉設置変更許可申請の取り扱いにつきまして、本議会での議論や地元の意見等を踏まえ、伊方原発環境安全管理委員会におきまして慎重に審議し、判断してまいりたいと考えております。
●平成16年 第287回定例会 (第3号 6月11日)No.23 笹岡博之議員(公明党)
(拍手)質問に先立ちまして、一言申し上げます。
昨今の報道をにぎわしております県警の捜査費不正支出疑惑につきまして、本来、法を遵守し社会正義を守る警察機関でありますから、より厳正に県民が納得のいく調査、解明、また、最大限の情報を公開するなど、前向きの対応を願うものであります。
また同様に、プルサーマル計画への対応にしましても、昨今御議論がございましたように、理解のためには専門的知識が求められる事柄であり、県民の生活、生命に直接関係する重要テーマでありますので、特段の対策を要請するものであります。
----












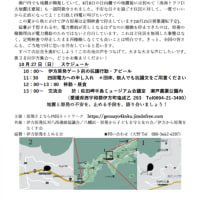

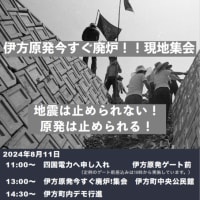
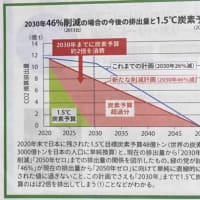
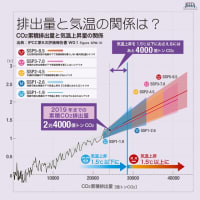
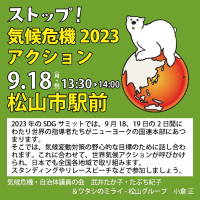
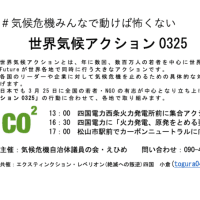
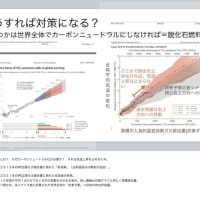






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます