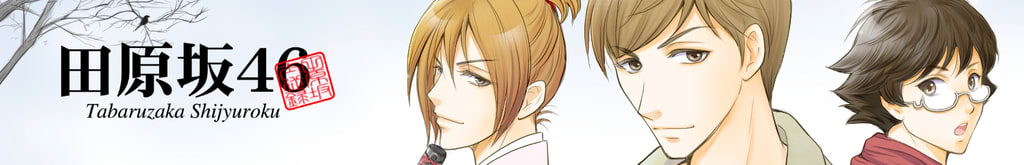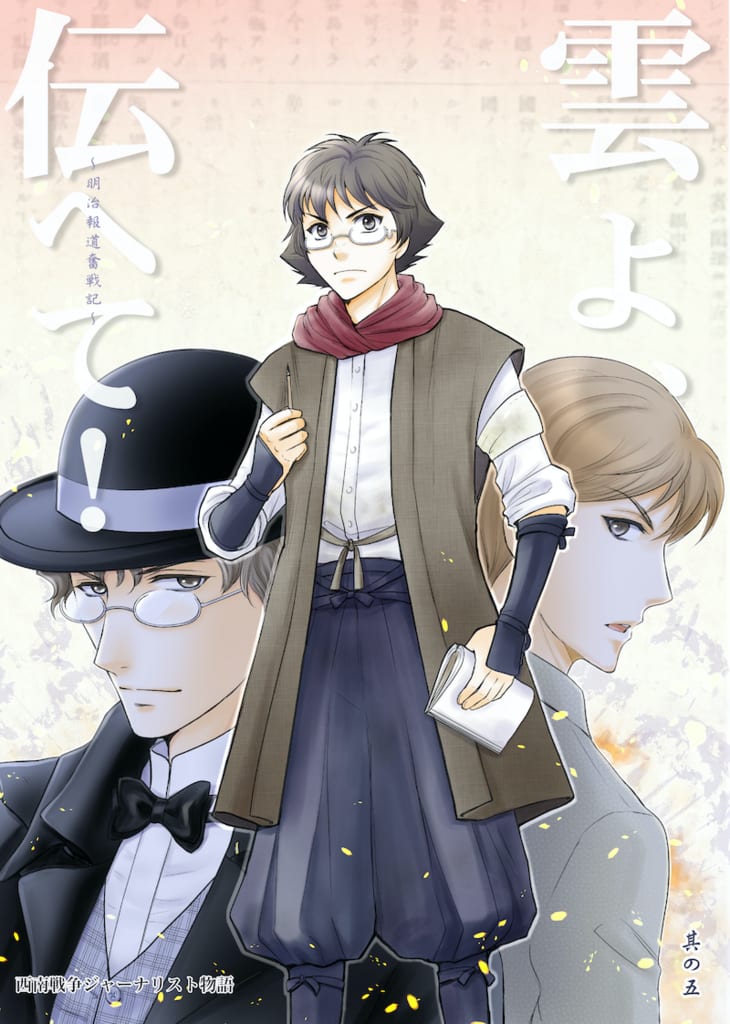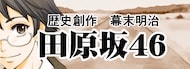苦手でしたね〜!読書感想文。
なんせ読みたく無い本を読めって言われるのが苦痛で。
自分の読みたい興味あるタイトルなんか1つも無かったもんね。
有島武郎の「一房の葡萄」とか、模試の時出たやつ
未だに納得できないですよ。
どうしろというんだよあれを。合わない作家とは合わんよ。
え〜世の中には科学と申しましても
「自然科学」「社会科学」「人文科学」とございます。
最近はこれに「システム科学」なんてのも入るようですが。
「本はたくさん読んでるよ」
なのに「読書感想文」になると「ハテ?」となる
そういう方は多分ですが
「人文科学」が苦手なのではと思います。
本はそりゃあたくさんありますよ、全ての世界に、
言葉で伝えるべきものがある限り、本はあります。
ところが「読書感想文」、「感想」を求められるのは
主に「人文」のジャンルです。
(最近はそこに配慮もされていて、いろんなジャンルの本が課題図書になってるようですが)
「感じる」という部分は圧倒的に人文系の方が多いかと思います。
でもこれが…
常に感じ方が受け身であると
「主人公はこう思ったので自分もそう思いました」
だと思うし
逆にちょっと捻くれたガキ…あ、いやお子様だとすると
自分の意見をしっかり持つが故に、学校や社会が優等生的な回答を求めるや
「書きたくない」「書かされる感が嫌」
と、思うかもしれません。
先生は「なんでもいいから本を読んで」と言っても
「テロリストが書いた本を読んだので明日から自分も大量殺戮」
などとは書いて欲しくないだろうし、逆に
「こういう生き方は絶対間違いなので、正しく生きようと思った」
だと先生は絶賛拍手なのではないの?
とか疑ってしまうわけですよね。
もしそうであれば、まずここで一旦
「文学とは素晴らしいもので、学校が道徳教育で使う」
ような文学への誤解は捨てませんか。
世の中には「悪魔文学」というものすら存在します。
堕胎にカニバリズムに連続猟奇殺人に薬物…タブーの連続のもある。
それから
「恋愛」苦手、もしくは人とそんなに関わりたくない
基本的に人間が嫌いだし、感情がどうこういうものは理解できない
という人もいると思います。
しかし、世の中は圧倒的多数で
「人の気持ちが理解できないのは異常」だの
「恋愛しなければいけない」だの、人に感情がある状態を正常としてきます。
怒ったり泣いたりキレたりイライラしたりでも十分なのに
そこに「人と一緒にいる多幸感」なんていう理想を押し付ける…。
そんなキャパ無い時だってあるんですよ、なんせ現代は多忙だから。
実は文学って案外
そんなに高尚なものでなくて、
そういう微妙〜にクールな部分をも書いてあったりするんですけど
文学アレルギーというのは、とにかく全く読みもしないで
「どうせ解らないのに、感情のもつれがどうこうを書いてあるんだろ?」
または
「どうせ、文学苦手な自分は人としてダメとか言うんだろ?」
ってなってんじゃないかと思います。
そしてまた「読みもしないで」と言われるのも苦手だ。
「読書家」は「読まない」人にマウントをとる。
学校であるいはマスコミが、本をたくさん読むのは偉いとか教えるからでしょうが。
私は書店の娘に生まれましたが、実は
「全然、文学作品を読めない、読まない子」でした。
そりゃそうだ、漫画の方が数倍面白かったんだもの。
親は頑張って文学全集を色々投下してきましたが、むしろ与えられた本は読めなかったです。随分大人になってから読み直したものは多いです。
文学が急に必要になったのは
「働きたくない」「受験なんか嫌だ」あたりからですw
世間一般と同様に働きたくないし、受験は嫌だし、人間なんか大嫌いだとか
大人社会ってクソすぎるとか、
世の中がぶっ壊れてくれないか、とか
そういう「闇落ち」状態にあった時です。
そんな人間に誰が寄ってくるわけでもなく、当然孤独になります。
そんな状態で初めて、まるで無言で隣に座ったかのように
スッと入ってきたのがヘルマン・ヘッセだとか
そんな感じです。
もしかして、一度泣き疲れて寝なければ文学なんかは要らないのかもしれません。
読書というのは、「誰かの話、誰かの声を聞く状態」で始まるので
自分の叫びを聞いてくれ!ばかりだと、読めないのかもしれない。
もしかしたら、読んでも同調はできず「はあ?」ってなるかもしれない。
納得いかないものもあれば、世間一般の解釈や感じ方、モラルと違ってしまうこともあるかもしれません。
「イマイチ解らん」もあるかも。
でも、それもやっぱり「感想」だと思うのです。
犯罪者である主人公に全く同意したり、逆にモラリストである主人公に殺意が湧いたり、するもんです。
そういうことは当然、大っぴらに言うと許されないのかもしれませんが、
文学というのは一旦、それも受け入れてしまうもんだと思います。
で、そこから「じゃあなぜ?」に発展するわけです。
ここからがきっと、「人文科学」なのだと、私は勝手にそう思っています。
「読書感想文と言っても難しく考えないで」とか言われるかもしれませんが
実は、人との距離が苦手だったり、自分自身に迷う時代は
案外書けないと思うのですが。
自分の場所がわからないでしょうが、そこは「私」「死」「思」「刺」「詩」
そういう場所であって、感覚的で文脈自体がうまれてこないかもしれない。
生まれてもそれは他人の言葉など必要としない、激烈なものかもしれないし。
だから無理して文学作品を読まなくても、漫画なり映画なりゲームシナリオなり、何らか心に響くものがあればそれでいいと思います。
ただ、心のどっかで
「文学はダメ人間の巣窟であり、ダメ人間でも一旦チャラにしてくれる場」
だと思っておいて欲しいかも…文学好きになった今としては。
テレビが、学歴の無い人や貧しい人をバカにして嘲笑しても
そのテレビに毒された「一般」が真似して叩いても
違う意味や美を見出しては、人が生きるってどういうことかを
逆に叩きつける人らがいたんだなって知って欲しい。
近代文学の限りにおいては
まあそういう物だと思ったらいいんではと
個人的に、そう思っています。