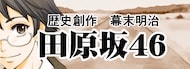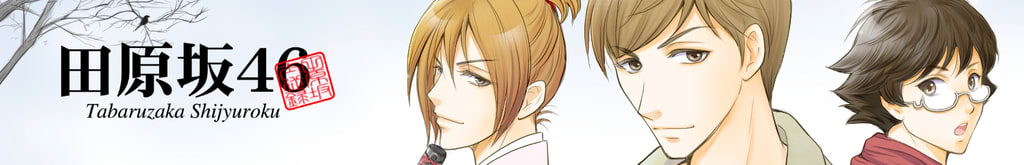
さて新刊もできてイベント前、準備中です。
石井貞興を通り名の方の「乙次」で出しました。
貞興の漢字の画数が多いなと思ったので;単に字面問題です。
石井さんは、鍋島藩主の親戚です。
一方、佐賀遊学で石井と知り合った熊本協同隊の平川は
百石取り…。これがどの程度の年収になるかは、計算方法にもよりますが
身分としては中流の武士だと思います。
ということは、石井さんはやっぱり随分フランクに
身分制度なんかはもう古いよ、という感じで接していた人物では
という気はいたします。
石井貞興は江藤新平の側近でした。
熊本協同隊の平川は、熊本で協力者を集めてほしいと言われたわけですが
佐賀の乱に行こうとする途中で終わっちゃうという…。
石井は佐賀の乱の後は薩摩に逃れ、桐野利秋が匿ったのだそう。
その後は西南戦争に参戦、夏ごろに西郷奇兵隊を率いたり
可愛岳突破も(官軍キャンプが目の前にある所を強引に突破していくという)…活躍しています。
山鹿戦はどうだったのか、今回はちょっとわかりませんでした。
桐野さんと仲はいいから山鹿にいたのか、それとも村田新八らと田原坂にいたのか?
石井貞興は…
司馬遼太郎が「歳月」という、江藤新平と佐賀の乱の小説を書いていて
石井竹之助という通り名で出していました。
あんまり目立って登場はしないけど。おとなしい感じでは無かったな。
今回の新刊に一つの考察ワードとして
佐賀の「葉隠」を登場させていただきました。
すでに時代遅れ…だったのかどうか。
葉隠は佐賀藩士の社交術をまとめたものですが、そのスピリッツのルーツはやっぱり
「論語」孔子孟子の類だと思います。
実は日本人の礼儀作法、謙虚さ、社交術、道徳心の中に「論語」はずっと残っていて
日本人にとってはやはり「聖書」の精神よりは
深くインストールされているのではないでしょうかね。
それで今回、調べていくうちに、植木学校はルソーのみでは無かったというのも知りまして
宮崎八郎や平川惟一の剣術、宮本武蔵の二天一流だったことからも考え
佐賀の葉隠論語における「常に民を思うべし」という考え方と、
ルソーの民権思想がうまいこと結びついたのでは…
なんてことを思ったのです。
「武士とは死ぬことと見つけたり」は別に死に急げという意味ではなくて
結局は志を持って生きれば、厚かましい我欲丸出しでなく
利他的精神で生きられるとか、そういう純粋さはあるのかと。
どんな考え方も利用されたら、捻じ曲げられてはしまいますが。
それはそうと、「小説」でないとつまんないだろうということで
あくまで物語として書き、物語としてまとめました。
余談が多くてw 今回は漫画では難しかったなあ。