EOS R3が発表になり、早くも品不足のアナウンスがされています。R3は縦位置グリップ一体型としては1015gと軽量です。これはμ43のE-M1Xと18g、ニコンのD850と10g差でほぼ同じと言っていいレベルです。今までEOS 1DXやニコンD6クラスを使っていたユーザーにとってはあきらかに1クラス小型化され、操作感はそのままで高機能化しているわけで、そのクラスのユーザーには受けると思います。
個人的にはE-M1Ⅱでも重すぎるので、1kgを超えるカメラは論外なのですがあまり購入する予定のない第三者的な視点からすると、R3はソニーのα9をキヤノンが作るとこうなりますといったカメラに見えます。α9は、スポーツ等の報道写真で使うことを想定した連写性能が売りでした。2016年に発売された当時は、2020年には8K対応し、オリンピックの報道では最も良く使われるカメラはソニーになると豪語していた記事を見ました。画素数的にも同じですし、ブラックアウトフリーの連写が特徴な点も同じです。
R3はオリンピックで実用テストをずいぶんおこなったようで、評判は上々のようです。新デバイスとして積層センサが採用されています。積層センサとはセンサの上に直接別のチップを乗せてしまう技術です。電気回路は配線が短いほど高速動作させやすいので、センサ内に作ってしまえば最も速く動作できますが大容量のメモリをセンサ上に作るのは困難なので、事前策として別に作ったチップをセンサに直接乗せてしまったのが積層センサです。このチップを載せた側から撮像はできませんから裏面照射タイプになります。
ソニーαもそうですがEOSR3でも1画面のメモリを積んでいるようです。つまり1画面の読み出しは高速におこなえます。ただ次に読み出しをおこなうまでにこのデータを画像処理回路をおこなう必要があります。したがって連続して読み出すためには、処理回路と伝送回路を高速化する必要があるので、積層センサにしても動画や連写性能が大幅に上がるわけではないようです。
読み出し速度を早くすることのメリットは第1に電子シャッターのローリングシャッター歪みの低減があります。これは電子シャッターでは露光の終了を読み出しで兼用しているので(開始タイミングは制御可能)読み出し時間が、そのままシャッターの動作時間になってしまいます。もちろん露光時間は露光開始時間を読み出しに合わせて可変するのですが、画面内では最大この読み出し時間だけ実際に露光しているタイミングが異なることになります。この館に画面内を移動するものがあると画像が歪んでしまうことになります。
実はこの現象はスリット露光をおこなうメカシャッターでも同様ですが、露光を完了する時間が1/250秒程度と短いので実用的にはほとんど問題になりません。
実はフィルムカメラもある時期までは、1/60秒程度だった時代が長く、プロが使っていたライカもニコンFもそうだったのですが、この歪みは(知られてはいましたが)ほとんど問題になっていませんでした。ソニーα1の読み出しがほぼ1/250秒程度、R3がそれよりやや遅く1/200秒程度と推定されます。(ストロボの同調スピードからストロボの発光時間約1msecを引いた値が読み出し速度と推定)
オリンパスのE-M1Ⅲ(Ⅱも)が積層センサ以外では結構早く1/50秒程度なのですが、先ほどのフィルムカメラの例から考えてこれぐらいでも十分実用的だと思います。従来のカメラでは1/15秒ぐらいのものが多く、これでは結構電車が歪んだりしてしまいます。
R3はR5に比べ画素数が少ないので、仮に積層センサを使わなかったとしても1/60秒程度の読み出しは十分可能なはずですし、そもそもメカシャッター(先幕電子シャッターでも)を使えばローリングシャッター歪みは十分抑えられているわけなので、あえて積層センサを使っている理由がよくわかりません。
積層センサはメモリチップを積層しなくてはいけませんし、裏面照射センサは裏面からの光が透過するように裏面を薄く削る必要もあります。とてもフルサイズセンサで安価にできるようになるとは思えないのすが、実際にはどうなんでしょう?少なくともEOS RPクラスに採用されるようになるのはかなり先になると思います。
高速読み出しができるとメカシャッターレスでも十分実用的なカメラができるはずなので期待しているのですが、積層センサだと低価格化ができなさそうで気になっています。
個人的にはE-M1Ⅱでも重すぎるので、1kgを超えるカメラは論外なのですがあまり購入する予定のない第三者的な視点からすると、R3はソニーのα9をキヤノンが作るとこうなりますといったカメラに見えます。α9は、スポーツ等の報道写真で使うことを想定した連写性能が売りでした。2016年に発売された当時は、2020年には8K対応し、オリンピックの報道では最も良く使われるカメラはソニーになると豪語していた記事を見ました。画素数的にも同じですし、ブラックアウトフリーの連写が特徴な点も同じです。
R3はオリンピックで実用テストをずいぶんおこなったようで、評判は上々のようです。新デバイスとして積層センサが採用されています。積層センサとはセンサの上に直接別のチップを乗せてしまう技術です。電気回路は配線が短いほど高速動作させやすいので、センサ内に作ってしまえば最も速く動作できますが大容量のメモリをセンサ上に作るのは困難なので、事前策として別に作ったチップをセンサに直接乗せてしまったのが積層センサです。このチップを載せた側から撮像はできませんから裏面照射タイプになります。
ソニーαもそうですがEOSR3でも1画面のメモリを積んでいるようです。つまり1画面の読み出しは高速におこなえます。ただ次に読み出しをおこなうまでにこのデータを画像処理回路をおこなう必要があります。したがって連続して読み出すためには、処理回路と伝送回路を高速化する必要があるので、積層センサにしても動画や連写性能が大幅に上がるわけではないようです。
読み出し速度を早くすることのメリットは第1に電子シャッターのローリングシャッター歪みの低減があります。これは電子シャッターでは露光の終了を読み出しで兼用しているので(開始タイミングは制御可能)読み出し時間が、そのままシャッターの動作時間になってしまいます。もちろん露光時間は露光開始時間を読み出しに合わせて可変するのですが、画面内では最大この読み出し時間だけ実際に露光しているタイミングが異なることになります。この館に画面内を移動するものがあると画像が歪んでしまうことになります。
実はこの現象はスリット露光をおこなうメカシャッターでも同様ですが、露光を完了する時間が1/250秒程度と短いので実用的にはほとんど問題になりません。
実はフィルムカメラもある時期までは、1/60秒程度だった時代が長く、プロが使っていたライカもニコンFもそうだったのですが、この歪みは(知られてはいましたが)ほとんど問題になっていませんでした。ソニーα1の読み出しがほぼ1/250秒程度、R3がそれよりやや遅く1/200秒程度と推定されます。(ストロボの同調スピードからストロボの発光時間約1msecを引いた値が読み出し速度と推定)
オリンパスのE-M1Ⅲ(Ⅱも)が積層センサ以外では結構早く1/50秒程度なのですが、先ほどのフィルムカメラの例から考えてこれぐらいでも十分実用的だと思います。従来のカメラでは1/15秒ぐらいのものが多く、これでは結構電車が歪んだりしてしまいます。
R3はR5に比べ画素数が少ないので、仮に積層センサを使わなかったとしても1/60秒程度の読み出しは十分可能なはずですし、そもそもメカシャッター(先幕電子シャッターでも)を使えばローリングシャッター歪みは十分抑えられているわけなので、あえて積層センサを使っている理由がよくわかりません。
積層センサはメモリチップを積層しなくてはいけませんし、裏面照射センサは裏面からの光が透過するように裏面を薄く削る必要もあります。とてもフルサイズセンサで安価にできるようになるとは思えないのすが、実際にはどうなんでしょう?少なくともEOS RPクラスに採用されるようになるのはかなり先になると思います。
高速読み出しができるとメカシャッターレスでも十分実用的なカメラができるはずなので期待しているのですが、積層センサだと低価格化ができなさそうで気になっています。


















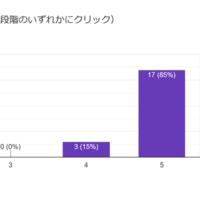
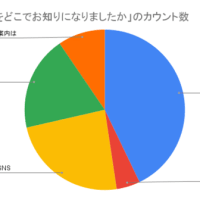






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます