2012年5月7日(月) 中尊寺入口より
GWの連休では、個人の観光客が多かったと思われますが、それが終わるとツアーや学生などの団体さんが多くなるようで、何処も大変な賑わいとなっていました。入口脇の駐車場も平日にも拘らず満車で駐車待ちができるほどですから、まだまだ休みの方も多いのかもしれません。自分もその一人ですけど・・・。
中尊寺の隅々まで歩き回って堪能した後、中尊寺の先に弁慶の墓なる案内を発見しました。

先ほどリラックマでもお世話(?)になりましたので、合掌
さて、そのまま駐車場に戻ってしまうのも芸が無いですから、弁慶といえば、次は、義経だろうとばかりに、少し歩いた場所にある高館義経堂に向かうことにしました。

場所は線路の向こう側らしいです
ちょっと観光地から外れるだけで誰も居なくなってしまうのは、平日といったところでしょうか

「卯の花に 兼房みゆる 白毛かな」
踏切を渡って直ぐ、義経に関連する曽良の句碑と湧き水を見つけました
・・・但し、水は枯れてしまったため、現在は水道水とのこと

ゆるゆるとした上り坂をあがると、受付がありました
管理は、毛越寺が行っているようです
拝観時間:8時30分~16時30分・冬季は、16時まで(年中無休)
拝観料:大人 200円
高館義経堂
ここ高館(たかだち)は、義経最期の地として伝えられてきた。
藤原秀衡は、兄頼朝に追われ逃れてきた義経を平泉にかくまう。しかし秀衡の死後、頼朝の圧力に耐えかねた四代泰衡は、父の遺命に背いて義経を襲った。文治五年(1189年)閏四月三十日、一代の英雄義経はここに妻子を道連れにして自刃した。
時に義経三十一歳。
吾妻鏡によると、義経は「衣河館」に滞在していたところを襲われた。今は「判官館」とも呼ばれるこの地は、「衣河館」だったのだろうか。
ここには、天和三年(1683年)伊達綱村の建立した義経堂があり、甲冑姿の義経の像が祀られている。
頂上からの眺望は随一で、西に遠く奥州山脈、眼下に北上川をへだてて東に束稲の山なみが眺められる。
束稲山は往時、桜山とも呼ばれ、西行が山家集で「ききもせず 束稲山の桜花 吉野のほかにかかるべしとは」と詠じた。
また、元禄二年、俳聖松尾芭蕉が「おくのほそ道」で詠んだ「夏草や 兵どもが 夢の跡」は、この場所といわれている。
平成六年四月 平泉町観光協会

義経堂に芭蕉句碑
正直イメージしていたものとは、大幅に違うものではありました

こちらが義経堂、甲冑姿の義経像が祀られています

こちらが上からの眺め、説明書きにあるようにいい眺めです
前方に駒形峯と束稲山

眼下には北上川が流れます
こうして振り返ってみると分かりますが、何の知識も無いまま観光地だと思って訪れても、そんなに楽しめない場所なのだと思います。義経のたどった背景や足跡、そしてその数百年後に訪れた松尾芭蕉が抱いたイメージ、そんな歴史を刻んだ場所であることをイメージしてから、この場所に立つと、歴史ロマンが萌え上がる・・・あれ、字が違うぞ・・・のでしょう。ただ、そんな素人向けにも、ちゃんと背景を説明をしてくれる資料館が併設されていますので、そこで勉強してから臨むといいかもしれません。
高館義経堂、ホームページもありますので、予習するとより理解が深まります。

平泉で良く目に付いたのは、四寺回廊 (しじかいろう) というポスター
関東のJRポスターで見かけますね
こちらは、平安時代 慈覚大師円仁がお開きになったみちのくのお寺を巡りましょうというキャンペーンです。松島 瑞巌寺、山寺 立石寺、平泉 中尊寺と毛越寺の四つの寺がそれにあたります。そういえば、奇しくもここ最近で気付かないうちに全てのお寺を廻っていたことになっていたことに偶然も在るものだと、ちょっと不思議な感じがしました。全ての御朱印を集めると何か戴けたようですが、御朱印集めしてませんから・・・。

観光案内板を見ながら、次は無量光院跡に行ってみようと歩き出します
・・・しかし、道を間違えたらしく

やってきたのは、柳之御所遺跡
「平泉館」と推測されており、奥州藤原氏の拠点だったと思われる場所です
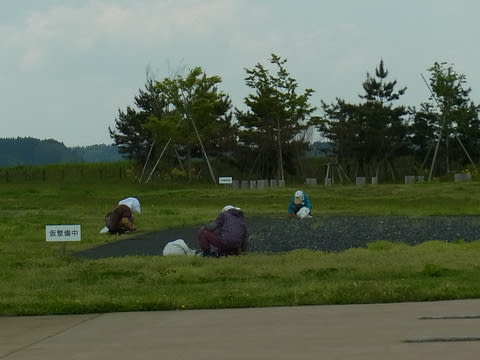
史跡公園となっていて、案内板などもありましたが
まだまだ完成はこれかららしく、リアルタイムで造っている途中でした
・・・なんでしょう、気まずいです

そして、そこに併設されているのが「柳之御所資料館」
そんじょそこらの資料館とは比較にならない位の情報量、そして非常に綺麗にまとめられていました
それなのに 「入館料無料」。
平泉文化遺産センターも入館料無料でしたが、何なのでしょうか、この地域の太っ腹っぷりは・・・・。
それなのに見学者が自分一人だなんて、平日だからだと思いたいです・・・。
この辺りの歴史を学んだ後は、ちょっと戻って無量光院跡に向かいます。

こちらが、無量光院跡
跡ということですので、建物等はありません

建物以外は復元されているようで、歩くことが出来るようになっています
昔こういった畦道でよく落ちたよなぁ・・・と、変な思い出が呼び出されます

宇治平等院の鳳凰堂を模して建立した寺院跡
鳳凰堂超えを目指したため、阿弥陀堂の柱間や翼廊の左右が鳳凰堂より大きくしてあったらしいです
これまでで十分歩いたこともあって、無量光院跡見学を終えたところで、そろそろ帰ろうと思ったのですが、この平泉の中心となっているある山が気になってしまいました。
その名も「金鶏山」。
無量光院跡は、「建物の中心線が金鶏山と結ばれており、その稜線上に沈む夕日に極楽浄土をイメージした造りになっていた」ということですし、「二代基衡が黄金で雌雄の鶏を造り、山中にこれを埋めて平泉を鎮護した」とか「北上川まで人夫を並べ、一晩で築いた」など伝説の山となっているのですから、やっぱり気になります。
観光案内図を見ても、場所も曖昧で観光地としてるようにも思えませんし、登れるなどという案内もありません。そうなると、やはり見に行きたくなるのは、性分なのでしょう。そこから、金鶏山探しが始まったのでした。

なんて格好よさげに書いてみましたが、ただの無計画な思いつき
山ですから見上げればそれらしい場所が見えますから、見つけるのは簡単そうです
距離はどのくらいあるのかは・・・近いことを祈るばかりです

その途中、大通りに面していながら、殆どの人が気付かないで素通りしてしまう「白山妙理堂」に立ち寄り
大通りからどう入るのか分からず悩みました

案内には、毛越寺境内附鎮守社跡 白山社 とあります
特別史跡白山社跡 白山妙理堂(別当 毛越寺一山 白王院)
本尊は十一面観世音菩薩。白山妙理権現をともに祀る。秀衡公の時代から明治初めまでは白山社山王社であり毛越寺・平泉の鎮守のひとつであった。1570年頃焼失。1678年二社を合祀し再建。現在の堂宇は1763年建立。境内地を囲む低地は「鈴沢の池」跡で史跡指定地である。
・・・おっと、寄り道してしまいました。
さてさて、金鶏山ですが、遠くから見ていると大体わかるのですが、近付くと分からなくなってしまうのは、低山ゆえでしょうか。大体方角はわかっているので、それらしい方向に向かっていくことにしますが、途中から「武蔵坊」という旅館を目指せばいいことに気付きました。これも弁慶のお導きでしょうか・・・。

ようやく案内標識も見つかりひと安堵、この先に金鶏山があるようです
後で知りましたが、源義経妻子の墓がその入口にあるため、その案内を目安に行くとよいようです

こちらが登山口、舗装路ですね

整備されていますので、特に苦労することも・・・いや、結構な勾配が

山頂へは、最後は階段で・・・と登り始めて数分も経ってません

山頂には祠と三角点がありました

残念ながら展望はありません
あっちが、先程の無量光院跡かなとか想像しつつ

下山後でこんな立派な看板に気が付きました
全然シークレットではないですね

お疲れの方は、下山後直ぐに見つかる「平泉温泉 悠久の湯」をどうぞ
そう、この山こそ、記事の始めに書いていた「最近登った山」で思い出した山だったのです(やっとつながった・・・)。
100mあるかないかの山ですので、山登りをしたという認定をされないかもしれませんし、黄金の鶏も見つかりませんでしたが、伝説にもなっている山に登れたのは、素直に嬉しく思えました。
ということで、気が付けば、世界遺産登録地域 <中尊寺><毛越寺><観自在王院跡><無量光院跡><金鶏山>を全て網羅することとなっていました。効率よく歩けばもっと楽に歩けると思いますが、ガイドブックなんて放り出して、案内標識にフラフラと流されて歩くのも楽しいものです。遠距離からの観光では、限られた時間で楽しむことが求められてしまいますが、じっくり腰を据えて楽しむと、また違ったものが見えてくるかもしれません。
今回は、世界遺産候補地域までは、範囲が及びませんでしたが、そういった楽しみもあるようですので、また季節を変えて来てみたいと思いました。


























まさに その通り!
遠い分、元をとろうだなんて欲深な人間には
奥行きも重さも感じられません。。。
ただ表面なめただけ。(ソフトかい)
にしても つくづくいけず。
>義経堂に芭蕉句碑・・
>説明書きにあるように、上からの眺めは良かったです
んで? なぜなぜなーぜ その画像なしなん?
とはいっても、マイナースポットばかり行って、メジャー所を外してしまっては、それこそ勿体無いですからね。
いきなりは難しいですから、気に入った場所には、何度も訪れてみるのが良いのでしょうね
画像の件、面倒だったの・・・もとい、あまり良い写真がなかったので掲載していませんでした。
かなり白んでしまいましたが、修正しておきましたので、ご覧くださいませ。
平泉で白山? ここまで遠くに? と思ってしまいましたが、「平泉」という地名自体が、福井県勝山市の平泉寺白山神社(へいせんじ~だったかな? 白山の昔の主要登拝口の1つ)から付けられた、とどこかで読んだことを思い出しました。
にしても、平泉、見ごたえも歩き応えもありそうですねぇ。
おおっ、コメントありがとうございます。
面白い情報ありがとうございます。
ちょっと調べただけでも藤原秀衡が白山権現を信敬していたことなど、多々出てきますね。
そういった視点でこのあたりを調べるのも楽しそうです。
平泉、ちゃんと見るとなったら見応え十分です。
ただ通常は、中尊寺と毛越寺 & 猊鼻渓(厳美渓)あたりが1日の観光コースですね。
猊鼻渓も楽しいですよ。