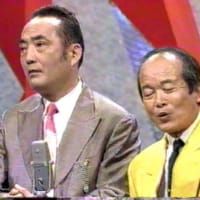話は、藤原一族に戻ります、、、って、長いこと忘れてました!٩( ᐛ )و
今年は、「光る君」のブームに乗って、紫式部と藤原道長の恋からの、藤原一族にスポットが当たってますが、そのルーツである、「藤原冬嗣」から、その子の「良房」、その養子の「基経」、そして「忠平」、「兼家」、「道長」、それに「筆マメの実資」まで触れましたが、大事なアクターを忘れてました!(°▽°)/
その名は、「藤原時平」、、、( ͡° ͜ʖ ͡°)
どんな人物だったか、ネットから引用しますと、、、
藤原時平は、摂政・関白となった藤原基経の長男として生まれ、昌泰2年(899)の29歳のとき左大臣(朝廷の当時の最高位)に任ぜられ、右大臣の道真とよく醍醐天皇を補佐した。
好色な人で、叔父の妻を自分のものにしたといい、笑い上戸で、いったん笑い出すと止まらない話があった。
ちょっと後半は看過できない表現がありましたが、そこそこ有能な人物だったようです。(^-^)
☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
この時平をめぐる出来事で、歴史上、最も名を残しているのは、やはり、あの菅原道真を九州の大宰府へ左遷した「昌泰の変」でしょう。m(__)m
こちらもネットで調べてみましょう。
「昌泰の変」は、901年(昌泰4年)に左大臣「藤原時平」の讒言(他人を貶めるためにありもしないことを言いふらすこと)により、右大臣「菅原道真」が大宰府へ左遷された事件。一般的には、藤原時平がライバルである菅原道真を追放した出来事と言われます。
しかし実際には、事件の背景に天皇家と藤原家の目に見えない綱引きがあり、それに菅原道真は巻き込まれてしまったのでした。
901年(延喜元年)の正月、醍醐天皇に対して「菅原道真が天皇を廃し、自分の婿である斉世親王を天皇にしようと企んでいる」と藤原時平が讒言。まだ15歳の醍醐天皇は、すぐ菅原道真に大宰府行きを命じます。
このとき、すでに醍醐天皇は反・菅原道真派に取り込まれていたのです。それを知った宇多法皇は、醍醐天皇に面会を求めましたが、宮廷の門は衛兵に閉ざされて入れず。
結局、醍醐天皇は、一晩中待ち続けた宇多法皇と会おうとしませんでした。こうして、宇多法皇・菅原道真勢力を政権から排除する計画は、大騒ぎにもならず、そして一滴の血を流すことなく成功。このクーデターは「昌泰の変」と呼ばれました。
左遷から2年後の903年(延喜3年)、菅原道真は大宰府で失意のうちに他界。一方で、昌泰の変から8年後の909年(延喜9年)に藤原時平は病死し、他にも昌泰の変に関与した官僚達も相次いで亡くなりました。
また同時に醍醐天皇も病に伏せ、政権の中心は再び宇多法皇へ移ります。そして藤原時平らの死は菅原道真の祟りとされ、923年(延長元年)に菅原道真の左遷は解かれて右大臣に復権。
しかしそのあとも清涼殿(天皇が日常的に過ごす館)に雷が落ちて多くの人が亡くなり、3ヵ月後には醍醐天皇まで崩御(天皇が亡くなること)したため、ついに菅原道真は「天神」として「北野天満宮」へ祀られることになったのです。
☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
藤原時平の陰謀も悍ましいことですが、菅原道真の怨霊も恐ろしいこと極まりないですね!( ; _ ; )/~~~
平安時代は、末法思想のせいか、怨霊信仰が広がりやすかったようですが、関係者の憤死や御所への落雷は史実のようですから、さもありなん、、、道真公の神通力はそれほどに強かったのでしょうね。m(__)m
「雷や謀りし者を蹴倒せり」 祖谷馬関
(注)雷(いかづち)は夏の季語。積乱雲の中などで雲と雲、雲と地上の間で放電現象が起きたもの。電光が走った後に雷鳴がとどろく。光と音の時間差でその遠近を測る。
今年は、「光る君」のブームに乗って、紫式部と藤原道長の恋からの、藤原一族にスポットが当たってますが、そのルーツである、「藤原冬嗣」から、その子の「良房」、その養子の「基経」、そして「忠平」、「兼家」、「道長」、それに「筆マメの実資」まで触れましたが、大事なアクターを忘れてました!(°▽°)/
その名は、「藤原時平」、、、( ͡° ͜ʖ ͡°)
どんな人物だったか、ネットから引用しますと、、、
藤原時平は、摂政・関白となった藤原基経の長男として生まれ、昌泰2年(899)の29歳のとき左大臣(朝廷の当時の最高位)に任ぜられ、右大臣の道真とよく醍醐天皇を補佐した。
好色な人で、叔父の妻を自分のものにしたといい、笑い上戸で、いったん笑い出すと止まらない話があった。
ちょっと後半は看過できない表現がありましたが、そこそこ有能な人物だったようです。(^-^)
☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
この時平をめぐる出来事で、歴史上、最も名を残しているのは、やはり、あの菅原道真を九州の大宰府へ左遷した「昌泰の変」でしょう。m(__)m
こちらもネットで調べてみましょう。
「昌泰の変」は、901年(昌泰4年)に左大臣「藤原時平」の讒言(他人を貶めるためにありもしないことを言いふらすこと)により、右大臣「菅原道真」が大宰府へ左遷された事件。一般的には、藤原時平がライバルである菅原道真を追放した出来事と言われます。
しかし実際には、事件の背景に天皇家と藤原家の目に見えない綱引きがあり、それに菅原道真は巻き込まれてしまったのでした。
901年(延喜元年)の正月、醍醐天皇に対して「菅原道真が天皇を廃し、自分の婿である斉世親王を天皇にしようと企んでいる」と藤原時平が讒言。まだ15歳の醍醐天皇は、すぐ菅原道真に大宰府行きを命じます。
このとき、すでに醍醐天皇は反・菅原道真派に取り込まれていたのです。それを知った宇多法皇は、醍醐天皇に面会を求めましたが、宮廷の門は衛兵に閉ざされて入れず。
結局、醍醐天皇は、一晩中待ち続けた宇多法皇と会おうとしませんでした。こうして、宇多法皇・菅原道真勢力を政権から排除する計画は、大騒ぎにもならず、そして一滴の血を流すことなく成功。このクーデターは「昌泰の変」と呼ばれました。
左遷から2年後の903年(延喜3年)、菅原道真は大宰府で失意のうちに他界。一方で、昌泰の変から8年後の909年(延喜9年)に藤原時平は病死し、他にも昌泰の変に関与した官僚達も相次いで亡くなりました。
また同時に醍醐天皇も病に伏せ、政権の中心は再び宇多法皇へ移ります。そして藤原時平らの死は菅原道真の祟りとされ、923年(延長元年)に菅原道真の左遷は解かれて右大臣に復権。
しかしそのあとも清涼殿(天皇が日常的に過ごす館)に雷が落ちて多くの人が亡くなり、3ヵ月後には醍醐天皇まで崩御(天皇が亡くなること)したため、ついに菅原道真は「天神」として「北野天満宮」へ祀られることになったのです。
☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
藤原時平の陰謀も悍ましいことですが、菅原道真の怨霊も恐ろしいこと極まりないですね!( ; _ ; )/~~~
平安時代は、末法思想のせいか、怨霊信仰が広がりやすかったようですが、関係者の憤死や御所への落雷は史実のようですから、さもありなん、、、道真公の神通力はそれほどに強かったのでしょうね。m(__)m
「雷や謀りし者を蹴倒せり」 祖谷馬関
(注)雷(いかづち)は夏の季語。積乱雲の中などで雲と雲、雲と地上の間で放電現象が起きたもの。電光が走った後に雷鳴がとどろく。光と音の時間差でその遠近を測る。