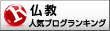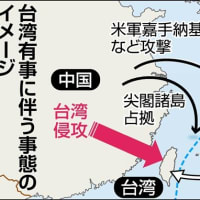著書のケーガン氏は本書の中で、死とは人格的な機能の停止をいうのか、肉体的な機能の停止を言うのか、という疑問を投げかけていました。確かに通常であれば、肉体的な死の直後に人格的な死が訪れるか、人格的な死の直後に肉体的な死が訪れるか。昔であれば大差は無かったので、こんな議論は無用であったのかもしれません。
日蓮正宗に伝わる「臨終用心抄」に於いても、死の判断は、鼻先に半紙をかざして揺れが止まった時(呼吸停止)を死と判断したと言う様な記述がありました。当時はそれで事足りた時代であったと思います。しかし近年ではここに差分が起きる状態が発生するので、この「死の区切り」を考察する必要のある時代になりました。
◆脳死について
近年の医療技術の進歩で、人工呼吸器が発明され、事故や脳疾患(脳梗塞などの類)で、人格的には死んでいるのですが、人工呼吸器により脳以外が生きている状態というのが存在します。これが「脳死」ですね。脳死の状態ですが、意識もなく、自発呼吸や瞳孔反射などは起こらないのですが、心臓やその他臓器の多くは生きています。この脳死については全脳死(脳全体が活動を停止した状態)と脳幹死(生物としての基本的な活動の停止、自発呼吸など)がありますが、欧米等では脳幹死を脳死としており、大脳の活動の兆候があっても「死亡」として線引きをしています。
全ての国で脳死を「人の死」としている訳ではありませんが、多くの国で、この脳死(全脳死もしくは脳幹死)を人の死と線引きをしている状況です。
ケーガン氏が著書の中で語っているのは、何も社会的な人の死と言う事ではなく、一人の人として、また哲学者として考察している内容を語らっていますので、ここで紹介した脳死については言及しては居ないようですが、今の人類社会としての「死」に対する考え方を理解しておく事も大事かと思いました。
◆ミリンダ王との対話
初期仏教には「ミリンダ王との対話」というのがあります。これはアレクサンダー大王の東征により、今のアフガニスタン方面には、ギリシャ人の国家があったと言います。そこの国のミリンダ王というのがいて、その王と仏教教団の長老ナーガ・セーナ師との対話について書かれたもので、ヘレニズム文化と仏教との出会いという意味あるものだと、過去から言われているものです。そこには初期仏教仏教が、「自我」の成り立ちに関してどの様に考えていたのかについても語られていました。
ここではミリンダ王はナーガ・セーナ師に質問します。自分とは一体どこにあるのか。心臓なのか、脳髄にあるのか、私の本体とは何処にあるものなのか。
それに対してナーガ・セーナ師は車を例にとって回答します。王よ、もし荷車があったとして、荷車とは何を指してそう呼ぶのか。荷台なのか、取っ手なのか、それもと車輪をもって荷車と言うのだろうかと。
すると王は答えます。それら一つひとつは部品であって、それをもって荷車とは言わないだろうと。
ナーガ・セーナ師は答えます。王よ、一文字同じように心臓だけをとっても、手や足だけをとっても、脳髄だけをもっても、その人とは言われないのです。自我とはそれら全てか集まり、その縁の上に成り立つものなのであると。
そしてナーガ・セーナ師は自我とはその様な、縁の上に成り立つものであって、どこか決まった臓器の上にあるものではなく、無我なのであると述べるのです。
とまあ、概要はこの様な対話をしていました。ここでナーガ・セーナ師は「無我」と言いましたが、それが仏教の云う無我を指すとは思えません。ただ人の命とは「縁の上に起きる=縁起」ということを、ミリンダ王に指し示したのです。
この「DEATH」という本で、ケーガン氏は「肉体的な死」と「精神的な死」について考察をしていましたが、実は私達の「生きている」という事について、仏教では「縁起」の上に成り立っていると述べ、「死」とはその縁起がとき解かれた時に訪れるものと述べています。
まあこれも、ご参考までのお話しですけどね。