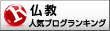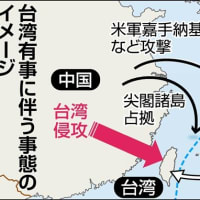この中で「一人で死ぬということ」について、以下の様にありました。
「(一人で死ぬ事について)だが、もちろんそれは正しくない。人は他の人がいる所で死ぬこともあるのは、誰もがよく承知している。たとえばソクラテスは友人や弟子たちの傍らでヘムロック(訳注:ドクニンジンから作った毒薬)を飲んで死んだ。だから彼は独りでは死ななかった。そして当然、知ってのとおり、友人や家族、愛する人々の見守る中で死んだ人のケースは他にいくらでもある。だから、私たちはみな独りで死ぬと言うのは、この主張の最初の解釈に基づけば、断じて正しくない。」
ここではシェリー・ケーガン氏は、多くの人が見守る中で死を迎える例は沢山あると言い、一人で死ぬという事は断じて正しくないと述べています。
確かに死に際して、親族や身内に見守られながらの死というのはよくある話しで、だから死というのは一人で迎えないというのも一理ありますが、私が思うのは、死という心の変化に伴う通過儀礼というか、その経験は必ず一人であると思うのです。
仏教では「死有」と呼んでいますが、そこを経験した多くの臨死体験等を確認すると、その際に、死にゆく人の周りには、その人の経験している事を共感する人が共に居たという話は聞いたことがありません。多くの臨死体験では、その先に例えば先に亡くなっている親族や友人と間見えたという様な話もありますが、やはり基本的に共感し、共にある人が居ないのであれば、それは「一人」と言う事ではないでしょうか。
思うに死有というのは、人生の一区切りを着けるタイミングでもあり、その際には自分の人生を省みる事があると言います。自分の人生を省みて、自分の人生は果たしてどの様なものであったのか、そこはやはり一人で評価しなければならず、そういう意味でもやはり「死にゆく人は一人」という事ではないでしょうか。
◆死は絶対に「協同作業」になりえない?
シェリー・ケーガン氏はこの本の中で、死は一人ではないという事と共に、この様な「共同作業」としての死についても語っています。
ふと思ったのは、誕生というのは多くが母子の共同作業と言っても良いでしょう。出産というのは女性にとっては、人生をかけた大事業であり、そこには産まれて来る子供との大変な作業があると思います。では「死」という事に果たして共同作業というのはあり得るのでしょうか。
この話を読んでいて、ふと思い出したのは、以前にNHKで難病の女性がスイスで安楽死を迎えるという事のドキュメンタリー番組をやっていました。スイスでは安楽死は合法的に認められております、ある一定の条件をクリアすれば、定められた手順(医師立会の元で薬による安楽死)で安楽死を選択する事が出来ます。このケースの場合、死という事については、希望者とその家族、そして医師との共同作業としての死と呼んでもいいかもしれません。
ただこの共同作業をするにしても、社会が死という現実、人は必ず死にゆく存在であるという理解が大前提となるので、今の日本もそうなのですが、人類社会としても、まだまだ難しいのかもしれませんね。
という事で、「DEATH」という本を読んだ中で、私が想った雑感でした。