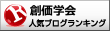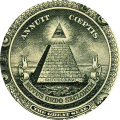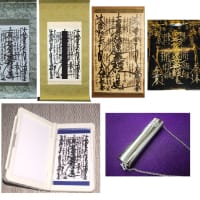今日の関東地方は青空が見えていて、気持ちが少し晴れる気がしています。やはり天気が良いのはいいですね。仕事は相変わらずテレワークなので、自宅に籠りきりですが、散歩に行きたくなってしまいます。
さて、今回は最近ネットを見ていて「仏罰」とか「成仏」というキーワードが目についたので、その事について少し考えている事を書いてみます。
◆仏罰について
これは創価学会や大石寺関係では、良く使われる言葉です。私も活動を離れる時期に、この言葉を先輩から言われました。
そもそも仏教で説かれる「仏」が人々に罰を与える事があるのか、ですが、仏とはこの世に出現する目的が「衆生救済」なので、その救済すべき衆生を仏が罰するという事はありません。例えば経典や様々な説話で、人々が悪道に墜ちたりする事も書かれていたりしますが、それらは仏から罰せられるというよりも、自身が道を踏み外した結果、悪道に堕ちていく姿が書かれています。そういう角度で見れは、「法罰」という事にも見えますが、またそれも少しは違うと思います。
大乗仏教の最高峰である法華経は「円教(丸く無駄がない教え)」と呼ばれていますが、それは一切に無駄の無いという意味があります。たとえ一時期、罰の様に苦しむ事があったとしても、結果としてその経験も自身の自覚に依って、全てを意味ある事にする事が出来るというのが、この円教の指し示す事であり、仏教の教えだと思いますので、敢えて罰を際立たせて語る必要が一体どこにあるのでしょうか。
因みにこの「仏罰」の様に罰を際立たせて語ったのは、初代牧口会長や、二代目の戸田会長でした。日蓮の文字曼荼羅の讃文(紙幅の両端上部に書かれている文言)に、「若悩乱者頭破作七分(説法者を悩乱したら頭が狂うという意味)」と「有供養者福過十号(法華経を供養する者は仏の持つ功徳がある)」という2つの文言が、それぞれ功徳と罰を表すと述べ、罰を与える力があるから功徳も約束されるという様な言葉を語っています。
まあ作用・反作用の様に功徳と罰を語るのも、大いに誤解を生むと思うのですが、これはどうなんでしょうか。。。
この讃文自体は日蓮の文字曼荼羅全てに書かれている訳でもなく、現存する日蓮直筆の本尊で、この「若悩乱者頭破作七分」と書かれているのは2体しかありません。この事からも、今で言えば「注意書き」程度に認識すべきものであり、殊更それを仏教の本道であるかの様に語るのも変な話です。
因みに少し話は異なりますが、西洋の黒魔術や日本でも丑の刻参りにある「呪い」とか、あと日本で言えば神社などの「神」による神罰というのは、実際に有るようです。しかしこれらと仏教をまぜこぜにして罰論をふりかざし、人々を恐怖させ縛り付けるというのは、仏教の基本的な精神とは相容れない事であり、自称、正統仏教教団を名乗る創価学会や大石寺の信徒たちが、そんな事を語るのも変な話であり、もう少し仏教なりを学んでから語ってもらいたいものですね。
◆成仏について
さて、次に成仏という事について。
この言葉ですが、一般的な理解では「仏に成る」という事を言います。これは主に小乗仏教や大乗仏教全般に言われている事で、ここでいう「仏」とは一般的には釈尊の事であり、簡単に言えば成仏とは「釈尊の様になる」という事を指します。
多くの仏典で語られる釈尊とは、ある意味ですべての執着を断ち切り、悟りを開いた理想像としての人物像で、人々はその姿にあこがれ、それを目指して必死に修行に励みました。要は「目指すべき姿」としての仏です。
しかし法華経の如来寿量品で明かされた「久遠実成の釈尊」とは、そのような目指すべき姿ではなく、人の心の奥底の本質ともいうべき処には、そういった心は誰にでも備わっているし、むしろ私達一人ひとりは、そこから派生して生きているという事が明かされています。だから「成仏」と言っても「仏に成る」のではなく「仏を開く(本源的にある心の本質を理解する)」という事になります。
しかし多くの成仏論では、この法華経以前の成仏観で語られているのではないでしょうか。日蓮はこの事について「四教の因果(爾前経で説かれている成仏の姿)」と喝破しており、如来寿量品でも「方便の姿」と説かれているにも関わらず、やれその行動で成仏出来るとか、そんな事では成仏しないという様な議論が平気で為されています。
成仏とは言っても、突き詰めれば私は「自覚と自身への確信」にしか過ぎないと、私なんかは思うのですけどね。
以前にある人は「釈尊は悟りを開いたのではない、理解したのだ」という言葉があり、「釈尊は弟子達に悟らされたのだ」とも言っていました。これは釈尊の弟子達が、自分の師匠を宣揚したいが為に、摩訶不思議な「悟り」なる言葉を作り、師匠の釈尊はその「悟り」を得たから「仏になったのだ」と規定したというのです。
こういった事も、考え直す必要があるのではないでしょうか。何故なら、日常の人間を離れて乖離した「仏」を、大乗仏教では求めていなかったと、私は考えているのです。
まあ「仏罰」にしろ「成仏」にしろ、人を束縛する言葉になっていなければ良いのですが、どうも呪縛を生む言葉になっている様に、私は思えてなりません。