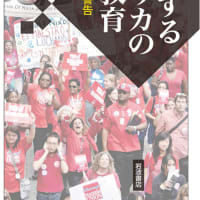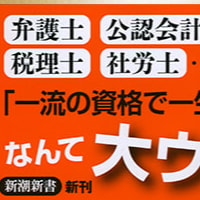子供や孫が3歳頃になったら親や祖父母は、なにか習い事をさせようと思い始めるのではないだろうか。専業主婦だった母親に連れれて、私もいろいろと習い事をさせられた。記憶にある習い事は、「バイオリン」「絵画」「英語」「野球のチーム」どれも長続きせず、特に「英語」はサボってばかりで、そのことがばれ、泣いてやめた記憶がある。当時は、まだ、塾という選択肢はなかったけれども、現在の習い事はどのようなものか、また、どのような習い事に通わせているのか興味があり、「習い事狂騒曲 正解のない時代の『習活』の心得(おおたとしまさ)」を読んでみた。

詰込み教育の反省から「ゆとり教育」が叫ばれ、さらに「脱ゆとり教育」へと時代が変遷した。教育熱心な親たちは、「ゆとり教育」の時代は、子供たちを「塾」へと走らせた。「脱ゆとり教育」の今は、「習い事」に重点を置いている状況かもしれない。ちなみに「脱ゆとり教育」は、2011年から開始しているが、基本の考えは、
---
<特に学力については、「ゆとり」か「詰め込み」かの二項対立を乗り越え、基礎的な知識及び技能、思考力、判断力、表現力等及び主体的に学習に取り組む態度という学力の三要素のバランスのとれた育成が重視される>
--
具体的な内容として、
<知識の定着を図るために、反復練習を多く取り入れた教科書を使用>
<道徳が教科化>
2020年からは、
<アクティブ・ラーニングの全面的な導入>(講義型の授業ではなく、生徒が提案したり話し合ったりすることで進められる授業)
<小学校におけるプログラミング授業の必修化>
<3年生から!小学生の英語教育>
---
つまり、学力だけでなく、発想力や表現力、コミュニケーション能力などあらゆる能力が企業や社会に求めれれるようになり、親たちも早い段階でいろいろな能力を付けさせたい、いろいろな経験をさせたいと願い始めているわけである。お金と時間が許す限り子供たちを頑張らせたい。この本では、そのことを【詰込み型ゆとり教育】と表現する。このフレーズを知って思わず笑ってしまった、言い得て妙。
親の時代と違う習い事として、
<プログラミング> 街角にプログラミング教室を見ることが多くなり、チラシなどにも小学生のプログラミング案内などを時々見るようになった。いったい何をどのように教えるのか疑問に思っていた。この本によると、一種の絵画教室、絵筆の代わりにコンピューターを使いロゴ遊びのような経験を積ませることらしい。「理系+アート」の習い事という説明がなるほどと思わせた。
<ストリートダンス> 2012年に中学の体育でダンスが必須化されている。また、「高校生ダンスバトル」などの影響もあり、バレエではなくダンススクールが隆盛である。
<キックボクシング> 空手や柔道、剣道でなくキックボクシング。フィットネス系のスポーツ。テコンドーなどと同じく、マイナーなスポーツであることのメリットを生かす習い事らしい。
その他、最新の<そろばん教室>や<ボーイスカウト>なども紹介されている。親の時代とは、かなり違った、あるいは、進化した習い事がめじろ押しである。
****
学力だけでなく、生きる力、へこたれない力をはぐくむためには、習い事は非常に有意義なものだと筆者は述べているが、習い事の問題点も詳しく述べている。特に子供に対する親の暴走には、気を付けたい。いかに東大生の2人にひとり、3人にひとりがピアノを習っていたと言ってもピアノを習わせれば、東大に入れるわけではない。
<主夫の作る夕食>
やっぱり秋はサンマ。不漁のサンマ、いつ取れたサンマなのだろう。

<想い出の一枚>
インド古代遺跡の門