ちまたの言葉
先日、草津へ行ったら年寄りたちが、
カエルの合唱のように、
「極楽」 「ゴクラク」「ごくらく」
と、白い湯のなかで言い合っていた。
子どもたちが、「ごくらくだね」
「すごくらくだね」
とだじゃれを言って笑っている姿も見たことはある。
温泉場でよく耳にする言葉だが、レストランや寝床で
つぶやく人はいない。
言葉の意味を調べると、
「極楽浄土、転じて心配のない安泰な境遇」とあるが、
なぜだか、風呂を「極楽」と言う。
だれも本当のそこへは行ったことがないはずだが。
しかし風呂にいる人々を見回すと、
うれしそうに底をけってシロクマみたいに泳いで、
湯口へ進む人、裸で湯げたのうえであおむけにとろけている人など
みんな自由を満喫していて仏さまのようにおおらか。
「あの世はこんなところかも」
という気さえしてくる。
「ゴクラクゴクラク・・・・」
と唱えれば唱えるほど、
あの世にいる気分が強まる。
私にはこの摩訶不思議な言葉の正体は、親から子へと
語り継がれた「呪文」のように思える。
俗世間を変えるための。
(朝日新聞 1999年5月7日 12面より抜粋)
言葉の違いとなると、地域ごとの方言であったり、
世代間で言葉も違ってくるだろう。
実家に帰ると、祖父はスプーンのことを「さじ」と言い、
一緒に食事をしていると、
「さじをとって」と言われることがある。
いつの間にか、自分の中には
さじ=スプーンという等式が成り立っている。
言葉の中には、具体と抽象があり、
人に何かを指示する時、伝える時には、
抽象では伝わらず、より具体的に、
採用試験における面接でも、
聞き手が具体化してストーリー(物語)をイメージに出来るように
話した方が良いとされる。
抽象的な言葉の典型例は、「頑張った」ではないだろうか。
近くでその人の発言や行動を見ていたなら、
まだしもわかるが、赤の他人に
自分のやったことを、一言で済ますとなると難しい。
また話し手にとっても、聞き手にとっても
「頑張った」という程度は、どれくらいのものなのかわからない。
自分自身は、頑張っているのか
そう自問自答しては、自らを追い込んでしまうものもいる。
自分は頑張っていると言えば、甘えにつながるかもしれない
自分はまだまだ頑張っていないと言えば、さらに厳しく追いこんでいく
感謝の気持ちを伝える「ありがとう」と比べて、
「頑張っているね」「頑張ったね」は、
側で、どこかで見ていないとわからないものだ。
だからこそ、この「頑張ったね。」「頑張ってるね」は
どこか人とのつながり感じさせる言葉なのかもしれない。
先日、草津へ行ったら年寄りたちが、
カエルの合唱のように、
「極楽」 「ゴクラク」「ごくらく」
と、白い湯のなかで言い合っていた。
子どもたちが、「ごくらくだね」
「すごくらくだね」
とだじゃれを言って笑っている姿も見たことはある。
温泉場でよく耳にする言葉だが、レストランや寝床で
つぶやく人はいない。
言葉の意味を調べると、
「極楽浄土、転じて心配のない安泰な境遇」とあるが、
なぜだか、風呂を「極楽」と言う。
だれも本当のそこへは行ったことがないはずだが。
しかし風呂にいる人々を見回すと、
うれしそうに底をけってシロクマみたいに泳いで、
湯口へ進む人、裸で湯げたのうえであおむけにとろけている人など
みんな自由を満喫していて仏さまのようにおおらか。
「あの世はこんなところかも」
という気さえしてくる。
「ゴクラクゴクラク・・・・」
と唱えれば唱えるほど、
あの世にいる気分が強まる。
私にはこの摩訶不思議な言葉の正体は、親から子へと
語り継がれた「呪文」のように思える。
俗世間を変えるための。
(朝日新聞 1999年5月7日 12面より抜粋)
言葉の違いとなると、地域ごとの方言であったり、
世代間で言葉も違ってくるだろう。
実家に帰ると、祖父はスプーンのことを「さじ」と言い、
一緒に食事をしていると、
「さじをとって」と言われることがある。
いつの間にか、自分の中には
さじ=スプーンという等式が成り立っている。
言葉の中には、具体と抽象があり、
人に何かを指示する時、伝える時には、
抽象では伝わらず、より具体的に、
採用試験における面接でも、
聞き手が具体化してストーリー(物語)をイメージに出来るように
話した方が良いとされる。
抽象的な言葉の典型例は、「頑張った」ではないだろうか。
近くでその人の発言や行動を見ていたなら、
まだしもわかるが、赤の他人に
自分のやったことを、一言で済ますとなると難しい。
また話し手にとっても、聞き手にとっても
「頑張った」という程度は、どれくらいのものなのかわからない。
自分自身は、頑張っているのか
そう自問自答しては、自らを追い込んでしまうものもいる。
自分は頑張っていると言えば、甘えにつながるかもしれない
自分はまだまだ頑張っていないと言えば、さらに厳しく追いこんでいく
感謝の気持ちを伝える「ありがとう」と比べて、
「頑張っているね」「頑張ったね」は、
側で、どこかで見ていないとわからないものだ。
だからこそ、この「頑張ったね。」「頑張ってるね」は
どこか人とのつながり感じさせる言葉なのかもしれない。










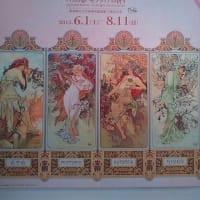









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます