待望のトキ 誕生へ日中協力
人工繁殖取り組み18年
絶滅の危機にある国際保護鳥トキの2世誕生が秒読みに入った。
新潟県佐渡トキ保護センターで、21日早朝、
ふ化の卵から、くちばしの一部が殻を突き破って、出てきた。
「チュー、チュー。」という鳴き声も、
はっきりと聞き取れるようになった。
ふ化に成功すれば、1981年に日本で人工繁殖の取り組みが
始まってから初めて。
ひなの親鳥2羽は、中国からの贈り物だ。
薄桃色の羽を広げて、大空を飛ぶ日は、
やがて来るのか。
かたずをのんで、待っている。
ひなの親は、雄の友友(ヨウヨウ)と雌の洋洋(ヤンヤン)。
ともに3歳の若いペアで、中国にある救護飼養センターから、
今年1月、日本に贈られてきた。
これまでに、卵を4個を産み、うち2個が有精卵だった。
21日午前5時半ごろには、卵の穴が5-7ミリづらいに広がり、
時折くちばしが、上下に動いて、殻を破ろうとしている。
殻を破る「はし打ち」が20日未明に始まってから、
3人の職員が交代で、寝ずの番を続けている。
ふ卵器内を映したモニターを監視しながら、
数時間おきに、ふ卵器を開けて様子を伺う。
現在、時の生存が確認されているのは、
日本と中国だけで、中国でも救護飼養センターなどで、
人工繁殖に取り組んでいる。
日本で人工繁殖が始まったのは、中国と同じ81年。
自然環境の中で、繁殖を断念した環境庁は、最後の1羽を
捕獲し、保護センターに移した。
だが、神経質なトキを飼育し、繁殖させることは難しく、
失敗が続いた。
日本産同士の繁殖の道が絶たれ、85年から日中協力が始まった。
トキ・・・・国際保護鳥で、学名は「ニッポニア・ニッポン」
日本では、国の特別天然記念物に指定されている。
明治時代の中ごろまでは、日本をはじめ、東南アジアに広く分布
していたが、乱獲や環境破壊などで激減した。
(1999年 5月21日 朝日新聞 夕刊 1面より一部抜粋)
2008年9月25日、
トキ10羽を佐渡から放鳥しました。
野生復帰まで、実に27年ぶりのニュースでした。
それから、半年が過ぎました。
佐渡トキ保護センターからの情報によると、
現在、国内で飼育されている数は112羽
野生のトキの数は、9羽になるそうです。
動物園などで、多くの動物が飼われています。
しかし、本来動物たちの生き方かすると、違うのかもしれません。
自然環境によって育つこと、生きることが出来たはずが、
今では、人工の環境によって、保護されながらでしか
生きられない動物もいる。
人工の環境から、自然の環境へと、戻ることが出来たら、
それは、素晴らしいことなのだろう。
自分自身、動物や植物には、ほとんど興味がないため、
名前を知らないことが多い。
人間との関係は、たいていどちらも話すことができるから、
相手の名前を知りたいという時には、簡単である。
しかし、動物や植物は、相手から「私の名前は○○だよ」なんて
言わないから、わからないことが多い。
だからこそ、興味・関心がなければ、名前は頭に入ってこない。
環境破壊によって、動物や植物が絶滅することは、
名前がなくなることと、一緒だ。
図鑑が好きな子ども、大人はたくさんいることだろう。
図鑑の写真だけで、見られるのではなく、
写真ではなく、本物の動物、植物が見られる環境づくりで
なければいけないと考える。
人工繁殖取り組み18年
絶滅の危機にある国際保護鳥トキの2世誕生が秒読みに入った。
新潟県佐渡トキ保護センターで、21日早朝、
ふ化の卵から、くちばしの一部が殻を突き破って、出てきた。
「チュー、チュー。」という鳴き声も、
はっきりと聞き取れるようになった。
ふ化に成功すれば、1981年に日本で人工繁殖の取り組みが
始まってから初めて。
ひなの親鳥2羽は、中国からの贈り物だ。
薄桃色の羽を広げて、大空を飛ぶ日は、
やがて来るのか。
かたずをのんで、待っている。
ひなの親は、雄の友友(ヨウヨウ)と雌の洋洋(ヤンヤン)。
ともに3歳の若いペアで、中国にある救護飼養センターから、
今年1月、日本に贈られてきた。
これまでに、卵を4個を産み、うち2個が有精卵だった。
21日午前5時半ごろには、卵の穴が5-7ミリづらいに広がり、
時折くちばしが、上下に動いて、殻を破ろうとしている。
殻を破る「はし打ち」が20日未明に始まってから、
3人の職員が交代で、寝ずの番を続けている。
ふ卵器内を映したモニターを監視しながら、
数時間おきに、ふ卵器を開けて様子を伺う。
現在、時の生存が確認されているのは、
日本と中国だけで、中国でも救護飼養センターなどで、
人工繁殖に取り組んでいる。
日本で人工繁殖が始まったのは、中国と同じ81年。
自然環境の中で、繁殖を断念した環境庁は、最後の1羽を
捕獲し、保護センターに移した。
だが、神経質なトキを飼育し、繁殖させることは難しく、
失敗が続いた。
日本産同士の繁殖の道が絶たれ、85年から日中協力が始まった。
トキ・・・・国際保護鳥で、学名は「ニッポニア・ニッポン」
日本では、国の特別天然記念物に指定されている。
明治時代の中ごろまでは、日本をはじめ、東南アジアに広く分布
していたが、乱獲や環境破壊などで激減した。
(1999年 5月21日 朝日新聞 夕刊 1面より一部抜粋)
2008年9月25日、
トキ10羽を佐渡から放鳥しました。
野生復帰まで、実に27年ぶりのニュースでした。
それから、半年が過ぎました。
佐渡トキ保護センターからの情報によると、
現在、国内で飼育されている数は112羽
野生のトキの数は、9羽になるそうです。
動物園などで、多くの動物が飼われています。
しかし、本来動物たちの生き方かすると、違うのかもしれません。
自然環境によって育つこと、生きることが出来たはずが、
今では、人工の環境によって、保護されながらでしか
生きられない動物もいる。
人工の環境から、自然の環境へと、戻ることが出来たら、
それは、素晴らしいことなのだろう。
自分自身、動物や植物には、ほとんど興味がないため、
名前を知らないことが多い。
人間との関係は、たいていどちらも話すことができるから、
相手の名前を知りたいという時には、簡単である。
しかし、動物や植物は、相手から「私の名前は○○だよ」なんて
言わないから、わからないことが多い。
だからこそ、興味・関心がなければ、名前は頭に入ってこない。
環境破壊によって、動物や植物が絶滅することは、
名前がなくなることと、一緒だ。
図鑑が好きな子ども、大人はたくさんいることだろう。
図鑑の写真だけで、見られるのではなく、
写真ではなく、本物の動物、植物が見られる環境づくりで
なければいけないと考える。










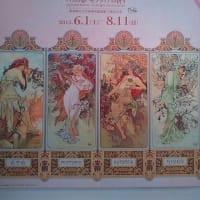









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます