国旗・国歌法の制定
政府方針 義務規定は盛らず
「日の丸」を国旗とし、「君が代」を国歌として
法律に定めるための検討を始めた政府は、
4日、その基本的な方針を固めた。
新しいひとつの法律を設けたうえで、
日の丸と君が代を国旗・国歌とする内容を
盛り込んだ。
また教育現場での日の丸掲揚や君が代斉唱は
盛り込まないことにした。今後は国旗・国歌を
尊重する内容を盛り込むかどうかなどについて、
外国の事例や国民の意識などを探りつつ具体化する方針だ。
野中官房長官は記者会見で、法制化について
「強要できると法の中で位置づけるものではない」
「国旗・国歌の根拠を明確に位置づけようというもの」などと述べ、
学校で義務付けるための規定は、法案には盛り込まない考え方を
強調している。
法律の形式は、海外では憲法に明記しているケースもあるが、
政府としては憲法には触れない方針。
自衛隊などの国旗の掲揚を定めた法律はあるが、
日本には、国旗と国歌そのものを扱う法律がないため、
現行法の改正とはせず、新規の独立法とする方針だ。
(朝日新聞 1999年3月5日付 1面より抜粋)
3月のこの時期になれば、卒業式のシーズンであり、
卒業式で君が代を歌うことが多いかもしれない。
1999年つまり10年前の今日までは、
正式に国旗・国歌として、日の丸・君が代は
認められていなかなったのである。
国民の意識の中に、あれ国歌って何だっけ
うん、式典で歌われているから、「君が代」なんじゃん
という形ではないだろうか
サッカーの国際試合が増えてから、君が代を歌っている姿を
目にすることが多くなった。
ほかの国の選手は、誇りを持って国歌を歌っているのに対し、
日本の選手は、なんとなくという感じがしてならない。
今日からはじまるWBCでは、前回にまして報道の加熱ぶりが
伝わってくる。
スポーツの国際試合を通して、国歌とはどうあるべきなのか
日本の代表として戦う選手が決して、歌うことが形式なのではなく、
歌うことの意味は何であるかを考えられたらよいのかなと考えた。
政府方針 義務規定は盛らず
「日の丸」を国旗とし、「君が代」を国歌として
法律に定めるための検討を始めた政府は、
4日、その基本的な方針を固めた。
新しいひとつの法律を設けたうえで、
日の丸と君が代を国旗・国歌とする内容を
盛り込んだ。
また教育現場での日の丸掲揚や君が代斉唱は
盛り込まないことにした。今後は国旗・国歌を
尊重する内容を盛り込むかどうかなどについて、
外国の事例や国民の意識などを探りつつ具体化する方針だ。
野中官房長官は記者会見で、法制化について
「強要できると法の中で位置づけるものではない」
「国旗・国歌の根拠を明確に位置づけようというもの」などと述べ、
学校で義務付けるための規定は、法案には盛り込まない考え方を
強調している。
法律の形式は、海外では憲法に明記しているケースもあるが、
政府としては憲法には触れない方針。
自衛隊などの国旗の掲揚を定めた法律はあるが、
日本には、国旗と国歌そのものを扱う法律がないため、
現行法の改正とはせず、新規の独立法とする方針だ。
(朝日新聞 1999年3月5日付 1面より抜粋)
3月のこの時期になれば、卒業式のシーズンであり、
卒業式で君が代を歌うことが多いかもしれない。
1999年つまり10年前の今日までは、
正式に国旗・国歌として、日の丸・君が代は
認められていなかなったのである。
国民の意識の中に、あれ国歌って何だっけ
うん、式典で歌われているから、「君が代」なんじゃん
という形ではないだろうか
サッカーの国際試合が増えてから、君が代を歌っている姿を
目にすることが多くなった。
ほかの国の選手は、誇りを持って国歌を歌っているのに対し、
日本の選手は、なんとなくという感じがしてならない。
今日からはじまるWBCでは、前回にまして報道の加熱ぶりが
伝わってくる。
スポーツの国際試合を通して、国歌とはどうあるべきなのか
日本の代表として戦う選手が決して、歌うことが形式なのではなく、
歌うことの意味は何であるかを考えられたらよいのかなと考えた。










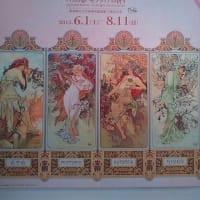









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます