薬、医療改革を前に
患者不在、揺らぐ治療への信頼
都内の私立大学医学部教授が、ある製薬会社の
臨床試験を引き受けたのは、2年前のことだ。
教授は会社の幹部に対し、治験を受ける「受託研究費」以外に
研究費の寄付を持ちかけた。
額は500万円。
治験が終わった後は、寄付は教授が研究員をしている
財団法人に振り込まれた。
この教授の場合、年間の研究費維持の為に4000万円が必要となる。
ところが、文部科学省や大学からの研究費では
そのおおよそ2割くらいでしかまかなえない。
残りは製薬会社に頼るしかないのだという。
治験は製薬会社と研究者との癒着の温床になりかねない。
新薬の安全性や効果を確かめる治療への信頼を揺らがせた事件も少なくない。
94年11月、血圧降下剤の治療をめぐる贈収賄事件が、
国立香川医大付属病院で摘発された。
新薬の治療に参加する「同意文書」にあった複数の
患者の著名の中には、実は病院の職員が書いたものがあった。
検察庁で文書を見せられ、自分が治療の対象者だったことを
初めて知った患者もいる。
この病院では年間200-300件もの治験が行われていて、
多くの治療をこなそうとするなかで、
改ざんやねつ造が起きた。
汚職事件の舞台になった病院の医師は、
厚生省の担当官にこう語ったという。
国内では、今、年間1000件前後の治療が進行している。
画期でなくとも、新薬であれば高い薬価がつく。
だから製薬会社は新薬開発に奔走する。承認後に薬を
売り込みやすいように、なるべく多くの治験を行う。
一方で、病院側は「研究費稼ぎ」の機会ととらえ、
引き受ける。
これらの事件から、新GDP「医薬品の臨床試験の実施に
関する基準」が大幅に改定された。
治療に参加する患者から同意で文書を得ること
治験が研究目的であること
副作用の危険があること
いやなら、途中で治療も降りることができること。
これら新GDPによって、
患者が治験に参加してくれないことも多くなったと
現場からは嘆きの声が聞こえる。
「患者が治療を断るのは、その新薬が患者にどうしても
必要ではないから。副作用があることを承知したうえで、
それでも治験に参加してくれる良い薬を開発していかなければならない。」
(朝日新聞 1997年9月13日付 第2社会面より 一部省略)
今、私たちの社会の流通しているものは、
多くが検査機関で認められて、そして社会に出ている。
使用方法、注意すれば、その多くが安全に使えるものである。
薬であっても、多くの臨床試験を行い、安全性が実証されてのものである。
今、口の中に口内炎が出来てしまい、なかなか治らないので
薬を買ってきた。薬のケースには効能、用法・用量、成分が
記されている。やたらと多い薬品が書かれているが、自分が
聞いたことのあるのはワセリンだけだった。
薬の新薬のために、犠牲という言葉は合わないかもしれない。
でも、薬だけでなく、食についても同じことがいえる。
今、私たちが食べられるのは、先代の人々が食し、腹を
壊したり、時には命を落としたことがあるから、
その食についての危険性が皆に伝わった。
世の中には、多くの不治の病が存在する。
日進月歩の医療において、新薬が開発されるためにも
国民の理解、医療を行う側の説明が大事であることを
強く感じる。
患者不在、揺らぐ治療への信頼
都内の私立大学医学部教授が、ある製薬会社の
臨床試験を引き受けたのは、2年前のことだ。
教授は会社の幹部に対し、治験を受ける「受託研究費」以外に
研究費の寄付を持ちかけた。
額は500万円。
治験が終わった後は、寄付は教授が研究員をしている
財団法人に振り込まれた。
この教授の場合、年間の研究費維持の為に4000万円が必要となる。
ところが、文部科学省や大学からの研究費では
そのおおよそ2割くらいでしかまかなえない。
残りは製薬会社に頼るしかないのだという。
治験は製薬会社と研究者との癒着の温床になりかねない。
新薬の安全性や効果を確かめる治療への信頼を揺らがせた事件も少なくない。
94年11月、血圧降下剤の治療をめぐる贈収賄事件が、
国立香川医大付属病院で摘発された。
新薬の治療に参加する「同意文書」にあった複数の
患者の著名の中には、実は病院の職員が書いたものがあった。
検察庁で文書を見せられ、自分が治療の対象者だったことを
初めて知った患者もいる。
この病院では年間200-300件もの治験が行われていて、
多くの治療をこなそうとするなかで、
改ざんやねつ造が起きた。
汚職事件の舞台になった病院の医師は、
厚生省の担当官にこう語ったという。
国内では、今、年間1000件前後の治療が進行している。
画期でなくとも、新薬であれば高い薬価がつく。
だから製薬会社は新薬開発に奔走する。承認後に薬を
売り込みやすいように、なるべく多くの治験を行う。
一方で、病院側は「研究費稼ぎ」の機会ととらえ、
引き受ける。
これらの事件から、新GDP「医薬品の臨床試験の実施に
関する基準」が大幅に改定された。
治療に参加する患者から同意で文書を得ること
治験が研究目的であること
副作用の危険があること
いやなら、途中で治療も降りることができること。
これら新GDPによって、
患者が治験に参加してくれないことも多くなったと
現場からは嘆きの声が聞こえる。
「患者が治療を断るのは、その新薬が患者にどうしても
必要ではないから。副作用があることを承知したうえで、
それでも治験に参加してくれる良い薬を開発していかなければならない。」
(朝日新聞 1997年9月13日付 第2社会面より 一部省略)
今、私たちの社会の流通しているものは、
多くが検査機関で認められて、そして社会に出ている。
使用方法、注意すれば、その多くが安全に使えるものである。
薬であっても、多くの臨床試験を行い、安全性が実証されてのものである。
今、口の中に口内炎が出来てしまい、なかなか治らないので
薬を買ってきた。薬のケースには効能、用法・用量、成分が
記されている。やたらと多い薬品が書かれているが、自分が
聞いたことのあるのはワセリンだけだった。
薬の新薬のために、犠牲という言葉は合わないかもしれない。
でも、薬だけでなく、食についても同じことがいえる。
今、私たちが食べられるのは、先代の人々が食し、腹を
壊したり、時には命を落としたことがあるから、
その食についての危険性が皆に伝わった。
世の中には、多くの不治の病が存在する。
日進月歩の医療において、新薬が開発されるためにも
国民の理解、医療を行う側の説明が大事であることを
強く感じる。










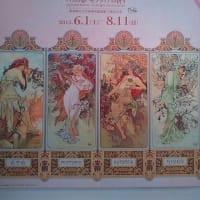









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます