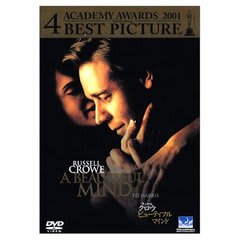
『ビューティフル・マインド』(2001年、ロン・ハワード監督)
第74回アカデミー賞作品賞、監督賞、助演女優賞、脚色賞、第59回ゴールデン・グローブ賞最優秀作品賞、最優秀主演男優賞、最優秀助演男優賞、最優秀脚本賞←こういうのに弱くて、ついついレンタルショップで選んでしまうミーハー(恥)。
この映画は公開されたときも知らなかったし、どんな内容かもまったく情報がないまま、DVDを借りてきました。こういうことって、あんまりないですよね。
だから、DVDのパッケージに書かれた解説で、てっきり天才数学者が国の諜報作戦に加担しつつ、どこかで良心に目覚めて、愛する妻ともに闘うドラマかと…。
そんな感じで観はじめたのです。
●だまされるほどに意外な展開
ストーリーの展開としては、サスペンスの要素も十分にあり、人間ドラマとして感動させてくれる部分もあり。おもしろかった~、というのが第一声でした。
主人公の数学者ジョン・ナッシュ(ラッセル・クロウ)は天才にありがちな(と勝手にこっちがイメージしているだけなんだけど)人付き合いの悪さを露呈しながらも、ルームメートのチャールズ(ポール・ベタニー)というまったく違うタイプの親友を得て、美しく賢い女性アリシア(ジェニファー・コネリー)と結婚し、望んでいた研究所に配属になる。
その後、国の諜報部門の暗号解読の仕事を得(1950~60年代だから、ちょうどアメリカ・ソ連の冷たい戦争の頃)、危険を冒しながら職務を遂行するようすはちょっとスリルもありサスペンス風なドキドキも用意されている。
そこにはまっていたら、突然、それらはすべてジョンの統合失調症による幻覚、という展開になるのだから、もうびっくり。諜報部員のヘリンガー(ジャド・ハーシュ)、チャールズ、チャールズの姪の三人は、実在の人物としての存在感さえあったから、それがすべて幻覚だったとは、にわかに信じられない。その証拠に、ジョンが再発して、再びその三人が現れたとき、やっぱり幻覚じゃないじゃない、あの精神科医も病院の職員たちもソ連のスパイだったよねえ、と自然に納得してしまったくらいだから。
だけど、やはり幻覚は幻覚だったようで、その後ジョンと妻アリシアは、苦難を乗り越え、病と付き合いつつ、彼が穏やかに暮らし、大学で昔の仲間の協力も得ながら、数学の道を歩んでいけるようになる。最後は1996年のノーベル賞受賞の場面で、「彼は今でも毎日、大学へ徒歩で通っている」というナレーションが流れる。
●幻覚の三人
印象的なシーンはいくつかある。
晩年のジョンは図書館の一角を自分の研究室のようにして、窓に数式を書きながら新しい理論の発見に余念がないのだが、そこで若い学生にユーモアをまじえて学問の真理について話しているところ。妻が友人に呼ばれてそこをのぞきにくるのだが、ここはいいなあ。病気のためか、人とのふれあいが苦手なジョンが、穏やかに微笑みながら若者たちに話しているさまに、妻はいろいろな思いを抱いているのだろう。
ノーベル賞の内定をもってきた男はジョンの病気の状態にさぐりをいれる任務もまかされてきたのだろう。若いときから足を踏み入れたことのない大学の食堂に入ってテーブルにつくと、周囲の仲間や後輩たちが次々に席を立って、彼の前にペンを置いて敬意を表していく。男も納得したようにジョンに微笑み返す。あそこもちょっと感動。偏屈で情緒不安定だった若い頃のジョンが、長い年月の闘いの中で、人としても学者としても、人々から尊敬される人物になっていたんだなあ、と。
それから、幻覚の中にあらわれるベンター、チャールズ、その姪の三人が、なんだかとても心に残る。
ジョンが自分の幻覚をちゃんと意識できるようになってからは、その三人が現れても無視できるようになるのだが、それで現れるのがなんだかせつない。あれは何を意味するのだろう。ジョンの心の中を何かの形で反映しているのかなあ、とか。
最後のノーベル賞の授賞式でも、パーティーの片隅に三人がひっそり立っている。もうジョンを惑わせたりせずに、そこに静かに立っているだけで、ジョンは三人をなんとなく意味ありげな目で見て去っていく。
登場人物の中でいちばん気になるのがこの三人っていうのは、ちょっと変わっていますか?
●精神疾患の扱い方
少し気になったのは、ジョンの病気である「統合失調症」(schizophrenia)(当時は「精神分裂病」と訳されていた)で、あんなにはっきりしたストーリー性のある幻覚があるのかなあ、ということ。症例でもみたことないけど、そういうこともあるのかな。ドラマとしては、これが大事なところなんだけど。私もこの幻覚の人物に心を揺さぶられたわけだし。
病気が主要のテーマだったりすると、患者さんや家族の方々からさまざまなメッセージや抗議が寄せられたりする、というけど、この映画でもそういうことがあったのだろうか。実在の人物を描いているといっても、ある程度フィクションととらえたほうがいいのか。そのあたりはよくわからないんだけど。
また映画の中で、「He is crazy.」が「彼は統合失調症だから」という字幕になっていたけど、これはちょっと違和感あり。「狂っている」とか「おかしい」という訳は人権擁護という意味で避けたのかもしれないけど、どうなんだろう。それは正確に伝えたことにはならないんじゃないかなあ。
映画としておもしろかったから別にいいんだけど、さっき「ジョン・ナッシュ:という実在の数学者について調べてみたら、いろいろ興味深い事実が判明。
真実は不明だが、反ユダヤ主義者であったとか、バイセクシャルで妻とは早くに離婚し、彼女は同居人としてつい最近再婚するまでジョンを支えていたということ、などなど。
この映画も賛否両論あるらしい。事実とは違うぞ、ということで。
だから、むしろフィクションとして楽しんだほうがいいのかな、ということです、きっと。物語としてはおもしろいし。
天才や英雄を描いたもので、陰の部分まできっちりと描いて名作、という作品には、なかなか出会えないですよね。
第74回アカデミー賞作品賞、監督賞、助演女優賞、脚色賞、第59回ゴールデン・グローブ賞最優秀作品賞、最優秀主演男優賞、最優秀助演男優賞、最優秀脚本賞←こういうのに弱くて、ついついレンタルショップで選んでしまうミーハー(恥)。
この映画は公開されたときも知らなかったし、どんな内容かもまったく情報がないまま、DVDを借りてきました。こういうことって、あんまりないですよね。
だから、DVDのパッケージに書かれた解説で、てっきり天才数学者が国の諜報作戦に加担しつつ、どこかで良心に目覚めて、愛する妻ともに闘うドラマかと…。
そんな感じで観はじめたのです。
●だまされるほどに意外な展開
ストーリーの展開としては、サスペンスの要素も十分にあり、人間ドラマとして感動させてくれる部分もあり。おもしろかった~、というのが第一声でした。
主人公の数学者ジョン・ナッシュ(ラッセル・クロウ)は天才にありがちな(と勝手にこっちがイメージしているだけなんだけど)人付き合いの悪さを露呈しながらも、ルームメートのチャールズ(ポール・ベタニー)というまったく違うタイプの親友を得て、美しく賢い女性アリシア(ジェニファー・コネリー)と結婚し、望んでいた研究所に配属になる。
その後、国の諜報部門の暗号解読の仕事を得(1950~60年代だから、ちょうどアメリカ・ソ連の冷たい戦争の頃)、危険を冒しながら職務を遂行するようすはちょっとスリルもありサスペンス風なドキドキも用意されている。
そこにはまっていたら、突然、それらはすべてジョンの統合失調症による幻覚、という展開になるのだから、もうびっくり。諜報部員のヘリンガー(ジャド・ハーシュ)、チャールズ、チャールズの姪の三人は、実在の人物としての存在感さえあったから、それがすべて幻覚だったとは、にわかに信じられない。その証拠に、ジョンが再発して、再びその三人が現れたとき、やっぱり幻覚じゃないじゃない、あの精神科医も病院の職員たちもソ連のスパイだったよねえ、と自然に納得してしまったくらいだから。
だけど、やはり幻覚は幻覚だったようで、その後ジョンと妻アリシアは、苦難を乗り越え、病と付き合いつつ、彼が穏やかに暮らし、大学で昔の仲間の協力も得ながら、数学の道を歩んでいけるようになる。最後は1996年のノーベル賞受賞の場面で、「彼は今でも毎日、大学へ徒歩で通っている」というナレーションが流れる。
●幻覚の三人
印象的なシーンはいくつかある。
晩年のジョンは図書館の一角を自分の研究室のようにして、窓に数式を書きながら新しい理論の発見に余念がないのだが、そこで若い学生にユーモアをまじえて学問の真理について話しているところ。妻が友人に呼ばれてそこをのぞきにくるのだが、ここはいいなあ。病気のためか、人とのふれあいが苦手なジョンが、穏やかに微笑みながら若者たちに話しているさまに、妻はいろいろな思いを抱いているのだろう。
ノーベル賞の内定をもってきた男はジョンの病気の状態にさぐりをいれる任務もまかされてきたのだろう。若いときから足を踏み入れたことのない大学の食堂に入ってテーブルにつくと、周囲の仲間や後輩たちが次々に席を立って、彼の前にペンを置いて敬意を表していく。男も納得したようにジョンに微笑み返す。あそこもちょっと感動。偏屈で情緒不安定だった若い頃のジョンが、長い年月の闘いの中で、人としても学者としても、人々から尊敬される人物になっていたんだなあ、と。
それから、幻覚の中にあらわれるベンター、チャールズ、その姪の三人が、なんだかとても心に残る。
ジョンが自分の幻覚をちゃんと意識できるようになってからは、その三人が現れても無視できるようになるのだが、それで現れるのがなんだかせつない。あれは何を意味するのだろう。ジョンの心の中を何かの形で反映しているのかなあ、とか。
最後のノーベル賞の授賞式でも、パーティーの片隅に三人がひっそり立っている。もうジョンを惑わせたりせずに、そこに静かに立っているだけで、ジョンは三人をなんとなく意味ありげな目で見て去っていく。
登場人物の中でいちばん気になるのがこの三人っていうのは、ちょっと変わっていますか?
●精神疾患の扱い方
少し気になったのは、ジョンの病気である「統合失調症」(schizophrenia)(当時は「精神分裂病」と訳されていた)で、あんなにはっきりしたストーリー性のある幻覚があるのかなあ、ということ。症例でもみたことないけど、そういうこともあるのかな。ドラマとしては、これが大事なところなんだけど。私もこの幻覚の人物に心を揺さぶられたわけだし。
病気が主要のテーマだったりすると、患者さんや家族の方々からさまざまなメッセージや抗議が寄せられたりする、というけど、この映画でもそういうことがあったのだろうか。実在の人物を描いているといっても、ある程度フィクションととらえたほうがいいのか。そのあたりはよくわからないんだけど。
また映画の中で、「He is crazy.」が「彼は統合失調症だから」という字幕になっていたけど、これはちょっと違和感あり。「狂っている」とか「おかしい」という訳は人権擁護という意味で避けたのかもしれないけど、どうなんだろう。それは正確に伝えたことにはならないんじゃないかなあ。
映画としておもしろかったから別にいいんだけど、さっき「ジョン・ナッシュ:という実在の数学者について調べてみたら、いろいろ興味深い事実が判明。
真実は不明だが、反ユダヤ主義者であったとか、バイセクシャルで妻とは早くに離婚し、彼女は同居人としてつい最近再婚するまでジョンを支えていたということ、などなど。
この映画も賛否両論あるらしい。事実とは違うぞ、ということで。
だから、むしろフィクションとして楽しんだほうがいいのかな、ということです、きっと。物語としてはおもしろいし。
天才や英雄を描いたもので、陰の部分まできっちりと描いて名作、という作品には、なかなか出会えないですよね。


























