2024.09.15
ロック大陸漫遊記
TOKYO FM
「敬老の日近辺のオンエアかな?」ということで、老眼鏡の話題から。
草野くんご自身は「老眼になってから」そこそこ時間がたったようですが、「この頃、世の中的には『老眼鏡』って言葉、使わないっぽいんだよね。お手元メガネとか、リーディンググラス、シニアグラスとか。調べたら、キャリアグラスってのもありました」。
やっぱり『老』という文字に抵抗を感じる人が多いのかな?と。
「『老眼鏡』の新しい呼び方考えるの、暇つぶしにいいかな」とか。「アリの観察もできちゃうってことで、アリンコグラスとか、星の砂みたいに小さいものもちゃんと見えるから、星の砂メガネ、略してHSMとかね」
肌の衰えと言わずに「年齢肌」とか、「加齢臭」じゃなく「大人臭」・・・、「最近はもはやトンチの世界になってるなと思いますけど」。
敬老の日も昔は「年寄りの日」と言っていたらしい。「敬老の日というのも、『老』の字が良くないって変わっていくかもしれない。『人生に先輩の日』とか『ベテランの日』とかになっていく?」
そして今日は、【ポストパンクで漫遊記】。
70年代後半のパンクロックを受けて、パンクのDIYの姿勢や反抗の精神は持ちつつ、あえてロックのスタイルには拘らないバンドたち。レゲエとかダブ、アフリカ音楽、現代音楽、ゴスたちの要素を取り込んだバンドたちのムーブメント。
「ロク漫史上、最もポップじゃない特集になるかもしれないですが、どうぞお付き合いいただきたいです」
オンエア
01 大好物(スピッツ)
02 Public Image(Public Image Ltd)
03 She Is beyond Good and Evil(The Pop Group)
04 Disorder(Joy Division)
05 Natural's Not in It(Gang of Four)
06 Dark Entries(Bauhaus)
07 Once in a Lifetime(Talking Heads)
08 エトセトラ(大場久美子)
漫遊前の1曲は、スピッツで「大好物」(2021年、45thシングル、配信のみ/2023年、17thアルバム『ひみつスタジオ』/『劇場版 きのう何食べた?』の主題歌として書き下ろす)。
今日はポップな曲がほとんどかからないかもしれないので、スピッツの曲くらいは「どポップ!な曲で」と。
最初の曲は、Public Image Ltdの「Public Image」(1978年、デビューシングル/1978年、デビューアルバム『Public Image: First Issue』)。
Public Image Ltdは、UKパンクのオリジネーターであるセックス・ピストルズのフロントマン、ジョン・ライドンが脱退後に作ったプロジェクト。
「ポストパンク」のバンドとしてまず浮かぶのは、このPublic Image Ltd。略して、PIL。
ピストルズ時代のわかりやすいラウドでシンプルなロックンロールから離れて、ロックの枠にとらわれない、ちょっと前衛的ともいえる音楽を鳴らし始める。
でも、この曲は「PILの中でもだいぶ聴きやすい。まだピストルズの雰囲気が残っているかな」。
PILとしては、2ndアルバム『Metal Box』の評価が高く(当時3枚のLPが丸い箱に入っていた)、その中でも「Albatross」が有名で、本来ならその曲を紹介したかったが、「単調な曲調の上に10分以上あるので、興味のある方は聴いてみてください」。
3rdアルバムの『The Flowers of Romance』の評価も高く、「当時カッコいいレコジャケだなと思っていたけど、今見るとちょっとホラーな感じだったかな」

「レコジャケについても、従来のロックアルバムから逸脱していてカッコいいです」
ポストパンクとは?
「商売の道具となり下がったロック、いわゆる産業ロックと呼ばれるものをもう一度ラジカルな音楽としてストリートに取り戻す」というのがパンクロックの革命。
それを通過したあとの「ポストパンク」なので、「姿勢としてはパンクなんだけど、音楽性はバラバラ」。
ノイズミュージック、ミニマルミュージックに寄った現代音楽的なものから、レゲエ、ダブ、アフロビートなど民族音楽に影響を受けたものもあるし、のちのゴスにつながるダークなものまで、さまざま。
ただ、「従来の音楽にはまらないものを目指している」というところで共通している。
「ラッセンよりピカソが好き、ルノアールよりカンディンスキーやパウル・クレーが好きだよ、みたいな、より芸術っぽいアンチコマーシャリズムなバンドが多いかな」
ノイジーで暗い曲が多い、ということでラジオではかけにくい・・・と「ロック大陸でもなんとなくスルーしてきたけど、でも避けては通れない」ということで。
草野くんも「実はあんまり詳しくなくて」。高校の頃にポストパンクが好きな友人からテープをよくもらっていた。
「そのときのテープを改めて聴き直すような漫遊になっています。詳しい方からすれば間違ったこと言うかも、ですけど、ツッコミながらきいてください」
次の曲は、The Pop Groupの「She Is beyond Good and Evil」(1979年、デビューアルバム『Y』)。
彼らも早い時期から、レゲエとか、アフリカンビート、ファンキーな音楽を独自のセンスで取り込んで新しい音楽を生み出そうとしていた、初期のポストパンクのバンド。
先ほどのPIMより早くからそういう音を鳴らしていたらしいが、「パンクは音楽のジャンルではなく既成の概念にとらわれずに表現する姿勢そのものなんだ」のお手本のような音楽。
この曲は、「昔はもっとアナーキーな音楽と思って聴いていたけど、今聴くとレゲエやダブの印象が強いかな」
次は、Joy Divisionの「Disorder」(1979年、デビューアルバム『Unknown Pleasures』)。
当時、草野くんの周囲では「ファンが多かったバンド」。
ポストパンクの中では「聴きやすいほうかな。シングルヒットもあるし」。
バンドの絶頂期に、ボーカルのイアン・カーティスさんが亡くなり、その後継バンドのNew Orderのほうが「今では知名度が高いかもしれない」。
しかし、Joy Division、New Orderともに、その後のUKミュージックカルチャーに大きな影響を与えた。
当時の草野くんは「ポストパンクにありがちなドタバタしたドラムが苦手だった」が、でも今聴くとカッコいいなと思えるようになったそうだ。
最近、Joy DivisionのレコジャケのTシャツを着ている若者をたまに見るそうで、「ちゃんと聴いてるのかな」と思っちゃうそうです。「こういう暗い音楽なんですよ、とおじさん、教えてあげたい」ww
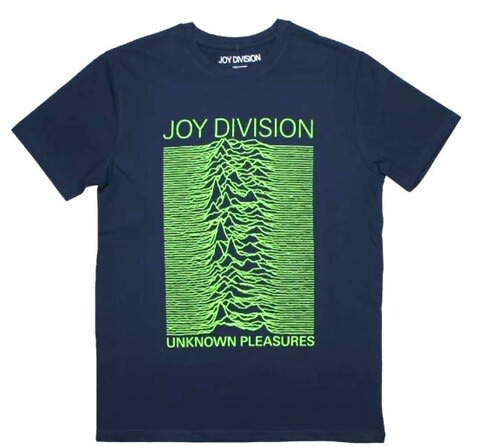
(こんなの?)
メッセージコーナー。
4年前にトルコドラマにはまり、トルコ語を勉強しているリスナーさんから。
この前のトルコロックの特集のオンエアリストをトルコ語の先生に見せたら、「渋いね」と言われたとか。
先生からの推薦曲リストを送ってくれたそうで、早速聴いてみたら、「モダンな感じの曲が多かった。こういう感じの曲もトルコにはあるんだな」と。
『Mother』のリメイクがトルコでヒットしたり、またトルコ語は日本語に似ているところもあるそうで、「トルコ語、ちょっとかじってみようかな」と思っている草野くんです。
そして次は、Gang of Fourの「Natural's Not in It」(1979年、デビューアルバム『Entertainment!』)。
このバンドも「ポストパンクに括られたバンドの中では聴きやすいほうかな」。
メッセージ性の強い歌詞も含めて、今日紹介されるバンドの中では「従来のロックのマナーにいちばん則ってるかな」。
その後のガレージロックリバイバルのバンドにも通じる、そんな質感のサウンドのバンド。
ウィルコ・ジョンソンさんの影響も強いらしく、今日の曲は特にシンプルなギターリフのロックなので、「今聴くと、サウンドの質感はAC/DCあたりのハードロックに近い」。
(今夜の中では最も響きました。私のここに)
メッセージコーナー。
「映画館で観客一人。貸し切り状態」を経験したリスナーさん。
すべて自分のためだけに・・・と思うと申し訳なく、また広い会場に一人というのも少し気味悪く、「コメディーでよかった」と。
そんな経験ありますか?
草野くんも「あれ、オレひとり?」と思ったことがあったけれど、ぎりぎりで二人組が入ってきたそうです。
「一人も入ってなくても時間になったら一応上映するのかなあ?」
と思ってGoogleで調べたら、誰もいなくても上映するそうですよ。昔は1時間後にまだ誰もいなかったら中止したり、もともと上映しない館もあったそうだけど。
「人気のない映画が好きになったりすることもあるので、(自分にも)そういう機会が訪れるかもしれない」
仲良しのお父さんが激しく忘れ物をする、どうにかできない?とリスナーさん。
「オレもね~、結構忘れ物多いので、直し方があるなら知りたいぐらい」
スマホを忘れることはよくあって、「2、3時間の外出なら、ま、いいか」と取りに帰らないことも。家を出てから気づくことがよくあるそうで。
忘れてはいけないものを書いてドアに貼り、指さし確認。「ま、基本ですよね」
話はちょっと違うけど、冷蔵庫を開けて、「あ、この牛乳そろそろかな」とか考えちゃうと、「何を取りに来たのかわすれちゃうことが最近増えたね」。
気を取られるものが周りに多すぎるんだろうね・・・。(うん、たしかにそうだ)
「とにかく紙に書いて指差し確認! 原始的だけど、これしかないんじゃないでしょうか」
次は、Bauhausの「Dark Entries」(1980年、インディーズ2ndシングル)。
このバンドは、ボーカルのピーター・マーフィーさんが耽美的なイケメンで、その後のゴスとかビジュアル系のバンドマンにも通じる、ちょっと退廃的なカッコよさ、美しさがあって、「当時女性の人気が高かった印象」。
「デヴィッド・ボウイさんの影響も強いのかな。『ジギー・スターダスト』のカバーもしてたしね」
先ほどかけた「Joy Divisionと同じ傾向で曲は暗め。Bauhausが好きという人は暗めの人が多かった印象あるな、うん」
Bauhaus 'She's In Parties' TOTP (1983) HD
曲終わりで、「80年代の日本のインディーズバンドで、Bauhausっぽいの多かったっすね。いろいろ思い出すわ」と。
漫遊最後は、「今日唯一のアメリカのバンド」、Talking Headsの「Once in a Lifetime」1980年、4thアルバム『Remain in Light』)。
Talking Headsは1stアルバムのときは「わりとわかりやすいバンドだった」。
そこからアフリカンビートを取り入れたりして、ロックの型から徐々にはみ出していった。
一聴するとちょっととっつきにくいが、今日のこれまでの曲のあとで聴くと「すごく聴きやすく感じるかも。キラキラした音のリフレインが続く楽曲で、「聴いていると気持ちよくなり人も出てくると思います。その後のデジタルのダンスミュージックに通じるところもあるかな」。
最近のTalking Headsは「ポップで聴きやすくなっていて、特集もやってみたいな」と。
特集の終わりに。
ポストパンクはその後、ゴス、マスロックとか、クラブシーンのダンスロックに、DNAをつないでいく。
先ほども言ったように、ポストパンクの重要な曲って、PILの「Albatross」のように長い曲が多い。今日は番組の構成上短い曲をセレクトしたが、「興味を持った方はぜひいろいろ聴いてみてください」。
今日の「ちょっぴりタイムマシン」は、大場久美子さんの「エトセトラ」(1978年、4thシングル)。
(イントロは、「青い車」・・・???」)
今日は暗めの曲が多かったので、ここでは「ちょっと能天気なアイドルソングを聴いてみようかな」と。
大場久美子さん、「小学生の頃の憧れのお姉さんでした」。
ドラマ『コメットさん』の主役で、「すごい人気でした」。
歌は上手じゃないけど、「聴いてるといい具合に脱力してくる・・・というか」と。
(かわいい・・・)
そして来週は、「ゼロ年代アメリカンロックで漫遊記」。
草野くんがよく聴いていたアメリカンロックといえば、80年代はR.E.M.、ピクシーズ、90年代はWeezer、Rage Against the Machine。
「だけど、ゼロ年代で夢中になったバンドっていたっけ?」と思って自宅のCD棚を探ってみたら、「結構いました」。
「来週はゼロ年代のアメリカのロックバンドを草野の偏ったセレクトでお送りします」だそうです。
「草野さん、最近寝相がよくなりました」
★ 「2018年1月にスタートしたこの番組、草野マサムネが話した言葉で印象に残った言葉を教えてください!」
ということですよ。
「SPITZ,NOW! 〜ロック大陸の物語展〜」への協力要請です!
https://www.tfm.co.jp/manyuki/
★ アルバム『空の飛び方』のジャケットにも使われたハンドチェアが展示されるそうです。
https://spitz-web.com/news/7520/
最新の画像[もっと見る]
-
 「次は8両で来ますよ」
12時間前
「次は8両で来ますよ」
12時間前
-
 「次は8両で来ますよ」
12時間前
「次は8両で来ますよ」
12時間前
-
 『スケアクロウ』と『ファイブ・イージー・ピーセス』
1週間前
『スケアクロウ』と『ファイブ・イージー・ピーセス』
1週間前
-
 2006年、やっぱり少し「懐かしい」。
2週間前
2006年、やっぱり少し「懐かしい」。
2週間前
-
 2006年、やっぱり少し「懐かしい」。
2週間前
2006年、やっぱり少し「懐かしい」。
2週間前
-
 ひさびさに「マーメイド」が流れたよ。
2週間前
ひさびさに「マーメイド」が流れたよ。
2週間前
-
 メンバーは結構イケてた~ライブハウスの思い出で漫遊記!
4週間前
メンバーは結構イケてた~ライブハウスの思い出で漫遊記!
4週間前
-
 オペラ、いつか食べたい。
4週間前
オペラ、いつか食べたい。
4週間前
-
 「掘っても掘っても・・・」、60年代のフリークビートで漫遊記
1ヶ月前
「掘っても掘っても・・・」、60年代のフリークビートで漫遊記
1ヶ月前
-
 「掘っても掘っても・・・」、60年代のフリークビートで漫遊記
1ヶ月前
「掘っても掘っても・・・」、60年代のフリークビートで漫遊記
1ヶ月前















