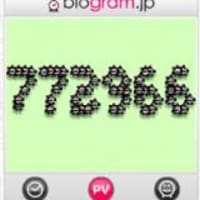天候が今一つ定まらず、着るものをあれこれ
迷った前日、ちなみものがないことに気づき、
 (討ち入りといえば…雪だよね)
(討ち入りといえば…雪だよね)
思案の末、雪の結晶柄が入った半衿を
夜半に慌てて襦袢につける。
なかなか、ちなみものまで気が回らない私、
長時間の観劇ということもあり、結局、着慣れていて楽な
白鷹織の白を無理やり雪に見立てたりして。
こんなコーデになりました。

帯は、二子玉川の松美屋さんでいただいた
博多織の八寸。とても軽くて締めやすいのです。
帯締めは松山好成さん。帯揚げはきねやさん。
後ろと半衿アップはこんな感じ。

でも、今になって

小糸染芸のこの小紋も、雪らしかったかしら、と
やや心残り……。
さて、14日は討ち入りの日だけあって、
 「劇場の喫茶に集まりましょうよ!」
「劇場の喫茶に集まりましょうよ!」大劇場で歌舞伎の忠臣蔵を観てらした、Yさんのお声掛けで、

忠臣蔵シスターズ(笑)の4人が集合。

左上のYさんは、雪を思わせる江戸小紋に、雪の結晶柄の帯。
帯飾りも私には「雪転かし(こかし)」の段を想起させます。
確かお草履の鼻緒も雪だったような……。
左下は、お久しぶり!のJ姐さん。
着物、帯ともに牛首紬だそう。雪のような柄の着物も、
小物使いもこなれていて、さすが大先輩!
右上は、歌舞伎やお能によくお誘いくださる

KKさん。
こちらも着物といい、帯の風情といい(確か羽織からおつくりになったとか)
冬、そして雪景色を思わせます。
右下は、集合写真には入っていませんが、
帰りがけにお会いしたRUさん。
こちらも着物は降りつむ雪のイメージ、そして帯飾りに陣太鼓!
みなさん、何と素晴らしい、ちなみもの

私も見習わないと……

-----------------------
(ここからは文楽 第二部の感想です。
今後ご覧になる予定がある方はご留意ください。筋はほとんど紹介できませんので
ご興味のある方はネット等で調べてくださいませ)

討ち入りの日記念で、眼鏡クロスが配られました。
三代目 歌川豊国による十一段目(版元は蔦屋吉蔵)。
さて、第二部は七段目「祗園一力茶屋の段」から。
登場人物が多く、太夫さんが入れ替わり立ち代わり。
途中、由良助を語る豊竹咲太夫さんと、力哉の咲寿太夫さんの
師弟が並ぶ時間があり、個人的にじーんときました。
咲太夫さんは、9月のまさかのチャリ場がとても印象的だったので
この場の由良助もさぞ、と期待していましたが、
裏切らない語り。くだけたユーモラスな場が合っているなあ、と……。

そして吉田蓑助さんの「おかる」。
2階(上の写真右端)に登場した瞬間から、“艶”な感じで、
よく考えれば酔い冷ましのシーンなので当然なのでしょうけれど、
その当然以上の、柔らかさ、女性の無防備な様子がひと目で見てとれる遣い方。
おかるだけでも感動なのに、
中盤から登場する桐竹勘十郎さんの平右衛門が圧倒的な存在感でした。
登場時のやや長い口上に合わせた動きが何とイキイキしていること!
私、この場面を10回くらいリピートして観たい!と思ったほどです。
床本では「殿様の御切腹を北国にて承りまして…いづれも様方の一味連判」
の部分です。
北国での勤めを終えてきた(おそらく北関東あたり?)キャラに
豊竹咲甫太夫さんのよく通り滑舌の良い語りが合っていたように
私は思いました。

勘十郎さん=加古川本蔵が見所、とずっと思っていましたが、
終わってみれば、私はこのときの平右衛門が一番好きだなー

場の終盤、
蓑助さんのおかる
勘十郎さんの平右衛門
吉田玉男さんの由良助 が舞台に揃って、オーラが出そうな眼福もの。
どうか一生、忘れないで記憶に残っていてほしい、とすら思いました。
おかるを語った、私の好きな豊竹呂勢太夫さんは、
節がないときは少し、甲高い感じがしましたが、
節があるときの語りはうっとりするほどなめらか。
この方の声には、油分、潤いがあって、華やぎますね。
というわけで、七段目から私はもう大感激。
今振り返っても、第二部の中で七段目が私は一番好きかな。
八段目「道行旅路の嫁入り」

こちらは踊りまではいかないのですが、義太夫に合わせた
母娘の振りで進む場面。
私は、踊りの要素があると文楽よりは歌舞伎の方が、とつい
思ってしまうのですが、
この場では特に、母娘の絡み(娘が母の懐にもたれるところなど)で
吉田和生さんが遣う母の動きが実に自然で、愛らしかったです。
この場は、どちらかといえば床に大注目。
というのも、三味線方に鶴澤清丈さん、太夫のツレに咲寿さんが
いらしたから

 なんて麗しいお姿なんでしょう!
なんて麗しいお姿なんでしょう!私、おおかたの時間、清丈さんと咲寿さんを交互に
オペラグラスで眺めていました…不謹慎でスミマセン。
咲寿さんはワンフレーズだけ一人で語ってらして
(「我が身の上をかくとだに。人しらすかの橋越えて行けば吉田や
赤坂の、招く女の声揃え」)
声はよく通るし、耳につくような癖はないし、言葉に表情もあったし、
成長なさっているなあ、と頼もしく思いました。
九段目「雪転しの段」「山科閑居の段」。

ここは、三味線が圧巻。
まずは何と言っても「雪景色に富助さんの太棹」
ちらちらと降ってくるひとひら、ひとひらに、
豊澤富助さんの哀愁ある、しかしストイックな音が重なります。
そして物語がクライマックスに向かうのを
華麗な音遣いで盛り上げる、鶴澤藤蔵さんの三味線に感動。
藤蔵さん、今まで何度かは聴いたことがあるはずなのですが、
今回すっかり惹きこまれました。
コンテンポラリーなリズム感をお持ちで、演奏が“ROCK”しているなあと。
「山科-」の段の後、藤蔵さんにとても合っている場だと思いました。

物語としては、やや滑稽というか極端というか
他人の家でいきなり母娘が自害しようとしたり、
(娘の、白無垢→死装束に黒帯、には胸が痛みました)
おもむろに、本当の母娘ではないことが明かされたり、
加古川本蔵が息絶え絶えなのに、嬉々として(?)討ち入り計画の
話に入ったり、個人的には突っ込みどころがもっとも多い段でしたが
まあそれも伝芸ならではということで。
加古川本蔵の見せ場でもあり、実際、勘十郎さんは
良かったし、物語に起伏もあったのですが、
長時間の観劇でこのあたり、さすがに疲れてきて、少し長く感じました。

十段目「天河屋の段」、十一段目「花水橋引揚の段」は
休憩後でまた気分新たに。
長持から由良助が出てくる場面が観られて満足です。
豊竹睦太夫さんはやや、語り分けが私にはわかりにくかったのですが、
いい声をなさっているな、と。

十一段目の、久々の若狭助は、馬に乗り扇子を広げているせいか
何だかとても晴れ晴れしているように見えました。
舞台を広く使って、義士が並ぶ様子は壮観でもあり、
幕切れに相応しい絵。最後は客電も点くのですね。
観客の、最後の大拍手は、
(十時間余も観た自分ってすごい!)といった、自分への拍手のようにも
感じてしまいました

来年、もし忠臣蔵がかかったら、歌舞伎の方を観てみようかな。