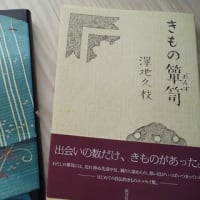もうご存知の内容かも知れませんが、
私にとっては、今年の“ちょっとした事件”(着物関係で)だったので
自分の覚書も兼ねて、記しておきます。
--------------------
今、我が家には2種類のえり芯がある。

左はよくある、薄いプラスティック製で
衣紋が自然にカーブになっているタイプ。
右は、今年に入って買った、
メッシュに近い柔らかな素材で、ご覧のとおり
やや長いタイプ。
入手したのはデパートの催事。衝動買いだった。
というのも、前々からネットでコレと同じものが
「首から浮いてこず、ぴったり沿う」と評判だったからだ。
そのヒミツは、たぶんコチラ。

長さがあるのもポイントなのだろうが、
衿の後ろ部分、衣紋を抜くエリアが低くなっていること(写真下)。
その分、芯の「上へ戻る(押し上げられる)」力が抑えられ、
程よく抜いた衿が保たれるのでは……と。
ところが。
いざ、使おうとして愕然とした。
襦袢の半衿に入らないのだ。

この写真では見難いが、
端の部分で約2.5mm、新たに買った方が太い。
たかが2.5mmといえど、私の手持ちの中では、
英(はなぶさ)さんで仕立てた襦袢と、
山本きもの工房で仕立てた襦袢は、通らないのだ。
仕方がないので
上から自分で別の半衿を重ねたときに使うか、
英さんの襦袢なら、端を10数センチ解いて、
やや無理に入れたえり芯を引っ張ると、どうにか通る。
山本さんの方は、半衿の背中心部分がえり芯よりも狭いので
別の半衿を重ねづけしない限り、どうしても通らない。
そのため私は今のところ、襦袢によってえり芯を替えるという
少々面倒なことをやっている。
「首から浮いてこない」新しい方のえり芯は、
まだ数えるほどしか使っていないけれど、
確かにぴたっとデコルテについて、前も浮かないし、
後ろもおさまりが、良いような。
常時、半衿を自分でつける人には問題なく使えますが、
そうでない人は、要注意だと思います。
このように、襦袢の半衿一つとっても、
微妙な幅のこだわりが創り手(お仕立てする人)にはあるのだなあ、と
その点にも気づかされた、一件でした。