日経新聞に長期にわたる被曝の、健康への影響についての記事が掲載されていました。
専門家の結論としては、分からないということみたいです。
分からないからこそ不安になります。
日経新聞から
福島第一原発事故による放射能の健康への影響を巡る公開討論会が6月22日、国立がん研究センター(東京都・中央区)で開かれた。
今回のように低い放射線量を長期に浴び続けた場合は「データがなく、健康への影響は明確ではない」との意見が大半で、多くの専門家が「住民一人ひとりに長期間の調査が必要」と訴えた。
放射線によるがんのリスクについて、北海道がんセンターの西尾正道院長は「国際放射線防御委員会(ICRP)の勧告をもとに考えると、年間1.001倍」と説明。「放射線に安全な量はない」として調査も不可欠との認識を示した。
ICRP委員でもある大分県立看護学科大の甲斐倫明教授も、国が参考にするICRPの基準は「『そこまでなら浴びてよい』という数値ではない」と強調。
「信頼できるデータは多くないが、(同じ放射線量)外部被曝より内部被曝の方が健康へのリスクが高いという証拠はない」と話した。
国立がん研究センター津金昌一郎予防研究部長は「たばこや自然界の放射能など様々な要因も考慮すべきだ」と指摘。
同センターの嘉山孝正理事長は「どこまでが分かることで、どこまでが分からないことなのかを把握してほしい」と述べた。
専門家の結論としては、分からないということみたいです。
分からないからこそ不安になります。
日経新聞から
福島第一原発事故による放射能の健康への影響を巡る公開討論会が6月22日、国立がん研究センター(東京都・中央区)で開かれた。
今回のように低い放射線量を長期に浴び続けた場合は「データがなく、健康への影響は明確ではない」との意見が大半で、多くの専門家が「住民一人ひとりに長期間の調査が必要」と訴えた。
放射線によるがんのリスクについて、北海道がんセンターの西尾正道院長は「国際放射線防御委員会(ICRP)の勧告をもとに考えると、年間1.001倍」と説明。「放射線に安全な量はない」として調査も不可欠との認識を示した。
ICRP委員でもある大分県立看護学科大の甲斐倫明教授も、国が参考にするICRPの基準は「『そこまでなら浴びてよい』という数値ではない」と強調。
「信頼できるデータは多くないが、(同じ放射線量)外部被曝より内部被曝の方が健康へのリスクが高いという証拠はない」と話した。
国立がん研究センター津金昌一郎予防研究部長は「たばこや自然界の放射能など様々な要因も考慮すべきだ」と指摘。
同センターの嘉山孝正理事長は「どこまでが分かることで、どこまでが分からないことなのかを把握してほしい」と述べた。

















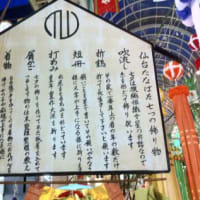





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます