2010年1月24日(日) 参加した中国「上海と江南4都市巡りの旅」 3日目の今朝、中国蘇州市内にあるホテルを専用バスで出発する。
同じ蘇州市内にある天下の名園 「留園」 を見学した後、近くにある蘭莉園刺繍研究所に向かった。
直ぐに蘭莉園刺繍研究所に到着する。
研究所は大きな塀に囲まれ、入口には大きな門があり、両側にある獅子の石像が私達を迎えてくれている。
この建物には、刺繍研究所とレストランが併用されている。

蘇州にある蘭莉園刺繍研究所の入口
入口から刺繍研究所に向かって進んで行くと、奇麗な池のある庭園や芝の庭なども整備され、私たちの目を楽しませてくれる。

蘭莉園刺繍研究所内の庭園で、妻と日本語の話せるガイド実習生の女性との記念撮影。
蘭莉園刺繍研究所内は、中国最大規模の刺繍研究所で、伝統工芸の特色ある作業場展示ホールがあり、変化に富み、色々な刺繍を見学することが出来る。
展示場には、多数の製品や、実際の作品が女性の手によって刺繍されている。
非常に極め細かい作業の連続で、一つの作品を描くのに、数十日から数カ月、数年の年月を必要とし、そうして出来た作品が多く展示されている
入口近くには、イギリスのダイアナ王妃の鮮やかな姿で刺繍された作品があった。最初は写真かな! と見えるほどで、とても刺繍した作品とは思えなかった。
展示作品の多くは、動物や花、日本の富士山など、景勝地の作品が展示されている。
特筆すべき作品の中で、特に両面刺繍の作品には驚かされる。
販売価格も数千円から数十万円、数百万円までの価格が付けられている。
私には、作品の価値は分からないが、一つの作品を作るのに多くの時間と根気、永年の熟練した技術を必要としている。
刺繍作品の鮮やかな色の美しさは抜群で印象深かった。

寒山寺の入り口へ向かうツアー一行
蘭莉園刺繍研究所の見学を終えた私達ツアー一行は、駐車場に戻り、同じ蘇州市内にある日本でもお馴染みの寒山寺に専用バスで向かって行った。
寒山寺には20分ほどで到着する。
高々とした五重の塔が聳え建ち、その周りを高くて黄色い塀が取囲んでいる。
この塀に沿って造られた広い参道を、現地ガイドのカクサンと、二人の若い女性に案内されながら進んで行く。
世界遺産に指定されている寒山寺は、500年代の初頭、妙利普明塔院という名で創建されたものであるが、幾度も焼失、現存する建物は清代末(1911年)に再建されたものである。
唐代貞観年間(627~649年)に、「寒山」と「拾得」という僧が、ここで修行したことから「寒山寺」と呼ばれるようになったと伝えられている。


参道からの寒山寺五重の塔「普明宝塔」 普明宝塔と塔の上にある法輪、日本とは少し形が違っている。
この普明宝塔は1995年12月に建てられた高さ52mの木造の塔で、唐の楼閣式仏塔を模して造られたものである。

多くの船が行き交う寒山寺前にある京杭大運河
寒山寺は隋の時代(518年~616年)に築かれた南北を結ぶ大運河(京杭大運河=北京~杭州まで1800km)沿いにあり、唐の時代(618年~907年)に「張継=ちょうけい」が科挙(かきょ=官史登用試験)に落ちて、寂しい気持ちでこの運河を通り、故郷に帰る途中、この付近で船中泊していた、その際に寒山寺の鐘の音を聞いて、詩にして詠んだものが 「楓橋夜箔=ふうきょうやはく」 である。
この詩が各地に知れわたり、寒山寺も一躍有名な寺になっていった。

入り口近くにあり、手前では参拝前の香を焚く人たちが絶えなかった寒山寺の大殿
寒山寺は、8世紀中頃、中唐の詩人で政治家でもあった「張継=ちょうけい」が有名な七言絶句 「楓橋夜泊=ふうきょうやはく」を発表し、世に広く知られるようになった。
この詩(①~④)は、都落ちした旅人張継が、蘇州西郊で寒山寺の側にある、楓江に架けられた楓橋の辺りで船中に泊まった際、旅愁のために眠れぬまま、寒山寺の鐘の音を聞いていた時の様子を詠ったものである。
①月落烏啼霜満天、 月落ち烏(からす)啼(な)きて霜 天に満(み)つ
月は西に落ちて闇のなかにカラスの鳴く声が聞こえ、厳しい霜の気配は天いっぱいに満ちている。


①月落鳥啼霜満天の碑 この寺にゆかりの深い寒山と拾得の像
②江楓漁火対愁眠 江楓(こうふう)漁火(ぎょか)愁眠に対す。
運河沿いに繁る楓と点々と灯る川のいさり火の光が、旅の愁いの浅い眠りにチラチラかすめる。
③姑蘇城外寒山寺 姑蘇(こそ)城外の寒山寺。
そのとき姑蘇の町はずれの寒山寺から、
④夜半鐘聲到客船 夜半の鐘声(しょうせい)客船(かくせん)に到る。
夜半を知らせる鐘の音が、私の乗る船にまで聞こえてきた。
漢詩をされる日本の方が、よく読まれている選集に『唐詩選』と『三体詩』がある、「楓橋夜泊」は、両方の漢詩選集に収載されている数少ない詩のひとつで、中国人はもとより、日本人にも、古くから馴染み深い詩となっている。
この詩が、広く人びとから愛好され、多くの人達に知られるようになってから、歴代の詩人や文学・美術などを志している人々が、次々に寒山寺を訪れて創作活動を行い、多くの作品を残しているといわれている。
「寒山」と「拾得」は、共に唐代の脱俗的な人物で、両者とも在世年代は不詳である。
非僧非俗の風狂の徒であったようであるが、仏教の哲理には二人とも深く通じていたようである。
詩作を良くし、ことに寒山は「寒山子詩」と呼ばれる多数の詩を残している。
寒山は文殊菩薩、拾得は普賢菩薩の再来と呼ばれることもあり、師の高僧は、釈迦如来に見立て、合わせて「三聖」あるいは「三隠」と称されている。


蘇州の除夜の鐘で日本でも有名な二階建ての鐘楼 鐘楼を訪れた観光客の撮影スポットにもなっている聴鐘石
日本では近年、寒山寺といえば 「除夜の鐘」で有名である。
年末になると多くの日本人が 「除夜の鐘ツアー」で、ここを訪れている。
日本での除夜の鐘は、一年最後の日である大晦日の夜を締めくくり、暮行く年を惜しむ意味と、それに即した色々な行事が行われ、その中に、新しい年を迎えるにあたり、日本各地の寺で108回撞かれている。
108回も撞かれる意味には、色々な説があるが、一般的には、人間の煩悩(感覚を司る六根=眼・耳・鼻・舌・身・意)に起因するもが108あるとされている。
中国では、寒山寺の鐘の音を聴くと、10歳 若返るといわれており、今日では、寒山寺の鐘を 「誰が撞き手の一番手に選ばれるか!」
大きな話題になっており、毎年、せりにかけて決める行事が行われ、大変盛り上がってている様子が伝えられている。
寒山寺の除夜の鐘を聴きながら新年を迎える行事は、1979年、藤尾昭という日本の方が発起人となって始められ、現在では日本だけでなく、韓国をはじめとする各国の観光客や、中国の人々も大勢参加するようになって、賑わっているようである。
また、寒山寺には、長安で修行した弘法大師空海も立ち寄り、2年間過ごしたと伝えられている。
弘法大師空海は、今から1200年ほど前の31歳の時に、真言密教を求めて遣唐使に応募し、4隻の遣唐使船団で、難波津(現大阪市)を出航している。
4隻の船団は、途中で台風に遭遇し、2隻が行方不明になっている。
幸いにして大使と弘法大師空海を乗せた船は、福建省に無事に漂着している。
その後、弘法大師空海は、そこから2400km離れた中国内部にある唐の都「長安」の青龍寺に行って修行、32歳の時に恵果和尚から真言密教を学び、相承した帰り道、寒山寺に立ち寄り修行する。
その後、日本に帰国、仏教伝来に大きな功績を残している。


長安からの帰りに立寄って修行した弘法大師の像 日本での仏教に大きな影響を与えた鑑真像
寒山寺には、弘法堂があり、当時、修行された弘法大師空海の像、日本に来日し、仏教伝来に努めた鑑真和上の像や、玄弉三蔵の像が安置されている。

大雄宝殿の中にある釈迦如来像

寒山寺五重の塔にある仏像

寒山寺五重の塔上部階からの景観

五重の塔からの寒山寺境内にある伽藍の景観、多くの人たちが訪れている。

五重塔からの景観、境内にある伽藍の屋根が続く、遠くには蘇州市内の高層住宅団地が見えている。
日本でもお馴染みの寒山寺であるが、私にとっては全く予備知識のない寺である。
しかし、寒山寺を見学していて、古くから日本との関わりの深さに驚かされる。
当時の中国は文化水準の高い先進国で、日本は未開の国であったことが容易に察せられる。
中国の歴史的な文化を観て、日本文化の経緯や流れが、一層理解しやすく、中国が身近になったように感じる。
何気なく申し込んだ今回のツアー旅行、日本国内での私たちの気ままな旅のような、自由奔放とした旅スタイルはとれないが、旅の楽しさを一層、色濃いくしてくれているようである。
ただ、日本に帰り、デジカメで撮影した旅行写真を、パソコンに取り込み中に、カメラがバッテリー切れをおこし、撮影したカード枚数700枚の内、190枚を消失させる大失敗をしてしまった。
消失した190枚は、この寒山寺で撮影したもので、本稿で使用している画像は、全て、妻が別のカメラで撮影したものである。
この件で、カメラの購入先やメーカー(ニコン)に問い合わせをするが、一旦、消えた画像を取り戻すのは難しそうで、諦めざるを得なかった。
こんなことは初めてで、今回の反省として、今後はデジカメから撮影画像を、パソコンに直接移すのではなく、新たに購入した、カードから直接パソコン移せる「カードリ-ダー」という、バッテリ切れの心配のないソフト機器で行うことにした。
今回は、特に大容量のカードに多量の撮影枚数を残し、パソコンに取り込むのは、時間もかかり、バッテリーの消耗が大きく、バッテリー切れの心配がある。
せっかく撮影した貴重なデータが、簡単に消えるデジカメの怖さと、カメラからパソコンに移す折の注意点を、痛切に学ばしてもらった。
同じ蘇州市内にある天下の名園 「留園」 を見学した後、近くにある蘭莉園刺繍研究所に向かった。
直ぐに蘭莉園刺繍研究所に到着する。
研究所は大きな塀に囲まれ、入口には大きな門があり、両側にある獅子の石像が私達を迎えてくれている。
この建物には、刺繍研究所とレストランが併用されている。

蘇州にある蘭莉園刺繍研究所の入口
入口から刺繍研究所に向かって進んで行くと、奇麗な池のある庭園や芝の庭なども整備され、私たちの目を楽しませてくれる。

蘭莉園刺繍研究所内の庭園で、妻と日本語の話せるガイド実習生の女性との記念撮影。
蘭莉園刺繍研究所内は、中国最大規模の刺繍研究所で、伝統工芸の特色ある作業場展示ホールがあり、変化に富み、色々な刺繍を見学することが出来る。
展示場には、多数の製品や、実際の作品が女性の手によって刺繍されている。
非常に極め細かい作業の連続で、一つの作品を描くのに、数十日から数カ月、数年の年月を必要とし、そうして出来た作品が多く展示されている
入口近くには、イギリスのダイアナ王妃の鮮やかな姿で刺繍された作品があった。最初は写真かな! と見えるほどで、とても刺繍した作品とは思えなかった。
展示作品の多くは、動物や花、日本の富士山など、景勝地の作品が展示されている。
特筆すべき作品の中で、特に両面刺繍の作品には驚かされる。
販売価格も数千円から数十万円、数百万円までの価格が付けられている。
私には、作品の価値は分からないが、一つの作品を作るのに多くの時間と根気、永年の熟練した技術を必要としている。
刺繍作品の鮮やかな色の美しさは抜群で印象深かった。

寒山寺の入り口へ向かうツアー一行
蘭莉園刺繍研究所の見学を終えた私達ツアー一行は、駐車場に戻り、同じ蘇州市内にある日本でもお馴染みの寒山寺に専用バスで向かって行った。
寒山寺には20分ほどで到着する。
高々とした五重の塔が聳え建ち、その周りを高くて黄色い塀が取囲んでいる。
この塀に沿って造られた広い参道を、現地ガイドのカクサンと、二人の若い女性に案内されながら進んで行く。
世界遺産に指定されている寒山寺は、500年代の初頭、妙利普明塔院という名で創建されたものであるが、幾度も焼失、現存する建物は清代末(1911年)に再建されたものである。
唐代貞観年間(627~649年)に、「寒山」と「拾得」という僧が、ここで修行したことから「寒山寺」と呼ばれるようになったと伝えられている。


参道からの寒山寺五重の塔「普明宝塔」 普明宝塔と塔の上にある法輪、日本とは少し形が違っている。
この普明宝塔は1995年12月に建てられた高さ52mの木造の塔で、唐の楼閣式仏塔を模して造られたものである。

多くの船が行き交う寒山寺前にある京杭大運河
寒山寺は隋の時代(518年~616年)に築かれた南北を結ぶ大運河(京杭大運河=北京~杭州まで1800km)沿いにあり、唐の時代(618年~907年)に「張継=ちょうけい」が科挙(かきょ=官史登用試験)に落ちて、寂しい気持ちでこの運河を通り、故郷に帰る途中、この付近で船中泊していた、その際に寒山寺の鐘の音を聞いて、詩にして詠んだものが 「楓橋夜箔=ふうきょうやはく」 である。
この詩が各地に知れわたり、寒山寺も一躍有名な寺になっていった。

入り口近くにあり、手前では参拝前の香を焚く人たちが絶えなかった寒山寺の大殿
寒山寺は、8世紀中頃、中唐の詩人で政治家でもあった「張継=ちょうけい」が有名な七言絶句 「楓橋夜泊=ふうきょうやはく」を発表し、世に広く知られるようになった。
この詩(①~④)は、都落ちした旅人張継が、蘇州西郊で寒山寺の側にある、楓江に架けられた楓橋の辺りで船中に泊まった際、旅愁のために眠れぬまま、寒山寺の鐘の音を聞いていた時の様子を詠ったものである。
①月落烏啼霜満天、 月落ち烏(からす)啼(な)きて霜 天に満(み)つ
月は西に落ちて闇のなかにカラスの鳴く声が聞こえ、厳しい霜の気配は天いっぱいに満ちている。


①月落鳥啼霜満天の碑 この寺にゆかりの深い寒山と拾得の像
②江楓漁火対愁眠 江楓(こうふう)漁火(ぎょか)愁眠に対す。
運河沿いに繁る楓と点々と灯る川のいさり火の光が、旅の愁いの浅い眠りにチラチラかすめる。
③姑蘇城外寒山寺 姑蘇(こそ)城外の寒山寺。
そのとき姑蘇の町はずれの寒山寺から、
④夜半鐘聲到客船 夜半の鐘声(しょうせい)客船(かくせん)に到る。
夜半を知らせる鐘の音が、私の乗る船にまで聞こえてきた。
漢詩をされる日本の方が、よく読まれている選集に『唐詩選』と『三体詩』がある、「楓橋夜泊」は、両方の漢詩選集に収載されている数少ない詩のひとつで、中国人はもとより、日本人にも、古くから馴染み深い詩となっている。
この詩が、広く人びとから愛好され、多くの人達に知られるようになってから、歴代の詩人や文学・美術などを志している人々が、次々に寒山寺を訪れて創作活動を行い、多くの作品を残しているといわれている。
「寒山」と「拾得」は、共に唐代の脱俗的な人物で、両者とも在世年代は不詳である。
非僧非俗の風狂の徒であったようであるが、仏教の哲理には二人とも深く通じていたようである。
詩作を良くし、ことに寒山は「寒山子詩」と呼ばれる多数の詩を残している。
寒山は文殊菩薩、拾得は普賢菩薩の再来と呼ばれることもあり、師の高僧は、釈迦如来に見立て、合わせて「三聖」あるいは「三隠」と称されている。


蘇州の除夜の鐘で日本でも有名な二階建ての鐘楼 鐘楼を訪れた観光客の撮影スポットにもなっている聴鐘石
日本では近年、寒山寺といえば 「除夜の鐘」で有名である。
年末になると多くの日本人が 「除夜の鐘ツアー」で、ここを訪れている。
日本での除夜の鐘は、一年最後の日である大晦日の夜を締めくくり、暮行く年を惜しむ意味と、それに即した色々な行事が行われ、その中に、新しい年を迎えるにあたり、日本各地の寺で108回撞かれている。
108回も撞かれる意味には、色々な説があるが、一般的には、人間の煩悩(感覚を司る六根=眼・耳・鼻・舌・身・意)に起因するもが108あるとされている。
中国では、寒山寺の鐘の音を聴くと、10歳 若返るといわれており、今日では、寒山寺の鐘を 「誰が撞き手の一番手に選ばれるか!」
大きな話題になっており、毎年、せりにかけて決める行事が行われ、大変盛り上がってている様子が伝えられている。
寒山寺の除夜の鐘を聴きながら新年を迎える行事は、1979年、藤尾昭という日本の方が発起人となって始められ、現在では日本だけでなく、韓国をはじめとする各国の観光客や、中国の人々も大勢参加するようになって、賑わっているようである。
また、寒山寺には、長安で修行した弘法大師空海も立ち寄り、2年間過ごしたと伝えられている。
弘法大師空海は、今から1200年ほど前の31歳の時に、真言密教を求めて遣唐使に応募し、4隻の遣唐使船団で、難波津(現大阪市)を出航している。
4隻の船団は、途中で台風に遭遇し、2隻が行方不明になっている。
幸いにして大使と弘法大師空海を乗せた船は、福建省に無事に漂着している。
その後、弘法大師空海は、そこから2400km離れた中国内部にある唐の都「長安」の青龍寺に行って修行、32歳の時に恵果和尚から真言密教を学び、相承した帰り道、寒山寺に立ち寄り修行する。
その後、日本に帰国、仏教伝来に大きな功績を残している。


長安からの帰りに立寄って修行した弘法大師の像 日本での仏教に大きな影響を与えた鑑真像
寒山寺には、弘法堂があり、当時、修行された弘法大師空海の像、日本に来日し、仏教伝来に努めた鑑真和上の像や、玄弉三蔵の像が安置されている。

大雄宝殿の中にある釈迦如来像

寒山寺五重の塔にある仏像

寒山寺五重の塔上部階からの景観

五重の塔からの寒山寺境内にある伽藍の景観、多くの人たちが訪れている。

五重塔からの景観、境内にある伽藍の屋根が続く、遠くには蘇州市内の高層住宅団地が見えている。
日本でもお馴染みの寒山寺であるが、私にとっては全く予備知識のない寺である。
しかし、寒山寺を見学していて、古くから日本との関わりの深さに驚かされる。
当時の中国は文化水準の高い先進国で、日本は未開の国であったことが容易に察せられる。
中国の歴史的な文化を観て、日本文化の経緯や流れが、一層理解しやすく、中国が身近になったように感じる。
何気なく申し込んだ今回のツアー旅行、日本国内での私たちの気ままな旅のような、自由奔放とした旅スタイルはとれないが、旅の楽しさを一層、色濃いくしてくれているようである。
ただ、日本に帰り、デジカメで撮影した旅行写真を、パソコンに取り込み中に、カメラがバッテリー切れをおこし、撮影したカード枚数700枚の内、190枚を消失させる大失敗をしてしまった。
消失した190枚は、この寒山寺で撮影したもので、本稿で使用している画像は、全て、妻が別のカメラで撮影したものである。
この件で、カメラの購入先やメーカー(ニコン)に問い合わせをするが、一旦、消えた画像を取り戻すのは難しそうで、諦めざるを得なかった。
こんなことは初めてで、今回の反省として、今後はデジカメから撮影画像を、パソコンに直接移すのではなく、新たに購入した、カードから直接パソコン移せる「カードリ-ダー」という、バッテリ切れの心配のないソフト機器で行うことにした。
今回は、特に大容量のカードに多量の撮影枚数を残し、パソコンに取り込むのは、時間もかかり、バッテリーの消耗が大きく、バッテリー切れの心配がある。
せっかく撮影した貴重なデータが、簡単に消えるデジカメの怖さと、カメラからパソコンに移す折の注意点を、痛切に学ばしてもらった。











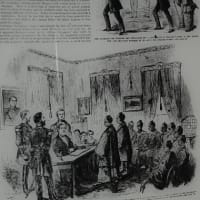
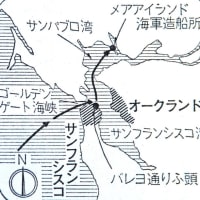






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます