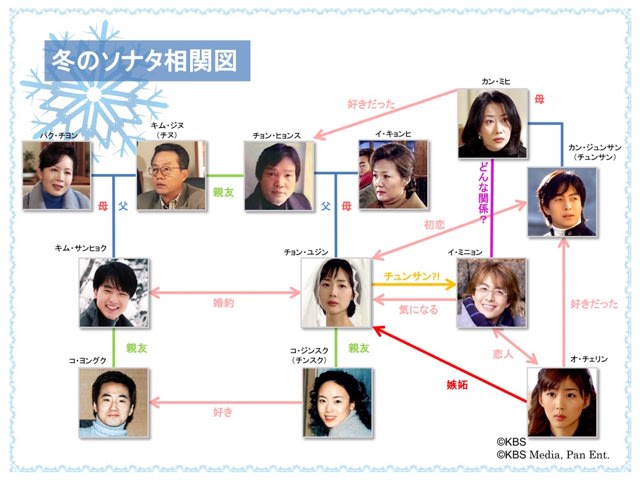
チュンサンが消えた次の朝、ソウルに戻ったユジンは、アパートのリビングでソファに座って一人ぼんやりとしていた。今は何も考えられないし、全てが信じられなかった。昨日まで二人はあんなに幸せだったのに、チュンサンは煙のように消えてしまった。そういえば、東海に行く少し前から、チュンサンはどことなく変だったけれども、それがなぜなのかユジンにはどうしてもわからなかった。きっと何か理由はあるはずだ、そんなはずはない、ユジンはどうしてもそれが知りたかった。すると誰かが訪ねてきてインターフォンを鳴らした。ユジンは急いで玄関に走ったが、立っていたのは、あろうことかサンヒョクの母親のチヨンだった。チヨンは般若のように険しい顔でユジンを見つめている。ユジンはびっくりした。チヨンが何のために来たのか全く分からなかったからだ。チヨンは椅子に座った後も、ユジンを厳しい目で見つめた。

「お義母さま、お茶をどうぞ。」
「ユジン、私はもうお義母さまではないわ」
「申し訳ありません」

すると、チヨンはふっと優しい顔になった。しかしその目はどこまでも冷たくて、ユジンを蹂躙しようとしているように感じた。
「謝らなくていいのよ。過去のことは水に流すから。でもね、今でもどうしてサンヒョクと会っているのかしら?」
「おかあさま」
「あなたにとって何?困ったことがあった時だけ呼んで、あとは知らん顔なの?」
ユジンはつらくてたまらずにうつむいてしまった。すべてサンヒョクが話したのだろうか。頭の中が混乱し始めた。
「あなた、スキー場の人と別れたんですってね。私も事情を聞いて驚いたわ。でもね、あなたとサンヒョクはもう終わったの。あなたとあの人が兄妹だとしても、サンヒョクに乗り換えるのはやめてちょうだい。」

すると今まで俯いていたユジンが急に顔色を変えて言った。
「おかあさま、いったい何の話をしているんです?」
「だから、あなたと彼が兄妹だって話をしてるの。私だって、それを聞いて驚いたわよ。でも、恨むなら自分の父親を恨んでちょうだい。サンヒョクに関係ないことでしょ。」
「おかあさま、何を言ってるんですか?チュンサンと私が何ですって?もう一度言ってもらえますか?」

今度はチヨンが驚く番だった。目の前にいるユジンの目は潤みはじめており、顔にはショックの色がありありと浮かんでいた。顔色は真っ蒼になり、唇はわなないている。
「あなた、知らなかったの?」
「お母様、教えてください。今なんておっしゃったんですか?」

チヨンは痛恨のミスを犯したことに気が付いて唇をかんだ。こんなはずではなかったのに。知らないなんてことがあるの?しかし、ここまで来たらもう引き返せない。チヨンは意を決して話をつづけた。
「サンヒョクから聞いたの。チュンサンとあなたが兄妹だって。てっきりあなたも知っていると思ったのだけれど、、、、。」

それを聞いたとたん、ユジンは泣きながらコートを着ると、荷物をつかんで外に出て行ってしまった。玄関のドアを閉めた瞬間に、チヨンが
「ごめんなさいね。あなたが知らないなんて聞いてなくて。ちょっと、どこ行くの?一人で置いていかないで」
と叫ぶのも構わずに。頭の中はチュンサンのことでいっぱいだった。今すぐチュンサンに会って真実を確かめなければ、そんなはずはないという思いでいっぱいだった。でも、認めたくないけれども、それが事実だとすれば、今までのチュンサンの不可解な行動にすべて説明が付く。あんなに愛してくれたのに、それ以外の理由でチュンサンが離れていくはずがないとも思っていた。ユジンはタクシーの中で、身体が震えるのを止めることができなかった。怖くて怖くてたまらない。こんなに怖いのは、チュンサンが死んだと聞かされたあの日以来だった。自分は真実を受け止めることができるのだろうか。ユジンはタクシーの中でずっと祈り続けた。「どうか私たちが兄妹でありませんように」と。























