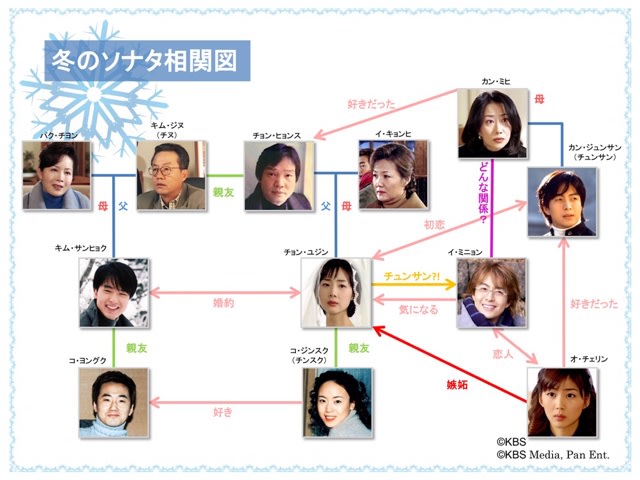
「母さん、違うんだよ。僕はユジンを愛していると思っていた。でも、それは愛じゃなくて執着だったんだ、、、。ほかの男に渡したくなくて執着してたんだ。いつも疑って傷つけて、でももう疲れてしまった、、、。ユジンも僕も苦しむからもうやめにするよ。ごめんなさい。」

チヨンはもうみんなに招待状を出してしまったとか、今更恥が外聞が、と言っていたが、サンヒョクは気にしなかった。静かに聞いていた父親のジヌも、サンヒョクの様子から、今回の決断は心からのものであると気が付いて、尊重することにした。そして静かに妻をなだめるのだった。
サンヒョクは自室にこもって泣いた。電気もつけずに一晩中泣いた。心を整理するためには、一人で涙を流すのが必要であった。

そのころ、ユジンとミニョンはサンヒョクの心も知らずに、住宅雑誌を見て、ミニョンの新居を探していた。すると、ミニョンは心配そうにユジンに言った。
「ねえユジン。ずっとここにいて平気なのか?」
「今日サンヒョクに会ったの、、、。大丈夫よ。」
そう言うとユジンはミニョンをじっと見つめた。その純粋であどけない瞳を見ていると、
それだけ聞けば十分だった。ユジンがサンヒョクと別れてきたことは明白だった。ミニョンは
「ユジン、ごめんな」とつぶやいた。ミニョンを見つめるユジンの瞳は、少女のように無垢であどけなかった。自分の全てを信頼して預けているその眼差しを前に、ミニョンはあらためてユジンを守らなければ、と心に誓うのであった。

その時、母親のミヒが駆け付けた。ミニョンの意識が戻ったあと、やっと来ることができたのだ。
「チュンサン」
ミヒは10年ぶりにミニョンをそう呼んだ。ミニョンが
「はい。お母さん」とうなずくのを見て、ミヒはミニョンをしっかりと抱きしめるのだった。

そんなミヒを見て、ミニョンは質問をした。
「母さん、僕の父親はだれ?父親を与えたかったんでしょう?僕はチュンサンだった時も父親が誰か知らなかったの?」
ミヒは顔をこわばらせたが、すぐに穏やかな表情になって言った。
「いいえ、教えなかったわ。気になるのね。やっぱり父親のことを聞くなんて、あなたはチュンサンなのね。ミニョンじゃないのね。」
ミヒはとたんに寂しそうな顔つきになった。
「僕はこうやって母さんを傷つけていたんだね。もう聞かないよ。ごめんね。」

「わかったわ。母さんはね、昔とても愛していた人がいたの。今まで一度だって忘れたことがないの。信じられる?でも、その人は私を捨てた。そして私のことなんか忘れて死んでしまったの。その人が私を忘れて幸せに暮らしていることが、そうしても許せなくて憎らしかった。そのことは今でも傷ついていて、胸が苦しいの。あなたがいてくれて、あなたのことだけ考えて生きてきたから耐えられた人生だった。だから、もう誰が父親なのかは、私にとっては重要じゃないのよ。あなたは私の息子で、あなたさえいればそれで十分なの。」
そういって目を潤ませるミヒを前に、ミニョンは何も言えなくなってしまった。それでも僕は自分の父親が誰か知りたいんですとは。

次の日の夜、ユジンの母のギョンヒは、夫のヒョンスの写真たてを手に話しかけていた。
「あなた、サンヒョクが電話をくれました。ユジンと別れるんですって。愛する人のもとに行かせるからって。ユジンはそれでよいかもしれないけど、サンヒョクのことを思うと、胸が痛むわ。」

しかし、まじめな顔をしてこちらを見つめるヒョンスの写真は、何も言わなかった。ギョンヒはサンヒョクのために、こみ上げてくる涙を抑えることができなかった。

それからしばらくは時は静かに流れた。ミニョンのことで失恋の涙を流したチェリンは、仕事に一途になってブティックの経営に精進した。もっとも、前にもましてイライラして気が強くなったチェリンに、チンスクはじめとする従業員はびくびくする毎日ではあったが。サンヒョクは相変わらずラジオの仕事をしていた。仕事は順調だったが、深酒とヘビースモーカーになってしまって、一緒に働くユヨルに注意される始末だった。ヨングクは、一人前の獣医として日夜問わず、動物たちの病気を治す日々だった。そんなある日、ついにミニョンが退院することになった。ミニョンとユジンはしっかりと手をつないで、病院の皆にお礼を言って車に乗り込んだ。





















