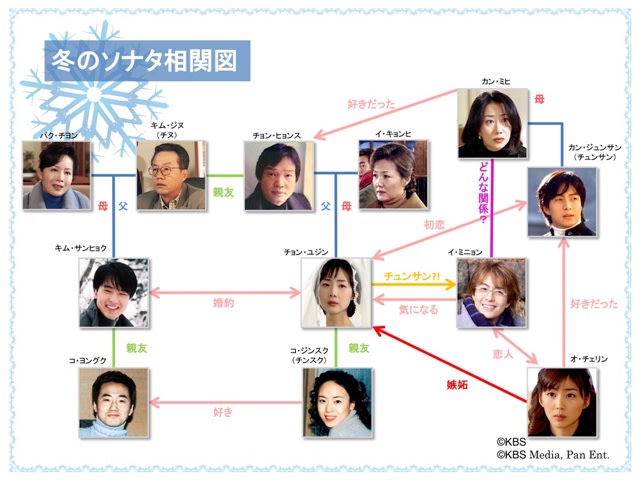
「チュンサン、急に呼び出して何よ?」
ミニョンは水色と青色のマフラーをクロスしてコートの上から巻いていた。その鮮やかな色彩と、ミニョンの柔らかな笑顔がマッチしていて、ユジンにはまぶしかった。するとミニョンは嬉しそうに言った。
「今から僕を手伝ってほしいんだ。君の記憶を貸してほしい。一緒に春川に行って、僕らが何をして何を話したのか教えてくれるかな。そうしたらいろいろと思い出せそうな気がする。早く昔のことを思い出したいなぁ。」
ユジンはきっとミニョンが昨夜の出来事を気にしているのだと思って気にしないでと言いたかった。しかし敢えて言葉を飲み込んで、素直についていくことにした。ミニョンは「行こう」と優しくいって、ユジンの手を握りしめて歩き始めるのだった。


ミニョンの提案で、二人は昔のようにバスに乗って春川に向かった。もちろんバスの席は昔と同じ一番後ろの右側の席。ユジンがミニョンの手を引っ張りいざなった。この日は冬にしてはとても暖かく、木漏れ日がキラキラと窓から降り注いだ。暖かい空気に誘われて、ユジンは高校生の頃のように、ミニョンの肩にもたれてすやすやと眠り始めた。するとミニョンは、そっと頭を向こうに押しやった。ユジンの頭はバスの揺れの反動で向こう側に大きく傾き、バスの窓枠にこつんとぶつかった。ユジンは不機嫌そうな顔で目を見開き、口をとがらせて「もうっ、いじわるね」とミニョンをにらみつけた。その顔が懐かしくてかわいくて、ミニョンはつい笑ってしまった。遠い昔、やっぱり僕らはこんな風に会話をして、二人で顔を見合わせた気がする。覚えていなくても、ミニョンの心は温かくなっていった。



ユジンは昔のように、そっと窓を開けて、新鮮な空気を吸った。冬の冷たい空気が二人のほほを撫でた。ユジンの髪の毛からはスミレの香りがして、ミニョンは思わず目を細めながらそっと顔を近づけて、胸いっぱいに香りを吸い込んだ。そんなミニョンの顔を、ユジンがまぶしそうに優しく見つめていた。こんな日が再び来るなんて思わなかった、ユジンは喜びで心が満たされていった。
「私たち、昔もこんなふうにこの席に座っていたのよ」
二人は穏やかに見つめあいながら、バスの旅を楽しんでいた。


やがてバスは、チュンサンの転校初日に、二人で乗り過ごしてしまったバス停に止まった。二人はそこからやはり昔のようにタクシーで高校まで向い、遅刻した時に二人で乗り越えた高校の裏の塀の前にやってきた。ユジンはその間、つ一つの思い出を語ってくれた。その楽しそうな表情を見ていると、ユジンがチュンサンとの思い出をどれだけ大切に胸にしまっていたのかがわかって、胸が熱くなるミニョンだった。ユジン悪戯っぽい目つきで言った。
「ここであなたが馬になって、わたしが乗って塀に登ったのよ。」
ミニョンは笑いながら馬になった。ユジンがよいしょっとミニョンの上にのると、下から「高校の時もこんなに重かったのか?」とミニョンが笑った。ユジンは軽く聞き流して「ちょっと、チュンサン、もっと持ち上げてよ」とミニョンをせかすのだった。ユジンが塀の上に上ると、ミニョンはユジンの説明通り、昔のように靴を履かせてくれた。そして怖がるユジンをジャンプさせて、しっかりと抱きとめてくれた。何もかもが昔と同じだ。「チョンユジン、本当は重いんだな」と楽しそうに笑うミニョンを見て、ユジンは記憶が戻らなくても、二人で思い出めぐりができて、うれしく感じていた。


それから、ふたりはいよいよ南怡島に出かけた。フェリーから見る景色は少しも変わらない。ユジンはミニョンの顔をそっと覗き込んだ。そして南怡島につくと、ミニョンはサドルとペダルが二つずつ付いている二人乗りの自転車を借りた。ユジンは、高校生の時に夕暮れの中自転車の後ろ座席に乗ったことを思い出した。その時つかまったチュンサンの厚い背中や広い肩幅、かすかに香るタバコのにおいや、黄金色に輝いたススキの波を思い出して感慨に浸っていた。


そのあと、二人がぶらぶら歩いていると、バレーのコートが見えてきた。ユジンは初雪の日に、ここで雪玉を使ってバレーボールをしたことを思い出した。ミニョンが珍しそうにコートの周りを見ていると、コートの向こう側からユジンがバレーのまねごとをしている姿が見えた。
「チュンサン、行くよ。それっ」
ユジンは見えないボールをサーブしたらしい。その顔は面白くなるほど真剣だった。ミニョンがぽかんとした顔でユジンを見ると、ユジンが叫んだ。
「ちょっとチュンサン、何やってるの?後ろにボールが落ちちゃったじゃない。」
すると、ミニョンもその気になって叫んだ。
「わかった。思い出すまで真剣勝負しよう。いくよ。」


それから二人はしばらくの間、人目もはばからずにエアバレーに熱中していた。ユジンの目には照れながら雪の中をスライディングしてエアボールをとる高校生の姿が見えた。ミニョンの目には、頬をバラ色に染めて、チュンサンに反則を言い渡す審判のポーズをしている高校生のユジンの姿が見えた。二人は久しぶりに童心に戻って大笑いしてコートを後にした。

疲れてしまった二人は、ユジンとチュンサンが高校時代に雪だるまを作ってキスをしたベンチに座った。日は少しづつ落ち始めて、夕日が湖面を照らしてあたりは黄金色に染まり始めた。何も思い出せないミニョンは
「ここで僕たちは何をしたの?」と問いかけた。
「当ててみて。何をしたと思う?」
「うーん。お弁当を食べた?」
「違う」
「うーん、うーん、わからないな。何をしたの?」
「二人でひとつずつ、小さな雪だるまを作ったのよ。」
「なるほど、チュンサンとユジンてわけか。」
「うん、それでね、チュンサンが雪だるま同士をキスさせたの。」
「キス?それじゃあ、僕たちもここでキスしたの?」
するとユジンはもじもじと下を向いてしまった。
「さてはほんとにしたんだな。どうやって?」
しかしユジンは恥ずかしそうにうつむいたまま返事をしなかった。ミニョンはユジンの腕をつかんでこちらを向かせると、ふざけて近づいていった。
「どうやって?こんな感じ?こんな感じ?」と言いながら、、、。
しかしユジンの顔を見るとキスする寸前のところで動きを止めた。ユジンの表情はそれは悲しそうだったからだ。
「こうじゃないんだね、、、何一つ思い出せないなぁ。ごめんな。」


そしてミニョンも悲しそうにうつむいてしまった。二人は涙をためながら、しばらくじっと見つめあっていた。ユジンの目の前には、あの日のチュンサンの顔が浮かんでいた。初雪デートの時に、「ユジナ」と名前を呼んで、驚いて振り向いた自分の唇に、素早くキスをしたチュンサン。あの時のチュンサンのびっくりした、でもうれしそうな顔を一生忘れないだろう。ミニョンも早く思い出してくれたらいいのに。ユジンは目の前のミニョンに向かって、寂しそうな顔で微笑んだ。そんな二人を、黄金色の湖面が優しく包み込むのだった。
























