

一方でミニョンはぼんやりと小舟が浮かぶ洋風画のパズルを眺めていた。ユジンと初めて会社で会ったとき、いやミニョンとして2度目に会ったとき、彼女はこのパズルを眺めていたっけ。思えばあの時、彼女はパズルの最後のピースを拾ってはめた後だったのだ。それがまるで今の自分の状況のように思える。しかし、パズルがはまったはずなのに、すっきりするはずが、ますます混乱するはめになった、、、。以前ユジンはこうも言っていた。「パズルが好きなのは覚えておきたい思い出がたくさんあるからで、それをひとつひとつはめているのだ。」と。今となってはチュンサンにとっては、それが妙に的を得たように感じられた。
すると、急にキム次長が入ってきて話しかけた。

「どこに行ってたんですか?」
「ちょっと人探しをしてました。」
「誰をですか?」
しかしミニョンは返事をしない。キム次長はため息をついていった。
「いいですか。人探しもいいですけど、自分を見失いそうじゃないですか。ほんとにひどい顔して。もういいですから、とりあえず急ぎの書類にサインをしてくださいよ。後で説明をするからサインだけ、ねっ。」そう言ってミニョンにペンと書類を差し出す。しかし、ミニョンは『イミニョン』と印字された名前を見て固まってしまった。自分が誰なのか混乱していたからだった。そして困惑するキム次長を置いて車で出かけてしまった。

サンヒョクは車で出かけるミニョンを目撃して急いで後を追いかけた。逃げられたら次にいつ会えるかわからない。サンヒョクは彼が常泊しているホテルに入っていくのを確認すると、先回りするために階段を使ってエレベーターから降りてくるミニョンを待ち伏せした。しかし、サンヒョクが声をかけたのにもかかわらず、一瞥した後、無視して歩き始めた。
「イミニョンさん、イミニョンさん、、、、、おいっカンジュンサン!」
するとミニョンはびくっと肩を震わせて止まった。
「、、、やっぱり。君はカンジュンサンなのか?」
二人はミニョンの部屋に行き、話をつづけた。といっても窓に背を向けるミニョンにサンヒョクが一方的に話しただけではあったが。
サンヒョクは冷たい目をして話した。

「やっぱり君も知っていたんだな。若い男が学校にカンジュンサンのことを調べに行ったと聞いて、きっと君だと思ったんだ。なんで自分がチュンサンだと知らなかったんだ?あの事故で記憶をなくしたのか?」
しかしミニョンは答えなかった。
「やっぱりな。」
ミニョンは途方に暮れたように言った。
「いったい僕はどうしたらいいんだ?」
そして向き直ってサンヒョクを見つめていった。その目は混乱と恐れと不安に満ちていた。
「サンヒョクさんは僕にどうしてほしいんですか?」
サンヒョクはミニョンの目をまっすぐに見つめてきっぱりといった。
「たとえあなたがチュンサンでも何も変わらない。僕は絶対にあなたにユジンを渡しません。もう二度とユジンの前に現れないでくれ」
予想通りの答えに、ミニョンは悲しそうな眼をした。
「ユジンをこれ以上苦しめないでください」
この言葉にはミニョンも驚いた。
「どうしてですか。僕はチュンサンで、チュンサンはあんなにユジンさんが会いたがっていた人じゃないですか。それなのにどうしてですか」
「あなたに、あんたなんかに、そんな資格はないんだ!ミニョンにもチュンサンにもどっちにもそんな資格はない。ユジンはあんたを本当に好きだっただろうが、あんたは違った。僕を大嫌いだったからユジンを利用したって僕に言ったんだ。本当に言ったんだ」
ミニョンは打ちひしがれていた。目に涙をためて言うしかなかった。
「思い出せないんです。本当にチュンサンがそう言ったんですか。僕は何も思い出せない、、、。僕がユジンさんを利用したんですか?」

すると驚いたことにサンヒョクは床に膝をついて懇願した。
「そっとしておいてください。どうぞユジンをこれ以上苦しめないでください。あなたは10年間もユジンを苦しめたんです。もう十分でしょう。どうぞほっておいてください。お願いします。どうぞ、ユジンをあきらめてください。」
それはユジンのためというよりも10年も待って自分を好きでもない女性と結婚できる、哀れな男の最後の願いにも見えた。
そんなサンヒョクを前に、ミニョンは何も言うことができずにただずんだ。その顔には苦悩の表情が浮かんでいた。ユジンのため、と言われると何もできない自分がいた。

そのころユジンとチンスクは近くの食堂で夕食を食べていた。チンスクは上機嫌でチャミスルを飲みながらおつまみを食べている。チンスクはチェリンがユジンに意地の悪いことを言ったのを気にして、夕食に誘ったのだった。しかしユジンはどうしても誰かにはなしてしまいたいことがあった。
「サンヒョクがね、聞いてきたの。ミニョンさんのどこが好きだったのかって。」
「、、、そう。で、なんて答えたの?」
「答えられなかったの。どこがいいなんて言葉では表せられなくて。」
「ユジン、、、」
穏やかな顔で話すユジンを、チンスクも穏やかな表情で見つめていた。

「チュンサンを見てるとね、急に心ごと吸い込まれるような気がしたの。私の心がチュンサンに向けて吸い込まれて落ちていく感覚。ああこれがこれが恋なんだ、これが運命なんだって思ってた。チュンサンが死んでからはきっと2度とそんな感覚はないだろうって思ったけど、ミニョンさんに会ってからある時、ふってまた吸い込まれて落ちていった、、、、。顔が似てるからじゃないの、本当にドキドキして胸が苦しくなる感覚を思い出したのよ。まるでチュンサンといるときみたいに、心があったかくなる感覚をミニョンさんは思い出させてくれた。本当に不思議なんだけど、二人は確かに別人なのに、ミニョンさんに同じようなことを感じるのよ。なぜだかわからないけど、私の心は2人がおんなじ人だと感じているの」
チンスクはユジンの独り言のような胸の内を静かに聞いていた。チュンサンに対するユジンの深い思いを初めて聞いたのだった。しかし、ふたりともユジンの直感が真実を言い当てているとはつゆほども思わなかった。
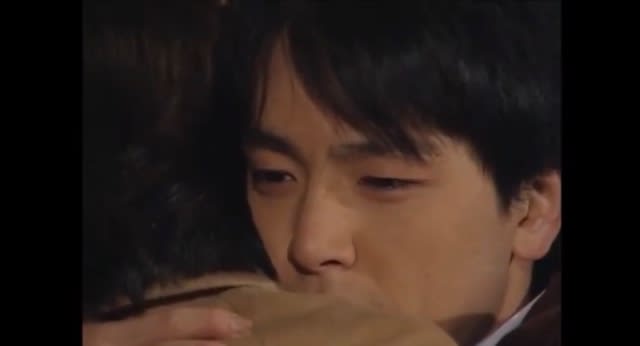
ユジンとチンスクは夕食を終えるとアパートの前までやってきた。チンスクは酔いが回ってチェリンの悪口を話している。ユジンは苦笑しながら友人の話を聞いていた。すると、アパートの階段に打ちひしがれた様子のサンヒョクが座っていた。驚く二人を目の前に、サンヒョクは何も言わずにユジンを抱きしめた。チンスクは奥ゆかしいサンヒョクらしくもないと目を真ん丸にして、ユジンは驚きと恥ずかしさで固まってしまった。サンヒョクにはそんな二人の様子は全く見えていなかった。考えることはただ一つ、ユジンを失う恐怖だけだったのだ。



























